|
|
|
|
![]()
真逆の夜の夢。 佐久間學
しかし、1970年にセルが亡くなった後は、指揮者はブーレーズ、マゼール、ドホナーニと変わりますが、セルの時代ほどの輝きはこのオーケストラにはなくなってしまったような印象がありませんか? ドホナーニなどは、名前からして存在感がありませんからね(「それなーに」)。 2002年から音楽監督となったウェルザー=メストも、正直あまりパッとしない指揮者でしたが、それでも在任期間はもう20年になろうとしているのですから、セルほどではないにしても相性はいいのでしょう。そして、遅ればせながら、2020年にはこのオーケストラの自主レーベルが新たに誕生することになりました。実際は、この「TCO」というレーベルは以前からあったものなのですが、それをリニューアルして再登場、ということのようです。最初にリリースされたのは、ベートーヴェンから現代作曲家まで集めた3枚組、続いて2回目はシューベルトとクシェネク、そして今回が3回目のリリースでシュニトケとプロコフィエフです。なかなかマニアックな選曲ですね。もちろん、指揮者は全てウェルザー=メストです。 このレーベルの発足にあたっては、この分野での先駆け的存在の「LSO LIVE」と提携して、そのノウハウなどを学び、プロモーション面での協力などもお願いしているのだそうですから、メディアもCDではなくSACDを採用して、ハイレゾでの再生を可能にしています。ただ、あいにくLSOでは行っているサラウンド再生には対応はしていません。 さらに、タイミング的にはレーベルの発足直後に起こったパンデミックによる「被害」も少なからずあったようです。ここに収録されている2曲のうち、プロコフィエフの「交響曲第2番」は2020年の1月の録音ですから、まだ通常のコンサートは開けていたようですが、シュニトケの「ピアノと弦楽合奏のための協奏曲」はその年の10月、公開の演奏会は不可能ですし、オーケストラのメンバーも「密」を避けた配置などが求められていた頃です。  それにしても、このアール・デコ調のホールは本当に美しいですね。実は、1929年に完成したこのホールは、セルの時代、1958年に、音響的に問題があったので、このステージの内面をオルガンも含めて反響板(「セル・シェル」と呼ばれました)で覆ってしまいました。それによって、オーディオ的には高水準の録音が可能になったと言われています。  もう一つのプロコフィエフは、このオーケストラのもう一つのホームグラウンド、マイアミにあるナイト・コンサートホールでの録音です。こちらは、全体の音が少し濁っていて、どんくさいサウンドになっています。 SACD Artwork © The Cleveland Orchestra and Musical Arts Association |
||||||
ここで、2台ピアノバージョンを演奏している、オルハ・チパクとオレクシー・クシュニルという2人のウクライナ出身のピアノストたちは、リストの編曲プランにはなかったことですが、ピアノの他にティンパニを加える、というアイディアを実践しています。もちろん、これが「世界初録音」ということになります。そのティンパニのパートは、オーケストラ版のパート譜をそのまま使います。演奏しているのは、スペイン出身で現在はベルリン古楽アカデミーのメンバーを務めているフランシスコ・マヌエル・アンガス・ロドリゲスです。彼は、かつて日本の桐朋学園大学で安倍圭子さんに師事してマリンバを学んでいたそうですね。 ここでは、ピアノがスタインウェイとベーゼンドルファーという、別のメーカーのものが使われています。おそらく、左の第1ピアノがスタインウェイで、右の第2ピアノがベーゼンドルファーではないかと思うのですが、これがかなり異なった音色の楽器として聴こえてきたのは興味深いことです。おそらく、彼らは2台の楽器の融合というよりは、別々の個性をぶつかり合わせることによって、より表現の幅を広げることを意図していたのではないでしょうか。そして、それは確かに聴くものにそれぞれの楽器の持ち味を感じさせることに成功しています。 そして、そこに加わってきたティンパニは、なんとも強烈なインパクトを与えてくれました。何よりも、ロドリゲスの叩くティンパニがとても豊かな表情を持っていたことに驚いてしまいます。さらに、普通のオーケストラの録音ではこの楽器は一つの点として聴こえてきますが、ここでは、高音用と低音用の2つの楽器がもろに左右から聴こえてくるような定位になっていますから、その存在感はより立体的に迫ってきます。 そして、オーケストラで聴いていた時には気が付かなかったようなところでこの楽器が加わっていたことに、頻繁に気づかされます。ただ、正直、そんなことは知らなかった方がよかったな、と思うことも、やはりてぃんぱんに(頻繁に)起こりました。あくまで「隠し味」という感じで作曲家が加えていたところがもろに聴こえてくると、ちょっとした違和感が伴います。 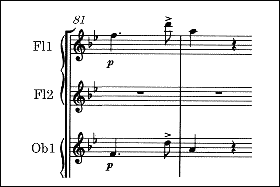 それから、ティンパニは、第4楽章のマーチが始まる前の「vor Gott」のフェルマータで、ディミヌエンドをかけていましたね。これは新旧のブライトコプフ版に見られる形、ここはぜひベーレンライター版のようにフォルティシモで叩ききって欲しかったものです。それでこそ、ここにティンパニを加えた意味がはっきりするというのに。 CD Artwork © GENUIN classics |
||||||
1曲目は先行配信されていたスタンダード・ナンバーの「It's Been A Long, Long Time」。このPVでは、そんなコンセプトが反映されているように、まずはマッチでキャンドルに火を点けてパーティーの始まりを印象付けます。これはアルバムでも同じ。その後に、ほのかなスクラッチ・ノイズがアナログ感を演出する中を、しっとりとスコットのソロが始まります。そこに、ミッチが加わり、さらにカースティンも加わって3人のハモリになります。この瞬間のハーモニーが、まさに絶品(カースティンは別嬪)。それぞれに微妙に音色は異なっているのですが、それが見事に一つの方向を向いて溶け合っています。さすがは、オリジナル・メンバーならではの強みですね。 一瞬の間を置いた後にミッチのソロが始まると、そこにマットとケヴィンの2人のベースが加わって、さらに厚ぼったい世界に変わったハーモニーが包み込みます。ソロはマット、カースティンと受け継がれるのですが、マットはとてもソフトな音色、単なるベースとは思えない柔軟性のある声の持ち主だということが分かります。最後は全員のア・カペラで幕を閉じます。これが、たった1分10秒の間に繰り広げられているのですね。それだけで、彼らの魅力がすべて伝わってきます。 そこからいきなりケヴィンのビートボックスが入ったポール・マッカートニーの「Wonderful Christmastime」が派手に始まります。どこかのどかな雰囲気のオリジナルが、とてもアグレッシブなビートで見違えるほどダンサブルなものに変わります。 その流れで、トラディショナルの「I Saw Three Ships」が、アイリッシュ風の複雑なビート(イントロでは、いったい何拍子なのか分かりませんでした)に乗って軽やかに歌われます。そして、ジョニ・ミッチェルの「River」などは、彼らの得意技「ヴォーカル・ピチカート」に乗ってとても敬虔な演奏に仕上がっています。本当に、この正確極まりないアルペジオには、いつもながら感心させられます。 トラディショナルの「Over The River」では、意表をついてリンジー・スターリングのオーバーダブのヴァイオリンなどがフィーチャーされ、スリリングに迫ります。これも、アイリッシュなテイストが満載です。 タイトル・チューン「Evergreen」には、今度はアコースティック。ギターが加わります。いにしえの「フォークソング」調の軽やかでさわやかな曲を、まるでPPMのような感じで歌っていましたね。とても和みます。 定番の「Frosty The Snowman」では、シンプルなア・カペラに乗って、ゲストのアレッシア・カーラがハスキーな声でソロを取っています。コーラスとは明らかに異質な声なのですが、そのあたりのミスマッチを狙ったいたのでしょう。さらに、スティーヴィー・ワンダーの「I Just Called To Say I Love You」では、ビートボックスは控えて、あくまで声だけのア・カペラで迫ります。それを、ディレイで深い響きに変えて、感動的に迫ります。特に、転調した後は、まさに「コーラス」の重量感が伴います。 かつて、シンガーズ・アンリミテッドが「Christmas」という名盤でしっとりと歌いあげていた「It Came Upon The Midnight Clear」が、ここでは、いかにも彼らならではの最新のサウンドに変わります。 ア・カペラの定番と言われている「My Heart With You」は、ほぼザ・レスキューズのオリジナル通りの、全部がホモフォニーという、ある意味とてもユニークなアレンジで、美しいコード進行を大切に聴かせて、ほとんど聖歌のような雰囲気を醸し出しています。 そして、最後の「We Wish You A Merry Christmas」がフェイドアウトで終わった後には、キャンドルを吹き消す音が。パーティーはお開きです。 CD Artwork © RCA Records |
||||||
そもそも、このオーケストラの名前も、最近はただの「コンセルトヘボウ管弦楽団」と表記されることの方が多くなっているようです。現実に、アルバムのジャケット上では「ロイヤル」(英語ではRoyal、オランダ語ではKoninklijk)という文字がなくなっていますし、コピーライトのクレジットからも、Koninklijkが消えています。 さらに、首席指揮者も、2016年に就任したダニエレ・ガッティがセクハラ問題で2018年にクビになってから、その後任は決まっていませんね。 それでも、客演の指揮者には、様々な方が登場しているようです。今回はパッパーノの指揮で、ベルリオーズの、いわゆる「レクイエム」が演奏されています。 アントニオ・パッパーノが、実はイギリス人だったということに、ごく最近気づかされました。今までずっとイタリア人だと思っていましたからね。確かに、両親はイタリア人なのですが、パッパーノはイギリスで生まれ育った、生粋のイギリス人だったのでした。そういえば、彼の名前の前には「サー」という称号が付いているさー(なぜか沖縄弁)。 彼は、これまでに多くのオペラハウスやオーケストラの指揮者を務めてきましたが、現在のポストは、ロンドンのロイヤル・オペラハウス(コヴェント・ガーデン)の音楽監督と、ローマのサンタ・チェチリア音楽院管弦楽団の音楽監督です。そして、2024年9月からは、なんとロンドン交響楽団の首席指揮者に就任することが決まっているそうです(2023年9月から暫定首席指揮者)。 この「レクイエム」は、編成が大きいことで有名です。その模様はブックレットの断片的なアングルでしか知ることはできませんが、合唱はオルガンの左右の客席にびっしり入っていますから、300人ぐらいはいるのではないでしょうか。そして、金管のバンダはオルガンと客席の間の左右の隙間に2組、さらに、左右のバルコニーの最もステージに近い部分にやはり2組設置されています(写真の丸印)。  録音スタッフはこのホールの響きを熟知しているポリヒムニアのクルーです。まずは、SACDを聴きはじめると、まさにコンセルトヘボウのアコースティックスがそのままに(いや、実際に行ったことはありませんが)眼前に広がっているのを感じることができます。絹のような肌触りの弦楽器が、ふっくらと浮かび上がるその空間は、言いようもない魅力をたたえていました。 合唱は、パッパーノがローマから連れてきたサンタ・チェチリア音楽院の合唱団です。出だしこそ、ソプラノのちょっと甲高い声が気になりましたが、次第にそれはほかのパートやオーケストラの中に溶け込んできて、とてつもない質感を主張するようになってきます。これは、かなりハイレベルな合唱団だったことが分かります。こういう合唱で歌われると、この曲の主役はやはり合唱なのだな、と思わずにはいられません。 もちろん、全てのプレーヤーが音を出している部分の大音響のインパクトはものすごいものがありました。それが、全く混濁しないで、それぞれのパートがくっきりと聞き取れるのも驚異的です。ティンパニのチームは、もちろん「Tuba mirum」での派手な音響はインパクトがありますが、最後の最後にとても静かな連打が遠くから聴こえてくる場面では、これこそが死者を悼む太鼓なのだと、実感するのでした。 「Sanctus」にだけ登場するテノールも、伸びのある声で素敵でした。 とても深いところでこの作品に共鳴することができる、素晴らしい演奏と録音です。 SACD Artwork © Concertgebouworkest |
||||||
パッケージは前回のようなLPサイズではなく、大判のハードカバーといった感じの長方形、厚さはかなりあります。   このアルバムのためのジャケット写真は、すでに、彼らのファーストアルバムの写真と同じ場所で、メンバーだけが新しくなったものが撮られていましたが、それは、後のベストアルバム(いわゆる「赤盤」と「青盤」)に転用されていますね。 最終的には、1970年にフィル・スペクターが、ジョンとジョージからの依頼を受けて、アルバムを作ることになりました。彼は、1週間という短い間に、曲を選び、さらに「I Me Mine」、「The Long and Winding Road」、「Across the Univers」の3つの曲にはストリングスとコーラスまで加えました。そこで出来上がったのが、現在の「Let It Be」というアルバムなのですね。そのオーケストラ・ダビングは4月1日に行われたのですが、その時にはリンゴが参加してドラムを演奏しています。ですから、これがビートルズとしての最後の録音になるため、なんだかんだと言ってもこれが彼らのラストアルバムとなっているのです。 ですから、1969年のジョンズ版「Get Back」は完全にお蔵入りになっていて、怪しげな海賊盤でしか聴くことは出来なかったのですが、半世紀以上経ってやっと公式に日の目を見たのですね。 これは、なかなか興味深いものでした。スペクター版に比べるととても素朴な仕上がりなのですが、「The Long and Winding Road」などでは、ポールのヴォーカルにほんのりリバーブがかかってたりしていて、ジョンズならではの美意識も感じることができます。 聴きなれたスペクターの公式盤については、リミックスされてはいても「Abbey Road」ほどの驚きはありませんでした。そもそも、このアルバムでは一発録りのライブ感を大切にしていて、極力オーバーダビングは行っていないので、リミックスによって大幅に変わることはなかったのでしょう。 ただ、スペクターが手掛けたオーケストレーション(実際は、専門のアレンジャーがいます)の部分は、特にサラウンドでは劇的に生々しさが表れていました。ヴァイオリンなども、とても豊かな質感がしっかんり感じられますし、コーラスの音も充実しています。でも、ハイレゾのステレオモードで聴くと、とたんにしょぼい音になっていたのは、なぜでしょう。 CD & BD Artwork © Calderstone Productions Limited |
||||||
もちろん、エリクソンはこの合唱団だけではなく、スウェーデン放送合唱団(1951年から1982年)や、男声合唱のオルフェイ・ドレンガー(1951年から1991年)などの芸術監督も務めています。さらに、スウェーデン以外の多くの国の合唱団との共演も数知れず、でしたね。 彼の録音としては、1968年から1975年にかけてEMIに録音した、ルネサンスから当時の「現代」までの5世紀にわたるヨーロッパの合唱音楽を集めたアンソロジーが有名でした。現在では6枚組のCDとしてリリースされていますが、初出はもちろんLPでした。まず、文字通り「5世紀にわたるヨーロッパの合唱音楽」という、4枚組のLPボックスが1971年にリリースされます。そして、それに1972年にリリースされたLPを加えて独自に編集した「20世紀の合唱音楽」というタイトルの3枚組の国内盤ボックスもリリースされました、それは、その年の「芸術祭参加作品」になっていました。 さらに、1978年までには、その続編として、何枚かの「名人芸の合唱音楽」というLPもリリースされます。そして、それらを編集して、その2つのタイトルで、それぞれ3枚組のCDが2組1994年にリリースされたのです。現在では、それをそのまま統合した6枚組のCDが、WARNERからバジェット価格で販売されています。この一大アンソロジーは、まさに古今の無伴奏合唱曲のお手本として、多くのアマチュア合唱団が参考音源として大切に聴いていたのでしょうね(合唱団が、ストックホルム放送合唱団となっているのはなぜ? 契約上、正式名称を使うことがストップされたとか)。 そんなエリクソンは、1990年前後に、PROPRIUSレーベルにバッハの4つの大規模な合唱曲、「クリスマス・オラトリオ」、「ロ短調ミサ」、「ヨハネ受難曲」、「マタイ受難曲」をライブ録音していました。それらは、もちろんCDとしてリリースされていたのですが、現在ではほとんど廃盤扱いで、入手は難しくなっています。それが、最近サブスクで聴けるようになりました。その中から、「ヨハネ」を聴いてみました。 これは、1993年の3月、イースターの頃に演奏されたものです。その時のエリクソンは77歳ですから、まだまだ「若かった」ですね。合唱はエリック・エリクソン室内合唱団ですが、オーケストラがピリオド楽器の団体、ドロットニングホルム・バロック・アンサンブルです。なんとなく、イメージとしてエリクソンという人は保守的な指揮者のような気がしていましたが、この時期にしっかりピリオド楽器と対峙していたのですね。というか、彼はもともとバーゼルのスコラ・カントルムで、「アーリー・ミュージック」を学んでいたのですから、しっかり「ピリオド」の語法も身に着けていたのでしょう。ただ、この時代ですから、まだ楽譜は新全集版を選択するしかなかったのでしょうね。 この「ヨハネ」は、とても軽やかなテンポで最初の合唱が始まります。そして、前奏が終わって合唱が出てくると、その声には思わず圧倒されてしまいます。まずは、とてもくっきりとした輪郭を持つ音圧、そして、まさに「いぶし銀」ともいうべき深い音色、もちろん、イントネーションやハーモニーには全く疵がありません。まさに、世界一の合唱指揮者が手塩にかけて育てた合唱団ならではの、強烈な存在感が迫ってきます。そこに、エリクソンはとても細かい表現を加えています。ピリオドのスタイルでも、しっかり歌わせるという合唱の基本は貫き通しているのでしょう。 ソリストたちもほぼ水準以上の演奏です。エヴァンゲリストとアリアの両方を歌ったハワード・クルークは大健闘、メゾのモニカ・グロープによるアルトのアリアも、素敵でした。 CD Artwork © Proprius |
||||||
そうなんです。まさに、そんなとんでもないことを、このヴァイオリニストは行っていたのです。CDがリリースされたのは結構前なのですが、予想通り、ここでの彼女の「朗読」は、各方面で絶賛されていましたね。おそらく、もう少ししたら、CDなどクラシック音楽の録音物に関してはこの国で最も権威がある賞である「レコードアカデミー大賞」を受賞することになるのではないでしょうか。 「ピエロ・リュネール」というタイトルは、そもそもはベルギーの詩人アルベール・ジローが作った詩集のタイトルですが、「Pierrot lunaire」というフランス語は、単に「月のピエロ」という意味しかないはずです。それを、「月に憑かれたピエロ」と訳したのは、明らかに意訳なのでしょうね。日本人にとっては、シェーンベルクの音楽だったら、そのぐらい格調高い訳語ではないと、やはりインテリの関心を引き付けることは難しかったのでしょう。堀口大學と清水脩だったら「月光とピエロ」で済まされますけどね。 この作品は、もともとはさる女優がこのジローの詩を朗読するときにそのバックに流れる音楽を、と、シェーンベルクに依頼して作られたのだそうです。ですから、その「朗読」の部分は別に音楽にする必要はなかったのでしょうが、シェーンベルクはしっかりその「歌詞」に音楽を付け、それを、「しゃべるように」歌うという指定を行いました。  それ以外にも、  もう一つ   こんなこまごまとした指定がなされているのですから、これはまさに専門の歌手にとってもかなりのテクニックと読譜力が必要とされるのでしょうが、それをコパチンスカヤはいともたやすく「演奏」しています。「×」の付いた音は、別に音程などは気にしなくていいはずなのに、ほぼ楽譜通りの音で「しゃべって」いたりしますから、すごいものです。そして、そのニュアンスの付け方は奔放そのもの、時には声色を変えたりして、縦横無尽に暴れまわっていますよ。 ですから、そういうのを聴いていると、これはシェーンベルクというとても難しい音楽を作った人の作品ではなく、まるで「ラップ」のように聴こえてしまいます。そう、識者はこういう歌い方を「シュプレヒシュティンメ」とか「シュプレヒゲザンク」とか、ゲップが出そうな名前で呼んでいますが、実はこれは「ラップ」だったのですよ。 このアルバムには、この曲のほかに、シェーンベルクの詩的演奏協会で演奏されていたヨハン・シュトラウスのワルツの編曲など、楽しい曲も満載です。そして、かつてポリーニの演奏で聴いてとても難解だと思っていたはずのシェーンベルクのピアノ・ソロの作品(Op.19)までが、とてもキャッチーなトラックに聴こえてきましたよ。 CD Artwork © Radio SRF 2 Kultur & Alpha Classics / Outhere Music |
||||||
そのうちの4回は、2019年4月と5月、そして2020年1月と2月に、代官山ヒルサイドテラスで浦久さんが主宰する「代官山未来音楽塾」の特別公開講義として、大勢の参加者の前で行われた対談です。ここでは、参加者の反応なども適宜加えられていますし、参加者からの質問に答えたコーナーも再現されています。 そしてもう1回は2020年5月に、朝日カルチャーセンター新宿教室の主催でオンライン(山田さんはベルリン、浦久さんは東京)で行われた山田さんのトークシリーズ「ヤマカズトークセッション」での記録を、再構成したものです。つまり、この中でこれだけはコロナ下での対談です。 代官山の方は一応それぞれの日に「宇宙は指揮できるか」、「オーケストラに未来はあるか」、「プロか? アマか? 生き残れるのはどっちだ?」、「理想のオーケストラとは?」というタイトルが付けられています。とは言っても、それらは全てその場で即興的に語られたものばかりですから、必ずしもそんなタイトルに沿った対談が行われたわけではなく、話題は広範囲に広がっていき、それらのタイトルに収束するわけではありません。ですから、そんなものにはとらわれずに、それぞれの刺激的なトークを楽しむべきでしょう。 浦久さんという方はここで初めて知りましたが、かつてはフランスを拠点に活躍されていたそうで、とてもグローバルな視点で歴史や文化を語られています。山田さんは、彼の圧倒的な知識量にひるみながらも、彼独自のユニークな意見を展開している、と言った感じで、対談は進んでいったようです。 そんな中で最もウケたのは、よく東京あたりでのコンサートのパンフレットに記されている「指揮者が指揮棒を下ろしてから拍手をしてください」という文言に対するツッコミです。山田さんは「あれ、やめてほしいですね。だからぼくはあえて指揮棒を、こう、ずっと上げておこうかなって」と会場の笑いを取っていましたし、浦久さんは「そんな冗談みたいな注意書きをじっさいに観たことがあります。ひどいね。そんなこと、世界中のどこでもやっていないですよね」と盛り上がっていましたね。 そして、そんな状況を「コンサートはエンターテインメントなのに、日本ではそうなっていない」と指摘し、「日本ではクラシックのガラパゴス化が進むのでは」という、ありがたくない結論まで導いていましたね。 そんな風に同じ意見でまとまることもありますが、それぞれに譲れないものもあるようで、例えば「現代音楽」に対するスタンスなどはこの二人は微妙に異なっているようです。たとえば、浦久さんは、クセナキスの功績について滔滔と語っていますが、山田さんは、「現代音楽をやると金縛りにあう」と、軽くいなしたりしています。 そんな、とても楽しい対談なのですが、1ヶ所、ちょっと気になったところがありました。それは、バッハの「ロ短調ミサ」についての浦久さんのコメントで、「ルター派のミサ曲はキリエとグロリアだけで、カトリックのミサ曲ではそれにクレド、サンクトゥス、アニェス(ママ、「アニュス」?)・デイを加えた5部で編成されている。ところが、バッハのロ短調ミサの構成はそのどちらでもない」と言い切っています。これは、かなりの誤解を招きかねません。というか、全くの事実誤認なのではないでしょうか。 最も気になる「プロか? アマか?」では、山田さんは「プロとは、アマチュアの精神を一生持ち続けること」と、あっさり定義してました。 Book Artwork © Artes Publishing Inc. |
||||||
ロンドン・フィルのレーベルであるLPOも、そんな感じで今年に入ってからはまだ2点しかCDがリリースされていませんから、ちょっとさびしい気がします。もちろん、「コロナ」の影響もあるのでしょうが、何とか頑張ってもらいたいものです。 ただ、このレーベルでは、とにかくジャケットデザインにだけは思い切りこだわるという姿勢はまだまだ健在のようなので、まずは一安心でしょう。それは、このオーケストラのロゴに使われている「星マーク」を、ジャケットのどこかに必ず入れる、というこだわりです。 でも、今回のジャケットでは、いくら探してもそれが見つかりませんでした。やはり「経済効果」とか、そんなものを重視する姿勢が表に出てきてしまったのかな、と、ちょっとがっかりしてしまいました。ところが、あったんですね。画像を拡大してやっと見つけた時は本当にうれしかったですね。ここです。最近は、「星」そのものをちょっとゆがめたりしていますから、難易度は上がってますね。  その最新アルバムは、ちょっと前、2017年のコンサートのライブ録音で、マーラーの交響曲第8番です。 なぜかこのレーベルには録音スタッフのクレジットがないのですが、今回はこの曲では最も重要な録音面でのクオリティが非常に高かったのには、まず嬉しくなりました。もちろん、CDですから普通のステレオなのですが、それでも前面いっぱいに広がった音場には、スケールの大きさを感じることができました。2つある大人の混声合唱が、くっきり左右に配置されていますし、児童合唱は左端にちょっと距離感をもって定位しています。 ユロフスキの指揮は、いつもながらのバランスの良さですが、この曲の場合編成が大きい分、つい大袈裟な身振りになりがちなところを、きっちり冷静さを保ってコントロールをきかせています。 いつもこの曲を聴くたびに、これははたして「交響曲」なのだろうかと思ってしまいます。何しろ、ソリストや合唱が大活躍しますから、第1部は壮大な「モテット」、第2部はほとんど「オペラ」のように感じられてしまいます。なんたって、そこにはしっかりゲーテの「ファウスト」という「台本」があるのですからね。 実際にオペラを作ることはなかったマーラーですが、こんな形でオペラっぽいことには手を出していたのでしょう。というか、メシアンの「アッシジの聖フランチェスコ」がオペラだというのだったら、これもすでに立派なオペラなのではないでしょうか。 ですから、たとえば、「幕切れ」近くに初めて登場する「栄光の聖母」の扱いなども、奇抜な演出も期待できますよね。いや、そこまでではなくても、普通のコンサートでこのソプラノが歌う場所をステージ以外のところに設定するようなことはよくあるようですね。 この録音でも、彼女の声はちょっと離れた場所から聴こえてくるように感じられますが、実際にはどうだったのでしょう。 そして、最後に出てくるのが、とても大人数の合唱による極上のピアニシモです。この合唱は、曲の冒頭からとてもクオリティの高い、聴きごたえのある演奏を聴かせてくれていましたが、この最後の部分も期待通りの素晴らしさでした。まさに、大合唱の醍醐味です。生で、これだけの大人数の合唱が聴けるようになるのは、いつの頃なのでしょう。 CD Artwork © London Philharmonic Orchestra Ltd |
||||||
その、ショーヴァンの「バンド」の名前は、18世紀にパリに存在していた「ル・コンセール・ド・ラ・ロージュ・オランピック」から取ったものです。ただ、創設時はその名前をそのまま名乗っていたのですが、いわゆる「オリンピック」の関係者からクレームが付いたため、1年後には「オランピック」という言葉をカットせざるを得ませんでした。ですから、このオーケストラの公式ロゴでは  その「本家」は、プロの演奏家だけではなく、レベルの高いアマチュアまでもメンバーになっていた、とても大きなオーケストラだったのだそうです。お年寄りはいませんが(それは「ロージン」)なんでもヴァイオリン奏者が40人、コントラバス奏者は10人もいたそうですからね。そして、なんと言ってもハイドンの「パリ交響曲」と呼ばれる、第82番から第87番までの交響曲を委嘱したことで、その名が知られています。 ですから、ショーヴァンもまずはこの6曲の交響曲をAPARTEレーベルに録音しています。そして、今回モーツァルトを録音するにあたって、彼は「Simply Mozart」というアルバム・コンセプトを掲げていました。それは、ここで演奏している3曲、「フィガロの結婚」序曲、ヴァイオリン協奏曲第3番、交響曲第41番がいずれもとても馴染みのあるもので、これらを聴く時には、なにか「デ・ジャ・ヴ」を感じてしまい、何もしなくても感情に訴えかけられることを表現した言葉なのでしょう。 確かに、このアルバムを聴きはじめると、そんな「既視感」とともに、その演奏が何の抵抗もなく体に入ってくるようなちょっと不思議な感じがありました。ここには、これまでさんざん聴いていた「ピリオド」の演奏のような、ちょっと身構えてしまう不自然なところが全くなかったのです。その理由はすぐ分かりました。彼らは、「ピリオド」ではタブーとされているビブラートを、しっかりかけて演奏しているのです。弦楽器だけではなく、時には管楽器からもビブラートを聴くことができます。もちろん、ヴァイオリン協奏曲でのショーヴァンのソロも、たっぷりビブラートをかけて甘〜く歌い上げています。 そのようなサウンドですから、いかにテンポが速くても、いかに途中でわざとらしいルバートをかけても、大袈裟なダイナミックレンジで驚かそうとしても、聴くものはすんなりとそれらを新鮮な表現として受け入れて、それを楽しむことができるのでしょう。 思えば、これまではまずノン・ビブラートありきで、必要な表現手段をフレージングなどで補っていたはずです。しかし、そんな不自然なことは、もはや現代の聴衆には受け入れられないことに、やっと気が付いたのでしょう。「ピリオド」も、新しいフェイズに入った、と言えるのではないでしょうか。 CD Artwork © Alpha Classics / Outhere Music |
||||||
おとといのおやぢに会える、か。
|
|
| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |
| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |