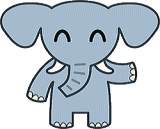静岡市の弁護士伊藤彰彦法律事務所
役に立つ情報をわかりやすく
役に立つ情報をわかりやすく
HOME 離婚 相続 交通事故 労働事件など 破産過払再生 弁護士費用 地図
こちらは,スマホ版です。PC版はこちらをクリックして下さい。
離婚-目次へ戻る
離婚の基礎知識 4
有責配偶者からの離婚請求
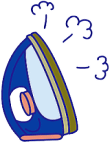 1 自ら離婚原因を作った配偶者のほうから離婚を請求する場合をいいます。
1 自ら離婚原因を作った配偶者のほうから離婚を請求する場合をいいます。浮気している夫からの離婚請求が典型例です。かつては,裁判所は離婚を認めませんでした。離婚させられる配偶者やその家族が酷でかわいそうだからです。現在でも,子供が成人しかつ別居期間として最低6年は経過しない限り,離婚は難しいでしょう。
2以下裁判例を踏まえて説明します。
昭和62年に最高裁が初めて有責配偶者からの離婚を認めました。
その要件は,次の3つです。
① 別居が長期間に及んでいること
② 未成熟の子がいないこと
③ 相手方配偶者に離婚により精神的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれないこと
3上記3つの要件を,その後の裁判例も踏まえながら,整理してみましょう。
① 別居期間
当初の裁判例は35年間の別居という長期のものでした。
現在は,同居期間22年・別居期間6年で離婚を認める判例(東京高裁平成14年6月26日)がある一方で,同居期間21年・別居期間9年でも離婚を認めなかった判例もあります(福岡高裁平成16年8月26日)。その理由は4で説明します。
② 未成熟子の不存在
未成熟子とは一般には20歳未満の未成年の子をいいます。しかし20歳未満でも,働いていたり結婚している場合は未成熟子にはあたりませんし,20歳を超えていても,学生とか障害者で,親の監護なしでは生活を維持できない子は未成熟子にあたります。
ところが最高裁平成6年2月8日判決は,高校2年生の子供がいるにも関わらず離婚を認めました。この事案は,別居期間は約13年11ヶ月,夫は別居後も毎月15万円生活費を送金,妻が不貞相手とその両親のほか,その前夫に対してまで嫌がらせをし続けていたという案件です。
③ 苛酷状態の不存在
精神的・経済的な困難さを指します。
4 (結論)
結局,上記1~3の要件を,有責配偶者の有責態様,相手方の生活状況,子の監護の必要性,別居後に形成された内縁関係等の諸事情を踏まえて,総合的に判断するのです。
具体的にお話をお聞きしないと,裁判所が離婚を認めるかどうか判断しにくいのですが,上にも書いたところからもおわかりのとおり,基本的には浮気した者からの離婚請求は難しいと考えて下さい。
親権者の決定基準
1 どちらが親権者になる方が,子供の福祉に叶うのか。
私の経験からすると,よほどの理由がない限り母とされるようです。子供が母と一緒に暮らしていれば99%は母が親権者になります。日本では母の元で育てた方が子はよく育つという観念があるようです。
それでは子供を置いて来た場合はどうでしょう。
その場合裁判長に、母に暮らした方が子どもに良いと思わせる事情、母の日常が子供の福祉にとってよいと思わせる事情を主張することが大事です。
2 親の経済状態
要するに、経済力はかならずしも関係ありません。相手より裕福である必要はなく(自分の方が資力があって子供の幸せに資するとの主張が父親からされることがママあります),定職に就いていて,母(父)子の生活が確保できる程度に収入があれば大丈夫です。その場合,父(母)親が支払う養育費も考慮されます。つまり相手方の養育費の負担でまかなえるケースもあるのです。
3 子どもの年齢との関係
① 0~10歳 母親が親権者になるケースが圧倒的です。
② 中学生 子どもの意思も尊重します。
③ 高校生以上 子どもの意思を尊重します。
4 環境の良さ・継続性
これまでの環境に問題がなかったか,環境を変えても子どもが適応できるか。
5 父に親権が行く場合
父親に親権が行く例外的ケースは,母が浮気をしている,母が子供を置いて出て行った, 母がだらしなくて子供の面倒を見ない等の場合です。
6 親権は取れないのに養育費は支払わないといけないのかと不満を述べる父親がいます。
しかし夫婦の問題と親子の問題とは分けて考えなければいけません。離婚しても親は子供が成人するまでは(原則)扶養する責任があるのです。この点は面接交渉権の保障で調整されます。親権は取れないが子供には会えるというわけです。しかし養育費の支払いを怠っていると相手から面接交渉を拒否されることがあります。
以下の基準(1~4)を総合的に考慮しますが,母が親権者になるケースが圧倒的に多いです。
1 どちらが親権者になる方が,子供の福祉に叶うのか。
私の経験からすると,よほどの理由がない限り母とされるようです。
日本では母の元で育てた方が子はよく育つという観念があるようです。
2 親の経済状態
相手より裕福である必要はなく(自分の方が資力があって子供の幸せに資するとの主張が父親からされることがママあります)定職に就いていて,母(父)子の生活が確保できる程度に収入があれば,大丈夫です。その場合,父(母)親が支払う養育費も考慮されます。
3 子どもの年齢との関係
① 0~10歳 母親が親権者になるケースが圧倒的です。
②中学生 子どもの意思も尊重します。
③高校生以上 子どもの意思を尊重します。
4 環境の良さ・継続性
これまでの環境に問題がなかったか,環境を変えても子どもが適応できるか。
5 父に親権が行く場合
父親に親権が行く例外的ケースは,母が浮気をしている,母が子供を置いて出て行った,母がだらしなくて子供の面倒を見ない等の場合です。
6 親権は取れないのに養育費は支払わないといけないのかと不満を述べる父親がいます。
しかし夫婦の問題と親子の問題とは分けて考えなければいけません。離婚しても親は子供が成人するまでは(原則)扶養する責任があるのです。この点は面接交渉権の保障で調整されます。親権は取れないが子供には会えるというわけです。しかし養育費の支払いを怠っていると相手から面接交渉を拒否されることがあります。
財産分与
財産分与の対象は次の通りです。
1 自宅などの不動産 名義は問いませんが,結婚後に取得したものに限りますし,親からもらったものも対象になりません。何れも夫婦が協力して得た財産ではないからです。住宅ローンの残はマイナス財産として差し引かれます。
2 預貯金 婚姻中に作ったものなら名義を問いません。へそくりも対象になるでしょう。
3 退職金 将来取得されるものも含めて清算の対象になります。
しかしもらえる蓋然性が高くないと対象から外されます。
4 年金 対象は厚生年金と共済年金。おおむね1/2が分割の対象になります。
申立は裁判所に定型的な申立書類がありますので,それほど難しくはありません。
5 車などの動産 対象になります。自動車ローンについては住宅ローンと同じです。
6 借金・各種ローン 前記したようにこれらもマイナス財産として清算の対象になります。
しかし,夫婦の一方が作ったギャンブルの借金など,家族の日常共同生活に必要な債務といえないものは含まれません。
不倫と慰謝料請求
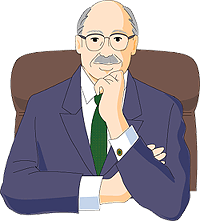
不倫をした夫婦間の慰謝料請求と,不倫の相手方に対する慰謝料請求とに分けて検討します。
1 夫婦間の慰謝料請求
民法は貞操義務を規定していませんが,貞操義務違反は離婚原因を構成し,不法行為を成立させます。
(1)夫婦の同居の期間,不倫をした者の有責性・不倫期間・資産収入・社会的地位,浮気された者の年齢・苦痛の程度,財産分与の有無,未成熟子の有無などを基準にします。
(2)金額は,①同居12年別居36年で1500万円,②同居38年別居17年で1000万円という高額の慰謝料を認めたケースもありますが,これは加害者が高収入だったからだと言って良いです。
一般的には500万円を越えることは稀です。ちょっと古いデータですが,昭和55年~平成元年に,東京地裁が慰謝料請求を認めた約200件の裁判例の平均慰謝料額は190万円でした。そのうちの8割は400万円以下でした。
まあ100万円~300万円程度が相場と言えるのではないでしょうか。
2 不倫の相手方に対する慰謝料請求
(1)金額の算定には,不倫関係を主導した者か,不倫期間,不倫相手の年齢・資力・社会的地位・不倫していた期間,夫婦関係が不倫により破綻されたか離婚となったか,不倫関係は解消しているか,不貞以前に請求者側の夫婦関係が不和になっており,そのことについて請求者には落ち度がなかったか等が,考慮されます。
(2)金額は50万円~300万円程度です。女性に対する請求よりも,不倫男性に対する請求の方が,高くなる傾向があります。それは男性が不倫の主導的役割を果たしているケースが多いこと,一般的に男性の方が資力があること,女性が非婚で子供をもうけて生活にも困っているケースがあるからだとされています。
(3)有名な判決例として,「婚姻関係がすでに破綻している場合には,不倫をしても,家庭生活の平穏を違法に侵害したことにはならない」として,慰謝料請求を否定した最高裁判所があります(最高裁判所平成8年3月26日の判決)。つまり夫婦関係が破綻していれば,浮気をしても許されるのだと言わんばかりの判決です。
ここでは「婚姻関係が破綻しているか」どうかが焦点となります。婚姻関係が破綻したと言えるためには,少なくとも相当な期間,別居していたことが必要だと解されています。ところが,この裁判例は,別居して3ヶ月目には早くも不倫を始めており,果たして別居期間3ヶ月で夫婦関係が破綻していると言えるかは疑問との批判があります。
そういうわけで,ここを読まれた方は,最高裁判所の判決を自分に都合良く鵜呑みにされないようお気を付け下さい。
離婚-目次
離婚の基礎知識 1
弁護士をつけた方がいい場合
離婚事件の最重要ポイント
最近の離婚の傾向
離婚の基礎知識 2
調停委員とは
離婚原因-性格の不一致・別居
離婚事件を得意とする弁護士
離婚の基礎知識 3
養育費・婚姻費用
調停手続きのやり方
面接交渉とは
離婚の基礎知識 4
有責配偶者からの離婚請求
親権者の決定基準
財産分与
不倫と慰謝料請求
学資保険と養育費
示談交渉・調停・本裁判の関係
離婚の基礎知識 6
離婚に関する男女感
子供の引渡し
離婚の基礎知識 7
離婚原因-概説
養育費-各論
離婚の基礎知識 8
養育費・婚姻費用に関するQ&A集
離婚の基礎知識 9
協議離婚・調停・裁判
婚姻費用と住宅ローン
面会交流その2
離婚の基礎知識 10
性格の不一致
破綻後の不倫と慰謝料
別居したら、鍵を変えられてしまった。
面会交流させないと離婚しないと言う夫
受付時間☎054-295-9766
am9.30-pm6.00(月曜-金曜)
相談受付はお電話で
伊藤彰彦法律事務所
弁護士 伊藤彰彦
静岡県弁護士会
静岡市葵区大岩3丁目29-13
タウンスクエア102号室
駐車場あります
電話054-295-9766
FAX054-295-9767
場合により土曜や夜間の相談もOK
9.30-18.00 受付(月-金)
メイルでのお問い合わせ
.gr7a-itu@asahi-net.or.jp
メイル相談は受け付けていません
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
HOME 離婚 相続 交通事故 労働事件など 破産過払再生 弁護士費用 地図