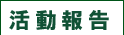2001年〜02年に2週に一度千歳民報社の「ゆのみ」に掲載されました。時間と希望をテーマに書いたものです。
心の玉手箱
人は身体に記憶を刻みます。喜びや悲しみ、香りや味と言ったものが、身体の奥隅に埋もれるように積み重なっています。それが、突然呼び起こされることがあります。偶然食べたものが、どこかお袋の味に似ていると思った瞬間、何十年も前のお袋の料理の温もりや香りが、突如として甦って来ます。それと一緒に、お袋の笑顔や食卓の情景が頭に浮かびます。更には、その時の満ち足りた安心感が胸の中に広がるのです。一つの味覚が、身体の中にしまい込まれた記憶の玉手箱を次々に開けるのです
一方で、頭に記憶されたものは意外ともろいものです。忘却という美徳に飲み込まれるのを食い止めることができません。しまいには、何かあったのかさえ分からなくなってしまうのです。しかし、その時感じた気持ちの動きは、しっかりと身体に刻み込まれるのす。香りや味覚のように。
人と人が共鳴できるのは、同じ身体があるからです。説明をしなくても、相手の悲しみや喜びが伝わり、その人の気持ちを理解することができます。小さな子どもが目の前で転んだりすると、胸が締まり痛みさえ感じます。共鳴し感じることは、知性で理解することにも増して、心豊かです。
サン・テグジュベリの星の王子様は、「肝心なことは、目には見えないんだよ」と言いました。私たちには、互いに共通する目に見えないものが沢山あります。それは、積み重なった時間や夢、希望でしょうか。その「肝心なもの」を隠し味に、一服の香りを届ける「ゆのみ」になればと書き綴りました。その香りが、皆さまの心の奥底の玉手箱に届けば何よりです。
間違いも楽し
私たちが、結婚25年の記念に冬のラスベガスを選んだのは、去年のことだった。
そこでは、ホテルにも街の中にも時計がない。そう言えば、時計屋も見当らなかった。これは、時間を忘れるひと時を演出する、街の人たちのサービスなのだと思った。時を忘れさせる仕組みはさらに続く。
ホテルの部屋にはテレビもなく、娯楽の要素が全くない。客は退屈してカジノへ降りて行くしかないのである。フロントにもレストランにも、どこへ行くにも必ずカジノを通る構造になっている。そして、夜を徹してゲームに興ずるのである。
私たちは、安着にビールでもとホテルのレストランに入った。注文の品が運ばれる度に、ウエートレスが「エンジョイ!」と笑顔で挨拶をする。このことばの不思議な説得力に、妻と私は思わず顔を見合わせてしまった。なかなかいい響きである。この一言で食事がおいしくなる。私たちは、時を失った時間を楽しんだ。
人生を楽しむなどと言う軟派な遊び心を排除したような時代を生きた私たち。その25年の人生は存外に重たい。その節目の年に、遊びに徹する人工都市を選んだのは、ささやかな抵抗心からだった。そして、ラスベガスを発つ日、金婚式の日まで人生を思いっきり楽しもう、と乾杯をした。心からエンジョイと。
無事帰国をし、日常の生活に戻った私たちは、とんでもない間違いに気がついた。銀婚記念にはまだ一年早かったのである。
村長ありき
十数年前の春まだ遠い2月のことだった。恵庭市役所の仲間6人で、かつて冬には豪雪で医者にもかかれなかったという岩手県の沢内村に、あえて最も雪の多い時期を選んで、意気揚々と乗り込んだ。
我が国の、保健医療のシンボルである村立沢内病院の横に建てられた故深沢晟雄村長の胸像の前で記念写真を撮ろうと、話はいよいよ盛り上がっていたが、村長は雪の中に埋もれて、近寄ることさえできなかった。ここで、早くも我々が想像する以上の厳しさを知らされた。
村役場の若手職員との懇談を楽しみに、村の酒屋の二階に泊めてもらった。その夜の役場職員の心から歓迎、杯と話を交わすごとに彼らの自信に満ちた誇りが眩しく感じられた。沢内村は、わが国の老人乳児無料診療制度の発祥の地である。それまで沢内村は、奥羽山脈の山ひだの無医村だった。
昭和30年代の初め、村長に就任した深沢は、村の予算の約半分をはたいて米軍の払い下のブルドーザーを購入した。中古のブルは故障が多く、村民からも議会からも「かまど返しのブルドーザー村長」と非難されたという。それでも深沢は、2台目の購入を決意した。病人を隣村の病院に運ぶための、命の道を確保するためだ。深沢の強い意志と勇気にいたく感動した。住民の命を守る村長の挑戦である。
今年の春再びこの地を訪れ、遂に深沢晟雄の前で写真を撮ることができた。若いころに感じた真摯な感動が、今も私の中に脈打っていた。恵庭が夢を発信するまちであり続けるために、私は今何をすべきなのだろうか。自問する私に、深沢晟雄はほほ笑んだ。
遙か大地
学生時代に、中学校の障害児学級の教育実習で出会った一人の男の子のことが、今でも妙に記憶に残っている。それは、放浪癖の子だった。
ある日、担任の先生がその子の様子かおかしいのに気がついて、下校する後をついて行くと、そこは札幌駅だったという。改札を通過するチャンスを探り始めたのだろうか、名前を呼んでも全く反応しないのだ。手を握っても目はうつろで、心はどこかに飛んでいたのだろう。その時は何とか家まで連れて帰ったが、翌日彼は家からまっすぐ旅立った。
一度旅立つと短くて2週間、長いときには2ヵ月ぐらい全国をまわっているのである。それも、毎年決まって2度の定期便である。そして周囲の心配をよそに、放浪が終わると、何事もなかったかのように家に帰り、翌朝には教室の自分の席に座っているのだという。
人間には、農耕民旅と狩猟民族の2つの血が混ざっているのだという話を聞いたことがある。前者は安住の地を求め、後者は新たな大地を目指すエネルギーになるのだ。われわれにはその両力の血が混ざっていて、その割合や濃さがその人の生きるスタイルに影響を与えているというのだ。
中東のある国では、遊牧民に対し、住宅と食事を無料で提供する定住政策を行った。しかし何力月もたたない内に、彼らは水も電気もない大地に戻ってしまったということである。遊牧民には、農耕民族とは相容れない大地への衝動かあるのだろうか。
あの子に会った時から、私の内にあった遊牧の血が騒ぎだしたような気がする。私もいつか遙か大地を旅し、満ち足りた思いで家に帰り、何もなかったかのように仕事に戻ることかできたらと考えると、不思議に楽しくなる。
いろり
青森県で高校の教師をしている学生時代の先輩の家を訪ねた時のことである。新築したばかりの居間の床に、取り外しのできそうな四角い仕切りが付いていた。床下の点検口にしては大きすぎるし、それも居間の中央付近にである。何だろう、と不思議に思った。
「無理を言って作ってもらったのよ」奥さんがうれしそうに仕切りのふたを間けると、囲炉裏が顔を出した。早速、座布団を周りに並べた。奥さんが慣れた手つきで炭を入れた。火を囲むと、何とも言えない暖かい落ち着いた雰囲気に包まれ、自然と笑みがこぼれた。
灰を掃きながら、「子どものころは、こうやって夜を過ごしたものよ」と、奥さんか懐かしそうに話してくれた。「これを見ると、みんな離れなくなるんだよ」と、先輩も嬉しそうである。
昔使っていた古い囲炉裏はとっくに壊してしまったので、今使っている灰は火鉢から移したものだそうだ。おじいちゃんやおばあちゃんの、そして目分たちの、何年も何十年もの思い出が積み重なった、大切な灰なのである。手入れをして、きれいな灰にするのだという。「火を見ていると、何だか気持ちか落ち着くのよね」と言う奥さんのことばが印象的だった。
囲炉裏を、居間の中央に本格的なサイズで作りたかった東北生まれ東北育ちの奥さんと、道産子の先輩の主張がほど良く調和していた。中央ではなく中央付近に、大きさは四人で向かい合って少し余裕がある程度。鉄瓶が威張って湯気を出し始めた。
火を囲んで人と人が語り合う静かで穏やかな時の流れに、すっかり魅せられて家路についた。先輩の笑顔と、顔を照らす囲炉裏の火のぬくもりが重なって、私の心の中で日本の心のふるさと東北の火が、今もチロチロと燃えている。
田舎倶楽部
おいしい物を食べることは、幸せである。昔からわれわれには、初物を大切にする風習があったし、旬を楽しむ文化があった。そして何よりも、食は生活の大切な一部だった。しかし今は、何でもいつでも手に入り便利になった代わりに、台所から季節が無くなったように思える。食に使う時間を惜しむような、慌ただしい生活を送っている人もいる。"食は文化なり"が心に響く。
私たちの周りには、北海道の気候が育てるおいしい野菜が沢山ある。カボチャもイモもトウキビも、本州では味わえない味を出す。ところがこの野菜たち、いい物は東京や大阪に送られ、われわれの口に入るのは、一度札幌の市場に送られた物だというではないか。地元では、いい野菜が食べられないばかりか、新鮮な物も口に入らないのである。
スーパーに並ぶ野菜を見ると、地元にこだわる意味なんて無いように思えてしまう。だが、地元の野菜はそこで暮らす人と同じ水、同じ空気で育っている。獲れた地で食べる野菜は、ミュンヘンで飲むビールが飛び切りおいしいように、きっとうまいに違いない。
おいしい物を食べたいという"志"を同じくする消費者が集まって、農家に契約栽培をしてもらうことになった。これが田舎倶楽部の始まりである。食べたい野菜を決め、農薬は最低限に、などと栽培法も約束をして契約をするのである。
草取りや収穫は、田舎倶楽部の交流の場である。収穫をすると食べ頃が分かるようになり、野菜売り場でも目利きが出来るようになってきた。いつもの年より天候が気になるのも不思議だ。食卓の野菜に、「○○さんの」と農家の名前が付いてくる。そして、わが家に旬が戻ってきた。
田舎倶楽部の試みが、わがまち恵庭の農業に一石を投じることができたらと思う。
キリンの花屋さん
待つということは、自分の願っていることが起こるであろうと思って時間を過ごすことであるという。なかなか含みのある言葉である。私たちは時間を彩りながら生活をしているのであろうか。たれもが時や人を待ち、子どもの成長を楽しみにし、そして自己実現を願っているのである。待つこと、それは時間で編んだ夢なのかもしれない。
娘がまだ幼かったころ「キリンの花屋さん」になりたいと言っていたのを思い出す。この子なら本当になれるかもしれないと、無責任にも願ったりしたものだ。仕事の帰りに、ふと花屋を覗いたり、店先の動物の縫いぐるみが気になったりと、思いのほか豊かな時間を味わったことが、懐かしく思い出される。
冷夏と言われた今年の夏も、何度か庭で焼き肉を楽しむことかできた。ありがたいもので、家族も半分あきれながら付き合ってくれる。そんな家族のために、今年は新しい料理に挑戦した。鶏一羽を塩で包み、フライパンで焼く塩釜蒸しと、ダッチオーブンでつくるローストビーフである。どちらも時間がいいだけかかるのか特徴だ。かぐわしい香りを楽しみながら、ワインとビールで出来上がりを待つのである。時間を味に染み込ませるという贅沢な趣向だ。
私の挑戦は、どちらも多少時間をかけ過ぎたようである。時間で編んだ夢は、無残な焦げになってしまったのだ。持つにも限度があるということか。娘は笑いながら、焦げていないところを試食してくれた。もしかしたら、この子はとっくにキリンの花屋さんになっていたのではないだろうかと思い、娘の笑顔を見上げた。
怠け者と愚か者
スペインには、「明日できることを今日するな」ということわざがある。何とおおらかな国だろう。日本なら、「今日できることは明日に延ばすな」と言われるところだ。国が違えばこうも違うものか、面白いものだ。しかしスペインでは、何もするな、と言っているのではない。自分の人生の最も大切なことを今日しなさい、ということばが隠されていることに最近気が付いた。
「ピレネーを越えるとそこはアフリカ」ということばがある。スペインはヨーロッパにあってアフリカと呼ばれる土地柄なのだ。地肌を出した大地は赤茶けて、荒涼としている。そんなスペインで、工業の進んだ北のバスクの人々は、南のアンダルシアの怠け者のおかげてヨーロッパの仲間入りかできない、と苦言を言う。アンダルシアはバスクに対して、人生の意味を知らない愚か者、と負けていない。生きる姿と価値観がこうも多様化するものかと思うと、楽しくなる。
私がまだ子どもだったころ、末は博士か大臣か、ということばが流行った。もちろんみんなが博士や大臣になれるはずがない。それなのに幸か不幸か、多くの子どもたちはそれを目指し、それなりの努力をしたのである。今思えば多少滑稽な気がする。将来に対する希望や不安が、そうさせたのかもしれない。
日本人はだれもが、目を覚ますことを疑わずに眠りにつく。ところがスペイン人は、そう考えないらしい。だからこそ、今日に命を燃やすのだという。
ところで、自分にとって今日しなければならない人切なことって何だろう。まずは、安ワインをやりながらスペインの地図でも開いて、じっくりそれを考えるとしよう。
逆流
世界の七不思議の一つに数えられ、毎年決まった時期に大逆流をする大河がある。アマゾンと黄河である。その日には、同十万という人が堤防に集まる。にわかに空か暗くなったかと思うと、風を巻き起こし、轟音とともに津波のように押し寄せる激流の映像の衝撃は忘れられない。世界は何と広いことか。それか地の果てだろうが、いつか自分の目で確かめに行きたいと、密かに思った。
もう20年にもなるだろうか。大雨で、千歳川が逆流して大水害になったことがある。川は上流から下流に流れるものと決まっている。それが下から上に流れたのだ。その話を聞いた時、一瞬黄河の逆流のシーンが頭をよぎり、大げさなことを言うものだと思った、しかし、それを見た人の話を聞くうちに、逆流は紛れもない事実であり、しかも想像以上に強烈なものだったことを知った。
私が子どものころの石狩川は、360kmもの大河だった。それがいつの間にか100kmも短くなり、降った雨が短時間で下流に集まる構造になっていたのだ。そして緩やかな勾配の千歳川より、一気に水かさが増した石狩川の水位の方が高くなって、あの逆流が始まった。上流と下流から挟み撃ちになって行き場を失った水が、恵庭で溢れ出して大水害になったのだ。
今年も、台風15号が北海道を襲い、多くの雨を降らせていった。洪水警報の中、防災用の土嚢づくりに多くの人が集まった。スコップで袋に土を入れる単純な作業だが、時間と戦う過酷なものだ。それでも、人海作戦で作れる量は知れている。小さな川でさえ必要な量は莫大だ。まして、千歳川のような大きな川が相手なら、お手上げである。もう恵庭の川で逆流は見たくない。土嚢作りの後遺症を揉みほぐしながらそう思った。
凱旋
"志しを果たして、いつの日にか帰らん"童謡ふるさとの一節である。何とも切ない短調の旋律が心に響く。ふるさとへの強い衝動は、心を動かすエネルギーになるのなろうか。石川啄木が心の拠り所にしたであろう、ふるさとの風景か脳裏に浮かぶ。しかし近ごろは、このようこことばが、古くさく陳腐にさえ感じられるのはどうしたことだろう。
ふるさとに錦を飾ると言えば、凱旋である。北海道では、大鵬、北の海、千代の富士などの大横綱の名前が次々に頭に浮かぶ。相撲の取り組みの時、毎回耳にする「北海道出身」の紹介は、いやおうなしに地域の声援をかき立てた。地本力士が優勝戦線でしのぎを削っていようものなら、それは大変な騒ぎになった。まして、毎場所北海道出身の横綱が頑張っているとなれば、道民がヒートアップする当時の様は想像に余りある。そして、初優勝、横綱昇進となれば、ふるさとへの凱旋がつきものだった。北海道の片隅で行われた町をあげての大歓迎が、全国に報道された。そして北海道中が熱くなった。
しかしここしばらく、心動く凱旋を知らない。北海道の不況は深刻であり、就職難と失業率は他県に比べても一層深刻である。若者にも年配者にとっても先が見えない。いかんともし難い時代になってしまった。北海道が勇気づく明るいニュースがほしい。
今年のプロ野球のセリーグは、ヤクルトの優勝が濃厚である。監督の若松さんの出身地留萌市では、さまざまな趣向で歓迎の催しが計画されているという話である。北海道か生んだ小さな大巨人の凱旋が実現しそうだ。北海道中が元気になればと思う。ヤクルトファンではないが、その日には留萌にいて、その空気に浸ってみたいと思う。
車窓にて
ゆのみの執筆を始めた時に、一年間という長丁場をどうやって乗り切れるものかと心配だった。そこで何人かの友人に相談をして、いろいろ知恵を授かった。友人の一人がこう言った。「ゆのみを読んでいると、身を削って書くタイプと、身をさらして書くタイプの二通りがある。猪さんはどっちかな」と。これは大変なことになった、と思った。どちらにしても辛い話である。妙に恥ずかしいと感じたのは、身をさらしている証拠なのだろうか。
それにしても、自分の文字が活字になるのは不思議な気持ちだ。顔も知らない人や、いつも会っている人たちと、紙面を通して時間を共有する緊張感からであろうか。字面がちょっと気取ってみたり、すましてみたり、と鏡の前に立っている娘のようになる。それを楽しみながらのひと時である。
私はいつか、「車窓にて」というテーマで書いてみたいと思っている。大好きな自由気ままの汽車の旅ができればいい。その一番の贅沢をしている時に、湯飲みを書くことを想像するだけで楽しくなってくる。しかし残念なことに、わが国の鉄道はそのような旅行が向かなくなってきた。ローカル線は脆弱化し、フリー切符も種類が少なく、しかも目が飛び出るほど高い。飛行機の方がはるかに安く、おまけにホテルまで付いている。何がなんでも、旅に時間を惜しめと言うのだろうか。
欧州には、17カ国1ヵ月問一等特急乗り放題で、数万円の切符がある。気の遠くなるようなシベリア鉄道横断も極めて安価である。体力と気力があるうちに、ぜひ試してみたい。何年後になるか分からないか、その時に、一回分余計に身をさらすスペースをもらえたら、と思った。
小柄な男と大柄な男
もう随分と昔のことだが、今でも思い出す光景がある。マドリッドの駅でパリに向かう寝台列車の中のことだった。まだ若くてお金もなかった私たちは、一番安い簡易寝台の切符を手に入れた。早速汽車に乗り込み、6人部屋の窓側の席を取ると、問もなくして労働者風の二人の男が入ってきた。ひと言挨拶を交わした。先に入ってきた男は小柄で、ギターを肩に怪しそうな感じだ。もう一人は少し大柄だが、こわそうな雰囲気だ。さらにもう二人、男が入ってきて遂に6人になった。どうも雰囲気が良くない。買う切符を間違ってしまったかと後悔した。
小柄な男は、窓の席に座りたいと言ってきた。もちろん、喜んで席を譲った。男はずうっと窓の外を見ていた。その視線の先にそっと目をやると、ホームの柱の陰に4人の子どもを連れた女の姿があるではないか。やがて出発の時間が近づくと男は走るようにデッキに行った。女と子どもも柱の陰から出てきて大げさに別れを惜しんだ。何のために今まで柱に隠れていたのか、理解に苦しんだ。そして、女の名前がマリアだと言うことを、間もなくホーム中の人が知ることになった。小柄な男は、張り裂けんばかりの声で、妻の名を呼んだのだ。
その夜、小柄な男の奥さんが作った塩味の効いたハムサンドをおかずに、革袋に入ったワインをご馳走になった。ギターの音色もなかなかで、小さな部屋は酒場のように盛り上がった。小柄な男には、ホームにいた4人の子どもの他に、乳飲み子が2人いるという。これから、大柄な男と2人でドイツに出稼ぎに行くのだと言う。ワインが回って、いい気持ちなった。
夜も更けて、出入国カードを書いていると、大柄な男が自分のカードを持って来た。字が書けなかったのだ。小柄な男に書いてもらえばと目をやると、自分のを書き終えて窓を見ていた。そして、時折涙を拭いていた。
2002年の運試し
2002年の扉は、ユーローの到来とともに聞かれた。ドル以外の国際通貨が流通する複数通貨時代の幕開けである。欧州人が突きつけたアメリカへの疑問符であろうか。これか3億の民の共同作業であることもさることながら、何より犬猿の仲のフランスとドイツが手を握ったことは驚きだ。一方で中世以来、大陸の様子見をしてきたイギリスは、今回も静観を決め込んでいる。「歴史は繰り返す」であろうか。さあ、役者か揃った。一生に一度の歴史実験の舞台を肴に酒が飲める。贅沢な年の幕が上がった。
一生に一度と言えば、ワールドカップサッカーが目前に迫ってきた。国連加盟国数を超える国と地域が参釦。オリンピックを凌ぐ世界最大のスポーツの祭典だ。選手は、国の歴史と文化を背負って戦い、とことんナショナリティを刺激する。世代を越えて語り継がれる逸話が生まれるのも、この大会の特徴である。もしかすると、それが北海道の地で息吹くかもしれないと思うと、胸が躍る。
とりわけ、札幌ドーム第三戦のアルゼンチン・イングランド戦は見ものだ。熱狂的なサポーターの応援合戦、フーリガンと日本の警備力のせめぎ合い、そしてゲームである。20年前に、フォークランド諸島の領有権を巡って戦争をした国同士だ。その時はアルゼンチンの実質的な降伏で停戦となったが、領有権問題は未解決のままだ。まさに、国と国の戦いになりそうだ。
もっと目の前のこととなれば、今日の運試しの「金杯」であろうか。競馬ファンでなくても、知る人ぞ知るレースである。毎年1月5日に行われる年初めのお年玉レースだ。馬券を買った人も買わなかった人も、勝負に勝った人も負けた人も、それぞれに新しい年が良い年でありますように。乾杯。
2つのおみくじ
一月も半ばを過ぎると、新しい年を迎えた清々しさと、また一年か過ぎてしまったのかという感慨か交錯して、不思議な気持ちになる。加えて、一年一年かどんどん早くなって、何か急がされているような気にもなる。気のせいなどではなく、本当に早くなっているのに違いない。そのくせ、もう去年と一昨年の記憶か一緒になって頭の中で渦巻いている。これは「過去を振り返らず明日に向かって生きれば吉」のおみくじであろうか。
先日、ニュース番組を見ていて思わぬ得をした気持ちになった。それは、サッカー日本代表のトルシエ監督のことばだった。サッカー協会幹部との軋轢と国民性や習慣の違いなどに苦しみ、解任の記事がスポーツ紙の一面を飾った時のことだった。意外にも、その時トルシエを守ったのは、日本語が話せないことだったというのである。「日本語が分からないことが、厚い壁になって私を守ってくれました」と述懐している。
言うまでもなく、人にはそれぞれに様々な能力がある。その中に「できない」という能力があることを教えてくれた人のことを思い出した。できないことをするためには、どうしても人の助けが必要になる。自分だけではどうしようもないから、人を動かし、人とつながる力が生まれてくる。だから、できないことが大切な能力なのである。そしてそれは、できることからは決して生まれることのない、最も人間らしい可能性なのである。
できないことに守られ、できないことで大切な人と出会い、素敵な人生が送れたとしたら、私たちは十分過ぎるほどに豊かである。これを、「自分らしく生きれば吉」の今年二本目のおみくじにしよう。
百人の村
日本語は不思議だと思う。表現の豊さと奥行きは、他の言語に類を見ないのではないだろうか。行間にさえ意味がある。文字そのものに意味があるのも面白い。日本人の会話に身振りや表情が少ないのは、ことば自体が豊かな表現力を持ってているからだろうか。
短い文面に様々な感情を盛り込むことができるのもまた、日本語の特徴だと思う。「一筆啓上火の用心」で始まる日本一短い手紙や、短歌や俳句では、一つひとつの語や文字に様々な情景が封じ込められ、読み返す毎にそのエキスが溶け出してくる。
短い文章といえば、藤村操の「巌頭の感」を思い起こす。弱冠十六歳の一高校生の早熟の悲劇から、今年で丁度百年になる。藤村が日光華厳の滝の大樹を削り、愚書で残した遺書の題名がそれである。地万の警察署では、自殺の原因を哲学のためとし、新聞は巌頭の感の全文を報道した。それから4年間で、40人の未遂者を含め約200人が華厳滝で自殺を図るという、社会現象的な連鎖反応の発端にもなった。だか今になって思えば、藤村が本当に伝えたかったのは、厭世でなく希望だったのではないだろか、という気がする。
近頃、新聞やテレビで「白人の村」のことをよく耳にする。もとは、インターネットでアメリカから広がった小さなメッセージだった。去年の暮れには日本語の訳本が出て、それか数週間でベストセラーに駆け上がった。
「世界がもし百人の村だったら」で始まる何の変哲もない統計数字で終始するこの短いメッセージが、何故か読む人に自信や責任感、使命感のようなものを呼び起こした。この村、すなわち世界のために自分にできる何かがあることを感じさせ、不思議な余韻を残すのである。行間に希望を読み取るのは、ひとり日本人だけではなかった。
チケット恋しや
いよいよ、アジア初のサッカーW杯の開催が近づいてきた。おそらく世界の関心は、東京オリンピックを凌ぐとも劣らないだろう。開催そのものが国民の誇りとなる大会とも言われている。そして我が北海道、札幌ドームで三試合が行われるのも嬉しい。座席数からして、12万人を超える人たちが、その歴史の舞台に立ち会うことができる計算である。
その観戦チケットを取るために、通常の考え得る手段をほとんど試みた。結構力のいる努力だったにも関わらず結局チケットは手に入らなかった。多分私たちにとって、日本で次のチャンスはもうないだろう。しかし、プレミアの付いたチケットを買うのは後ろめたいし、不正義である。胸を張って、テレビ観戦と決めた。
丁度そのような時に、栗山で合宿内定のメキシコが「最終調整のための親善試合をコンサドーレとドームで希望」の報道があった。これは有り難い。世界の強豪メキシコと北海道のプロチームか、W杯の香りいっぱいで戦うなんて夢のようだ。このチケットだけは何があっても手に入れたい、と心に決めた。
しかし何と、そのキャンプが福井県に持って行かれてしまった。栗山町が、一億円を越える仲介料に名を借りた裏金を拒んだことが原因らしい。袖の下でメキシコのキャンプが実現したところで、何の意味があるだろうか。悔しいが、栗山町の正義の英断を信ずる。スポーツ文化を花咲かせ、多くの了ども達の夢を育むことで、この勇気を後世に残る真の財産にしてほしいと思う。誇り高いまちに、心から拍手を送りたい。
そんな話で盛り上がっていた時である。友人がささやいた。「韓国で開催される試合のチケットが、まだ残っているらしいよ」
荷物になる
「便利なものは荷物になる」、面白いことを言うものだ。小柄だが屈強な、ドイツ人の愛車に書かれていた。彼は30年以上もの間、自転車で世界中を旅していた。男の名はハインツ。
彼と会ったのは、数年前の夏の札幌駅だった。彼の愛車は25キロの頑丈な特注自転車で、40〜50キロの荷物を振り分けた上に、一冊500円の冊子が10キロ以上も場所を取っていた。それを売って旅を続けているのだ。
その冊子を肴に、友人と近くの居酒屋でビールをやることに決めた。ジョッキを傾けながら冊子に目をやると、間もなく40万キロを走破しようとしていること、何度も危険な目や事故にあっていることが分かった。最後のページには、交通事故で顔や頭を縫った痕の痛々しいハインツの写真があった。語りかけるような眼差しが目に刺さった。何かに心を揺さぶられたよう不思議な気持ちになった。もう少し、ハインツや旅の話を聞きたいと思った。
ハインツが冊子を売っていたところに戻ってみると、そこに彼はいた。冊子を全部売ったら、ウラジオストック経由でベラルーシのミンクスに行くのだと目を輝かせた。そこに、彼女がいるのだ。彼女はとても美人で、一人娘と二人で暮らしている。ハインツはテントも持たず、荷物のほとんどは、スライドや日記や地図だ。便利な物を全て捨てて、旅の記録と思い出を満載にした愛車でミンクスを目指した。
あのハインツは、今どうしているだろうか。もう60歳を少し越えたころだ。旅には家族も荷物になると言っていたハインツ。彼のことだから、丸ごと全部愛車に積み込んでいるかもない。それとも、自転車が荷物になってはいないだろうか。
火を使う魔法使い
人間は、百年も生きれば大変な長寿である。ところが、長寿巨大木で名高いセコイヤは、数千年もの長生きである。この大木は毎年々々種を落とすものの、日陰や草の生えているところでは芽を出すことがない。それなのに種を蒔き続けている。せいぜい、一万年に二本か三本の大木が育てば十分なのだろう。
セコイアは、成長のためのあらゆる条件が全て整った時でなければ、命を引き継ぐことをしない。周りに光を遮る木がなく、土壌は栄養に満ちて、その栄養を取り合う草もない、という絶好の条件でなければ芽を吹かない。森の中では余りにも過酷と言うか、あり得ないと思われるその日が、千年に一度の確率で森にやってくる。山火事だ。
森が火に飲み込まれ、焼け跡には肥料となる木や草の灰が積もり、地面には光が差し込み、その時が準備される。セコイヤは、山火事でも生き残れる太い幹で、この日を待っていた。千年に一度の、特別な種を地上に落とすために。山火事がないと引き継がれることのない命。奇跡を信じて立ち続けるセコイヤは、この一瞬で、気の遠くなる歳月の意味を物語る。
人も千年の奇跡を背負って、今を生きているのだろうか。どうかすると、無駄や無意味に思える今の積み重ねも、それが意味づけられる時に、光りを放ち色彩に包まれる。人の命を意味づけ、物語るのは私たち。種を携えて、奇跡を準備しているのは私たち。そして、種を蒔くのは私たち。
セコイヤの奇跡を演出するのは、もしかすると火を使う魔法使い。それは私たち自身ではないだろうか。