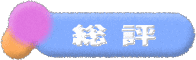 |
| 佐藤 文夫 |
| 今年で三七回を迎える詩人会議の新人賞は、その第二次選考に選ばれた八五名+四名(評論部門)を年代別にみてみると、十代・十三人、二十代・九人、三十代・十六人、四十代・十五人、五十代・十六人、六十代・八人、七十代・五人、(年代不詳・四名)となっている。なおこの第一次選考の作業には、選考委員のほかに青井耿子、青木みつお、小森香子、樋野修、南浜伊作の五名が加わった。 ところで、この「新人賞」の「新人」とはなにか。毎年、選考の場で問題となるところだが、辞書をみると「新顔・新たに加入した人」のほかに「新進・新しくその社会に現れた人」の意が書かれている。すなわち「新顔」も「新進」も、一切年齢には関係がない。今回応募された十代から七十代にいたる方々、一人一人の原稿からたちのぼる詩的熱気は、まさしく「新人賞」のみがもつ、世代に共通した熱気であった。 さて、その寄せられた多くの作品を、私なりに大別すると、テーマは別として日常の生活からえられた、詩的な感動なり感覚を、そのまま紙上に書き写したもの。さらにその対象への単なる描写にとどまらず、執拗に推敲をかさねて書かれたもの、の二つであった。 だが問題は、その感動と詩的感覚(と作者が自負するもの)とが、いかに表現され、新人賞にふさわしく、新鮮で清新なものであったかどうかだろう。そして、それが一篇の詩として、読者の胸にどう届いたか、どのように響いたかであろう。 かくして、選考は、三次、四次、五次と選考委員相互の討論と採点を経てすすみ、六次選考には入選・佳作者と立石百代子、水田佳の六名がのこされた。また評論部門では「詩人・河上肇」の宮下隆二と「十五歳のアリアー夭逝の詩人 杉尾優衣」中原文也の二名がのこされた。さらに最終選考の結果、詩部門は入選・木目夏、佳作・宍戸ひろゆき、いがらしのりこ、三田麻里。評論部門は入選はなく、佳作・宮下隆二に決定した。 入選された木目夏の「植民地的息」は、夜、台所で家計のやりくりに四苦八苦し、思案する主婦の溜息吐息を作品化したもので「ライオン」「ポイントカード」などによるその表現のユニークさが評価された。日常の暮らしのなかに充満する溜息吐息を、カロリーやお金だけでなく、人の怒りに変換していこうという発想がよかった。 佳作・第一席の宍戸ひろゆきの「凍土を掘る」にみる生活実感をこめた重厚な反戦平和への思いも、私は切実にうけとめた。いがらしのりこの明るい恬淡とした叙情。三田麻里の生活をユニークな視点からとらえた自在な発想も評価された。評論部門・佳作の宮下隆二は、河上肇という不世出の経済学者の、その知られざる詩人としての一面をあくまでも今日的立場で、多方面にわたって探究している。その視点の確かさと、真摯な研究内容が評価されたが、今一歩、惜しくも入選にはいたらなかった |