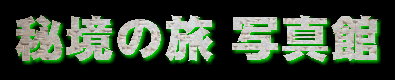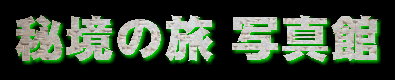旅ノート イラン西部の旅(1999年9月23日〜10月4日)
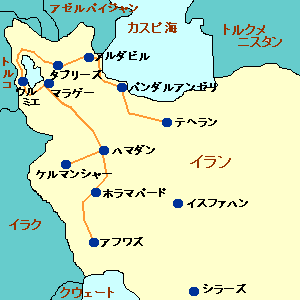 |
|
◎旅の日程◎ |
| 1.成田 〜 テヘラン |
| 2.テヘラン〜カズビン〜バンダルアンゼリ |
| 3.バンダルアンゼリ 〜 アスタラ 〜 アルダビル 〜 タブリーズ |
| 4.タブリーズ 〜 キャンドバン村 〜 タブリーズ |
| 5.タブリーズ 〜 ウルミエ湖〜ウルミエ |
| 6.ウルミエ 〜 ハッサンルー 〜 マラゲー |
| 7.マラゲー 〜 タフティ・スレイマン 〜 ハマダン |
| 8.ハマダン 〜ケルマンシャー〜 ハマダン |
| 9.ハマダン 〜 ホラマバード |
| 10.ホラマバード 〜 スーサ 〜 チョガ・ザンビル 〜 アフワズ |
| 11.アフワズ 〜 テヘラン 〜 |
| 12.〜 成田 |
|
イラン航空
成田からイラン航空に乗るのは6年ぶりです。以前は成田のゲートの所でも手荷物の厳しいチェックがありましたが、今回はすんなり飛行機に乗れました。観光客が増えたせいでしょうか。
北京に着いて大勢の日本人が降り、機内はイラン人でいっぱいになりました。ここで前と同じようにアメニティセットが配られました。以前に比べてポーチが少し上等になった気がします。中身は靴下・アイマスク・歯ブラシ・靴べらなどで、なかでも靴下はイランに行ってからモスクの観光のときに重宝します。
| 2日目 (テヘラン 〜 カズビーン 〜 バンダルアンゼリ) |
カズビーン
テヘランから約150km、ザンジャン州の州都・カズビーンは、ガイドブックにも載ってないような町ですが、かつてはサファービー朝の首都だったところです。イマーム・レザーの息子であるシャーザード・フサインの廟は、タイルとガラスの装飾が美しい、いかにもサファービー朝らしい建物です。チャドルを借りて男女別に分かれた入口から中に入ると、現地の女性が話しかけてきて、「こうやって棺にキスをしてお祈りするのよ」と身振りで教えてくれました。
 |
|
 |
| シャーザード・フサインの廟 |
|
シャーザード・フサインの廟にて |
カスピ海
エルブルズ山脈を越えてカスピ海が見えてきたときには、日が沈んであたりは暗くなっていました。夕闇の海岸に行ってみると、白いまあるい月が出ていて、幻想的な雰囲気でした。昼間は海水浴場になって賑やかなようだったので、夜になってから来て、かえって良かったのかもしれません。
 |
| カスピ海と満月 |
| 3日目 (バンダルアンゼリ 〜 アスタラ 〜 アルダビル 〜 タブリーズ) |
アスタラ
カスピ海沿岸のアゼルバイジャンとの国境の町アスタラは、これといった観光名所はなく衣類などを売っているバザールを覗きました。その後少し内陸の国境地帯に行き、警備兵の監視の下、アゼルバイジャンの領土を眺めました。
アルダビル
サファービー朝の発祥の地アルダビルには、サファービー教団の祖、シェイフ・サフィーオッディーンの廟があり、町のシンボルとなっています。廟には、彼の子孫でサファービー朝の創始者、シャー・イスマイールをはじめとする一族の棺があり、ドームの外側はブルーのタイルの幾何学模様、内側も立体的で繊細な装飾が施されています。
| 4日目 (タブリーズ 〜 キャンドバン村 〜 タブリーズ) |
キャンドバン村
タブリーズから約50km南にあるキャンドバン村は、トルコのカッパドキアにようにニョキニョキとした岩が林立しています。でもカッパドキアほど広範囲に渡るのもではなく、小さなこの村の周辺だけなので近くに行くまでは気が付きませんでした。奇岩をくりぬいた家は電気も通じていますが、村の人々は家畜を飼ったり蜂蜜をつくったりして昔ながらの暮らしをしていました。
タブリーズ
13世紀のモンゴル朝時代には、東西の交易の中心として繁栄を極めたタブリーズのバザールは、現在も中東有数の規模を誇っていて、多くの買い物客で活気に満ちていました。タブリーズといえば絨毯で有名ですが、覗いたのは食料品・日用品などのバザールで、チーズやはちみつ、ドライフルーツなどが豊富にありました。
| 5日目 (タブリーズ 〜 ウルミエ湖 〜 ウルミエ) |
ウルミエ湖
今日はイラン最大の塩湖、ウルミエ湖の北側をぐるっと周りウルミエに向かいます。塩湖といっても青々とした水を湛えていて、海水浴場のような所もあります。そこに来ていたウルミエの女子大生に、ツアーメンバーのTさんが漢字を書いてみせると、それが大受けで、次から次へとサインをせがまれ大サイン大会になってしまいました。
ウルミエの町
昼過ぎにはウルミエに着き、3時までフリータイムとなりました。早速ホテルを出て「地球の歩き方」に出ていたセ・ゴンバドを目指しました。写真を見せながら道を尋ねて歩いていると、ポスター張りの作業をしていた人が、親切にも連れて行ってくれました。セ・ゴンバドは12世紀、セルジューク期に造られたお墓です。西イランの旅行では、ゴンバドというお墓をたくさん見ました。
ホテルに戻ってからモスクやバザールの見学に出かけました。ここはトルコとの国境に近く、頭にターバンを巻いてだぶだぶズボンをはいたクルド人の姿も見られました。日本人は余程珍しいのか、バザールでは視線の集中砲火にあって、「見に行った」というより「見られに行った」という気がしました。
 |
|
 |
| セ・ゴンバド |
|
ウルミエのバザールにて |
| 6日目 (ウルミエ 〜 ハッサンルー 〜 マラゲー) |
ハッサンルーの遺跡
ウルミエ湖の南にあるハッサンルーの遺跡は、紀元前1000年頃のマンナ人の都市遺跡ですが、いまだ発掘途中で詳しいことは解明されていません。遺跡は土壁の仕切りのようなものがあるだけで、あまり見栄えのするものではありません。でも遺跡の隣の小学校で生徒たちに大歓迎されるという、思いがけない嬉しい出来事がありました。
マラゲー
マラゲーもガイドブックに載っていない田舎町ですが、モンゴル朝時代の要人の墓をいくつか見学しました。モンゴル時代のものだけあって、建物の感じがサマルカンドやブハラのものに似ています。それらの墓の一つの隣に女子校があり、ちょうど下校時に行ったので、女子高生に取り囲まれてサインや握手攻めにあいました。
 |
|
 |
| 赤いドームの墓 |
|
青いドームの墓 |
| 7日目 (マラゲー 〜 タフティ・スレイマン 〜 ハマダン) |
タフティ・スレイマン遺跡
「ソロモンの玉座」という意味の遺跡ですが、現在残っているのはササン朝時代の城塞の上にイル・ハーン時代の夏の離宮が築かれたものです。あまり有名ではないので期待していなかったのですが、来てみると今までに見たことのないような不思議な遺跡だったので感動しました。
小高い丘の上にある遺跡に上がって城門を入ると、中央に真っ青な水を湛えた池があり、一個所から水がどんどん流れ出ているのです。この水は地下110mの所から湧き出ているそうです。遺跡の方もイル・ハーン時代に立て直した比較的新しいものもあるので、結構、建物らしきものが残っていました。
| 8日目 (ハマダン 〜 ケルマンシャー 〜 ハマダン) |
ビストゥーン
今日はハマダンからケルマンシャー周辺の遺跡を訪ねます。ビストゥーン山にはペルシャの王・ダレイオスの戦勝記念のレリーフが彫られていますが、これは楔型文字解明の手がかりになった重要なものです。以前ケルマンシャーに来たときに見る時間がなかったので、今度は絶対見たいと思っていたのに、あいにく修復中で足場が邪魔をして、隙間からほんの少ししか見られませんでした。
 |
|
 |
| ダレイオスの戦勝記念のレリーフ |
|
ビストゥーン山 |
ターク・イ・ブスタン
ケルマンシャー近くの岩山にあるササン朝期の彫刻で、3つある彫刻のうち2つはアーチ型の洞窟の中にあります。どの彫刻もササン朝の王とゾロアスター教のアフラ・マズダ神などが描かれていて、6〜7世紀頃つくられたものです。周りは公園になっていて野外レストランなどもあり、今回の旅行では珍しく観光地らしいところでした。
 |
|
 |
| ホスロ2世王とアフラ・マズダ神 |
|
狩りのレリーフ |
ケルマンシャーで家庭訪問
ケルマンシャーでは現地ガイドさんの親戚の家にツアー一行でお邪魔しました。通りからはそんなに大きな家には見えなかったのに、玄関を入るとペルシャ絨毯を何枚も敷いてある30畳くらいのリビングに通されました。ご主人は農業技師をされているそうで、裕福な家庭のようでした。女性は家の中ではチャドルを身に付けなくていいので、中学生の女の子は、TシャツにGパンのようなごく普通の格好をしてました。
ハマダン
紀元前2000年頃から都市として発達し、紀元前600年頃はメディア王国の首都エクバダナとして、バグダードへ続く「王の道」の重要拠点であり、その後アケメネス朝の時代には夏の都として繁栄を極めたという、歴史のある町です。エクバダナ時代のものといわれるライオン像は、摩耗してただの石のようにしか見えず、子供たちが乗っかって遊んでいました。
ガンジナーメ
ハマダン近郊にあるガンジナーメは、紀元前5世紀頃に岩山に彫られたアケメネス朝の碑文です。古代ペルシャ語・エラム語・アッカド語の3種類の楔形文字で彫られており、ダリウス1世と息子のクセルクセスについて記されたものがあります。近くには勢いよく水が落ちている滝があり、休日の金曜日だったのでピクニックに来た人達で賑わっていました。
| 10日目 (ホラマバード 〜 スーサ 〜 チョガ・ザンビル 〜 アフワズ) |
スーサ
紀元前16世紀頃に栄えたエラム王国時代の行政の中心都市で、アケメネス朝時代にはペルセポリスと並ぶ宮殿があったという歴史的にとても重要な遺跡ですが、保存状態が悪いので当時の繁栄の様子を窺い知ることはできません。ここでは貴重な出土品も多く発見されていて、有名な「ハムラビ法典」もこの地で出土しています。これはエラム時代にバビロニアから戦利品として持ち帰ったものだといわれています。しかし出土品の数々はルーブル美術館やテヘランの博物館にあるので、47℃という暑さのスーサで見たのは、土台と馬の彫刻のかけらでした。
 |
|
 |
| 馬の彫刻と柱(後方) |
|
馬の彫刻のかけら |
チョガ・ザンビル
世界遺産チョガ・ザンビルは紀元前13世紀に、エラム国の宗教的中心として建設されたジッグラド(階段状建造物)です。チョガ・ザンビルとは「大きな籠のような山」という意味で、石油採掘調査の飛行機から偶然に発見されました。建設当時は高さが50mもあったといわれていますが、現在は3分の1程度になっています。それでも壮大さに圧倒されてしまいました。レンガに囲まれた細い階段を登ると、両側に所々楔形文字の刻まれたレンガを見ることができます。ここに着いたときは夕方になっていたので、夕日があたってジッグラドは紅く染まっていました。
| 10、11日目 (アフワズ 〜 テヘラン 〜 成田) |
アフワズ
7時の飛行機でテヘランへ出発したので、アフワズではホテルに泊まっただけでした。でも、空港の近くに製油所があり、離陸すると赤々とした炎があがっているのが間近に見えて、ペルシャ湾の石油の町らしい光景でした。
テヘラン
テヘランで今回初めて訪ねたのは、中央銀行の宝物庫です。ものものしいボディチェックを受けて地下金庫に入ると、薄暗い部屋の中にまばゆいばかりの宝石の数々がガラスケースの中に展示されていて、ケースに触ると鳴るらしい盗難防止用のサイレンが鳴り響いていました。宝石が沢山ちりばめてあって座ると痛そうな玉座や、182カラットという本物とは思えないような巨大なダイヤモンドには、宝石にあまり興味のない私も思わず見入ってしまいました。
●参考にさせていただいたもの●
地球の歩き方 イラン(ダイヤモンド社)
世界遺産3 西アジア(講談社)
メソポタミア文明(ジャン・ボッテロ/マリ=ジョゼフ・ステーヴ著
創元社)
旅のメモ(ユーラシア旅行社 添乗員さん)
このページの先頭へ
Copyright (C) 2006 All rights reserved by Noriko Yamaya
|