ショパン全作品を斬る
1838年(28才)
次は1839年(29才) ♪
前は1837年(27才) ♪
目次 ♪
音楽の間に戻る ♪
詠里庵ホームに戻る
- [142] ノクターン第11番 ト短調 作品37-1
作品37の二つのノクターンは1840年出版された。
献呈はなし。
ノクターン第13番ハ短調のような遅い行進曲風のノクターン。
前打装飾音符がふんだんに使われているが、
これはMadam Duboisのノートにショパン自身が書き付けた指示(次の譜例)を考慮すると、
おおかたは拍の前でなく拍と同時に入れるべきものである。
譜例1
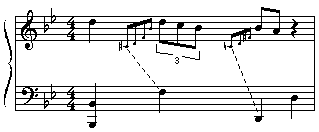
ただ個人的には、
機械のようにこれを守る必要はなく気分に応じて自由な弾き方(たとえば左手拍の前でも後でもなくまたがって右手装飾音が入るなど)をすればよいと思う。
変ホ長調の中間部は四分音符しか現れない極めて単純な和音の連続であるにもかかわらず、
宗教的な雰囲気すら感じられる荘重なコラールである。
子供のような単純和声に深い情感を込める新境地を開いたかのようであるが、
既にノクターン第6番ト短調でも同様のことを行っている。
版による違いが僅かにある。
音符では第14小節最初の装飾音がパデレフスキーと全音(旧Peters)ではDであるのに対しヘンレではE♭である。
スラー、アクセント、強弱も微妙に違っていて、
ここでは一々全部は挙げないが、
目立つのは第83小節目、
パデレフスキーと全音(旧Peters)ではpであるのに対しヘンレではfであることだけ指摘しておこう。
- [143] 前奏曲 イ短調 作品28-2
作品28の「24のプレリュード」は大部分は1839年に作曲、同年出版、
フランス版とイギリス版ではカミーユ・プレイエル(ピアノ会社社長、ショパンの後援者)に、
ドイツ版ではヨゼフ・クリストフ・ケスラー(「15の練習曲」で知られるピアノ教育者)に献呈。
調性感が希薄で不思議な雰囲気のある、
当時としては非常に斬新な音楽である。
幽霊が力無くノコギリを挽くような不気味な左手伴奏に乗る寂しげな旋律。
最後にやっとイ短調の曲だったことが示されるが、
それはどうでもいいような強烈な印象を残す曲。
なお作品28の前奏曲集全体についての一般的コメントは1839年の[160] 前奏曲ハ長調作品28-1に記す。
- [144] 前奏曲 ホ短調 作品28-4
出版と献呈は前項参照。
右手の単純反復旋律を彩る左手和音の半音下降推移が実に効果的。
この高度な和音推移が感傷的な楽想を甘ったるいロマンチシズムに堕することを避けさせている。
前項の2番イ短調の特異さに比べればずっとノーマルな作品だが、
ショパンの面目躍如たる名曲である。
作品28の前奏曲集全体についての一般的コメントは1839年の[160] 前奏曲ハ長調作品28-1に記す。
- [145] ポロネーズ第3番 イ長調「軍隊」 作品40-1
作品40の二つのポロネースは1840年出版され、
友人のフォンタナに献呈された。
「軍隊ポロネーズ」として第6番の「英雄ポロネーズ」とともにポピュラーな曲だが、
もちろんショパン自身はニックネームを付けていない。
他のポロネーズのテーマが単旋律であることが多いのに対し、
このポロネーズでは機関車のような和音連打を基調とする。
それにもかかわらず技巧的に難曲の部類というわけでもないので、
元気で気持ちの良い楽想も相俟って通俗名曲としての地位を確立している。
中間部はニ長調だが、
ドとソしか使っていない単純なメロディーとは思えない充実感のある堂々としたテーマで、
行進曲のトリオ部といった趣がある。
ショパンとしては珍しく全編を通して明るいフォルテで、
そのテンションが一瞬たりとも翳ることがない。
- [146] マズルカ第22番 嬰ト短調 作品33-1
作品33の四つのマズルカは1838年出版。
ローザ・モストヴスカ伯爵夫人に献呈。
自筆譜では四つのうち第2と第3の順番が入れ替わっていたが、
書き込み(ショパンの?)にしたがって現在の順で出版された。
寂しげなクヤヴィヤク。
小さな曲だが冒頭の嬰ト短調にしても21小節目からのロ長調にしてもそれぞれのモチーフは魅力的で味わい深く、
もう少し規模の大きな曲向けの様相を呈している。
発展させて長いマズルカとして楽しみたいところだ。
一見単調な小曲だが室内楽や管弦楽に編曲したくなるようないろいろな要素のメロディーから成る。
- [147] マズルカ第23番 ニ長調 作品33-2
出版と献呈は前項参照。
まるで実用ワルツのような社交性随一のマズルカ。
主部は速めの明るいクヤヴィヤク。
わかりやすい和声と構成に加えて中間部はマズルとオベレクも奮発され、
いかにも「そろそろ終わりですよ」というコーダも相俟って、
舞踏会の雰囲気を演出する。
レ・シルフィードに編曲された一曲。
- [148] マズルカ第24番 ハ長調 作品33-3
出版と献呈は[146]参照。
これも速めの明るいクヤヴィヤクで、
中間部の変イ長調へはいきなり転調し、
また主部のハ長調へいきなり戻る。
間奏曲風の短い曲。
- [149] マズルカ第25番 ロ短調 作品33-4
出版と献呈は[146]参照。
全部で224小節の規模の大きなマズルカ。
A(ロ短調クヤヴィヤク)-B(変ロ長調マズル)-A-B-C(ロ長調クヤヴィヤク→マズル)-A-コーダから成る。
Aはもの悲しく、
それに対比的にBは原調から遠い元気な挿入句。
Cは原調を想起させるロ長調の明るい中間部である。
最後ハ長調の終結句から一小節ごとの単音がG-C-G-C-Gと続き意表を突く。
これはもちろんナポリ六だが、
その定石通り急転直下ロ短調ドミナント→トニックで終わる。
- [150] ワルツ第4番 ヘ長調「華麗なる大円舞曲」 作品34-3
作品34の三つのワルツは1838年出版された。
第1曲([114] ワルツ第2番変イ長調)は1835年作曲されドゥ・トゥン=ホーエンシュタイン伯爵令嬢に献呈され、
第2曲([61] ワルツ第3番イ短調)は1830年作曲されディブリー男爵夫人に献呈され、
この第3番はA. アイヒタール男爵令嬢に献呈された。
めまぐるしく駆けめぐるような諧謔的ワルツ。
単純明快な構成で、
序奏(1〜16小節)、
A(ヘ長調・17〜48小節)、
B(変ロ長調・49〜80小節)、
C(変ロ長調・81〜128小節)、
A(129〜144小節)、
コーダ(145〜173小節)となっている。
通称「子猫のワルツ」とも呼ばれるが、
これは全体が猫が駆け回る感じで、
特にCの部分が猫のあくびのようなモチーフと猫が飛び回るようなモチーフの組み合わせでできているからだろう。
コーダもこの動機によっている。
- [151] 歌曲「春」ト短調 作品74-2(遺作)
ヴィトフィツキ詩。1859年フォンタナ出版。
牧場や小川の流れに見える春の息吹を歌った歌だが、
ときおり心のひだを描写したりもする歌詞。
単純な旋律(1837年[126]練習曲作品25-4イ短調の項参照)がト短調と変ロ長調で特に展開もなく延々と繰り返される。
ショパンには珍しいくらいの素朴さに意表を突かれる。
同じメロディーで歌詞が変わって行くさまに味があるので、
ショパンはそういう効果を考えたのかも知れない。
次は1839年(29才) ♪
前は1837年(27才) ♪
目次 ♪
音楽の間に戻る ♪
詠里庵ホームに戻る