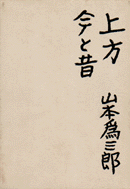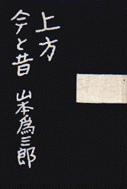● 里見とん『恋ごころ』(文藝春秋、昭和30年)
これは先月に荻窪のささま書店で買った本。久保田万太郎の『さんうてい夜話』(春泥社、昭和12年)という、造本がとても愛らしい本を見つけて、わーいと里見とんの『恋ごころ』とセットで買った。各800円だったか。後日入手した『久保田万太郎全集』にこの『恋ごころ』の短い書評があったのも嬉しかったこと。それから一ヵ月ほどして、今度は装幀と編集をした車谷弘による『恋ごころ』にまつわる文章を、『銀座の柳』で読むことができたという巡り合わせ。本当のことを言うと、買った当初はそんなに心に留まった装幀というわけではなかったのだけれども、『銀座の柳』の文章と合わせて眺めてみると、やっぱり、しみじみ感じ入ってしまうものがある。里見とんの『恋ごころ』の装幀について、車谷弘は『銀座の柳』の「装幀一夕話」にて、以下のように書いている。 私は活字が好きで、よく活字を写真拡大してタイトルなどに使用する。活字を好きなのは子供のときからで、印刷所で活字をわけてもらって、署名がわりにつかったりしたものだが、その頃の号活字だが、ポイント活字にきりかえられたのは、大震災後ではないかと思っている。それははっきり分からないが、それまでの活字の五号が、10.5p とよばれるようになって、書体のタテの線が細くなった。それは清新な感じを与えたが、同時に、文字としての面白さは減少したようである。と、抜き書きがとても長くなってしまったけれども、さっそく、車谷弘の「活字好き」というくだりに思いっきり共感。日本語でもアルファベットでも、活字のかたちや本や雑誌記事の見出しレイアウト、そこでの活字がまずとてもいい感じ、と思うことはしょっちゅう。文字のかたちを存分にいかした装幀は菊地信義のそれでおなじみだし、去年夏の「暮しの手帖」の展覧会で見た花森安治のポスターでも、文字のかたちそのもののうつくしさと色彩そのもののうつくしさを目の当たりにしたことも懐かしい。色といえば、車谷弘の文章を読むまで気づかなかったけれども、『恋ごころ』の見返しのあさぎいろ、縞の表紙を開いてパッと目にした瞬間、やっぱりとても垢抜けている。多くの色見本から選ばれた選りすぐりの色なのだと思う。そして、車谷弘が強調しているように、函の墨の風合いを出した活字のかたち、じっくり眺めてみると、本当にもうゾクゾクしてしまうような微妙な味わいで、車谷弘の文章を読んでいなかったら見過ごしてしまうところだったので、『銀座の柳』を読むことができて本当によかったと思う。上記の車谷弘の文章の最後には、「白地に黒は、清潔でいいね。それに、墨色がいい」と、久保田万太郎による感想があった。 ……などと、里見とんの『恋ごころ』、これまで装幀のことばかり書き連ねてしまったけれども、九篇の短篇が収録されているこの一冊、中身もしみじみ素晴らしい。好きな作家の名前を挙げると、里見とんの名前も絶対にはずせないのだが、里見とんを読むようになったのは小津安二郎がきっかけで、今からちょうと五年前、『秋日和 彼岸花』(武藤康史編、夏目書房)を読んで、クラクラしっぱなしで、以来、まず文庫本、それから今回の『恋ごころ』のように古本屋さんでたまにひょいと見つけて読むというふうにして、読み続けている書き手。と、当初は小津安二郎がきっかけだったのだが、近年は久保田万太郎や水上瀧太郎や小村雪岱といった「九九九会」の人物誌に夢中になって、また違った方向から里見とんに接近している。 その巧すぎる語り口、ところどころの小説で散見されるハイカラさは名家出身の出自がもたらすのか、昔の日本のハイカラ世界のなんとかっこいいこと、と、久生十蘭を読んでいるときと少しだけ似たような胸がキュンとなるところが多々あって、それから、多分に映像的というかなんというか、時折あらわれる映画的瞬間にクラクラすること限りない。一方で、人間の心の闇を見透かすような一筋縄にはいかないような悪魔的なところもある。小津安二郎がきっかけだったせいもあり、里見とんの小説には小津映画的味わいを醸し出す作品も数多くて、それも嬉しいこと。でも、やっぱりとどのつまりは、その文章、語り口の歓びで、……といった感じで、里見とんの魅力を語ろうとすると、収拾がつかなくなってしまうのだった。とにかくも、その魅力の重層性に震える。この『恋ごころ』にも、里見とんの魅力がふんだんに詰まっている。甥っ子、森雅之らしき描写もちらりと登場していて、ちょっと嬉しかった。 ● 山本為三郎『上方今と昔』(文藝春秋、昭和33年)
これは数カ月前、とある古書展で見つけたもの。『上方今と昔』というタイトルに惹かれて手にとってみると、佐野繁次郎の装幀だと一目で判別できる白い函、どれどれと中身を出してみると、ワオ! と、佐野繁次郎の装幀だと予想済みであったにもかかわらず、本体の手触りと色合いに胸が躍った。スキャナにはよく映らないけれども、本体の方は藍色の布張りで、その手触りと色合いにうっとり。さらに! 中をペラペラと目繰ってみると、跋として、朝日新聞の名ジャーナリスト、扇谷正造による文章、その冒頭は《小説「大番」の舞台が、大阪に移ったころだったから、多分去年の夏のはじめだったと思う。或る日、山本さんを中心にして大阪商人の話を聞こうという会が催された。作者の獅子文六氏、それに飯沢匡、私という顔ぶれであった。……》と、獅子文六の『大番』のことが登場しているものだから嬉しくって、値段をチェックすると、たしか300円か400円くらいだったかと思う、くどいようだが、古本とはなんと安い道楽であることだろう! | ||||||