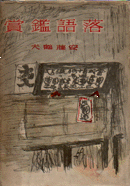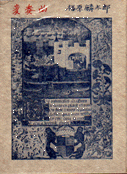● 安藤鶴夫『落語鑑賞』(苦楽社、昭和24年)
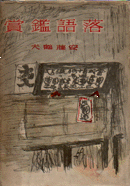

|
安藤鶴夫の『落語鑑賞』は、『わが落語鑑賞』としてちくま文庫で出ている。ちくま文庫の方を買ったのは一昨年、小林信彦の文章で興味を持った。以来、一度通読してからも、何度も何度もひもといている。
ジワリジワリと熟成するような味わいが、この本にはあって、さながら、戸板康二の『歌舞伎への招待』のよう。とにかく本全体がいとおしい。こういう本はそうあるものではない。
先週買った苦楽社発行『落語鑑賞』は初版、その後、創元社で改訂され、ちくま文庫版は三度目の改訂のもの。この本のもとになった「落語鑑賞」は、大佛次郎を中心に発刊された、戦後のうつくしき雑誌「苦楽」に連載されていた。「苦楽」に安藤鶴夫の「落語鑑賞」が連載されたそもそものきっかけは久保田万太郎で、当初は須貝編集長が万太郎に連載を依頼しようとしたところ、「わたしよりも適任者がいます」と安藤鶴夫に白羽の矢がたったのだそう。
そんなこんなで、『落語鑑賞』には、序文代わりに、万太郎による句が添えられていて、その俳句は、収録されている噺にちなんだ句で、いっけんなんでもないようでいて、実に見事で、何度も何度も胸のなかで反芻しては、しみじみ感じ入ってしまいものがある。安藤鶴夫の『落語鑑賞』を宝石のような見事な一冊たらしめている大きな要因が、序として添えられた万太郎俳句にあるのは間違いない。それにしても、こんなに見事な本はそうあるものでない。
安藤鶴夫はちくま文庫『わが落語鑑賞』あとがきで、苦楽社版の『落語鑑賞』の装幀について、《装幀は木村荘八氏。わたしのプランで、表紙を寄席の表、見返しは下足と木戸番のある入口の土間、扉はもうひとつ中へ入って、高座の、向かって左の方の杉戸が少しみえるアングルの寄席、裏の見返しは楽屋で、裏表紙は楽屋口のある路地であった。表通りは、なにか縁日の晩かなんかのように、ひとがおおぜいもやもやしている》というふうに書いている。上の画像、左がカバーの表表紙、寄席は大入りだ。右が寄席の表。カバー→本体の表紙→見返し→扉、というふうに本を開くと同時に、徐々に寄席のなかへと入ってゆくという仕掛け。一冊全体が美術品のような仕上がりになっている。
苦楽社版『落語鑑賞』では、初めて四代目柳家小さんの芸談を読むことができたのが嬉しかった。龍岡晋著『切山椒』という久保田万太郎と龍岡晋の語りを収録した本で何度か登場しているのを見て以来、気になっていた噺家なのだ。自分の弔いに演じてもらうとしたら四代目小さんの『万金丹』がいいと、龍岡晋は万太郎に言っている。これを読んでいいないいなと思って、五代目小さんのディスクを買いに行って部屋でホクホクと聴いたのもよい思い出。と、そんな感じに、ここ数カ月、落語ディスクに夢中、あれこれ聴き漁っている。その気分はさながら、苦楽社版『落語鑑賞』の木村荘八の画、寄席を昔の東京をぼーっと憧れるように遠くから眺めているかのよう。この至福がいつまでも続くといいなと思う。
● 福原麟太郎『変奏曲』(三月書房、1961年)

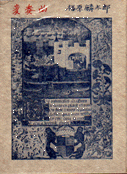
|
これは、三月書房の小型本。あまりスキャナの写りがよくないのだけれども、手にとってみると、やっぱりなんともいい感じ。右が本体で、大英博物館所蔵の1500年頃の光彩本、ロンドン塔の古画が使われていて、英文学者で随筆の名手の著者の雰囲気をよく伝えている。
福原麟太郎を読むようになったのは去年のこと。いそいそとやっきになって読むのはいかにも不釣り合いで、じっくりじっくりとひもときたい書き手。まだ、いろいろと読みたい本が待っている。自分がお婆さんになってから読んでみると、また違った味わいがありそうで、ワインのように大事に熟成させたい気にさせられる書き手だ。
『変奏曲』、まずそのタイトルが大好き。標題のエッセイは巻末にあって、島崎藤村の『春』についての文章。野上弥生子さんを通して興味津々の明治女学校を知る上での必須文献だ。ぜひとも近いうちに読んでみようと思った。福原麟太郎の「変奏曲」が絶好の導き手となりそう。
それから、この本には、前の持ち主による書き込みが一カ所だけあった。ある文章の余白に、万年筆で流麗な筆致で英文の書き込み。書き込みのあった文章は「日本の正月」というタイトル、その冒頭、福原麟太郎はディケンズの文章を掲げつつ、次のように書いている。
「すべての仕事の、あの規丁面な召使い、太陽が、一八二七年五月十三日の朝、正にその姿を現わして光線を射しはじめた時、サミュエル・ピックウィック氏は、またもう一つの太陽のように、むっくり眠りから醒め、部屋の窓を開け放して下界をひろく眺め渡した。」
これがチャールズ・ディケンズの名作「ピックウィック倶楽部」の物語の書きはじめであるが、こんなに大らかな気持にさせる文章がたくさんあるものではない。アンドレ・モロウは、ディケンズの文学は「永遠につづくクリスマス」だと言ったが、この文章を読むと、ディケンズの文学は、永遠につづくお正月だと言いたくなる。この開巻の季節は五月でも、印象は人間の心にある初日の出だ。
と、ここまで読んだところで、万年筆の流麗な筆致の書き込みに目を転じてみると、あらまあ! そのディケンズの文章の原文が書き込まれていたのだった。思わず書き込んでしまった前の持ち主さんに共鳴、本当にそう、「永遠につづくお正月」ディケンズ、印象は人間の心にある初日の出よねえ、と、あらためて福原麟太郎の文章を心のなかで反芻して、スーッとしたなんだかよい心持ちだった。今年初めて買った古本でこんな事態に遭遇するなんて、あまりにも出来過ぎで嬉しかった。というわけで、前の持ち主さんの書き込みを参照して、ディケンズの「ピックウィック倶楽部」の物語の書きはじめ、以下がその原文。
That punctual servant of all work, the sun, had just risen, and begun to strike a light on the morning of the thirteenth of May, one thousand eight hundred and twenty-seven, when Mr. Samuel Pickwick burst like another sun from his slumbers, threw open his chamber window, and looked out upon the world beneath.
あとがきには、《……藤村の「春」を読みかえし、その中の人々について私の覚えていることを書いてみたのだが、いわば「春」の小変奏曲だという心持でそういう題にしたのであった。それがこの本全体の題にもなったのは、ある人の一生は、いつでも誰にとっても、人生という、ある原曲の変奏曲であるというふうにも考えられると思ったからである。》と書かれていて、やっぱり、「変奏曲」、いいタイトルだなあと心から思う。と、これを書いている今、部屋で流れているのは、バッハの《ゴルドベルク変奏曲》、グールドのデビュウ盤、あらあら、どこまでも出来過ぎだ。
|