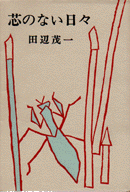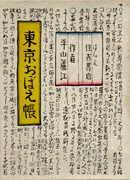春に見学に行った漱石展で初めてその名を知った新宿歴史博物館に出かけたのは真夏のある日。特に胸が躍ったのはやっぱり文学関係のところ。牛込、四谷など地区別に、漱石や子規などの文章の抜き書きパネルなど「明治の文学」コーナーがとてもよかった。それから、紀伊国屋書店の創業者、田辺茂一のコーナーもよかった。戸板康二の『あの人この人』でもその名前がある田辺茂一、著書はまだ読んだことがなかったけれども、月の輪書林や石神井書林の目録に田辺茂一の名前が登場するコーナーが醸し出す空気、都市の雑踏がとてもいい感じだったなあということを思い出したりもした。
さてさて、この『芯のない日々』を見たのは、10月の鎌倉散歩の折、由比が浜通りを歩いていた夕方、公文堂書店の軒先でのこと。そのときは古本屋での買い物はしないつもりでいたのだけれども、ふと目にとまった田辺茂一の本、熊谷守一の装幀に惹かれて手にとり、値札を見るととても安いので、これはもう熊谷守一目当てで購入決意、お会計しようと店内に足を踏み入れることとなった。中身は、艶笑エッセイというかなんというか、そんな感じの軽めの読物で、「私という男は……」という一節が多用されているところが笑える。
● 平山蘆江『東京おぼえ帳』(住吉書店、昭和27年)
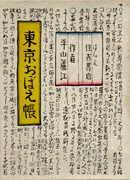
|
と、軒先の田辺茂一を手にとって足を踏み入れた鎌倉の古本屋さん、お会計の前になんとはなしに眺めていた棚でこの『東京おぼえ帳』を見て、前々から読んでみたい本だったので、衝動的に購入を決意。著者自装の函がなかなか愛らしい。が、中身はもっと洒落ている。冒頭の「明治風俗絵巻」は自筆の文字と絵によるページ。上部に明治の東京の様々な職業人の絵が並んでいて、その下になんとも味わい深い自筆の文章。『東京おぼえ帳』の絶好の導入部で、一気に本全体が大好きになってしまう。続いて、歌舞伎役者や花柳界にまつわる人物エッセイ、芸人さまざま。最後の「街頭情趣」なるコーナーではそれぞれのトピックの題字にあしらってあるちょっとした挿絵がかわいい。と、持っているだけで嬉しくなってしまう本なのだが、いざ文章を読んでみると、本全体がさらに愛おしくなってしまうという幸福な本。それにしても「古本は安い道楽だなア」とついいつも同じことを言ってしまう。明治大正昭和初期の日本の近代小説を読む上での副読本としても読めそうな一冊。今後の本読みがさらに楽しくなること請け合い。それにしても、世の中には素敵な本がまだまだたくさんあるのだなあと思う。軒先の田辺茂一を導き手に思わぬところで読む機会がめぐってきた『東京おぼえ帳』だった。
● 平山蘆江『きもの帖』(住吉書店、昭和29年)

|
今年は、初期の「暮しの手帖」をわりかしたくさん手に入れることができた。神保町の小宮山書店のガレージセールの3冊500円コーナーで、昭和20年代の「美しい暮しの手帖」を数冊購入したのだ。デザイン的にはあとの号の方が面白いのかもしれないけれども、わたしは文字ばかりの初期の「美しい暮しの手帖」の頃の誌面が一番好きだ。と、上記の『東京おぼえ帳』に感激していた頃、「暮しの手帖」300号記念号が発売になって、これを機にあらためて古本屋さんで仕入れた「美しい暮しの手帖」数冊を少しずつ読み直す、ということをするようになった。前々から「美しい暮しの手帖」で特に好きだったページ、「きもの帖」という連載ページをふと見てみると、その書き手はほかならぬ平山蘆江なので、あらびっくり。それにしても、「暮しの手帖」の執筆陣のなんと豪華なことだろう、とあらためて胸が躍った。
というわけで、すぐさま、平山蘆江の「きもの帖」は本になっているのかなと検索を始めたのだったが、『きもの帖』は暮しの手帖社からではなくて住吉書店の刊行、戸板康二の『演芸画報・人物誌』によると、住吉書店は蘆江物専門と称していたのだそうで、ここから出た本は著者自装のものがすくなくないのだそう。さいわいわりかし安価で売っているのをネットで簡単に見つけることができて、さっそく取り寄せることができた。この『きもの帖』は著者自装ではなくて装幀は石山武という人によるもの。中身は文字だけで挿絵は皆無、でもでも表紙をパッと見たときは「まあ!」と嬉しかった、なかなか愛らしい。そして、中身の文章がさらに素敵。きものに関する、全方位的な文章で、今まで読んだきもの本のなかでもっとも好きなもののひとつ。全体を通して読んでみると、『東京おぼえ帳』とおんなじように、日本の近代文学の副読本として読めそうな一冊ということがよくわかった。たとえば、漱石や荷風の小説でチラリと目にする登場人物の着物を描写しているくだりを『きもの帖』を読んだあとに目にしたとき、ちょっとした着物描写に対する自分の視点が敏感になっているということに気づかされた。と、ちょっとした新しい視覚を手に入れることができる、これまた幸福な一冊。蘆江によると、尾崎紅葉の小説のきもの描写が面白いらしい。未読の紅葉を読む日がモクモクとたのしみになってきた。