曲目解説
小山清茂 「管弦楽のための木挽歌」
小山清茂(1914〜)は長野県の農家に生まれ、小・中学校で教師をしながら作曲を学びました。彼は時流に関わらず、日本の風土感と密着した独自の作品を数多く発表してきましたが、それらすべてを代表する作品が「管弦楽のための木挽歌(こびきうた)」(1957年)です。この曲は、小山と親交のあった佐賀県出身の劇作家、三好十郎から直接教えられた九州地方の民謡「木挽歌」(木こりが木材をのこぎりで挽くときにうたう唄)を主題とした一種の変奏曲で、民謡の発生と発展を管弦楽で表現しようとした曲です。見事なオーケストレーションとひなびた民謡とのユニークな結合から、多くのオーケストラ団体に好まれて演奏されており、作曲者自身の手で編曲された吹奏楽版もあります。国内のみでなく、日本のオーケストラの海外公演においても、外山雄三の「管弦楽のためのラプソディー」と共によく演奏されています。(「ラプソディー」も有名な曲で、あんたがたどこさ、炭坑節、ソーラン節、信濃追分、八木節などが出てくる楽しい曲ですね。)また、小・中学生の音楽鑑賞用の教材としても採用されています。今回は小穴雄一編曲による「マンドリンオーケストラのための木挽歌」として演奏いたします。
民謡「木挽歌」の歌詞は、次のようなものです:
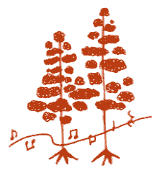
(チートコ パートコ)
ヤーレ 鋸(のこ)よさがれよ 墨ままさがれ*
われとおれとの 金もうけよー (ヤレヒケ ソレヒケ)
木挽ゃ出てゆく 木場の麦やうれる/何を力に 麦刈ろか
山で子がなく 山師の子じゃろ/山師ゃ やもめで子はもたぬよー
親がやるとも 木挽きさんにゃ行くな/仲のよいのを 挽きわける
山師さんたちゃ 山から山よ/花の都にゃ 縁がないよー
*(注:墨の線のとおり一直線に)
「管弦楽のための木挽歌」の曲全体は次の4つの部分からなっています。
第1部(主題):深い山間で一人、大木を刈っている木挽き職人は、退屈紛れに歌を口ずさみながら木を挽いている。弦楽器の不協和音によるのこぎりの擬音に始まって、独奏ギターがのびやかに主題(木挽歌)を歌い出す。ここでは2/4 と 3/4 の混合拍子により、拍節的でないリズムが生かされている。やがて遠くの寺の鐘が聞こえて日も暮れた。そんな情景を表している。
第2部(盆踊り・第1変奏):暑い夏である。仕事を終えた木挽き職人は村に帰ってきて、山で仕事をしながら口ずさんだ歌を歌うと、これが村中の人々の人気を集めて歌われ、盆踊りの歌となって村中に広まっていく。この楽章の間中、締太鼓(しめだいこ)、櫓太鼓(ろだいこ)のリズムが一貫して奏される。さまざまな楽器が音頭をとり、他の楽器がそれに和する。途中にひょうきんな囃し言葉を真似た、合いの手が加わる。だんだん高潮していき、ffの全合奏と櫓太鼓のフラ打ちで終わる。
第3部(朝の歌・第2変奏):名もなかった歌は木挽歌と呼ばれて歌い広められ、都市にも流行し人々に歌われていく。速い5拍子で書かれている。高音部楽器が加わって明るい音色になり、朝のさわやかさや都市の生活を感じさせる。木管によって奏される主要旋律は、次第に厚みを増していく。楽章は前半と後半に分かれており、ギターのグリッサンドで後半となる。後半も音楽は変わらない。木管の旋律はさらに楽器を重ねてゆく。最後、伴奏音形と旋律断片の交互の呈示があり、しだいに伴奏音形の動きは消えてゆく。
第4部(フィナーレ・第3変奏):木挽歌はついに日本の民衆の心に根ざし、全国で歌われるようになり、力強く成長していく。そして、人々の生活の原動力ともなって生き続ける。小太鼓とマンドリンのきざむ激しいリズムによって始まるダイナミックな楽章であり、全楽器が次第に熱狂してくる。ティンパニの独奏のあと、大部分の楽器群が、大きな感じの2部輪奏をする。小休止のあとテンポは遅くなり、今まで断片的だった主題は、この幅広いテンポの中で全合奏で力強く奏され、高らかなクライマックスの終わりで最強打でどらが打たれる。この余韻のうちから曲頭のハーモニックスの弦の和音が生まれ、それを背景にギターがゆったりと「木挽歌」を暗鬱な調子で唄い、再び静寂の世界へ戻っていく。
小穴雄一編曲 児童合唱とマンドリンアンサンブルのための「日本のうた」
「日本のうた」と聞いて皆さんはどんなうたを想像されますか? 唱歌、童謡、わらべ唄、短歌、俳句、詩、詩吟、民謡、フォークソング、キャンディーズ、ピンクレディー、たのきんトリオ、そしてSPEED、安室奈美恵などなど、いろいろありますね。それでは、子供のころを思い出す懐かしい日本のうた、と言ったらどんなうたが思い出されますか? 「かごめかごめ」など、遊びながら歌ったわらべ唄、幼い頃お父さんやお母さんが寝る前に歌ってくれた歌、幼稚園や小学校で習った童謡や唱歌などなど。これらのうたを歌うと、今でも昔の記憶がよみがえってきて、何だかむしょうに懐かしくなってきますね。日本人にとって、わらべ唄、童謡、唱歌などは、イギリス人にとっての「マザーグース」と同じように、ふだんは意識していなくても、実は「心のふるさと」なのかもしれませんね。
そんなわけで今回は、わらべ唄、童謡、唱歌を中心とした「日本のうた」特集です。今年はいよいよ一年ぶりに、光和小学校の少年少女合唱団の皆さんが帰ってきました! どんな歌声を聞かせてくれるのか、とても楽しみですね。今回演奏する「日本のうた」は、アンサンブル・アメデオ第6回定期演奏会で演奏したマンドリン・アンサンブル用の「日本のうた」を改作して、光和小学校との合同演奏用に編曲し直されたものです。第6回定演のパンフレットには、編曲者本人による曲目解説が書かれています:
『・・・じつは、この解説原稿を小生、野辺山発東京行きの小海線〜中央線の車中にて書いております。本日はまっことに晴天で、空気はじつに透明で爽快そのものであります。大変けっこう。こういうときには、おもいっきり新鮮な空気をすいこんでしまうに限ります。車窓よりそとを眺めますと、右手には八ケ岳連峰の勇姿、行く手前方にはそれこそ真っ白な南アルプスの山々、そしてなんと左手には朝日を背にした富士山が見えるではありませんか。こうなると、もうちっぽけなことなんてどうでもいいという気になってしまいます。ほんとうに、つくづく「日本ってなんて美しいんだろう!」とジーンときてしまいます。
てなわけで、第一部1曲目は「日本(にっぽん)のうた」。そんな美しい日本を唄いあげた四季のうた撰集であります。編曲方針は、もうすっかり黄ばんでしまった紅葉色の幼き日々のアルバム、その扉をそっと開いて、懐かしさのあまりおもわずポロッと涙してしまう、そんな気分で綴っちゃおうというわけです。決して子供達のためだけのものでなく、むしろ大人のためのノスタルジー童謡集であります。全体の色彩トーンは当然セピア色。たそがれていく人生、風前のともしびが瞬間にボーッと燃え盛る如く、それは熱い熱い思いでまいりましょう。山田耕筰の作品が比較的多くなったことに特別の意味はありません。全編を通して「どじょっこふなっこ」がプロムナード、ライトモチーフとなって四季の節目ごとに顔を覗かせます。「はるになればーっ」とか「あきになればーっ」などと次々に季節の到来を告げます。曲は、かごめかごめのプロローグにはじまりかごめかごめのエピローグで永遠の彼方に消え去って行きます。とくに学術的根拠に立脚しているわけではありませんが「かごめかごめ」のメロディーは日本的童謡の元祖のような存在に思えてなりません。「かーごめ、かーごめ」の節は「ゆうやけこやけでひがくれてー」(ゆうやけこやけ)「はーるになればー、しーがこもとけてー」(どじょっこふなっこ)あるいは「はーるがきーた、はーるがきーた、どこにきたー」(はるがきた)など皆ほとんど同じメロディーみたいに聞こえます。きっと日本人の好みの旋律なのかもしれません。ちょっとくるしい感じですが、「はるーはーはよーからー」(あわて床屋)「はーるよこい、はーやくこい、あーるきはじめたミヨちゃんがー」(はるよこい)なども関連のあるメロディーですね。』
1、はるのうた
曲は「かごめかごめのプロローグ」で静かに始まります。わらべ唄は、日本の唱歌や童謡のふるさとです。言葉に密着した単純なメロディーで歌われるわらべ唄を模範として、数多くの童謡が作られました。わらべ唄が持つ懐かしいような、ノスタルジックな雰囲気に誘われて、時はさかのぼります。
「朧(おぼろ)月夜」
高野辰之作詞・岡野貞一作曲(大正3年)/文部省唱歌(小6)
|
| | |
菜の花畠(ばたけ)に、入日(いりひ)薄れ、
見わたす山の端(は) 霞(かすみ)ふかし。
春風そよ吹く、空を見れば、
夕月かかりて 匂(にお)い淡(あわ)し。
|
里わの火影(ほかげ)も、森の色も、
田中の小路(こみち)を たどる人も、
蛙(かわず)の鳴くねも、鐘(かね)の音も、
さながら霞(かす)める 朧(おぼろ)月夜。
|
(『山の端』ここでは山々の輪郭のこと。『里わ』里のあたり。『火影』灯火の光。『田中』田と田の間。『蛙の鳴くね』カエルの鳴き声。『さながら』そっくり、そのまま。『朧』ぼんやり、ほんのり。春の季語。『朧月』春の夜などの、ほのかにかすんだ月。春の季語。)
この歌の作詞をした国語国文学者の高野辰之は、有数の豪雪地帯である長野県北部の飯山市近く(豊田村)に生まれました。当時、雪解けのあと4月下旬から6月下旬にかけて、飯山市一帯の千曲川河畔は、灯油をとるための菜の花で黄一色に染まったそうです。今でも、奥信濃の千曲川沿いでは、菜の花の栽培が盛んに行われているそうです。一度見に行ってみたいですね。
また、唱歌「故郷(ふるさと)」の作詞をしたのも高野辰之でした。「朧月夜」に出てくる鐘、「故郷」に出てくる山や川は、豊田村周辺の風景だと言われています。高野辰之と岡野貞一の組み合わせによる唱歌は、「朧月夜」「故郷」の他に「春の小川」「春が来た」「紅葉(もみじ)」があります。みんないい歌ばかりですね。「夏の思い出」の作曲者である中田喜直さんは、「滝廉太郎、山田耕筰はみんなもよく知っている。だけど岡野貞一という人を忘れてはいけない。岡野さんは、滝、山田と並んで、時代を越えた作曲家だ。」と言っていたそうです。
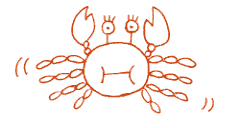
「あわて床屋」
北原白秋作詞・山田耕筰作曲(大正8年)
春は早(はよ)うから川辺の葦(あし)に、
蟹(かに)が店出し、床屋(とこや)でござる。
チョッキン、チョッキン、チョッキンナ。
(以下省略)
カニの床屋に兎(うさぎ)が来るのですが、兎があまりにカニさんをせかしたばかりに、カニさん慌ててしまい、兎さんの耳が切り落とされてしまうというお話です。兎さん、兎さん、あんまりせかしちゃだめですよ。春なんですから、慌てず、のんびり行きましょう。「春眠、暁(あかつき)を覚えず」と言いますね。春の朝はなかなか目が覚めないものです。新古今和歌集にも「風かよふ 寝覚めの袖の 花の香に かをる枕の 春の夜の夢」(藤原俊成女)という和歌があります。意味はよくわからないけど、なんだか春の朝のいい気分が伝わってきますね。新古今の基本は「つかず、はなれず」ですので、うたの意味は「なんとなく」わかればいいんです、きっと。春は昼間もなんだか眠いです。でも外に出ると、ぽかぽかあたたかくって、ゆらゆらと渡ってゆく春風に、何だかうれしくなって、首すじがくすぐったくなりますね。

「待ちぼうけ」
北原白秋作詞・山田耕筰作曲(大正14年)
待ちぼうけ、待ちぼうけ。
ある日、せっせと、野良(のら)かせぎ、
そこへ兎(うさぎ)が飛んで出て、
ころり、ころげた
木のねっこ。
(以下省略)
ある日、農夫が 畑仕事をしていたら、兎が切り株にぶつかって転んでしまいました。農夫はラクをして兎を捕ることができたので、なんだ、まじめに働かなくても寝て待っていれば兎の方からやって来てくれるじゃないか、と考えて、その翌日からは仕事もせずに、また兎が切り株にぶつかるのを待っていました。だけど兎はもう二度と現れず、畑は荒れてしまった、というお話です。中国の伝説を元にして作られた歌です。春は眠いからといって、さぼっていてはいけないんですね。皆さん、仕事に学業に頑張りましょう。
北原白秋と山田耕筰のコンビの作品にはこれらの他に「この道」「ペチカ」「からたちの花」などがあります。山田耕筰は日本語のアクセントに忠実に作曲しているので、流れるような感じの曲になりますね。ところが、同じ山田耕筰が作曲した「赤とんぼ」の始めの部分「夕焼け小焼けのあかとんぼ」の「あかとんぼ」については、アクセントが日常会話とは異なっています。でも、このメロディーだからこそ、胸に深く響いてくるような気がしませんか?
鈴木三重吉が大正7年に創刊した雑誌「赤い鳥」によって始まった童謡運動は約10年間続き、その間に、北原白秋、西条八十、野口雨情らの作詞家、山田耕筰、中山晋平、本居長世らの作曲家によって、多くの名作が生みだされました。白秋は、わらべ唄という民族的伝統と日本の子供の生活感情をうたいこんだ歌を尊重し、それが当時の童謡運動の基調になっていました。したがって、童謡がわらべ唄に似てくるのは当然のことでした。その10年間に、てるてる坊主、七つの子、ゆりかごのうた、どんぐりころころ、赤い靴、しゃぼん玉、月の砂漠、どこかで春が、肩たたき、夕焼け小焼け、春よ来い、兎のダンス、証城寺の狸囃子、汽車ポッポなどが生まれました。みんな懐かしいうたばかりですね。
2、なつのうた
さあ、夏が来ました!「夏が来た」を昔の言い方で言うと「夏は来(き)ぬ」になります。
「夏は来ぬ」
佐佐木信綱作詞・小山作之助作曲(明治29年)/文部省唱歌(小5)
卯(う)の花の匂う垣根に、時鳥(ほととぎす)
早も来鳴きて、忍音(しのびね)もらす 夏は来ぬ。
(以下省略)
(『卯の花』ウツギの花。夏の季語。『ほととぎす』夏の到来を告げる渡り鳥。「てっぺんかけたか」と鳴く。夏の季語。『忍音』旧暦4月頃、ほととぎすがまだ声をひそめて鳴くときの声。)
この歌は全部で5番まであり、1番、2番・・・と段々歌っていくうちに、初夏の風景が順々に浮かんでくるようになっています。作詞をした歌人・万葉学者の佐佐木信綱(1872〜1963)は第一回の文化勲章を受賞しています。
「茶摘(ちゃつみ)」
作詞作曲不詳(明治45年)/文部省唱歌(小3)
|
夏も近づく八十八夜、
野にも山にも若葉が茂る。
「あれに見えるは茶摘じゃないか。
あかねだすきに菅(すげ)の笠。」
|
日和(ひより)つづきの今日此頃(このごろ)を、
心のどかに摘みつつ歌う。
「摘めよ摘め摘め摘まねばならぬ。
摘まにゃ日本の茶にならぬ。」
|
子供の時に「せっせっせ」の歌としてうたった思い出のある人が多いのではないでしょうか。この曲の「3・4・4・3・3・4・5」という歌詞のリズムは日本の民謡のリズムと同じだそうです。「八十八夜」とは、立春から数えて88日目で5月2日頃のことです。ちなみに立夏は5月5日頃です。

「たなばたさま」
権藤はなよ/林柳波作詞・下総皖一作曲(昭和16年)/文部省唱歌(小2)
|
ささの葉 さらさら、
のきばに ゆれる。
お星さま きらきら、
きん ぎん 砂子(すなご)。
|
五しきの たんざく
わたしが かいた。
お星さま きらきら、
空から みてる。
|
(『のきば』軒(のき)のあたり。『砂子』金銀箔の粉末で、短冊などに吹き付けるもの。『五しき』いろいろな色。)
7月7日といったら七夕ですね。天の川の両岸にある織姫星(こと座・ベガ)と彦星(わし座・アルタイル)が年に一度再会するというこの夜に、星を祭る年中行事です。なんと奈良時代から現在まで続いているそうです。縁側やベランダに竹の枝を立て、短冊に願いごとを書いてつるしておき、織姫と彦星に願い事をかなえてもらうようにお祈りします。皆さんは今でも竹を立ててお願いごとをしていますか? 今年はどんなお願いをしようかな。ちょっとだけ教えてあげましょう。と思ったけど、やっぱりや〜めた。だって、夢もお願いも、言ってしまったら叶わなくなってしまうような気がして。だから、そっと胸に秘めておきましょう。
3、あきのうた
夏も後半になると、空高くに薄っすらとした秋の雲が現われ始め、激しかったセミの鳴き声も段々と和らいできます。そして一雨ごとに秋は深まっていき、知らないうちに夏は終わります。田畑の上には赤とんぼが飛び交い、柵や塀などの上には静かに羽根を休めているとんぼが一列に並び、夕陽を受けて真っ赤に照らされます。山々は紅葉に色づき、風はだんだん冷たくなり、河原ではススキがきらきら光りながら風に揺れています。そうして静かに、秋は暮れていきます。木枯らしが木々をざわざわと揺らしながら吹き抜けていくようになると、季節は晩秋から初冬へと移っていくのです。
「赤蜻蛉(あかとんぼ)」
三木露風作詞・山田耕筰作曲(大正10年)
 夕焼、小焼の あかとんぼ
夕焼、小焼の あかとんぼ
負(お)われて見たのは いつの日か。
山の畑の 桑(くわ)の実を
小籠(こかご)に摘んだは まぼろしか。
十五で姐(ねえ)やは 嫁に行き
お里のたよりも 絶えはてた。
夕やけ小やけの 赤とんぼ
とまっているよ 竿(さお)の先。
「負われて見たのは・・・」は「追われて」ではなく、姐やに背負われて見た、という意味です。また、「桑の実」とは、5〜6月ころに桑の木になる実で、「どどめ」とも呼ばれます。
僕は今まで、3番(十五で姐やは〜)の歌詞の意味がはっきりとわからずにいました。それで、インターネットで調べてみたら、次のような文章にたどりつきました:
「終戦の歌だとかいう噂ですが、それは誤りです。以前、テレビ番組の三木露風の特集で、詳しく解説されていました。露風には一つ不可解な記憶があり、それは幼児の頃にいた少女の記憶です。その少女の背中によく負ぶわれたりしたそうですが、ある時いなくなりました。成長するに従い「あの姐やは誰だったんだろう」「あの姐やの記憶は幻だったのだろうか」と思っていたそうです。そして、ある時、自分に年の離れた姉がいたことを知ったのです。その姉はまだ幼くして遠くへ嫁に行き、そのまま若くして結核で亡くなったそうです。当時のことですから、里心を出してはいけないという理由で、里帰りはおろか手紙もやりとりできなかったとか。その生死すら、実家の両親に連絡していたかどうか不明だということで、露風も調べてやっと、姉が既に亡くなっていたことを知ったのです。その姉の悲しい生涯を想い、数少ない記憶を思い起こして歌詞を作ったそうです。」
このことを考えながら歌詞を読み直してみると、なんだか感慨深いものがあります・・・
「僕が小さかったころ、まだ1〜2歳の頃かな、誰だかわからないけどお姉さんの背中に負われて、夕方、夕焼けで真っ赤に染まった周囲の中で、赤とんぼを見たような記憶があるけど、あれはいつのことだったのだろう。
あと、春に、山の桑畑に実っている桑の実を、その人と一緒に小さなかごに摘んだような気がするんだけど、あれは幻だったのかな。
そのお姉さんは15歳のとき、お嫁に行ってしまった。僕は当時、まだ小さくて、そんなこと知らなかったけど、故郷にいる両親と連絡を取ることもできずに、ひとりで、病いに倒れて亡くなってしまったお姉さん・・・
あれから何年もたった今、僕は、あのときの記憶と同じように真っ赤に染まった夕焼けの下で、竿の先に静かにとまっている赤とんぼを見ながら、じっとお姉さんのことを思い出しています。」
こんな感じの意味でしょうか。この歌の1番と2番を、ご来場いただいた皆さんと一緒に歌いたいと思います。私たちもみな演奏をやめて、全員で歌います。
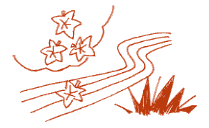
「どじょっこふなっこ」
東北地方わらべうた・岡本敏明作曲(昭和23年)
秋になれば 木(こ)の葉こ落ちて
どじょっこだの ふなっこだの
舟(ふね)こ来たなと思うベナ
(春・夏・冬は省略)
青森県の民謡をヒントにして新たに作られた歌です。元歌の歌詞は、例えば夏については次のようなものでした。
「夏来れば、田堰(たぜき)、小堰(こぜき)サ温(ぬく)くなる。/泥鰌(どじょ)コ鰍(かじか)コアせア、喜んで喜んで、/湯コサ入ったと思うベアネ、/コリャコリャ。」
どじょうやふなの気持ちになって、やさしく語りかける様子に、とてもあたたかみを感じますね。この歌を聞くと、思い出す詩があります。それは金子みすゞの「積つた雪」という詩です。
「上の雪/さむかろな。/つめたい月がさしてゐて。//下の雪/重かろな。/何百人ものせてゐて。//中の雪/さみしかろな。/空も地面(ぢべた)もみえないで。」
みすゞの詩(童謡)は、このように、人が気づかないものや忘れてしまいそうなものをやさしくいたわるような詩ばかりです。みすゞは「見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。」とうたいます。1996年から、小学校の教科書にも取り入れられているそうです。この他にもたくさんいい詩があるのですが、あと一つだけ、僕の大好きな詩を書きたいと思います。
「私と小鳥と鈴と」
私が兩手をひろげても、
お空はちつとも飛べないが、
飛べる小鳥は私のやうに、
地面(ぢべた)を速くは走れない。
私がからだをゆすつても、
きれいな音は出ないけれど、
あの鳴る鈴は私のやうに、
たくさんな唄は知らないよ。
鈴と、小鳥と、それから私、
みんなちがつて、みんないい。
小6の国語の教科書に、司馬遼太郎さんが「二十一世紀に生きる君たちへ」と題した文章を書いています。その中に、人の痛みを感じる人間になってもらいたい、という内容のことが書かれています。そして、人の痛みがわかるようになるには、簡単な訓練をすればよい、例えば友達が転んだら、「ああ、痛かったろうなあ、と感じる気持ちを、その都度、自分の中で作り上げてさえいけばいい」とあります。「どじょっこふなっこ」や金子みすゞの詩に通じるものがありますね。司馬さんの文章の最後は、次のように締めくくられます。「君たち、君たちは常に晴れ上がった空のように、高々とした心を持たねばならない。同時に、ずっしりと、たくましい足取りで、大地を踏みしめつつ歩かねばならない。私は、君たちの心の中の、最も美しいものを見続けながら、以上のことを書いた。書き終わって、君たちの未来が、真夏の太陽のように輝いているように感じた。」
とつぜん、和太鼓の音が聞こえてきました。そうです、秋と言えば収穫の秋。収穫といえば、豊作を祝う村祭りです。みんなで神社に繰り出して、太鼓に合わせて歌えや、踊れや。これが日本人の魂だ! おーし、うっし、うっし、どんどこ、どこどん、どどんがどん。どんどこ、どこどん、どどんがどん。どんどん、すととこ、どんどんどん。どんどん、った、った、たんたんたん。でんでけ、でんでけ、ででんがでん。っだ、っだ、っだ、っだ、どんどんどん。せいや!!
「村祭」
作詞不詳・南能衛作曲(明治45年)/文部省唱歌(小3)
|
村の鎮守(ちんじゅ)の神様の
今日はめでたい御祭日(おまつりび)。
どんどんひゃらら、どんひゃらら、
どんどんひゃらら、どんひゃらら、
朝から聞こえる笛太鼓。
|
年も豊年満作(ほうねんまんさく)で、
村は総出(そうで)の大祭(おおまつり)。
どんどんひゃらら、どんひゃらら、
どんどんひゃらら、どんひゃらら、
夜まで賑(にぎわ)う宮の森。
|
(『鎮守』 その土地の守り神、あるいはその神をまつる神社。)
日本の町々では、10月に収穫祭が開かれ、その年の収穫を喜び、翌年の豊作を願います。また1年分の農作業が終った区切りの打ち上げ的な要素もあります。皆さんは最近、お祭りに出かけたりしていますか?
4、ふゆのうた
冬、一面の銀世界。真っ白な空から、粉雪がきらきらと舞い降りてきます。あたり一面を真っ白に覆った雪は、日の光もないのに、まぶしいくらいに輝いています。子供たちが家から飛び出してきて、「わあっ、雪だ!雪だ!」とはしゃいでいます。子供のころ、雪が降るのがとても待ち遠しかったですね。雪だるまをつくったり、雪合戦をしたり、楽しくて、楽しくて、寒さなどちっとも感じずに走り回りましたね。そんな情景を想起させるオープニングで「ふゆのうた」が始まります。
「雪」
作詞作曲不詳(明治44年)/文部省唱歌(小2)
|
雪やこんこ霰(あられ)やこんこ。
降っては降ってはずんずん積る。
山も野原も綿帽子(わたぼうし)かぶり、
枯木(かれき)残らず花が咲く。
|
雪やこんこ霰やこんこ。
降っても降ってもまだ降りやまぬ。
犬は喜び庭駈(か)けまわり、
猫は火燵(こたつ)で丸くなる。
|
「雪やこんこん」ではなくて「雪やこんこ」です。ご存知でしたか? 「こんこ」の語源は、雪の降る擬音だと言われていますが、一説では「雪よ来う来う」が語源で、元来、雪の降るのを歓迎した歌だそうです。
次第にあたりは暗くなって、雪の夜になりました。家族みんなが暖炉のまわりに集まってきます。
「ペチカ」
北原白秋作詞・山田耕筰作曲(大正14年)
雪のふる夜はたのしいペチカ。
ペチカ燃えろよ、お話しましょ。
むかしむかしよ、
燃えろよ、ペチカ。
(以下省略)
ペチカとは、ロシア式暖炉のことです。ペチカのまわりに家族みんなが集まって、いろいろ話したりしていて楽しそうですね。みんなの笑顔がきらきら輝いている様子が目に浮かびます。外は寒くても、ペチカのまわりにいる家族みんなの心の温もりが感じられて、それだけでとても暖かそうですね。何だか、自分が子供のときの両親のことが思い出されます。大きくなった今になって初めて、あの頃の両親の、子供に対するまなざしの温かさがわかりました。何の心配もなくここまで育ってこられたのは、お父さんお母さんがペチカのように、子供たちに向かってひたむきに温もりを与え続けて、守ってきてくれたからだったのですね。
大人になった今になって改めてその歌詞の意味をかみしめた歌があります。
「故郷(ふるさと)」
高野辰之作詞・岡野貞一作曲(大正3年)/文部省唱歌(小6)
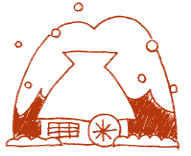 兎(うさぎ)追いしかの山、
兎(うさぎ)追いしかの山、
小鮒(こぶな)釣りしかの川、
夢は今もめぐりて、
忘れがたき故郷(ふるさと)。
如何(いか)にいます父母、
恙(つつが)なしや友がき、
雨に風につけても、
思い出(い)ずる故郷。
志(こころざし)をはたして、
いつの日にか帰らん、
山は青き故郷、
水は清き故郷。
(『います』「居る」の尊敬語。いらっしゃる、おられる。『友垣』友達。交わりを結ぶことを垣を結ぶのにたとえて言う。『つつがない』異常がない、無事である。便り(手紙=筒)がないのは良い便り、という諺による。)
作曲者の岡野貞一は大学で教鞭をとる傍ら、教会のオルガン弾きの仕事もしており、子供の時から賛美歌に慣れ親しんでいました。猪瀬直樹氏は、もしかしたら「故郷」のメロディーには賛美歌の音階がしのびこんでいるのかもしれない、と指摘しています。また、3/4拍子の2小節を、6/8拍子の1小節と考えると牧歌的な感じになり、田園風景が見えてきて、日本の伝統的なリズムに近い、懐かしいものになる、と分析しています。
ふるさとを唄った歌には、この他にも素晴らしい作品がたくさんあります。
「ふるさとの 山に向ひ言ふことなし ふるさとの山は ありがたきかな」
「かにかくに 渋民村は恋しかり 思い出の山 思い出の川」(石川啄木)
「ふるさとは遠きにありて思ふもの/そして悲しくうたふもの/よしや/うらぶれて異土の乞食(かたい)となるとても/帰るところにあるまじや/ひとり都のゆふぐれに/ふるさとおもひ涙ぐむ/そのこころもて/遠きみやこにかへらばや/遠きみやこにかへらばや」(室生犀星「小景異情・その二」)
大きくなって親元を離れてからこれらの歌を思い出してみると、その歌詞が胸に深くしみてきます。以前、詩や歌の鑑賞の仕方を聞いたことがあります。詩を読んで、いい詩だなと思ったら、それを覚えてしまいましょう。意味はよくわからなくても構いません。そして時々思い出して味わってみるのです。そうしているうちに、何年もたったときにきっと、ああそうか、そういう意味だったのか、とわかるのです。経験を積むことによって、初めて意味が深く理解できることがあるのです。だから、気に入った詩や歌があったら、意味がよくわからなくても覚えてしまいましょう。いつかそれらの詩や歌が、自分の宝物になるのです。
最後に、また「かごめかごめ」が戻ってきました。まるで、唱歌や童謡の母親のような存在であるわらべ唄に見守られて、その子供たちである童謡や唱歌が、自由に変奏を繰り広げてきたかのようですね。そして、夕焼け小焼けで日が暮れて帰ってきた子供たちを「おかえりなさい」とでも言わんばかりに、お母さんであるわらべ唄が戻ってきます。バッハの「ゴルトベルク変奏曲」についてのグレン・グールドの解説が思い出されます。わらべ唄の演奏は静かに終わり、この曲の演奏は終わりますが、皆さんの心の中で、わらべ唄はいつまでも繰り返し響きつづけ、そこからいろんなうたや思い出があふれ出すことでしょう。だからこの「日本のうた」は、日本人として生まれて生き続けている限り、いつまでも終わりません。そして時代を越えて、この美しい日本、青い地球の上で、日本の心のうたは、歌い継がれていくことでしょう。僕たち大人の心にしみいる懐かしいうたを、今、小学生の皆さんが歌っているのを見ると、なんだかほっとしたような、うれしいような気持ちになりますね。
参考文献
金田一春彦、安西愛子「日本の唱歌」(講談社文庫)、与田準一「日本童謡集」(岩波文庫)、山住正巳「子供の歌を語る」(岩波新書 352)、金子みすゞ「わたしと小鳥とすずと」(JULA出版局)、司馬遼太郎「二十一世紀に生きる君たちへ」(大阪書籍「小学国語・六年」より)、猪瀬直樹「唱歌誕生─ふるさとを創った男」(文春文庫)、グレン・グールド「グレン・グールド著作集」(みすず書房)
服部 正 「迦樓羅面(かるらめん)」
作曲者服部正氏は、慶應義塾大学在学中より慶応義塾マンドリンクラブ(KMC)の指揮者に抜擢され、以後半世紀ちかく指導にあたられました。マンドリン音楽のみならず、「次郎物語」をはじめとする多くの映画音楽、オペラ、さらにはラジオ、テレビ関係の分野でも活躍。だれもが知っている「ラジオ体操第一」は彼の作曲によるものです。マンドリン合奏のためにも精力的に作曲・編曲を手がけられ、現存する楽譜を数えるだけでも、作曲90曲、クラシック編曲170曲、ポピュラー編曲150曲にも及んでいます。代表作としては「人魚姫」(1955年)「かぐや姫」(1957年)など、お伽噺をミュージカル風にまとめあげた合唱付の大作や、正倉院の御物に因んで作られた雅楽を基調とせる舞曲「迦樓羅面」(1931年)、海を駆ける健康で可憐な少女を描いた小品「海の少女」などがあげられるでしょう。服部氏の作風は抜けるように明るく、常に大衆性を忘れず、どれもわかりやすいものばかりです。
今回演奏する「迦樓羅面(かるらめん)」は、氏23歳のときの作品です。作曲のいきさつは、作曲者本人の文章から詳しく伺い知ることができます:
昭和6年、塾を卒業した私は、人並みに某会社に入社したのであったが、一週間もたたぬ某日、「君は音楽をやらないのか!」という酷しいお言葉を菅原明朗先生から頂いた。
この、先生からの電話は私にとって大きなショックであった。その時点で私は生涯を音楽一途で生きる決意を定めたのであった。そして私を音楽家に育て上げてくれたKMCとは終生離れまいと思った。その時の私の燃えに燃えた心で作曲した作品が「迦樓羅面」である。昭和6年8月の作曲で、オルケストラシンフォニカ・タケヰの演奏会に菅原先生の指揮で発表して頂いたのであった。
この作品について、演奏会主催の武井守成氏は私のスコアの表紙裏に次のようなお言葉を書き残して下さいました。
「1929年、本オルケストラの作曲コンコルソに『抒情的風景』を以って当選したこの作曲家は翌1931年8月、此「迦樓羅面」を以って、一挙にして不動の天地を獲得してしまった。
正倉院御物の伎楽面の一つ迦樓羅面の丹色の球を含んだ繊と朱色の鶏冠(とさか)とをもったグロテスクな風貌にインスパイアされてものされた此一曲は、たとえ此作家が将来に幾多の名品をあらわしたにせよその陰にかくされることはないであろう。」
(慶応大マンドリンクラブ第136回定演のパンフレット(1986年)より抜粋)
 「迦樓羅面」とは、正倉院御物の伎楽面(伎楽で使うお面)の一つで、「迦樓羅(かるら)」と呼ばれる仏教の神のお面です。正倉院の迦樓羅面の顔は、猿と鶏を足したような感じで、鶏冠(とさか)とくちばしを持っています。全体が緑色で、頬・とさか・くちばし下などには朱色が施してあります。迦樓羅の起源はインド神話にあります。インド神話で「ガルーダ」は、人面を持ち、蛇を食べる巨大な鳥でしたが、その後仏門につき、天竜八部衆の「迦樓羅」となりました。極楽の生き物であり、万全の構えで仏教を護る神であります。この鳥の大きさはとても巨大で、カナダインディアンのサンダーバード、中国の大鵬などと同様の起源を持つと考えられます。
「迦樓羅面」とは、正倉院御物の伎楽面(伎楽で使うお面)の一つで、「迦樓羅(かるら)」と呼ばれる仏教の神のお面です。正倉院の迦樓羅面の顔は、猿と鶏を足したような感じで、鶏冠(とさか)とくちばしを持っています。全体が緑色で、頬・とさか・くちばし下などには朱色が施してあります。迦樓羅の起源はインド神話にあります。インド神話で「ガルーダ」は、人面を持ち、蛇を食べる巨大な鳥でしたが、その後仏門につき、天竜八部衆の「迦樓羅」となりました。極楽の生き物であり、万全の構えで仏教を護る神であります。この鳥の大きさはとても巨大で、カナダインディアンのサンダーバード、中国の大鵬などと同様の起源を持つと考えられます。
正倉院には迦樓羅面のような伎楽面が164面あります。伎楽とは、古代チベットやインドの仮面劇のことで、「日本書紀」によると、聖徳太子の頃に百済から日本の宮廷に伝わってきたものであり、主として供養会の時などに使われたそうです。当時、これらの面を頭の上からかぶって、行列をしたり舞曲に合わせて舞を舞ったりしたのだろうと言われています。
伎楽の曲は今日まで伝わっていないので、どのような音楽か詳細はわかりませんが、宮廷の音楽との関連から、雅楽のような調べであったと服部氏は考えたのでしょうか、本作品は雅楽を基調とした音楽になっています。曲は3楽章形式で、雅楽の雰囲気をもつ前奏曲(Preludio)、2拍子でテンポの早いバレエ(Balletto)、そして静かな終曲(Finale)と、緩-急-緩の3曲が続けて演奏されます。また、コントラアルト等も使われており、大編成のマンドリンオーケストラの魅力を満喫できる曲です。若き服部氏の意欲作であり、作曲から70年近くたった今でも、新鮮な響きを与え続け、不思議な光彩を放っています。
鈴木静一 交響詩「失われた都」
作曲家鈴木静一氏は1901年に東京に生まれ、幼少の頃よりオルガンと謡曲を父親から習い、中学教師に作曲法と和声法を師事し、さらにサルコリ氏のもとでギターやマンドリンを習いました。マンドリン独奏が得意で、若いころはマンドリニストとして活躍したそうです。
1927〜28年、オルケストラ・シンフォニカ・タケヰ主宰作曲コンクールに、1位該当なしの2位入賞。1936年に日本ビクターに入社後、黒沢明監督の「姿三四郎」を始めとして、500曲もの映画音楽を作曲。また薗ひさし、三宅幹夫のペンネームで作詞を担当したこともあるそうです。23, 32, 48歳のときにシベリウスに会い、入門を許されましたが、多忙のために留学を断念。1965年、旧友小池正夫氏の死と、竹内マンドリンアンサンブルからの委嘱をきっかけにマンドリン音楽界へ復帰し、多くの作品を発表しました。「スペイン」第1組曲(1966年)、「スペイン」第2組曲、交響的幻想曲「シルクロード」(1967年)、劇的序楽「細川ガラシャ」、交響詩「失われた都」(1968年)、交響譚詩「火の山」(1969年)などはこの頃に作曲されたものです。以後、作曲・編曲や多くの団体の音楽指導にあたり、マンドリン音楽の繁栄に大いに貢献されましたが、1980年に79歳で永眠されました。
鈴木氏の作品は壮大で、かつ劇的であります。交響詩「失われた都」も鈴木氏の代表作の一つであり、多くの映画音楽作曲の経験を通して培った表現力が遺憾なく発揮されている作品と言えるでしょう。1968年に、九州大学マンドリンクラブによって初演されました。作曲者自身が書いた曲目解説がありますので、見てみましょう:
 |
青い夏草の中に、いくつもの礎石が散らばっていた。その配置からは、壮麗な建物が堂々軒をそばだてていたことが読みとられる。赤い太い円柱--白い壁--そして青の屋根--この遺跡<都府楼>の名称からの印象では、此処を中心とし繰り広げられていた<都>のたたずまいである。
すぐ近くから拡がる玄海を隔て相対する朝鮮、そしてその頃、既に近京--西欧と交流を持っていた唐-宋を通じ流れこんでいた外来文化が、この<都府楼>を色どっていたという--では? そこではどんな生活が営まれていたであろう。
此処は1300年以前から大陸に向けて開いた日本の玄関であった。かつては多くの遣唐使や留学生を唐に送り出し、優れた先進文化を迎え入れ、ある時は、新羅-高麗に向け、度々軍船を送り出したという。
この太宰府の西で筑紫平野をよぎる<水城>(みずき)と呼ばれる防塁の遺構は、此処が、けっして平和のみではなかったことを物語る。此処は幾度となく外敵に襲われたが、中にも、鎌倉時代に起った<元寇の乱>は、最大の国難であったようだ。もしその時、博多の海を埋めつくした蒙古の群船が、一夜の大暴風で全滅させられなかったなら、日本の歴史は大きく塗りかえられていたかも知れない。
回想は、菅原道真の悲劇を織りまぜ果てしなく拡がる--しかし、礎石は何も語らない。たゞ夏草に埋もれ、とりつくしまもない。沈黙に沈んでいる--。
<1968年太宰府にて>
「失われた都」の「都」とは、北九州の「都府楼」のことだったんですね。太宰府や元寇、菅原道真については、中学・高校の歴史の授業で学んだ方も多いのではないかと思いますが、ここで復習しておきましょう。大和朝廷は536年に政庁(当時の官家。つまりは九州のお役所のことですね)を、福岡の海近く(那の津)に作りましたが、660年に白村江(はくすきのえ)の戦いで唐・新羅連合軍に敗北後、朝鮮半島からの侵攻に備え、政庁を、より内陸の太宰府に移しました。白村江の戦いとは、滅亡の危機にある百済の再興を目ざした百済・大和連合軍と、唐・新羅連合軍との戦いです。朝鮮半島の白村江に到着した大和軍は唐・新羅連合軍の挟み撃ち遭って破れました。朝鮮の三国史記によれば、船は火災につつまれて次々と沈没、海に呑まれる兵士は数知れず、炎は天を焦がし、海の水は朱に染まったそうです。こうして百済は滅びました。太宰府のまわりには、防衛のための水城(みずき)や複数のお城が建設されました。水城とは、太宰府政庁を守るために2つの山の間にわたって築かれた大きな土塁であり、全長1.2 km、高さ10 mを越える大きなものです。土塁の海側には堀を造り、水を貯えて敵を防ぐようになっていました。その後、太宰府の政庁は、奈良時代から平安時代にかけて壮麗な建築を誇りました。それはまるで京の都に匹敵するような豪華な建物だったそうです。太宰府は、九州全体の統治、日本の西の守り、外国との交渉の窓口などの重要な役割を果たしました。
しかし、当時、京の都から見れば九州は辺境の地であり、太宰府への転勤は即ち左遷を意味していました。光源氏の左遷先が明石だったことを考えると、太宰府まで行かされてしまった菅原道真(すがわらのみちざね)は、さぞや悲しい思いをしたことでしょう。道真(845〜903)はまれにみる天才で、天皇の信頼を得て異例の出世を果たしましたが、宇多上皇が出家するとき(901年)に、道真をねたんだ藤原時平の策略にかかり、太宰府に左遷されました。このとき彼は自宅の紅梅の前で、都を離れる心境を次のように詠っています。 「東風(こち)吹かば 臭ひおこせよ 梅の花 主(あるじ)なしとて 春をわするな」(東風が吹く春になったら、美しい梅の花を咲かせて香っておくれ。 たとえ、この家の主である私が居なくなっても、暖かい春を忘れないで欲しい。)この梅がのちに太宰府まで飛んで行ったという「飛び梅」伝説は有名ですね。太宰府への道中は7人のみの寂しい旅で、食べ物や馬も与えられず、太宰府に着いたときには今にも倒れそうな状態だったそうです。こののち道真は、二度と京都の土を踏むことなく、失意のうちに、太宰府でその生涯を終えました。道真の死後、都では、藤原時平らが変死しました。人々は道真の怨念が祟っているのだと噂しました。そこで天皇は道真の名誉を回復し、天満宮を創祀しました。京都の北野天満宮、福岡の大宰府天満宮、東京の湯島天神が有名です。以後、彼が異例の出世を果たした天才であった事から、天満宮は学問の神として信仰を集めています。
道真の死後まもなく、太宰府の壮麗な建物は、940年に藤原純友の乱で焼失してしまいましたが、その後も太宰府は13世紀頃まで九州 一円に対する権威を存続させていました。そんな時に思いがけず起きたのが、元寇(蒙古襲来)でした。1274年、フビライ・ハン率いる元と高麗の混成軍(計4万)が博多に上陸しました(文永の役)。当時、日本は鎌倉時代であり、北条時宗が執権でしたが、ご家人からの支持が薄れた幕府には兵は集まらず、また元の集団戦法、鉄炮、毒矢に日本軍は苦戦を強いられ、博多は炎と血で朱に染まったそうです。しかし元軍の前線は鳥飼の湿地帯で膠着し、また夜になると地の利を知っている日本軍のゲリラ戦に大打撃を受けたため、元軍は船に引き上げました。元軍は思ったより戦況が進展しなかったため兵を引き、故国へと向かったのですが、その途中で台風に遭い、兵力の半数が海没しました。しかし元軍はこれに懲りず、1281年に14万の兵を率いて再び日本遠征に向かいました(弘安の役)。対する日本軍は、沿岸に石塁を築いて防御を固め、今度は12万以上の兵で迎え撃ちました。元軍は石塁のない志賀島だけに上陸しましたが、ここで敗北し、対馬まで引き上げましたが、台風に遭い全滅しました。こうして日本軍は、元の襲来を2度もくい止めたのでした。
このように、鎌倉時代以前に起きた日本と外国との戦いではすべて、日本軍の基地は太宰府にありました。現在ではその建物もなく、広い野原にレプリカの大きな礎石が並んでいるのみです。この政庁跡は、菅原道真の和歌をもとに「都府楼跡」と呼ばれています。鈴木静一氏はこの都府楼跡に立ち、上記のような歴史に思いを巡らせたのでしょうか。
曲は、ゆっくりとした重々しい旋律から静かに始まり、廃墟(都府楼跡)に立つ様子が描かれます。次に、玄界灘の荒波を想像させるような低音の3拍子の音型に乗って、マンドリンが、オクターブの跳躍のある悲痛な旋律を奏します。「過去追想」の場面です。玄界灘の上を吹きすさぶ海風が聞こえてくるようです。都府楼は、たとえその建築物が壮麗であっても、辺境の地であり、左遷の悲しみは深く、また外国との戦いで血塗られた悲惨な歴史を持っています。そんな太宰府の過去を思うと、胸の内から悲しみが沸き出して来ないではいられない、そのような作者の気持ちが感じられるような気がします。
嵐が去ったかのように静かになったあと、マンドリンのソロで、異国の雰囲気を持つ旋律が奏されます。平安時代のころ、博多には多くの唐人がやってきて、大陸の物品や文化をもたらしました。遣唐使に行かなくても唐の物品が入ってくるので、道真の進言で遣唐使は廃止になります。しかし道真は策略にかかり、太宰府に左遷されます。譜面に「行列」と書かれたヘ短調の部分は、道真の下向の様子を描いたものなのでしょうか。
すると突然、地鳴りのような激しい音が聞こえてきます。「蒙古軍船の襲来」です。海風に乗って、海の彼方にある元の軍船のホラ貝の音が聞こえて来るかのようです。敵は段々と近づいてきて、ついに戦いの火蓋が切って落とされます。敵は執拗に迫ってきます。悲しみに打ちひしがれて嘆いている間もなく、その嘆きは元軍の弓矢や歩兵の攻撃で消されてしまいます。まるで地獄のようです。元は一度は引き上げますが、また攻め込んできます。しかし暴風雨によって元軍は全滅し、都府楼はやっと静けさを取り戻します。静けさの中で聞こえてくるのは鎮魂歌、レクイエムなのでしょうか。
曲は再び、玄界灘の荒波のような低音の音型に乗って、マンドリンが悲しい旋律を奏します。曲頭で奏されたのと全く同じ旋律なのに、今度は何だか、悲しみだけでなく、何か祈りのようなものが聞こえてくるような気がしてなりません。コーダでは、全合奏でテーマが奏され、長和音が力強く鳴り響き、強い強い祈りの気持ちが、余韻の中に聞こえてくるかのようです。過去の人々に対する祈りのみでなく、未来に対しても、何かを語りかけようとしているような気がしてなりません。鈴木氏が亡くなってしまった今となっては、譜面を見ながら、ただひたすら想像するばかりです。
参考文献
「鈴木静一 そのマンドリン音楽と生涯」(鈴木静一没後15年記念演奏会実行委員会)
