![]()
当院オリジナルの、鍼、灸による治療方法もございます。 伝統を重んじながら、最新の西洋医学治療を行うことが当院では可能です。 |
|
急性の頭痛ではくも膜下出血、脳出血、急性水頭症、髄膜炎、脳炎など現代医学的に治療を有する危険な頭痛を診断、除外します。その上で、「傷寒論」に基づき、発症からの経過日時と脈状と随伴症状から病期を判断し、証を決定して処方を行います。一般に漢方薬は長く飲まなくては効かないと思っている方が多いと思われますが、急性期の症状は、正確な診断の基づいた漢方処方により、服用後15分もあれば、その効果が実感されます。 | ||||
慢性頭痛の代表は偏頭痛です。偏頭痛の原因は血管反応性の亢進や三叉神経の異常興奮だと考えられています。西洋学的治療は、三叉神経の反応性を鈍くする薬剤を使ったり、消炎鎮痛剤を用いて炎症の広がりを押さえ込もうとします。病態の要素を分析し、それぞれに対応していくという考え方です。 |
|
一方、慢性頭痛に対する漢方治療は「金匱要略」に基づき、(冷えの強い状態)陰証なのか(熱の強い状態)陽証なのかといった病態と、虚弱体質(虚証)なのか体力充実している(実証)なのか、のぼせに伴う手足の冷えはないのか(病位)といった、病人全体のバランスの変調を診断して処方内容を決定します。頭痛が反復するときに、頭痛が起こりやすい生体の状況も健康な状態からは陰とか陽にシフトしていると考え、それを補正することで、結果的には頭痛の予防につながるのです。 慢性の頭痛の中には、症状は急激であるが、何度も繰り返し緩解するので、長い間放置されている現代医学的治療が必要な疾患もみられます。その中には慢性硬膜下血腫や低髄液圧症候群、正常圧水頭症、慢性副鼻腔炎などがありますが、やはりこういった西洋医学的治療が第一選択になる場合も、漢方薬を併用することで西洋薬の使用量を減量でき、良好な経過をたどる場合が多くあります。 |
 |
 眩暈(めまい)の漢方治療 眩暈(めまい)の漢方治療 |
|
| |
|
| めまいは漢方治療の得意分野です。特に、目、耳、脳、脊髄、心疾患による原因かつかめていない診断除外になっためまいに対し、東洋医学的診断技術を用いた漢方治療により症状の改善が見られます。例えばメニエル病の病態は内耳にある内リンパの水腫だと言われていますが、漢方医学的には水毒(水滞)という病態です。水毒の際には水様物の分泌異常や停滞の他に、めまい、めまい感などが代表的な症状として出現します。漢方医学的診断技術により証を決定し、こういった異常な水の分布を正常な状態に戻す方剤(駆水剤)を用いますと、めまいは改善します。また、虚血によるめまいには血を補う漢方薬を、起立性低血圧によるめまいには昇圧作用のある漢方薬など、漢方薬を用いたさまざまな治療手段があります。 |
 疼痛、痺れ、感覚異常、麻痺に対する治療 疼痛、痺れ、感覚異常、麻痺に対する治療 |
| |
|
世界最古の医学書、黄帝内経素問の痺論の文中に「風寒湿の三気のまじわり至りて合し痺となす。」とあり、痛みや痺れの原因として風と寒と湿が互いに複合して症状を出現させると言われています。これを踏まえ、漢方医学的治療では、実際に痛みの場所をよく観察し、全身の状態を詳細に診察した上で、寒(冷え)が原因の場合は血行を改善する方剤を、湿(水の停滞)が原因の場合は駆水剤を、風を起こす熱が原因の場合は解熱の方剤を処方します。また、黄帝内経霊枢には「不通即通」と記載されており、「(血や気が)通じていなければ即(すなわ)ち痛みが出てくるが、それを改善すると痛みも消失する」と教えています。虚血に伴う痛みの例としては、閉塞性動脈硬化症や脊柱管狭窄症での脊髄の虚血による痛みが特徴的ですが、血流改善作用のある方剤が効果があるので明らかです。また、気のめぐりの悪さが痛みに影響を及ぼす例としては、うつ症状に伴う頭痛などがその典型例で、抗うつ作用のある方剤が奏効します。 |
 うしろにいるのが院長 |
現在院長が師事している東洋医学会会長寺澤先生のもとへ、News23が取材に来ました! |
![]()
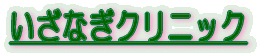 |
|||||
| 〒272-0837 千葉県市川市堀之内3丁目23-13 TEL 047-372-3631 FAX 047-300-7000 |
|||||
| |
|||||