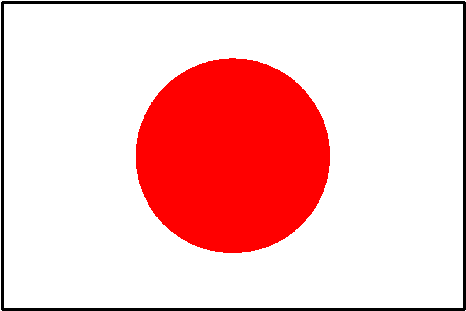 |
中国黒竜江省酪農乳業発展計画 |  |
|---|---|---|
| top › 中国黒竜江省酪農乳業発展計画 › 飼料生産管理 › 活動と成果(未利用資源の飼料化技術) › 未利用資源の実態調査 | ||
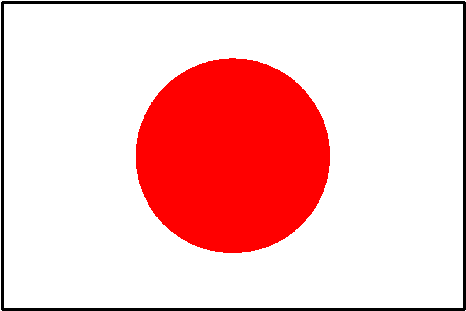 |
中国黒竜江省酪農乳業発展計画 |  |
|---|---|---|
| top › 中国黒竜江省酪農乳業発展計画 › 飼料生産管理 › 活動と成果(未利用資源の飼料化技術) › 未利用資源の実態調査 | ||
当プロジェクトの飼料生産部門において「未利用資源」とは、農作物収穫後の残渣であるトウモロコシ茎葉を想定している。しかし、当地で乳牛飼養農家ではトウモロコシ茎葉は既に冬季における主要な粗飼料の1つとして利用されている。この意味では「未利用資源」とはいえない。トウモロコシ茎葉を未利用資源というのは、これを飼料として活用していない日本的な感覚である。
しかし、言葉の厳密な定義の問題はさておき、当プロジェクトの飼料生産部門の「未利用資源の飼料化技術」分野においてはトウモロコシ茎葉の飼料利用を一層進めることを中心に検討を行った。なお詳しくは後述するが、耕種専業地帯におけるトウモロコシ茎葉の多くは畜産側からすれば未利用資源であり、今後はこれの流通利用が進められることが望ましい。
当プロジェクトの「未利用資源の飼料化技術」分野の対象としては当初から上記のトウモロコシ茎葉をターゲットとしており、稲わらは想定されていなかった。しかし黒龍江省内には稲作も行われているため、稲わらに関しても調査を行った。
日本においては稲わらは主に肉牛の飼料とされている。しかし、当地では稲作を行っている地域では牛の飼養は少なく、稲わらを飼料として活用することはほとんど行われていない。その意味において稲わらこそ「未利用資源」であるといえる。しかし、稲作を行っている地域はプロジェクトサイトの近くに無く、トウモロコシ茎葉を優先して取り扱う観点から、稲わらに関しては、その実態調査を行うにとどめた。
黒龍江省としてもトウモロコシ茎葉は重要な飼料資源とみなしており、これの利用促進を図ることとしている。
トウモロコシは黒龍江省における最も主要な作物の一つであり、食用及び飼料用に栽培されている。食用としては完熟した穂を収穫し、穀物としてのトウモロコシを生産するものが主であり、一部が生食用(茹でトウモロコシ用)となっている。飼料用としては、当地では近年サイレージ調製が振興されているものの、まだ多くは行われていない。飼料用としても食用と同様に穀物として収穫し、これを濃厚飼料として給与している。
このように食用、飼料用いずれの場合も完熟したものを収穫しており、その後に茎葉が残される。農家はこれを借り倒し、圃場周辺あるいは住居の近くに堆積し、牛を飼っている場合には飼料とし、また冬季の暖房用にも用いている。
トウモロコシ茎葉は大家畜飼養農家では既に冬期間の飼料として有効に活用されている。自作地からのトウモロコシ茎葉で不足する場合には近隣の耕種農家より購入もしており、耕種農家から牛飼養農家へのトウモロコシ茎葉の流通もかなり行われている。牛飼養農家がトラクターを有している場合には自ら購入して運搬するが、一方でトラクターを有している農家がこれを有していない農家の依頼により有償で運搬する場合もある。トラクター牽引のトレーラーにトウモロコシ茎葉を満載し、これが数台まとまって走行しているのもかなり見られることから、農家グループでトウモロコシ茎葉の運搬を請け負っているものと思われる。
なお、耕種専業農家で近くに牛飼養農家がいないところではほとんど冬季の暖房にのみ使われていると思われるが、春以降になってもまだかなりトウモロコシ茎葉の堆積が見られる。近年は農家が家を新築した場合には暖房はそれまでのオンドル式の暖房(主にベッドの下で燃料を燃やしてベッドと部屋を暖める)からスチーム式の暖房に切り替えることが多く、この場合は主に石炭を燃料とする。このように農村においても燃料としてのトウモロコシ茎葉の必要性は次第に低くなってきており、今後ともこの傾向は続くものと思われる。
このように資源量としてのトウモロコシ茎葉は豊富であるが、トウモロコシ茎葉はかさばり、運搬しづらい。また酪農地帯とトウモロコシ栽培(畑作専業)地帯とは混在しておらず、それぞれ地域としてまとまっている。これは畑作に適した土壌の所は畑作地帯に、アルカリ性が強くて畑作に適さない所が酪農地帯になってきたという自然条件に基づく歴史的経緯によるものである。畑作農家と牛飼養農家が混在、あるいは比較的近くにあるような条件では畑作農家から牛飼養農家へのトウモロコシ茎葉の流通は現に行われている。
しかし、畑作専業農家と酪農地帯が混在するのではなく、それぞれ大きな地域を形成している場合には、それらの間のへトウモロコシ茎葉を運搬するとなると、運搬距離が長く、運びづらいということから運搬コストが高いものについてしまう。トウモロコシ茎葉は低質粗飼料であり、これに対して高いコストをかけても乳牛飼養農家が使う飼料としては実用的なものとはいえなくなってしまう。
乾燥して貯蔵、細断して給与
トウモロコシ茎葉を家畜に給与する方法としては、細断機により細かく切って給与する方法が一般的である。細断機の動力は小型トラクター直装、小型トラクターからベルトで動力を受け取るもの、あるいはエンジン付きのもの等各種のものがある。
冬季、農家において細断したトウモロコシ茎葉の給与及び牛の採食状況を観察したが、嗜好性は悪くないように思われた。
茎葉サイレージの調製
安達市内近郊においてかなり大型のバンカーサイロで茎葉サイレージを調整し、給与している事例もあったが、今のところまだ農家に普及するには至っていない。
尿素処理
トウモロコシの生育に伴い、茎を強化するために、消化され、栄養になりうるセルロース(繊維素=家畜に給与した際に消化され、栄養になる)にリグニンが付着し、消化率が悪くなる。サイレージ調製は牛の嗜好性を高める効果はあるが、このように低くなった消化率を大きく高めることはできない。セルロースにリグニンが付着することにより低下した消化率の向上させる方法としてアルカリ処理がある。近年は日本において稲わらに対して尿素処理を行い、添加された尿素が植物自体が有している酵素によりアルカリ性のアンモニアに変化し、アンモニアの働きで消化率を向上させるという技術が開発された。この技術を適応することにより、トウモロコシ茎葉の飼料価値が高まることが期待される
当面は乳牛飼養農家において生産されるトウモロコシ茎葉の一層の有効利用を図ることが重要であり、その方策としてサイレージ利用や、既述の尿素処理がある。これら技術の普及、定着によりその飼料としての有効性を有畜農家が認識するようになり、自家産のトウモロコシ茎葉の利用の一層の有効利用が図られるようになるのが第一段階であると思われる。そしてトウモロコシ茎葉の価値が高まった段階で、畑作農家から有畜農家へのトウモロコシ茎葉の流通を図るようにするのが良いように思われる。
|
トウモロコシ茎葉関係写真 (下記の項目をクリックしてください) |
稲わらは日本においては主に肉牛の飼料として用いられており、乳牛に対しても、それが高泌乳牛でない場合には、かなり有用な粗飼料源として用いることができるものと思われる。
2003年10月に黒龍江省西部、内蒙古自治区にほど近い甘南県にある査哈陽農場において稲わらの発生・利用状況を調査した。なお、「査哈陽農場」は地理的には甘南県に含まれるが、行政的には黒龍江省農墾総局管下にあり、県クラスの位置づけがなされている。
ここは昭和の初期に日本人の入植も行われたところで、当地の稲作は日本人により行われた(敗戦により日本人は全て引き揚げた)。その後も日本人による指導もあり現在まで稲作が行われているとのことであった。
ここは全くといって良いほどに稲作専業地帯であり、水田以外の畑地は農家の自家用と見られるものを除いては見られなかった。また家畜の飼養も、役畜としての驢馬がわずかに見られたのみであり、牛は全く見られなかった。
当地における稲の収穫方法は、先ずモアーで刈り倒し、10日程度放置し乾燥させる。次に取り込み部分がピックアップ形式(既に刈り取ってあるものを拾い上げる)のコンバインでこれを拾い上げ、脱穀し、籾は貯留槽に貯め、稲わらはコンバインの後部より排出するものである。ここで排出された稲わらは既に乾燥した状態になっている。
当地では稲わらは一部が家庭用の燃料として集められるが、残りは全てその場で焼却される。
査哈陽農場の人に対して、稲わらは牛の飼料になりうることを話したが、当地の人にとって稲わらが牛の飼料になるということは全く知らず、ましてやこれを資料として牛を飼うということは考えても見なかったとのことであった。
このため、稲わらは牧草よりも栄養的には劣るが、飼料として使うことができる旨指導した。
今後における当地の稲わらの活用方策としては、当地において複合部門として牛(肉用牛)を飼養し、これの飼料として用いることと、他の酪農・肉用牛地帯へ稲わらを販売することが考えられる。前者の場合は稲わらと組み合わせる良質粗飼料としてはマメ科牧草、特にアルファルファが適していると考えられる。また、後者の場合には牛を飼っている地帯で稲わらを飼料として活用できることをPRし、そこでの需要が高まることが前提となる。
|
稲わら関係写真 (下記の項目をクリックしてください)
|
| 活動と成果:未利用資源の飼料化技術へ | |||
| 「飼料生産管理」のメニュー画面 | |||
| プロジェクトのトップへ |