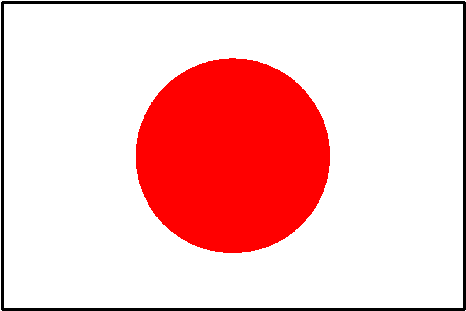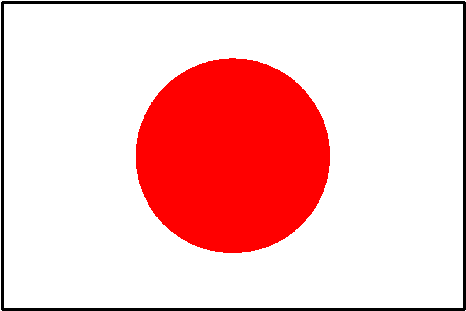2.草地改良試験
草地改良手法及び改良草地の管理技術を明らかにするために、これまでに下記の試験を行った。(実施したが成果を得られなかったもの及び現在実施中のものを含む)
以下、これらの調査の概要を記す。
- 土壌のアルカリ性が強くて植生の無いところを試験対象地とした。ここに堆肥及び泥炭のそれぞれについて、表面施用及び土壌と混和した試験区を設け、それぞれに羊草、星星草、アルファルファを播種した。
- 泥炭を施用した区画では播種した牧草、雑草とも全く発芽・定着は見られなかった。
- 堆肥施用区においては牧草は発芽したが、越冬できるまでの大きさに生育できず、翌年においては牧草の定着は見られなかった。しかしここでは堆肥に混入していたと見られる雑草(虎尾草が主体)が発生し、生育した。雑草は堆肥を施用した所にのみ生育し、その周囲には広がらなかったことから、堆肥施用は一般に利用されている牧草が発芽、生育できる程度には土壌pHは改善されないものの、虎尾草のような比較的アルカリ性にも強い(しかし不植生地のような強いアルカリには耐えられない)植物が生育可能になる程度の土壌改良効果をもたらすことが示唆された。
- また、有機質土壌改良資材としては、当地では入手が難しい泥炭よりも、農家が自給できる堆肥の方が土壌改良効果が高いことが示唆された。
- 更に、不植生地を一度の処理だけで牧草地化することは難しく、第一段階として虎尾草のようなアルカリに強い野草を生育させ、これにより徐々に土壌の改善(有機質の増加とこれにより土壌のアルカリ性を弱める)を図り、次の段階として牧草を導入するという方法がここから示唆された。
- 堆肥の効果は上記「堆肥、泥炭施用試験(2003)」である程度明らかになった。このため、堆肥を用いた規模を拡大した調査を行うと共に、未発酵有機質資材による土壌改良効果がどの程度あるかを確認するために低質乾草(雨に当たったり雑草が多い等のために牛が食べ残した乾草)を施用した区を設けて調査することとした。この背景には、農家では草地改良のために大量の堆肥を用いることは困難であるということがある。農家においては未発酵有機質資材としてはトウモロコシ茎葉があるが、友誼牧場ではトウモロコシはサイレージ用のみ栽培しており、大量のトウモロコシ茎葉を試験に用いることができないため、トウモロコシ茎葉の代替えとして低質乾草を用いることとした。
- また、これと組み合わせて、複数の種類の牧草を播いて、このようなアルカリ性土壌における牧草導入を行う場合の適草種を見いだすこととした。牧草の種類としては以下のとおりである。
-
| 草種(組み合わせ) |
特徴、調査の目的 |
| 星星草 |
栽培牧草の中ではアルカリ性に強い。 |
| 羊草+披碱草 |
比較的草質が良く、当地で広く栽培されている羊草(Aneurolepidum chinense(Trin)Kitag)に、初期生育の早い披碱草(Dahurian Wildryrgrass(和名:ハマムギ):Elymus dahuricus Tulcz.)を配合した。当地で推奨されている組み合わせ。 |
| 羊草+披碱草+シロクローバ |
上記組み合わせにシロクローバを配合した。当地ではシロクローバの利用は行われていないが、哈爾濱では公園の植え込み等でシロクローバの利用が見られることから、当地でのシロクローバ導入の可能性とイネ科牧草とマメ科牧草の混播の可能性を検討するためにこの組み合わせを試みた。 |
| 羊草+披碱草+アルファルファ |
羊草と披碱草に、(単播ではあるが)当地での栽培実績があるアルファルファを組み合わせた。混播草地に利用するマメ科牧草としてのアルファルファの可能性と、アルファルファにより固定された窒素がイネ科牧草にも利用されることを期待する組み合わせ。 |
| アルファルファ |
アルファルファ単播。アルカリ性土壌を改良することによりアルファルファ導入ができるかどうかを試みる。 |
- 調査は先ず草地の中で強アルカリのために草が生えていない所に堆肥と低質乾草を散布した。2004年6月4日に低質乾草を草地の中の強アルカリ土壌の部分に散布した。散布量は散布直後の厚さが4〜5cmになる程度とした。堆肥は6月下旬に人力及びマニュアスプレッダーにより散布した。散布量は砕かれた堆肥が地表を覆い、上から見ると地面のほぼ半分が見えるという程度とした。このほか、有機質資材を投入しない試験区を設けた。
- 堆肥、低質乾草散布した後、デスクハローで軽く耕起した。播種は2004年7月29日に行った。羊草と披碱草はそれぞれの種子を混合してグラスシーダーで播種した。アルファルファと白クローバは人手で播種した。
-
- 当地では草地に施肥することは全く行われていない。草地に施肥することによる効果を調査するために友誼牧場の調査ほ場に試験区(2反復)を設けて、尿素、化成肥料(15-15-15)及び燐酸アンモニウム(16-47-0)をそれぞれ10kg/10a施用し、収量調査を行った。1調査区当たりの面積は約5m2である。
- 施肥を行ったのは2004年5月25日であったが、その後降雨がほとんど無く、まとまった降雨が見られたのは7月初旬になってからである。またその後も十分な降雨は無く、施肥の効果は十分現れなかった可能性が高い。
- 更に、担当長期専門家が体調を崩し、調査適期である8月下旬〜9月上旬に調査が行えなかった。また調査地の草が友誼牧場により刈り取られてしまい、収量調査は行えなかった。次年に同様な調査を行うこととしたい。
- 十八村草地において尿素、化成肥料(15-15-15)及び燐酸アンモニウム(16-47-0)をそれぞれ10kg/10a施用し、収量調査を行った。施肥は2004年6月1日に行った。施用した肥料の種類及び面積当たり施用量は上記試験と同様である。ただし試験は1試験区面積が約10aの1反復のみとした。また10m2程度の小面積ながら堆肥施用区を設けた(施用量は目分量で1kg/m2程度)。
- 刈り取り調査は8月17日に行った。
| 区分 |
実測値 |
指数(無施肥=100) |
| 草丈(cm) |
収量(g/m2) |
草丈 |
収量 |
| 無施肥 |
36.0 |
317 |
100 |
100 |
| 尿素 |
39.1 |
470 |
108 |
148 |
| 15-15-15 |
43.2 |
584 |
120 |
184 |
| 16-47-0 |
41.4 |
319 |
115 |
101 |
| 堆肥 |
40.7 |
434 |
113 |
137 |
- 草丈に関しては化成肥料(15-15-15)が最も良く、次いで化成肥料(16-47-0)、堆肥、尿素と続き、いずれも対象区(無施肥)を上回った。
- 収量についても化成肥料(15-15-15)が最も良かったが、これに続くのが尿素、堆肥区となり、化成肥料(16-47-0)は対象区(無施肥)をわずかに上回るにとどまった。
- また、化成肥料(15-15-15)、尿素、堆肥については、収量の指数が草丈の指数を上回った。これは肥料の施用効果が草丈のみならず、茎葉数や茎葉自体の充実にも効果があったことを示唆している。
- 以上のことから、羊草が優先する草地への施肥は窒素、リン酸、カリのバランスのとれた肥料が適していると判断された。
- なお、当該試験は1回のみ、しかも反復なしの調査であり、施肥の効果の詳細を把握するためには、更に綿密な調査(反復を設ける、1反復内でも調査点数を多くする等)を行うことが必要と考える。
-