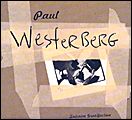1999.3.18

|
 |
The Mountain
Steve Earle and
The Del McCoury Band
(E-Squred)
|
|
オルタナ・カントリーのカリスマ、スティーヴ・アールの新作は、ストレート・アヘッドなブルーグラス・アルバムだ。
現在最強のトラディショナル・ブルーグラスを聞かせるデル・マッコーリー・バンドと組み、偉大な先達ビル・モンローへの愛情を全開にしてみせる。といっても、楽曲はすべてスティーヴ・アールのオリジナル。彼ならではのエッジ感を失うことなく、かつてビル・モンローがブルーグラスという音楽を作り上げたとき、モンローがどれほど先鋭的/攻撃的であったか――つまり、どれほどロックンロール的であったか――を思い知らせてくれる。
エミルー・ハリス、ジョン・ハートフォード、マーティ・スチュワート、サム・ブッシュ、ギリアン・ウェルチらが参加したオールスター曲もあり。こりゃ名盤です。ぼくがちゃんとマメに更新さえしてれば、間違いなくピック・オヴ・ザ・ウィークでした。
|

 |
WacoWorld
Waco Brothers
(Bloodshot)
|
|
イギリスのパンク・バンド、The Mekons のフロントマンだったジョン・ラングフォードを中心に、シカゴで結成されたオルタナ・カントリー・バンドの新作。たぶん4枚目だと思う。
相変わらずクラッシュとハンク・ウィリアムスとを行き来するような、なんとも乱暴かつ刺激的な音楽を聞かせてくれる。得意のカウパンクあり、クランプスのようなネオ・ロカビリーものあり、サーフ・パンクっぽいアプローチもあり。かなりイケてます。
|

 |
Half Mad Moon
The Damnations TX
(Sire/Watermelon)
|
|
ルーツ・ロック系の音が好きな人なら誰もが気にしているはずの音楽都市、テキサス州オースティンから登場した新バンド。ヴォーカル&作詞作曲を手がける二人姉妹と、ギター、バンジョーなどを手がける男性ひとりが基本メンバーだ。
様々なアディショナル・ミュージシャンを従え、ハッピーなカントリー・ロックから、バンジョー入りのソニック・ユースのような曲、そしてナゲッツ系ガレージ・ロックンロールまで、奔放に聞かせる。
|

 |
The Strange Remain
The Other Ones
(Grateful Dead/Arista)
|
|
95年にジェリー・ガルシアが他界してグレイトフル・デッドが活動停止となってからも、フィッシュを筆頭に、デイヴ・マシューズ・バンド、ブルース・トラヴェラーなど、往年のデッド的快感をライヴで体験させてくれるバンドがアメリカでは人気を博していて。ああ、デッド的なるものは今もなお必要とされているんだなぁ、と思い知らされたものだ。
で、当の、残されたデッドのメンバーたちはどうしてたのかというと。96年から各地をツアーして回っていた。ボブのラットドッグ、ミッキーのミステリー・ボックス、そしてガルシアの生前から時折ライヴにも参加していたブルース・ホーンズビーのバンドなどが勢揃い。公演地によってはフィルも登場。97年以降もツアーは続き、なんだよ、これだけ集まってんなら……ということで、98年、ふたたびバンドが本格的に誕生。デッドの曲名にあやかってジ・アザー・ワンズと名付けられたということらしい。
そんなジ・アザー・ワンズの98年のツアーの模様を収めたのがこの2枚組。確かにガルシアはいないけれど、スピリットは生き続けている。ウィルソン兄弟のいないビーチ・ボーイズというより、いったん解散してロビー・ロバートソンが抜けたあと後輩のケイト・ブラザーズなどを加えてツアーしていたザ・バンドみたいな感じかな。ジェリー・マギーがリード弾いてるベンチャーズ、でもいいけど(笑)。特に昔を再現しようとしているわけでもなさそうなプレイも多く、けっこう好きです。
ガルシア作品も5曲含む、主に70年代のデッド・ナンバーに、ミッキーの「オンリー・ザ・ストレンジ・リメイン」やブルース・ホーンズビーの「ホワイト・ホイールド・リムジン」「レインボーズ・キャデラック」などを加えた選曲もいい。92年のライヴからレパートリーになったという「コリーナ」や、ミッキーが歌う「ババ・ジンゴ」、ボブが歌う「バニアン・トゥリー」というロバート・ハンター絡みの新曲も聞けます。
|

 |
Summer Teeth
Wilco
(Reprise)
|
|
for What's In? Magazine
95年のデビュー以降、96年の2枚組セカンド・アルバム『ビーイング・ゼア』を経て、98年、偉大なフォーク歌手、ウディ・ガスリーが生前に残した未発表歌詞を甦らせたビリー・ブラッグとの共演アルバム『マーメイド・アヴェニュー』へと至る旅の中で、ウィルコはとりあえず第一期の活動を総決算。本サード・アルバムで新たなスタートを切った、と。そういう感じだ。
これまで彼らのサウンドを言い表わす際に、“オルタナティヴ・カントリー”あるいは“ルーツ・ロック”という言葉がよく使われた。ぼくもウィルコのことを、そうした方向性を持つ新世代アメリカン・ロック・バンド群の代表選手であるととらえてきた。が、そんな印象を決定づけるうえで最大の“肝”となっていたフィドル、ラップ・スティール、バンジョーといったカントリー系楽器を一手に担当していたマックス・ジョンソンがこのほど脱退。ギター、キーボード、ベース、ドラムというごく普通の4人組へと姿を変えたウィルコは、もはや細かい分類を拒絶するかのような、よりポップでストレートなアメリカン・ロック・アルバムをここで作り上げてみせた。
同じアンクル・テュペロを母体に生まれたサン・ヴォルトが、ザ・バンドにとっての“ビッグ・ピンク”を思わせる“ジャジューカ・プレイス”なる倉庫にこもって、持ち前のオルタナティヴ・カントリー〜ルーツ・ロック感覚を研ぎ澄ました新作をリリースしたのとは正反対。もちろん、どっちもかっこいい。中心メンバー、ジェフ・トウィーディのメロディメイカー的資質も炸裂だ。
|

 |
Vestavia
John P. Strohm
(Flat Earth)
|
|
ブレイク・ベイビーズ、ヴィロ・デラックス、アンテナ、ハロー・ストレンジャーズなどのメンバーとして、あるいはレモンヘッズやマイク・ワット、キム・フォックスらのアルバムへの参加で知られるジョン・P・ストロームのセカンド・ソロ。
ハモンド・オルガンが気持ちよく鳴りまくるフォーク・ロック/カントリー・ロック系のサウンドがたっぷり。バーズとかトム・ペティとか、あるいはリプレイスメンツとかが好きな人にはたまらない1枚かも。
ちなみに、アルバム・タイトルはストロームが近年住んでいるバーミンガム郊外の地区の名前だとか。この人、ボストン出身のイメージが強いんだけれど、近ごろはすっかりアラバマ男になっちゃったのかな。それもまたいいっすね。
|

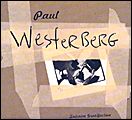 |
Suicaine Gratifaction
Paul Westerberg
(Capitol)
|
|
つーわけで、元リプレイスメンツのこの人の新作も取り上げておきましょう。ちょっと前のリリースなので、今さら感を拭うため、箱入りの初回限定仕様盤のジャケットを載せてみました(笑)。
ソロは3作目だったっけ? 基本的なトラックは、自分ちの地下室スタジオで、ほぼ自分ひとりで作り上げたものだとか。なので、かなり内省的で静かな、まさに現代のシンガー・ソングライターものって感じの仕上がり。
そこに共同プロデューサーとして参加したドン・ウォズが、あとから、ベンモント・テンチ、ジム・ケルトナー、スージー・カタヤマ、スティーヴ・フェローン、エイブ・ラボリエルらの協力のもと、もうちょい外向きでロック的な要素を付け加えている。
でも、いっそひとりで録ったヴァージョンってのだけで構成してしまったほうが、今のこの人の気分をよりストレートに味わえたかも。歌詞的にもジャクソン・ブラウンみたいな感触があったりするし。
|

 |
Minor Chords and
Major Themes
Gigolo Aunts
(E Pluribus Unum)
|
|
なんか、ずいぶんと久しぶりの感じ。5年くらい前にメジャーから『フリッピン・アウト』を出したあと、2〜3年前にミニ・アルバムというかEPというか、そういうのをインディーズから出して。彼らの動きっていうと、そのくらいしか認識してないもんなぁ。
何はともあれ、久々のジゴロ・アンツ。カウンティング・クロウズのアダム・デュリッツのサポートのもと、彼のレーベルに移籍しての心機一転盤だ。ギターのフィル・ハーリーはやめちゃったみたいだけど、とりあえずゲスト参加。というわけで、思う存分、得意のパワー・ポップ感覚を全開にしたアルバムが仕上がった。「スーパー・ウルトラ・ウィッキッド・メガ・ラヴ」(笑)なんてタイトルの曲も入ってて、そのスジの美学を全うしてます。
かと思うと、昨今の新世代シンガー・ソングライターに通じる世界を聞かせてみたり。前作の勢いにはかなわないけれど、今回は曲がさらに粒ぞろいになった感、あり。プロデュースは前作同様、マイク・デニーンです。
|

 |
Music to
Mauzner By
Spy
(Lava/Atlantic)
|
|
スパイというのは、ニューヨーク大学フィルム・スクール在学中の23歳、ジョシュア・ラルフくんのことだとか。
ヒップホップ感覚も盛り込んだキャッチーなダンス・チューンから、ニュー・ラディカルズふうの80年代ふうポップ・メロディ、ベックっぽい屈折したグルーヴ・ナンバー、ソウルフルなミディアム・バラード、そして56人編成のオーケストラを駆使したという映画音楽ふうの曲まで、もう何でもありのポップ・ワールド。
サンプリングと生音の組み合わせ方も、まあ、特に新鮮というわけではないけれど、なかなかうまい。こいつ、化ければでかいかもね。
|

 |
Fan Mail
TLC
(LaFace)
|
|
今さらぼくのところで紹介しなくても誰もが知ってるね。本人たちのプロモーション来日まであって日本でも売れまくっているこのアルバム。
ぼくはとにかく彼女たちがデビューしたとき、もうこれしかいらねーやと思ったくらいハマって。で、セカンドの『クレイジーセクシークール』が出て、あれー、なーんか大人になっちゃったなぁと思いつつも、「ディギン・オン・ユー」にどっぷりいって。
まあ、時代を超えたガール・グループ好きだから(笑)。
で、やはり多くの人同様、ぼくにとっても待ちに待った1枚。5年ぶりくらい? すごくよくできたアルバムで、曲もよく練られていて、キャッチーで、バック・トラックも充実していて。問題なしなんだけど。ただ、良くも悪くも5年待っちゃったから。3年前くらいにこれが出ていてくれれば、まじ、すごかったんだと思う。
と、ごちゃごちゃ言ってますが、内容はほんとにいい。5年待ったことさえ忘れちゃえば、よりクレイジー、よりセクシー、よりクール。ナスティ路線も健在。オールド・スクール・グルーヴもかっこいい。ダイアン・ウォーレン作のバラードもある。もちろんダラス・オースティン、ジャム&ルイス、ベイビーフェイスらもいい曲を提供。長く付き合えそうな1枚です。
|

 |
She Talks To
Rainbows (EP)
Ronnie Spector
(Creation)
|
|
で、永遠のガール・グループ・ファンとしては見逃せなかった3曲入りCDがこれ。ジョーイ・ラモーンのプロデュースによるロニー・スペクターの新曲だ。
ブライアン・ウィルソンのドキュメンタリー・ビデオ『イマジネーション・ザ・ビデオ』の中で、どっかのラジオ局に行ったブライアンがロニーの歌う「ドント・ウォリー・ベイビー」を聞いて感激しているシーンがあったけれど、あそこでかかっていた「ドント・ウォリー・ベイビー」も2曲目に入ってます。
で、話題はその「ドント・ウォリー・ベイビー」に集中してしまうわけですが。この曲が生まれたきっかけになった「ビー・マイ・ベイビー」を歌っていたロニー本人によるカヴァー……という、その事実は確かに感動的なわけで。外野ながら、ブライアンの喜びもそれなりにわかるのだけれど。でも、実際の仕上がりはそんなによくないので(笑)。同時に行き場のない淋しさも感じてしまう困った1枚でもあるわけだな。
その辺は想像力で補わねばなりません。ご注意ください。でも、想像力さえあれば感動的な盤っす。
|

 |
Things Fall Apart
The Roots
(MCA)
|
|
相変わらずヒップホップのアルバムはざくざくリリースされていて。ぼくもけっこうたくさん買い込んではいるのだけれど。最近はかつてほど、こう、ぐぐぐぐっと胸をざわつかせてくれるものが少なくなってきた。ヒップホップという本来もっともっと流動的であるべきコンセプトがスタイル的にも安定してきてしまったせいなのかもしれないけれど。
その辺の考察は本格的に始めたら長くなりそうなので、ほっとくとして(笑)。それでも、やはりニュー・リリースを待ち望むヒップホップ・アーティストは何組かいて。このザ・ルーツもそのひとつ。この人たちの提示してくる空気感というか、音像の肌触りというのは本当に得がたいものだなぁ……と。本盤を聞いてまた思いを新たにした。
生身のバンドなだけに、サンプリングに必要なネタを全部演奏できちゃうというとんでもない強みを活かしながら、無敵の快進撃を続ける新作だ。DJジャジー・ジェフ、エリカ・バドゥ、ディアンジェロ、モス・デフ、ダイス・ロウなどなど、サポート陣も充実。前作以上の緻密さに賛否が分かれるかも。歌詞も問題意識深し、です。
|

|