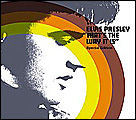2000.8.3

|
 |
Kids In Philly
Marah
(E Squared/Artemis) |
|
2年くらい前、ブラック・ドッグ・レーベルからデビュー盤を出していた連中。スティーヴ・アールのレーベルに移籍してのセカンド登場だ。
初期のブルース・スプリングスティーンとニュージャージーとの関係みたいなものが、ここんちの中心メンバーであるデイヴ・ビエランコとフィラデルフィアとの関係にも感じられたりして。なかなか魅力的だ。あ、つーか、サウスサイド・ジョニーのほうに近いかも。サウスサイド・ジョニーにも通じるしゃがれた歌声をドライヴするロック・サウンドに乗せてたたみかけてくる。かっこいいです。
|

 |
Vavoom!
The Brian Setzer Orchestra
(Interscope) |
|
for What's In? Magazine
来日公演も大成功させたブライアン・セッツァー・オーケストラの通算4作目。第二の黄金時代を迎えたセッツァーの勢いに満ちた素晴らしい新作の登場だ。
結果的に大ヒット作となった前作は、しかし予算の都合もあったのか、ライヴっぽいグルーヴを大事にした一発録りっぽいストレートな仕上がりだった。それに対して今回はよりスタジオ・ワークを駆使した仕上がり。フル・オーケストラという超アナログなバンド編成にこだわらず、曲によってはファンキーなループ・ビートと合体してみたり、ダブル・トラックによるドゥーワップ・コーラスをバックに配してみたり、多彩なエフェクトを効果的に使ってみたり。様々な試行錯誤が盛り込まれており、聞く者を飽きさせない。
もちろん持ち前のスウィンギン・ロックンロール感覚が炸裂する剛速球ど真ん中系楽曲もたっぷり。セッツァーならではのジャンピーなオリジナル・ロカビリー曲やホットロッド系ロックンロールのかっこよさは言うまでもないだろうが、それだけじゃ終わらない。今回もまたカヴァー曲がいかしている。グレン・ミラーの6、ルイ・アームストロングなどで知られる8、デューク・エリントンの9といったジャズものから、クイーンの3まで。おなじみのスウィング・ジャズ・スタンダード曲を基調にセッツァーが再構築した1もドライヴ感たっぷり。
が、今回の必殺カヴァーきわめつけは、キャディラックスの至宝ドゥーワップ・バラードを取り上げた15だろう。前作の名カヴァー「スリープ・ウォーク」とタメをはる名演だ。
|

 |
Dancin' With Them
That Brung Me
Stacey Earle
(E Squared) |
|
これに続くセカンド。1曲目にお兄ちゃんであるスティーヴ・アールがマリア・マッキーと共作した「プロミス・ユー・エニシング」が入っていて。かつてお兄ちゃんがレコーディングしたとき、ステイシーがバック・コーラスで入っていた曲だ。なかなか味なオープニングって感じ。
で、他のすべての曲はステイシーのオリジナル。相変わらず独特の歌声で歌い綴っている。もう40歳になるんだとか。でも、まだまだキュートな感触を残したまま、お兄ちゃんの強大な影にも惑わされることなく、マイペースで成長を続けているようだ。スティーヴがドラッグとかでダメだった時期、ステイシーはちょうどバツイチ&子連れでがんばっていて、スティーヴの子供の世話なんかもしていたらしくて……そんな時期のことを歌っていたりするのも、なかなか興味深いです。
|

 |
Flying Saucer Blues
Peter Case
(Vanguard) |
|
この人も着実にいいアルバムを作り続けている。以前、ここでもレビューしているけれど、プリムソウルズをやめてソロになった当初はまだまだ腰がすわっていなかった彼も、その後じっくり熟成して、かけがえのないアメリカン・ストーリーテラーになったって感じ。
懐かしさ、無垢さを強くたたえた曲から、やり場のない諦観、挫折感をたたえたものまで。すべてがピーター・ケイス自身の物語でもあり、聞き手みんなの物語でもある、と。これはつまり、逆説的にすぐれたフィクションであるってことなんだけど。いい歌、書いてます。
|

 |
Chinese Work Songs
Little Feat
(CMC International) |
|
のっけ、いきなりザ・バンドの「ラグ・ママ・ラグ」のカヴァーでスタート。これが、大元のアレンジを大幅に崩すことなく、しかししっかりリトル・フィートしちゃってるというなかなかの出来で。ぐっと期待感が高まる。
他にもボブ・ディランの「悲しみは果てしなく」とか、フーターズの「ギミ・ア・ストーン」、フィッシュの「サンプル・イン・ア・ジャー」をカヴァー。この辺はけっこう聞かせてくれる。その他は、まあ、フィートらしいイメージをたたえたオリジナル曲なわけで。これは可もなく不可もなく。てことは――わりと楽しめたアルバムだったことを前提に言うんだけど――結局、この人たち、問題があるとすれば、昔ほどはいい曲が書けないってことが最大の難関なのかなぁと思った。
ロビー・ロバートソン抜きのザ・バンドとか、ブライアン・ウィルソン抜きのビーチ・ボーイズとか、いわば現在のフィートはそういうものなわけで。バンドとしては往年に劣らぬ立派なコンビネーションを聞かせてくれてはいるものの、ライヴで昔のレパートリーを演奏するとき以上の輝きを新作オリジナル・アルバムで発揮できるかというと、これがね、なんつーか、こう、聞き手側の“好感度”次第だったりするんだよなぁ。
なので、好感をもって聞けば問題なし。いい新作。でも、ぼくの場合、チマタで言われているほど新加入の女性シンガー、ショーン・マーフィが好きになれないもんで。そのせいもあって、首を傾げる局面も少なくはなかったです。
|

 |
Madeline
Randy Weeks
(Hightone) |
|
ちょっと前、ピーター・バラカンさんをお迎えしたときのCRTトーク&レコード・コンサートでも紹介した1枚。ピーターさんも興味を示してたな。ぼくはルシンダ・ウィリアムスとかキャシー・ロバートソンへの曲提供を通して名前を知ったんだけど、もともとは80年代からロンサム・ストレンジャーズなるバンドで活躍していた人らしい。
で、人脈的にはまさしくオルタナ・カントリー系の人ながら、このアルバムではむしろソウルフルな感覚が炸裂。ダン・ペンあたりの系譜としてとらえればOKかも。あくまでシンプルなアレンジで全編を貫く男気もよし。
|

 |
Jeremy Kay
Jeremy Kay
(Surfdog) |
|
今年のアタマに出たガレージ/パンク系アーティスト多数参加のサウンドトラック・アルバム『ルーズ・チェンジ』で、ちょっと異彩を放っていたカリフォルニア出身のシンガー・ソングライター。これがデビュー・フル・アルバムってことになるらしい。
フォークとソウルが絶妙に交錯する曲作り/音作りが持ち味。アコースティック・ソウルって感じ。そういう意味じゃ、ランディ・ウィークス同様、この人もダン・ペンの流れと理解してよさそう。プロデュースしているデイヴィッド・ダーリンって、メレディス・ブルックスを手がけていたあの人かな。
|

 |
Frankly A Cappella:
The Persuasions Sing Zappa
The Persuasions
(Earth Beat) |
|
今なお、永遠のストリート・コーナー・シンフォニーの美学を受け継ぎ続けるアカペラ・グループ、パースエイジョンズが、彼らをレコード・デビューさせてくれた恩人、フランク・ザッパのレパートリーをアカペラで聞かせる1枚。
これはすごいです。かっこいいです。こんな曲、アカペラになるのかよ……というものもやってて、盛り上がるけれど、やっぱりザッパのドゥーワップ・ルーツが全開になった『クルージング・ウィズ・ルーベン&ザ・ジェッツ』の収録曲が特にぐっとくる。
|

 |
Radigan
Terry Radigan
(Vanguard) |
|
パティ・ラヴレスやトリーシャ・ヤーウッドらへの曲提供でおなじみ、テリー・ラディガンさんの、たぶんセカンド・ソロ・アルバムだ。他人に提供する曲はけっこうポップ・カントリー系だったりするのだが、ここで自ら展開するのはよりカントリー度が低いポップ・ロック。なかなかよくできてます。いい曲多し。良く言えば、ジャッキー・デシャノンの現代版みたいな、そんな感じかも。
ただ、そつがなさ過ぎる感じもあって。個人的にはもうちょい“際(きわ)”の部分を狙ってほしい気がするなぁ。そっちもイケるキャラだと思いますが。
|

 |
Freedom
The John Doe Thing
(SpinArt) |
|
今回のジョン・ドウ・シングの新作は、ぐっと内省的なフォーク/カントリー味もまぶしたハイブリッド・トワンギー・ミュージックとでも呼びたくなるような仕上がり。まあ、この人の場合、Xに在籍していたころにもイクシーンやDJとともにザ・ニッターズってカントリー・プロジェクトをかましたこともあったわけで。そのスジへの素養は、たとえばソーシャル・ディストーション/マイク・ネスあたりと共通するというか、根っこの部分というか。
ジョーイ・ワロンカー、スモーキー・ホーメル、マニー・マークなどがバックアップ。1曲、エクシーンとデュエットしているのもうれしい。
|

 |
Love, God, Murder
Johnny Cash
(Columbia/American/Legacy) |
|
御大ジョニー・キャッシュが自選でコンパイルしたコンセプチュアルなベスト盤。“ラヴ”と“ゴッド”と“マーダー”をそれぞれテーマに、各1枚ずつコンピレーションを作って。基本的には3枚バラ売りされているんだけど、その3枚をひとつのボックスに詰め込んだものも出ていて。ぼくはそっちの箱のほうを買いました。
各16曲入り。アメリカでは未発表だった音源なども交えつつ、50年代から90年代まで、さすがは自選だけあって、ジョニー・キャッシュ色が横溢する楽曲が次から次へと飛び出してくる。特に“ゴッド”、つまり神に関する曲ばかりを集めたディスク2が素晴らしい。こいつを聞くとジョニー・キャッシュの深い歌声のさらに奥深くに潜む“意味”のようなものがほんの少しだけだけどわかってくるような気がする。
リマスターも最高。ジョニー・キャッシュ自身のライナーに加えて、ボーノ、クウェンティン・タランティーノ、そしてジューン・カーターが興味深い文章を寄せている。あ、そうそう、ジャケットに描かれた3つのマークのタトゥー・シールもオマケで入ってますよ。
|

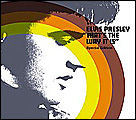 |
That's The Way It Is:
Special Edition
Elvis Presley
(RCA) |
|
映画『エルヴィス・オン・ステージ(That's The Way It Is)』(デニス・サンダース監督/MGM)の“主題歌集”という形で70年暮れにリリースされたアルバムをもとに、同じレコーディング・セッションで録音されたスタジオ音源を追加したり、映画のほうの『エルヴィス・オン・ステージ』のために収録されたライヴ音源/リハーサル音源をふんだんに盛り込んだりしながら、映画/アルバム両方の『エルヴィス・オン・ステージ』の魅力をより一層深く追求した密度の濃いパッケージ。CD3枚組での登場だ。
ディスク1の12曲目までが70年発表のオリジナル・アルバムの収録曲。その後に続く7曲が、主に『ラブ・レター・フロム・エルヴィス』に収録されたスタジオ音源中心のボーナス曲。ボーナス曲も含めて、70年6月のナッシュヴィル・セッションの充実ぶりを思い知らせる1枚として構成されているようだ。ディスク2は70年8月12日、ラスヴェガスのインターナショナル・ホテルにおけるミッドナイト・ショーの模様をオープニングからエンディングまでまるごと記録したもの。強烈なジェームス・バートンのロックンロール・ギターが炸裂です。でもって、ディスク3が、やはり映画のために収録された別の日のライヴ・パフォーマンスと、本番に先駆けて行なわれたリハーサルの模様。
未発表ものの中では、やはりリハーサル音源が特に興味深い。とにかく、映像としては公開されていたものの、レコードなりCDなりとしては未発表だった音源も含め、初お目見え音源が満載されたディスク2と3は強力だ。以前、ピック・オブ・ザ・ウィークで取り上げた『エルヴィス・カントリー』ともども、70年のエルヴィスがいかに充実していたかを思い知らせてくれる。
|

|