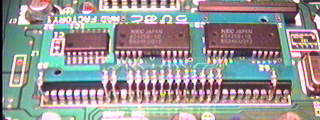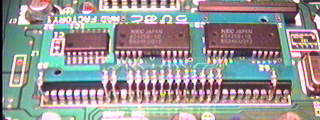■FM音源関連について
P88SR.EXEでは、サウンドボード2のエミュレーションにはPC-9801-86互換音源が必要です。
サードパーティ製のものの多くはFM音源部のみ互換となっていることが多く、ADPCMまで含めてエミュレーションするにはNEC純正品でなければなりません。サードパーティでは唯一、Q-VisionのWaveMaster/WaveMasterCard/Card86あたりが一応の互換性を持っているものの、PC-9801-86と比較してPCMの音質が落ちたり重かったりすることがあるという噂です。98ノート系ではCard86
/ WaveMasterCard以外の選択肢はないのでこれを使うしかないでしょう。
Q-Vision製WaveStarについては音源チップがYM2608(OPNA)からYMF288系に変わっているようなので、ADPCMのエミュレーションができない、CSM音声合成モードを使ったソフトがしゃべらないといった制約があります。
86音源でのADPCMのエミュレーションはかなりの負荷がかかります。スキームあたりを動作させるとよくわかるのですが、ADPCMが発音するタイミングでコマ送りしているかのように遅くなります。P88SR.EXEではOPNAの自体の持つADPCM機能を用いて実現されているようなのですが、発音の度にADPCMのデータをOPNAに転送してやる必要があります。データの転送はOPNAの仕様により8bit単位で、かつたっぷりとウェイトが乗っかるため(ウェイトを取らないとデータが化ける)、いくらCPUの処理速度が早くてもここがボトルネックになるのは目に見えています。
私が確認した限りでは、Xt16(Pentium-166MHz)でもほとんど処理が追いつかない現象を確認しています。
また、88のかなり後期には32kHz ADPCM再生を使ったソフトもありましたが(ワードラゴンなど)、これらはADPCMデータの転送がまず間に合わず、結果として「すごい音」が出ました。
これらの対策としては、サウンドボード2と同様に、最初からOPNAが持つADPCM用バッファのDRAM(256KB)を積んだFM音源ボードを使うことです。この仕様になっているFM音源ボードは、98のFM音源ボードの製品は数多く作られましたが、唯一α-DATA製の「スピークボード」だけでした。なお、スピークボードは当初販売がアイドルジャパン/開発がM.S.I.でしたが、その後M.S.I.が販売するようになり、さらにその後M.S.I.がα-DATA社と合併してα-DATAを名乗るようになったため、メーカー名は3種類の製品が存在しています。
このスピークボードは、FMP,PMD,MUAP,MXDRV98,MDRV2などの数多くのMS-DOS用のFM音源ドライバが対応し、数多くのデータが作成されました。
■ ちびおと (C)Mad Factory
86音源が登場した当時、86音源の(ADPCMと比較すると高音質な)PCM音源も魅力的ではあるが、過去との互換性も捨て切れないため、スピークボードと86音源のどちらを購入すべきか非常に悩む時期がありました。
86音源自体もOPNAが搭載されているため、要はADPCM用DRAMさえ追加で載せることさえできれば、86音源でもスピークボード対応のソフトが動作し、CPUが発音の度に転送を行う必要がないため、再生時の負荷も軽減されます。同人ハードウェアサークル「Mad
Factory」のGRIFF氏の手によって作られたサブボード「ちびおと」はこうして生まれました。これを実装したPC-9801-86では、P88SR.EXE上でADPCM対応ソフトを動作させても非常に軽快に動かすことができます。(なんでもPC-9801FA(80486SX-16MHz)でも問題なく発音されるとか。)
P88SR.EXEではこのようなADPCM DRAMを搭載したFM音源ボードに対応するための専用オプション(-p)が用意されています。このオプションを使う利点はもう一つあり、PC-8801Mシリーズで装備されている拡張128KB
RAMのエミュレーションを行うオプション(-M)と併用することができます。(通常、86音源のみではADPCMデータを読み込むメモリの関係上、-Mを指定するとADPCMの発音が行えなくなります。)
ちびおとの販売は現在でも行われているようですが、実装方法がOPNAの足への半田付けのため、半田ごてを扱う自信のない人は実装作業を依頼したほうがいいでしょう。また改造の範疇になりますのでメーカーのサポートは受けられなくなります。PC-9801-86以外への搭載も、OPNAが存在し物理的実装スペースがあれば可能です。(An/Ap2/As2は可能らしいですがAp/Asでは物理的空間がないため不可能だということです。しかし世の中にはフラットケーブルで信号線を引き出してまでAsに搭載したつわものもいました:-)
)
「ちびおと」関連の資料としては、前はあったんですがもうないです。
中身の「ちびおと.TXT」を抜粋しておきましたので、価格・申し込み方法などはこちらをご覧ください。(見ても買えません)
ちびおと購入方法の問い合わせなどは、Mad FactoryのGRIFF氏のページに詳細がありました。(過去形)
実装写真
(前からみたところです。)

(後ろからみたところです。)