母親集団の世代構成は、
団塊の世代から1950年代前半生まれ中心。
ポスト第二次ベビーブーム世代を産んだお母さんたちを集めたとしましょう。どんな世代構成になるでしょう?
その答えが、下のグラフ。
|
俯瞰図socio-economic macro-data on → ポスト第二次ベビーブーム世代 ・生息状況:出生(出生数/出生地)、生存と死亡(人口/全人口に対する構成比/)、 (c)Tirom!,2004. |
母親集団の世代構成は、 ポスト第二次ベビーブーム世代を産んだお母さんたちを集めたとしましょう。どんな世代構成になるでしょう? |
|
|
|
|
| 母親集団の世代構成の偏りが戦後最大 | |
1975年生まれの人たちの母親のうち、団塊の世代(1946-50年生まれ)は、53% 。1980年生まれの人たちの母親のうち、1951-1955年生まれは51% 。 この53% とか51%とか言う数字、大きいのか、小さいのか。「お母さんたちの半分以上が同一世代に集中してるなんて、そんな偏った話 …」と反応したほうがいいのか、「同一世代は、お母さんたちの半分だけで、ほかは、いろいろなのね」と見たほうがいいのか。 他の世代の母親集団の世代構成と比較してみよう(右グラフと下表)。 結論。53% 、51%は、きわめて大きい。1970-1975-1980年生まれの人の母親集団は、半分前後が同一世代に集中し、世代的に偏っている。 歴史的な流れをみよう。戦後直後生まれの人たちの母親集団は、多様な世代から構成されていた。これが、60年生まれ、65年生まれ、と、時を下るにつれ、その母親集団は単一の世代に集中していった。その集中の「きわみ」が、1975年生まれの人たちの母親集団。その53%が団塊世代に集中している。 ところが、この後、流れは反転する。80年代生まれ、90年代生まれ、2000年生まれと、最近生まれた人たちの母親ほど、世代的に分散化していった。 つまり、1970年代生まれ(第二次ベビーブーム世代+ポスト第二次ベビーブーム世代)は、戦後生まれの人たちのなかで、最も「世代的に偏った」「世代的に均質な」母親をもっているのだ。80年代前半に、子供の半分の間で成り立っていた「ボクのママも、キミのママも、同世代」という状況は、特殊「1970年代生まれ」的状況だったのだ。 この特殊「1970年代生まれ」的状況ゆえに、親子の世代間継承に着目した「団塊ジュニア世代」といったネーミングもある程度許容されているのだろう。 ところが、1950年代生まれや2000年生まれでは、親の世代が極めて分散している。このような世代に、「×ジュニア世代」などというレッテルを貼っても、説得的だとは思えない。 上図のデータソース最新版→ |
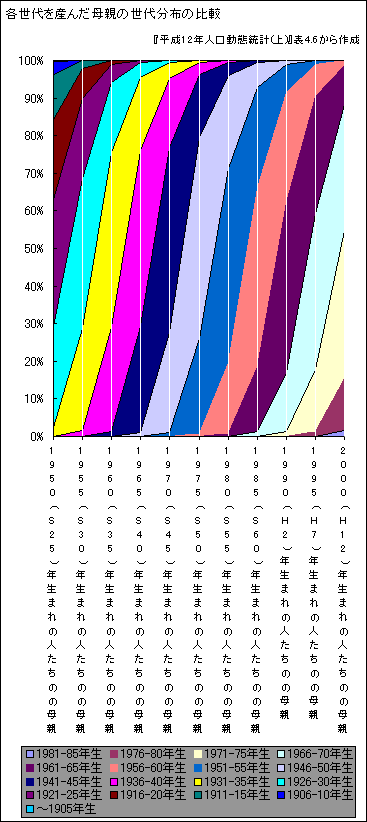 |
上図のデータソース最新版→『人口動態統計上巻』 資料所蔵機関検索→ここから |
上図のデータソース最新版 |
|
俯瞰図socio-economic macro-data on → ポスト第二次ベビーブーム世代 ・生息状況:出生(出生数/出生地)、生存と死亡(人口/全人口に対する構成比/)、 |
(c)Tirom!,2003.
![]()