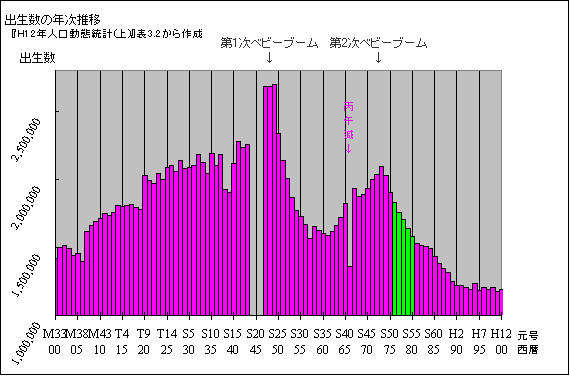
出生数の最新速報→平成15(2003)年人口動態統計年間推計
上図のデータソース最新版→『人口動態統計上巻』『人口動態統計中巻』『人口動態統計下巻』
資料所蔵機関検索→ここから
|
俯瞰図socio-economic macro-data on → ポスト第二次ベビーブーム世代 ・生息状況:出生(出生数/出生地)、生存と死亡(人口/全人口に対する構成比/)、 ©Tirom!,2004. |
| 1976-80年生まれの出生数 ― どれくらい生まれた? | ||||||||||||
|
出生数の最新速報→平成15(2003)年人口動態統計年間推計
|
|
|||||||||||
|
東京・大阪生まれが減少傾向。 「1975年の全国出生数」に対する「1975年の各都道府県別出生数」のシェアを示したのが左のグラフ、「1980年の全国出生数」に対する「1980年の各都道府県別出生数」のシェアを示したのが右のグラフ。 76−79年のデータは入手できなかったが、76年と79年を見比べると、北海道生まれが埼玉生まれを追い越した以外、大きく異なる点はないので、この間に、大きな変動はなかったのだろう(と信じたい)。 結果。東京・大阪生まれが多いのは、やっぱりという感じだが、それぞれ一割以内。「東京一極集中!」なんて言えるほどの迫力はない。 |
|
|
||||||||||
|
ポスト第二次ベビーブーム世代の半数弱が 行政単位としては別でも、我々の実際の活動・感覚からすると、東京・神奈川・千葉・埼玉、京都・大阪・兵庫は、不可分である。したがって、この二つの都市圏をまとめて、シェアを見るほうが、実態に即しているといえるだろう。東京・神奈川・千葉・埼玉を首都圏として、京都・大阪・兵庫を京阪神として、それぞれ一つにまとめたのが右図。 こうしてみると、同世代の四人に一人は首都圏生まれ、同世代の四割が首都圏・京阪神の二大都市圏生まれ、同世代の半数弱が、首都圏・京阪神・名古屋の三大都市圏生まれ。 また、大都市圏生まれの減少傾向も、注目すべき。 ポスト第二次ベビーブーム世代の出生地分布は、 以上見てきたポスト第二次ベビーブーム世代の出生地分布は、長期的趨勢のなかで、どのように位置づけられるのだろうか。 |
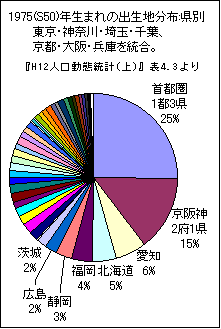 |
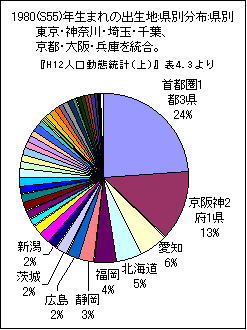 |
||||||||||
|
下の帯グラフは、1935年生まれから2000年生まれまでの出生地分布を示したものである。戦争の被害のためもあってか、終戦後、大都市圏生まれのシェアは、戦前の水準から低下していた。流れが変わったのは、昭和30(1955)年。首都圏・京阪神・愛知の三大都市圏生まれのシェアが急速に膨張。そして、その絶頂が昭和45年(1970)年。これ以降、90年代まで、三大都市圏生まれのシェアは、再び、停滞ないし収縮に向かう。 この三大都市圏生まれのシェアの収縮期にあたるのが、70年代後半のポスト第二次ベビーブーム世代であるといえよう。 |
||||||||||||
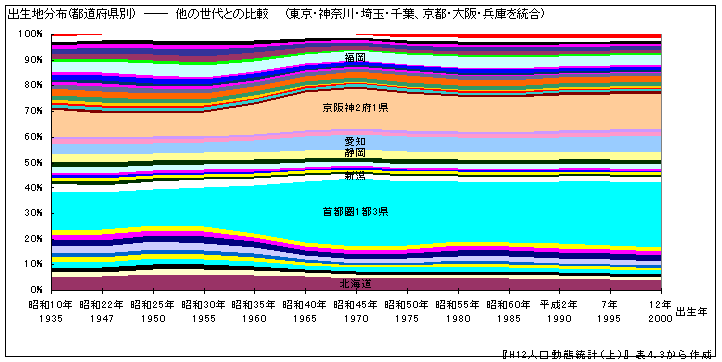 |
||||||||||||
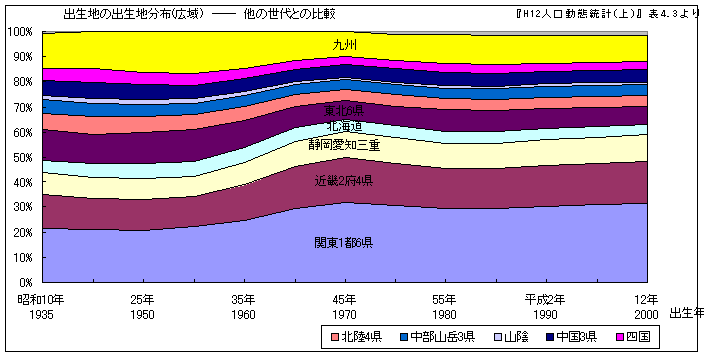 |
||||||||||||
|
俯瞰図socio-economic macro-data on → ポスト第二次ベビーブーム世代 ・生息状況:出生(出生数/出生地)、生存と死亡(人口/全人口に対する構成比/)、 ©Tirom!,2004. |
|
|
||||||
|
|
||||||