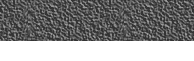 |
|||||||||||||||
 |
|||||||||||||||
|
↑NEXT
|
| 03.07.25 | Deep Purple Last Concert In Japan | |||||||
|
BurnとSmoke on the Waterは、確かによい。でも、そのほかの曲が眠すぎる。 あまりにありがちで、退屈で、単調で。 結局、すてきなアイディアがたまたま降ってわいてくれれば名曲になるけど、そんなにアイディアがでてこない、ごくふつうのときには、退屈な曲しかできない、というのが、ロックなのだろうか。 理論がないことが自由だと思われがちだが、実は逆なようだ。 理論なしに、無意識にやると、結局、みなれたもの、ひとがやっているようなものしか出てこない。 逆に、既成の音楽がどういうものなのかを、意識的に、理論的に研究し尽くすならば、そうでない音楽を理論的に構想することができる。 どうも、このあたりが、自由なはずのロックで、斬新なものは、ごくまれにしか出ず(だいたい、どのミュージシャンも、名曲といえる名曲は数曲しかもっていない)、不自由なはずのジャズやクラシック→現代音楽から、斬新で、いくら聴いても飽きない音楽が輩出される、メカニズムのようだ。 |
|
|||||||
| 03.07.20 | 『プロミス』 | |||||||||||
|
少年少女の目に映ったパレスチナ問題を、フィルムに焼き付けたドキュメンタリー。 イスラエル、パレスチナ双方から、何人かの子供を選び、インタビューしたものだが、少々変わった趣向。 はじめの方は、それぞれの子供に対する取材を別個に記録しているだけなのだが、そのうち、イスラエルの少年に、パレスチナの少年を取材したビデオを見せたり、パレスチナの少年に、イスラエルの少年を取材したビデオを見せるようになり、最後には、イスラエルの少年とパレスチナの少年を実際に引き合わせてしまうところまでいく。 感想。 ・パレスチナ問題についての子供の見解を通して、大人が家庭で話している本音が見えてくる点が興味深い。 ・パレスチナ問題、そして、その背後にある世界観に関して大きな断絶がイスラエル内部に存在することがあらわになっている点が興味深い。テレビなどみてても、世俗的なユダヤ人と、なかば狂信的なシオニストのあいだの距離を、ここまで、あらわにしたルポは、見たことがない。世俗的なユダヤ人の子供が、「嘆きの壁」で祈る信心深いユダヤ人をみて、怖がるという映像は、はじめて見た。 ・イスラエルの子供の話からは、全く地に足の着かない、ある種「幻想的な」印象を受けてしまう。対して、パレスチナの子供の話からは、地に足についた現実的な印象を受けてしまう。パレスチナ人地区で何が行われているのかに対して、目隠しをされ、「きれいな世界」内部で育ったイスラエルの子供と、現実の中で全てを見てしまわざるを得ないパレスチナの子供の違いということになるのだろうが、興味深い。 なお、監督は、イスラエルで生まれ育ったが、その後米国へ渡ったユダヤ人。 そして、世界のユダヤ人内部で、パレスチナ問題にたいする見解が、現在どのような状況にあるのか(「一枚岩」とか、「対立がある」とか、あるいは、「イスラエル政府が怖くて批判したくても批判できないひとが多数」だとか、)、知りたくなってしまった。 一度目は、ジャーナリスティックな関心で、へー、こんな風なのか、などといって見ていましたが、二度目は、人間って、なんて悲しいんだろう、と、涙で目をウルウルさせながら、見てしまいました。 結構、お勧めの作品。 |
|
|||||||||||
| 03.07.12 | 永六輔 | |||||
|
土曜の午前中。 J-Waveがいまいちつまらないので、tbsラジオを聴く。 もちろん、永六輔の時間。 彼いわく「フランス革命があったからアメリカがあるんです。」フランス革命の影響でアメリカが独立した、だから、フランスの民主主義の方が伝統がある、アメリカは生意気だ!といった論調。 たぶん、永六輔氏は、アメリカ独立戦争が、フランス革命より前に起きたということを知らないのだろう。もちろん、フランスの思想家の影響があったこと、アメリカ独立のために戦ったフランス人の義勇兵もいたなどなどを持ち出して、フランスのアメリカ独立への影響を強調することはできるだろう。しかし、フランス革命があったから独立戦争が起きた、というのは、時間的前後関係が逆転している。アメリカが独立したときまだフランスでは革命は起きてない。もう一度教科書をみようね。 そういえば、何週か前、永六輔氏が、「外山君。なんで三越っていうか知ってますか?三井と越後屋が合併したから、三越になったんです。」とか何とか言っていた。おや、そうだっけ、もともと、経営者が三井さんで屋号が越後屋じゃなかったっけ、と思い、僕は図書館で経済史の本を引っ張り出してみた。経済史の大学教授の執筆した本によれば、やっぱり、永六輔氏の間違い。もともと、三井が商売をはじめたのは、伊勢松坂。はじめは酒・味噌の販売と質屋を手がけていたという。越後屋の由来は、このころ、「越後殿の酒屋」と呼ばれていたからとのこと。では、なぜ、「越後殿」なのか?なんと、松坂に出る前、三井氏は武士で越後守だったのだ!六角佐々木氏の家臣だったが、1582年滅亡、松坂に移り住み、武士を離れ商人となったのだという。 正しい知識を語るのには才能は要らない。労力を使えば誰でもできる。しかし、嘘出鱈目を話して稼ぐというのは、誰でもはできない。きっと、これが才能というものなのだろう。 |
|
|||||
03.07.05 |
ヒデキ | |||
|
資料を見ていたら、林英機という名前が目に付いた。「どういうヒデキですか?」と訊かれたら、「西城のヒデキでなくて、東条のヒデキです!」って答えるんだろうなあ、このひと、などと、ぼんやり頭の中に思い描いていた。 それでフッと気づいた。「西ジョウ・ヒデキ」って芸名、たぶん、「東ジョウ・ヒデキ」のパロディ。何の確証もないけど。 東を西に変えて、別の漢字を当てて出来上がり。 |
||||
