日本の歴史認識 > 小論報: 卒業式封鎖と1968年5月革命
R29
卒業式封鎖と1968年5月革命
2025/10/12
私の青春時代の思い出の一つに、高校の卒業式の封鎖(中止)があります。あれから半世紀以上が過ぎ、当時、世間をにぎわした「学生運動」などはすでに世界的な「歴史」として刻まれるようになってきています。ではその「歴史」はどのように刻まれているのでしょうか、私なりに調べてみたら、思った以上に重要なポイントとして認識されているようです。
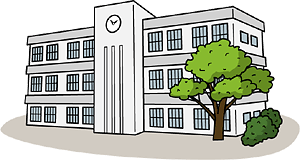
1969(昭和44)年3月13日、高校生としての最後の朝、私はいつもより少しシャキッとした学生服姿で自宅を出ました。最寄りの駅から歩いて校門の前まで来ると、校門は封鎖され、警官の姿もチラホラ見え、異様な雰囲気に包まれていました。事情がわからないまま、ウロウロしていると、誰かから「学校は封鎖された、卒業式は中止だ、今日は帰宅せよ」と言われ、エッ何?と思ったけどそれ以上、聞いても答えてくれるような雰囲気でなく、すごすごと自宅に引き揚げるしかありませんでした。
それから約1カ月後、大学の入学式に行くと、あちこちに立て看板が立ち、騒然とした雰囲気の中で式は行われました。その頃、テレビや新聞は、連日のように「全共闘がぁ!」と叫んでおり、それは、次第に収束しつつ、私が大学を卒業するころまで続きましたが、最後にはいわゆる浅間山荘事件、となって消えました。
私はこうした活動を肯定するわけではありませんが、その歴史的背景や意義が世界でどのように見られているかを知ることは大切なことではないか、と思います。
こうした若者たちの「反乱」は日本だけのものではなく、またゲバ棒や立て看板のみならず、音楽や美術その他様々な手段を通して、世界中あちこちで繰り広げられていた行動でした。それから半世紀以上が過ぎ、世界の歴史学者たちはこれらの活動を「1968年5月革命」と呼んでいます。
「革命」のきっかけとなったのはパリ大学の騒動です。1968年2月、パリ大学で男女学生寮間の往来を禁止する規則の撤廃を求めて学生たちが騒ぎ出し、火炎瓶が投げられる事態となりました。背景には、戦後のベビーブームに加えて大学の大衆化が進み、学生人口が大幅に増加したことがありました。学生たちは大学運営に関する問題だけでなく、ド・ゴールの独裁的な政治にも抗議し、5月13日に数十万人のデモとなり、17日には学生に共感した労働者1000万人がストライキに入りました。

同様の学生運動はドイツでも起こり、アメリカや日本にも波及しました。日本の場合、世代間ギャップ、つまり当時の社会の指導者層が戦前の教育を受けた人だったのに対して、若者たちは戦後教育を受けており、価値観のギャップが大きかった、という問題もあったかもしれません。ただ、いずれの国においても大学内の問題だけでなく、ベトナム戦争への抗議や人種差別・奴隷解放、(ヨーロッパの)身分制社会の撤廃などを訴えた運動を触発しました。
名著「近代世界システム」を著したI.ウォーラーステインは、500年続いた「資本主義的世界経済」がいま分岐点に到達しつつあるか、あるいはすでに到達してしまっている、としたうえで、次のように1968年の革命は分岐点のひとつであり、冷戦の終結に大きな影響を与えた、と述べています。
{ 「史的システムとしての資本主義」の分岐点として、1968年の世界革命の影響は、次の分岐点である1989年の共産主義の崩壊まで続き、それを含むものであった。1968年の世界革命は、地域によって多様な形態をとって発現したが、そのなかには…アメリカ合衆国のへゲモニーに対する叛乱があった。他方で、旧来の社会民主主義なども拒否された。… 1968年の革命派にとっては、改良主義、啓蒙主義の価値観、変革の政治的道具としての国家機構への信頼、の3つに反対した。彼らがまとっていた対抗文化の衣装は個人主義の肯定ではなく、個人の資質を十分に発揮できる方向に向かう圧力を支持した。
こうした彼らの要求は、資本主義的世界経済の中核地域では比較的認められたが、社会主義諸国で認められることは少なかった。それらの政権には68年革命のような運動が政府の政策にかけるはずの圧力がなかったからである。}(I.ウォーラーステイン著川北稔訳「新版 史的システムとしての資本主義」(1995年),P221-P223<要約> 下線は筆者)
註)ウォーラーステインの「近代世界システム」についてご興味ある方は、こちら をどうぞ。
これらの運動はまた、若者たちの生活や文化とも共鳴しました。若者たちをひきつけたのが、ビートルズやローリング・ストーンズといったロック・グループやボブ・ディラン、ジョーン・バエズ、PP&Mといったフォークシンガーたちであり、1969年8月に行われたウッドストックに熱狂したのも1968年革命の延長線上にある行動といっていいでしょう。ベルリンの壁の向こう側から聞こえてくるビートルズが東ベルリンの人たちを刺激したのです。

ベルリンの壁(筆者撮影)
ジョン・レノンはこう言っています。
「突然、僕らは選ばれた者となり、あらゆる自由への導火線に火をつけた。僕はその導火線に火をつけた張本人は、60年代という時代そのものであり、僕らはその一部に過ぎなかったと思っている」。
(参考文献: I.ウォーラーステイン著 川北稔訳「史的システムとしての資本主義」(1995)、松尾秀哉「ヨーロッパ現代史」(2019)、NHK映像の世紀「世界を変えたビートルズ」)
以上