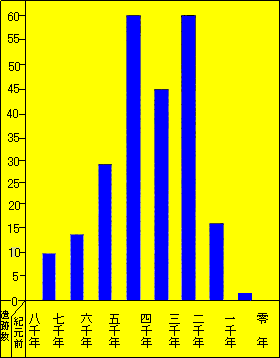寒冷な氷河期が過ぎ、地球は次第に温暖化していき、針葉樹林や草原から照葉樹林
(常緑広葉樹林)や広葉樹林が広がっていき、様々な木の実が豊富になり、動物は大型
哺乳動物に代わってイノシシ、シカなどが繁殖するようになりました。
<土器の発明>
今から1万2千年ほど前になると人々は土器を作り出し、煮炊きをしなければ食べる
ことの出来ない堅い物や、生では体に毒となる食べ物を食料とすることが出来るよ
うになり、食料を保存し四季を通しての食料の安定化を図るようになりました。
縄文時代は使用された土器形式の変化によって次の様に六期に分けられています。
【三浦半島の縄文時代実年代区分(BC)】
草創期 10000~7000年
早 期 7000~4500年
前 期 4500~3000年
中 期 3000~2000年
後 期 2000~1000年
晩 期 1000~ 0 年
【縄文土器の変遷】
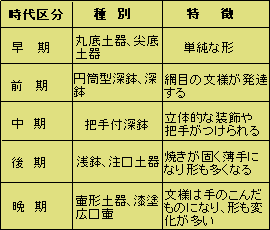 | 
吉井貝塚で発見された縄文式土器
(横須賀市立博物館蔵) |
縄文人の生活を知る貴重なものに貝
塚があります。
三浦半島では夏島貝塚と平坂貝塚が
よく知られています。
夏島周辺は太平洋戦争終了までは海
軍航空隊の基地でしたが、太平洋戦争
終了後、アメリカに接収中の1950年と
1955年に貝塚の発掘調査が行なわれ、
釣針などの動物の角や骨で作った道
具やそれまであまり例がなかった縄
文時代早期の土器が見つかり、今から
9500年ほど前の日本で最も古い貝塚
の一つであることが分かりました。
平坂貝塚は1948年、当時小学校5年生
だった藤井泰造君が横須賀の平坂坂
上で発見したもので、土器のかけら、
石器や骨角器(動物の骨で作った釣
|
| 針)などにまじって「平坂人骨」と呼ば
れる人の骨が今からおよそ7千年前の
ものと分かりました。
 夏島貝塚(横須賀市・夏島町)
夏島貝塚(横須賀市・夏島町)
|
温暖化と人口の増加により自然の資
源の採集のみに頼っていた縄文時代も
資源の枯渇により、行き詰まります。
三浦半島ではBC3百年頃になると、
殆ど人の生活の跡が見られなくなり、
山裾の低地から土器片を僅かに散見で
きる程度です。
採集文化の限界は、縄文文化圏のいず
れの地域でも見られますが、特に三浦
半島ではこの現象が他のどの地域より
も早く、より鮮明に現れています。縄文
時代の終わり近づくと遺跡の減小と土
偶、石棒など神頼み用祭祀具の増加か
らこれを窺うことが出来ます。
前のページへ
次ページへ
トップページへ
| | 三浦半島の遺跡推移
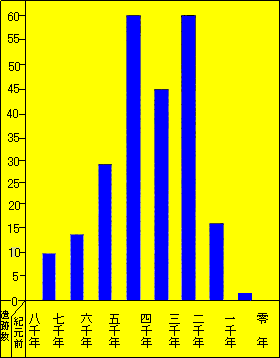 |
|
略 年 表
縄文時代
草創期
BC10000
夏島貝塚
~7000
早 期
BC7000
平坂人骨
~4500
前 期
BC4500
~3000
中 期
BC3000
~2000
後 期
BC2000
~1000
晩期
BC1000
~0
|
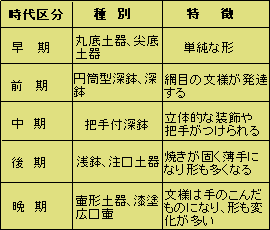

 夏島貝塚(横須賀市・夏島町)
夏島貝塚(横須賀市・夏島町)