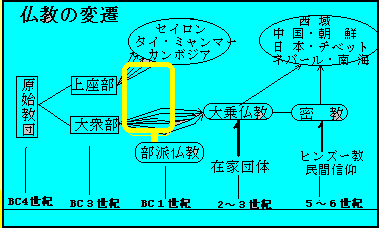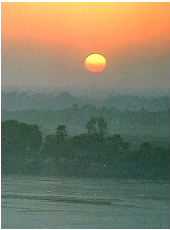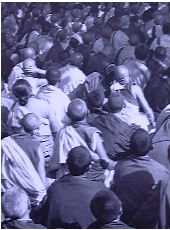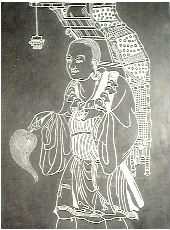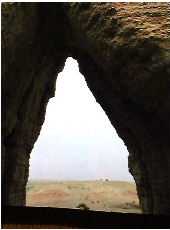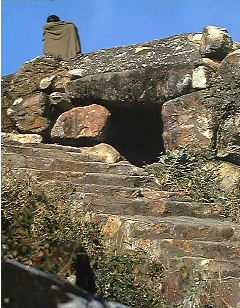原始教団の分裂 |
釈尊入滅(紀元前383年)後最初の雨安居(*1)にラージャグリハで釈尊の教えの正確な伝承(口誦)のために、弟子たちによる編集会議が行われました(第一結集)。
第一結集の100年後第二回目の編集会議(第二結集)が行われましたが、この時教団は保守派と進歩派が戒律や釈尊の教えについての解釈をめぐって対立し、上座部(保守派)と大衆部(進歩派)に分裂します。
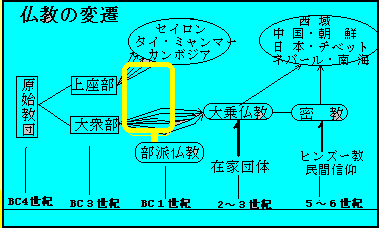 |
(*1)雨安居
インドでは4月15日(または5月15日)から3ヶ月間が雨期にあたるので、修行者たちはその間洞窟や寺にこもって修行しました。これを雨安居といいます。 |
部派仏教の成立 |
釈尊の教えについての解釈についての論争や派の分裂はその後も続き、紀元前100年頃には上座部が10、大衆部が8つという部派に分かれますがこの時代の仏教を部派仏教と言います。
部派仏教の特徴
大衆部系はのちに大乗仏教の母体となりますので、部派仏教の特徴は上座部仏教の特徴としてとらえられます。
①一仏思想・・・・・仏陀(悟りをひらいた者)は一時代には一人し
か現れないという考えで釈尊の時代は釈尊の
みが仏陀であるという考え(*2)。
②自利自覚・・・・・自分だけが悟り救われることに重点があり、
他を救済することは比較的おろそかでした。
③出家主義・・・・・悟りを開くには僧侶のならねばならないとして
在家の信仰には無関心のきらいがありました。
④形式主義・・・・・釈尊の決めたことはすべてきめられたとおり
受け取り時代の変化に対応しませんでした。
|
(*2)過去仏と未来仏
一仏思想では過去には七人の仏陀が現れ釈尊はその七番目であり、第八番目の仏陀は現在都率天に待機している弥勒が五十六億七千万年後に出現することになっていると考えられました。
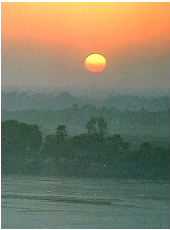
釈尊が体を清めたナイランジャナー河
(田村仁・仏陀の風景)
|
大乗仏教の成立 |
紀元前一世紀ころから戒律や教法にこだわりいたずらに伝統にこだわり形式化しつつあった部派仏教にあきたらない大衆部と在家の信者の団体により大乗仏教が生まれました。
大乗仏教(*3)の特徴
①多仏思想・・・・・この世においても仏陀は十方いたるところに
満ちみちているという思想(*4)で内在仏思想
(仏陀が現在既に人々の心の中に存在すると
いう考え方)にまで発展しました。
②利他・覚他・・・・・自分一人の悟りを求めるだけでなく自分の悟
りを人々にも及ぼし、他者の救済をめざす活動
を理想としました。 ③在家主義・・・・・出家した僧侶だけでなく在家の信者にも菩薩
(*5)としての修行(他者の救済をめざす活動)
をすすめ六波羅密(*5-2)の完成により誰で
も仏陀になれることを主張しましました。
④直観主義・・・・・それまでの分析(分別)的手法=知識による
理解=に傾きすぎ、民衆から敬遠されつつあっ
た仏教を、直観(無分別)的実践=本当の真理
を悟る心=に重点をうつし大衆の手に戻そうと
しました。
大乗思想の変遷
大乗思想は三世紀に活躍した竜樹・堤婆を中心とする中観派
と四世紀に活躍した無着・世親を中心とする唯識派によりさらな
る発展をとげます。
中観派は一切の存在は因縁・縁起によって成立したものであ
り絶対的、永遠、不変なる実体はないとする空の思想とともに
虚無を否定する中道を説きました。
唯識派は竜樹の「この世のものはすべて空である」という主張
を認めながらも、それは人間の意識があってはじめて認識され
識こそ(唯識)絶対者であるという唯識思想を説きました。
|
(*3)大乗仏教と小乗仏教
人々を迷いの世界から悟りの世界へわたすことを乗り物にたとえて「乗」といい、大乗仏教とはすぐれた乗り物という意味です。これにたいして大乗仏教派は部派仏教をけなして小乗仏教(劣った乗り物)と言いました。
(*4)多仏思想
代表的なのが西方極楽浄土の阿弥陀如来、東方瑠璃光世界の薬師如来。
(*5)菩薩
従来は修行者として仏道に励むものという意味でしたが大乗仏教ではこれに他者の救済を目指す活動も加え仏教徒の理想像としました。
(*5-2)六波羅密
菩薩が実践すべき六つの行
いで六度とも云います
①布施・・・困っている人に物
心両面から施しをすること
②持戒・・・戒律をまもること
③忍辱・・・完全な忍耐
④精進・・・理想に向かって努
力すること
⑤禅定・・・正しい精紳統一
⑥智慧・・・すべてのことを明
確に見抜く鋭い理知。
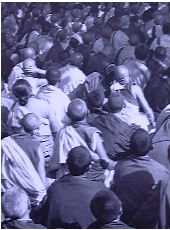
説法を聞く僧達(田村仁・仏陀の風景)
|
密教の成立 |
五、六世紀頃になると大乗仏教は哲学理論や注釈学的な専門
化に陥り、衰退の兆しがあらわれ、ヒンズー教が台頭してきました。
そこで民衆にとって難解な教理を、当時のインド一般の風潮であった象徴主義によって理解しやすくすると共に、ヒンズー教や民間信仰も取り入れて、仏教の理想実現と勢力回復を図ったのが密教だと言われています。 密教の特徴
①神秘主義・・・・・手に印を結び(手の指で種々の形をつくるこ
と)、口に真言・陀羅尼(*6)を唱え、心に本尊
(大日如来)を念ずることによって、仏の不思議
な力により煩悩にまみれた生身のまま成仏(即
身成仏)できるとされています。
②象徴主義・・・・・密教の教えを分かりやすくするために、曼荼羅
などのシンボル(象徴)を使います。
③祭式主義・・・・・加持祈祷とくに護摩の儀礼が重要視されてい
ます。これはバラモン教の儀式がとりいれられ
たもので護摩によって息災(災難をはらうこと)・増
益(繁栄をいのること)・調伏(怨敵をのろうこと)が得ら
れるとされています。
|
(*6)真言・陀羅尼
真言とは呪文のことで、この言葉の霊力で人々の願望が成就され現世の安穏と利益がえられるとするもので、長文のものを陀羅尼、短文のものを真言といいます。

護摩壇
(東京美術・目で見る仏像)
|
アジアへのひろがり 仏教伝播図
|
紀元前3世紀半ばにインドを統一した阿育王(アショーカ王(*7))はインド各地に仏教をひろめましたが更に世界各地に使節を派遣して世界的宗教としての基礎をつくりました。
部派仏教の流れ
阿育王によって部派仏教は南方地方に広まり、今日もなお脈々として生きつづけています。
[セイロン]・・・・・阿育王によって派遣されたマヒンダ王子と四人
の上座部長老によりセイロン仏教の基礎がつく
られ後世ミャンマーやタイの仏教に大きな影響を
与えました。
[ミャンマー]・・・・・五世紀頃セイロンの上座部が伝えられ、その
後大乗も伝わり両派併存時代もありましたが、十
一世紀の半ばアノーラタ王がビルマを統一した時
上座部を国教的地位においたため、以来上座部
が主流になっています。 [タイ]・・・・・十三世紀の初め上座部はミャンマーからタイへと伝
わり、歴代の国王が帰依したため仏教は国教となりま
した。寺の費用は国費で支出され教団の役員は公務
員となるなどタイは完全な仏教国です。
[カンボジア]・・・上座部と大乗、それにクメール人の民俗信仰が
が溶け合って独自の発展をとげ、アンコール
(クメール王朝の首都)のトムやワットの仏教芸
術を生み出したのですが、現在はセイロン上座
部が主流になっているようです。
大乗仏教の流れ
大乗仏教は紀元前一世紀頃からおこり、数百年かけて完成されたものですが、その間さまざまな形でインドの内外へ拡がりました。
[西域]・・・・・シルクロードの道として知られるこの地域には紀元
前一世紀頃に伝えられたものと考えられています。
ここには「西域仏教」とも言はれるものが生まれ、特
に仏教美術の面では注目すべき成果があります。
[中国]・・・・・中国へは西域を介して紀元前後伝来、当初は一部
の知識層の間のものでしたが、二世紀以後三国時
代、五胡十六国時代となり国内の政情不安定から
各国の王たちは国家の鎮護と安泰を仏教に求め競
って西域の僧を招き(渡来僧)、また身命を顧みずイ
ンドに渡り(求法僧)仏法を求めた人たちにより中国
各地に広まることになりました。
渡来僧では多くの経典を漢訳した鳩摩羅什、また
求法僧では三蔵法師のモデルになった玄奘(*8)が
有名です。
中国にはいった仏教は儒教や道教の影響を受け
て独自の発展をとげます。
膨大な仏教原典の翻訳がなされ、多くの宗派がで
きました。
その後も幾多の変遷をへながら文化大革命など
動乱の時代をくぐりぬけて人々の間に根をおろしま
した。(詳細はこちら)
[朝鮮]・・・・・朝鮮半島への伝来は四世紀の中頃といはれており
高句麗と百済がその舞台だったようです。
中国の隷属的立場にあった朝鮮では、中国の仏教
発展にともない経典や教理だけでなく、西域や中国
で実をむすんだ仏教美術も多く移入されています。
[日本]・・・・・わが国へは六世紀半ばに朝鮮から伝えられました
が「日本の仏教」のところで説明します。
[チベット]・・・・・七世紀頃インドから密教を主体に直接伝わり、
ラマ教として発展します。
その後ダライ・ラマ(*9)の活躍などでモンゴルや
中国、シベリアなどにも広がりました。
[ネパール]・・・・・インドから直接伝わり、ことに十二、三世紀頃イ
スラム教徒によって迫害を受けた僧侶たちがヒマラ
ヤ山中に逃れたため、多数の梵語仏典が伝えられ
たようです。
[南海]・・・・・インドネシア地方(マライ、スマトラ、ジャワ、ボルネ
オ、セレベス)にも伝わり、十四世紀ころイスラム教
の進出により衰退するまで栄えていたようです。
|
(*7)アショーカ王(BC268~232)
王位争奪のために多くの兄弟を殺し国家統一のために数十万の人々を犠牲にしたことを後悔して仏教に帰依、全国各地に精舎(寺院)・仏塔を建立、仏教の普及をはかり釈尊ゆかりの地を巡拝し、各地に供養の石柱を建立しました。

アショーカ王の石柱(サルナート考古博物館蔵)
(*8)玄奘(602~664)
13才のとき洛陽の浄土寺で出家、仏教を学びインド留学を決意しましたが国王の許可を得られぬまま、629年に長安を立ち、中央アジアを経てインドに入り、仏典を学び645年に帰国しました。16年のおよぶ困難に満ちた旅は「大唐西域記」に記されています。
(玄奘の行程はこちら)
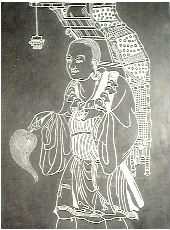
玄奘の旅姿
(三蔵法師の道・松本栄一)
*(9)ダライ・ラマ
モンゴルへの布教に成功したソナムギャンツオ(1543~88)は1578年モンゴルの王より「ダライ・ラマ」の称号をうけました。
ダライとはモンゴル語で大海(偉大)、ラマとはチベット語で高僧の意味です。
ダライ・ラマ五世(1617~82)は1642年チベットを統一、ダライ・ラマ十四世(1935~)は欧米でのチベット仏教の普及活動に対し1989年ノーベル平和賞を受賞しました。
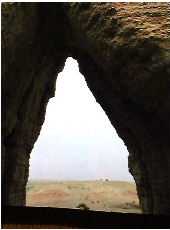
シルクロードへの起点玉門関
(松本栄一・三蔵法師の道)
|
インド仏教の衰退 |
六~七世紀頃よりインド本土の仏教はヒンズー教の台頭とイスラム教の侵入により次第に衰退します。
ヒンズー教はバラモン教がインド在来の民間信仰を取り入れて成立した宗教で、民衆は次第に仏教からヒンズー教を信奉するようになり現在は人口の約8割がヒンズー教徒と言われています。 ヒンズー教が勢いを得つつあった八世紀の初め、アラブ人の軍隊がインダス河中流地域に侵入し仏教を圧迫しましたが、13世紀の初めデリーを拠点とするトルコ系異民族の政権成立とともに遂にはインド本土における仏教の殆どが滅び去ることになります。
近代になってアンベードカル(1891~1956)によってカースト制を否定する仏教が再評価、復興されますが現在では仏教徒は600万人(人口の0.7%)に留まっていると言われています。
前ページへ
|
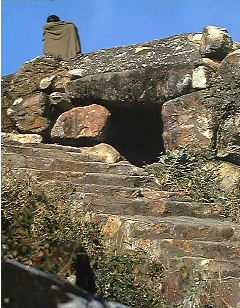
王舎城跡
(田村仁・仏陀の風景)
|