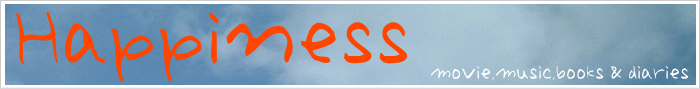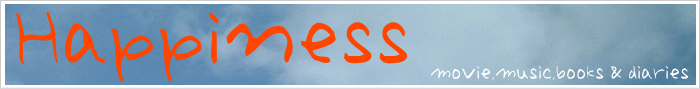|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |

この画像をクリックするとamazon.co.jpの各商品紹介ページにジャンプします。試聴や解説、たくさんのレビューが読めますので、ぜひ参考に! |
|
 |
| トップページ> 音楽> 2005年 > 12月 |
 |
December, 2005 |
 |
| John Legend |
| Get Lifted |
|
 |
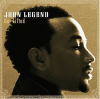 |
01. Prelude
02. Let's Get Lifted
03. Used To Love U
04. Alright
05. She Don't Have To Know
06. Number One
07. I Can Change
08. Ordinary People
09. Stay With You
10. Let's Get Lifted Again
11. So High
12. Refuge (When It's Cold Outside)
13. It Don't Have To Change
14. Live It Up |
 |
 |
 公式サイト(英語) 公式サイト(英語)
 Release Date : 2004.12.28 Release Date : 2004.12.28 |
|
 |
うわぁーーーー、想像以上にいい!!!
グラミー賞に多数ノミネートされたことをきっかけに
買ってみました、ジョン・レジェンド。
カニエ・ウェストが発掘したアーティストだというのが
売り文句なだけに、バリバリ最先端のR&Bかと思いきや!
心温まるソウル・ミュージックでした!
カーティス・メイフィールドの曲をサンプリングした
"Number One"なんて、すんげぇかっこいいし!
彼が弾くピアノの音色のあたたかさと
カニエが薄味に味付けしたヒップ感覚が
うまいことマッチしてますねぇ。
おそらく、ピアノだけでも充分に魅力的なんでしょうけど
(特に、やっぱり"Ordinary People"は絶品!)
その上にいろんなトッピングを盛り付けることで
より一層魅力的な音楽にランクアップしてる感じね。
で、ジョン・レジェンドの生い立ちを
日本のレコード会社のサイトでながめてるんですけど、
「ジョンは、音楽に溢れた家庭で育ち、
幼少時代に祖母からゴスペルとピアノを弾くことを教わり、
8、9歳の頃には教会の聖歌隊で演奏していた。」
って書いてあるところで、激しく納得してしまいました。
アメリカにはそういう土壌があるんだよなぁ。
ゴスペルに聖歌隊。
音楽に囲まれた毎日。
こういう人たちには、かなわないよなぁ。
久保田利伸がいくらがんばっても
宇多田ヒカルがどんなに才能を開花させても届かない世界に
ジョン・レジェンドのような人はいるのかもしれない。
なーんて、遠い目をしてしまうほど、素晴らしい音楽。です。 |
| posted on 2005.12.16 |
|
| ▲TOP |
| Starsailor |
| On The Outside |
|
 |
 |
01. In The Crossfire
02. Counterfeit Life
03. In My Blood
04. Faith Hope Love
05. I Don't Know
06. Way Back Home
07. Keep Us Together
08. Get Out While You Can
09. This Time
10. White Light
11. Jeremiah |
 |
 |
 公式サイト(英語) 公式サイト(英語)
 Release Date : 2005.10.17 Release Date : 2005.10.17 |
|
 |
イギリスの「叙情派」ロックバンド、スターセイラーの3作目。
今回は、ベックや故エリオット・スミスのプロデュースで有名な
Rob Schnapf を迎えて、ビシッとした作品に仕上げてきました!
デビュー作は、
「沈む太陽に向かって、一本道を着実に歩いていく青年」を
イメージさせる、おぼろげだけど力強い雰囲気。
2枚目は一転して、何かを吹っ切ったような突破力のある
雰囲気があって、ビックリした記憶があるんですけど、
この3枚目は、その2つの中間的な感じがして、好きです!
今まででいちばん好きかもしれない。
聴いてると、なんか「集中力」を感じさせてくれるんですよね。
視点がひとつに定まった感じというか。
ビシッとしてるんです。背筋がシャンとしてるんです。
目が本気なんです。
「次のオアシスはコイツらだ!」みたいな喧騒から離れて
ようやく自分たちの音楽が表現できるようになった、
その証しがこの1枚に現れてるのかなぁ、なんて思いました。
タイトルもジャケ写も、「外側」にいることを表していますしね。
と、感想は短いですが、激しくオススメします!
ただし、日本盤はCCCDですのでご注意を。 |
| posted on 2005.12.08 |
|
| ▲TOP |
|
 November,2005 | back number | January,2006 November,2005 | back number | January,2006  |
|
 |