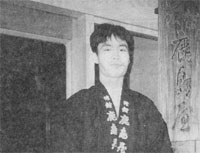 第57回定演で取り挙げたこの曲のことを振り返ると、多くの皆さんに沢山の手間をかけたことが思い出されます。特に管楽器の上回生の方々には負担が大きな曲であったに違いありません。そしてパーカッションの皆さんにとっては、人数自体足りないことに加えて団が所有していない楽器の調達、運搬、賛助OBの方へのコンタクトなど、練習以外のマネージメント面においても大変な苦労を強いてしまったのではないかと思います。 第57回定演で取り挙げたこの曲のことを振り返ると、多くの皆さんに沢山の手間をかけたことが思い出されます。特に管楽器の上回生の方々には負担が大きな曲であったに違いありません。そしてパーカッションの皆さんにとっては、人数自体足りないことに加えて団が所有していない楽器の調達、運搬、賛助OBの方へのコンタクトなど、練習以外のマネージメント面においても大変な苦労を強いてしまったのではないかと思います。この曲がピックアップされたのは自分たちからの発想ではなく、実は、客演指揮者の金洪才先生からの提案が発端でした。これはPL会議をやっていたある晩のこと。夜10時頃の先生との電話でのやりとりの中でこの曲の提案を頂きました。そして、僕がその翌日朝一番に当時香林坊にあった楽譜屋ミューズ・インへ行くと、その時届いたばかりの宅急便の荷物の中に偶然にもこの曲のスコアが入っていたのです。スコアとCDをチェックしたところオーケストラの編成は3管編成でトロンボーン、チューバも入っていること、演奏時間が20分程度で(比較的短く負担が軽いこと)あること、弦楽器については一部演奏不可能と思わせる譜面があったものの全体としては負担が少ないと思われたことなどが、この曲を有力候補にしました。 ここで当時の団の音楽面の運営状況などついて話を少し、広げてみましょう。 この頃、校舎が角間移転したことも理由のひとつだったかもしれませんが、長老と呼ばれた方々がステージにのらなくなり、平均年齢が下がっていく傾向がありました。 そんな中、僕は1994年、1回生の秋にはじめて選曲会議に参加するようになりました。 今練習している55回定演が終わったら次の20回サマコンはどんなメンバーになってしまうのだろうかという不安。この曲ではメンバーが組めない、難しすぎる・・、負担が大きすぎる・・、などと問題が思い浮かぶばかりでした。選曲会議の中では試聴する曲でもなじみの曲には耳が向くけれど、耳に慣れない曲はただ聴き流すだけで、自分達の知っている曲だけに関心が向くという傾向がありました。僕自身についても、全くこの通りだったと思います。まず、知っている曲数が圧倒的に少なかったし、さらに、曲の内容なんて十分理解できませんでした。選曲会議の雰囲気も消極的になりがちでした。 この時(20回サマコン)は最終的に運命をメインプログラムにすることで団員の気持ちを鼓舞しようと前向きな結論を得て選曲を終えました。 僕は都合4回の選曲に関わりましたが、その中で一番考えさせられたのは「全乗り」という仕組みでした。これは全員参加という目的のため、出演を希望する管楽器奏者全員が、プログラムの中で、最低ひとり1パートを確保されるように選曲を行うという意味です。(3回生以下が原則この「全員」であり、上回生になると3回生以下の人数が多ければ希望を遠慮し、逆に少なければ(無理に)出演を余儀なくされることもあったのです) PL会議はこの「全乗り」によって選曲段階でパート間の人数調整・各奏者の演奏能力や誰と誰が同じ曲で吹くのかといったことまで考慮に入れる必要がありました。また、むやみに曲数を増やしたり編成の大きいものを選ぶと、弦楽器が大変になるなどの問題が次々と挙がりました。 「全乗り」が選曲にとって大きな制限になっていたため、そこまで「全乗り」を押し通す必要がどこにあるのかというのが当初の率直な思いでした。 こんな僕の思いを少しづつ変えていったのが当時の団員の練習に対する取り組み方の実情でした。僕の足元の弦楽器セクションは練習の出席率が非常に悪かったのです。それと比べると管楽器セクションは欠席する時の体制や練習への取り組みなど1人1人の責任感が強いものに見えました。「全乗り」も裏を返せば人から与えられた所に安住してしまうという危険な部分があるけれど、この現実の状態は「全乗り」に異を唱えることをためらわせていきました。 ここで弦楽器セクションのあいまいな部分が気になってきます。練習の出席率の悪さについても、練習に来ない人に対して演奏会に出るのをやめてもらうといった方法をとれば簡単なのでしょうが、そこまで強硬なやり方はためらわれます。なにより、僕自身は参加人数が減ってしまうことを恐れ、本番に演奏者の人数が揃うことを重視せざるを得ませんでした。なんとか弦楽器、せめてVnパートのメンバーの意識を変えられないかと思っていました。 その1年後1995年、第21回サマコンの選曲の時期を迎えてVnパートは平均年齢が20歳前後に下がり、さらに出演する人数も減ることが予想されました。はっきり言って不安でした。Vnパートでは、特に、上回生はメインだけに出演するという風潮がありました。(全員が全員ではないですが)これは悪意があるわけでなく、忙しい中を時間をやりくりして何とか「メインだけ」参加するというのがほんとうのところです。しかし、このことがバイオリンのパート分けに微妙に影響を与え、言葉は良くないのですが、年功序列で行われるパート分けが多くの全曲乗りのメンバーに何か閉塞感をもたらしていました。 確かに1stVnはオケの華であり、技術的にも経験的にも豊かなメンバーが多い方が良いでしょう。オケに入団して最後にメインプログラムの1stVnを弾きたいという気持ちも無理はないと思います。しかし、この21回サマコンの時点ではふたつのVnパートを成立させることが急務でした。Vnパート員の意識を変えるにはこのタイミングしかないと思いました。まず、原則としてVnパートの出演希望者は全曲に乗ること、1st・2ndのパート分けはバランス良く配置することを始めてみました。言うならば弦楽器の「全乗り」というところでしょうか。楽器の弾ける弾けないにもかかわらず、ひとりひとりがひとつの演奏会に対して責任を持つこと。弦楽器にもこれが必要だと考え、それを実際のパート分けにも適用しました。しかし、これらの変化を採り入れたところで絶対的な人数不足であることに変わりはなく、一体どうなってしまうのだろうという気持ちは常にありました。そして春合宿の頃でしたが、数少ない1stVn出演者の中のさらに一人が出演できないということになって、僕の中のもやもやしたものがふっきれてきました。 『今いる人数でできることをやったらいいじゃないか。本番だけ体裁よく人数を間に合わせる演奏は自分たちの演奏ではないのではないか。形を繕う必要はないじゃないか。』 この時から少しずつ目標が見えてきた感があります。 そんな中、4回目の選曲(57回定演)を迎えました。僕は次の定演ではブラームスをやると公言しはじめました。本来なら複数の選択肢を団員に提示すべきなのでしょうが、この時はPL会議として団員へ明確な目標を提示することが必要であると考えました。そして、それを選曲で表そうと思ったのです。PL会議の中でも選択肢が必要だとの立場から、せめてブラームスの交響曲4番も候補にしたらどうかという主張も強くありました。しかし、最終的にはブラームスの1番一本でいくことになりました。オープニングには「全乗り」のこともあり、サブメインに挙げる曲のバリエーションを狭めないためにもワーグナーのリエンチ序曲をやろうと早々確定していました。そこで、冒頭の金先生との電話に戻ってきます。『サブもワーグナーの管弦楽曲でも入れたら面白いのでは』という考えを金さんに伝えたところ、ヒンデミットという名前が出て来たわけです。 サブメインについてはワーグナーとヒンデミットという選択肢を団員に提示したところ、PL会議としてヒンデミットを強く推した部分もあったためかヒンデミットに最終決定しました。 僕は選曲の時、ヒンデミットの斬新な音の響きに向かい合って、曲を完成にまでもっていけるか確固たる見極めを持つことは出来ませんでした。しかし、挑戦しようという気になっていました。ワーグナーについてもブラームスについても確固たる自信はなかったのが事実です。 ただ、そんな中でも何とか演奏会を迎えることができたのは、狭い選択肢のなかで選ばれた曲に真剣に取り組んでくれたメンバーがいてこそです。僕が感謝すべきメンバーからの忘れられない言葉があります。本番でブラームスの1番が終わり舞台の袖に戻った直後、あるバイオリンの上回生が僕に言ってくれました。「私が入団してはじめて練習と本番のメンバーが一緒だった。」 選曲は難しいです。PLになる時からそう言われ、やってみて、やっぱり難しいと感じました。「今いる人間で何ができるのか」と「魅力あるプログラム」は一見両立しそうで、メンバーが安定しない学生オーケストラにとっては1回ごとの演奏会で立ち向かわなければならない難問です。僕は音楽的に少々不満が出るのを承知で前者を重視しました。金大フィルにとっては譲ってはいけないポイントだと感じたからです。僕が金大フィルの歴史を振り返って一つはっきり言えること、このことだったではないかと思うのです。「全乗り」という言葉を引き継ぐ意味があると、今、自信をもって言えます。 1996年度コンサートマスター 最終更新 2001/3/21 |