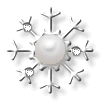5
ノルディスを含めた錬金術師たちが、聖騎士隊のグラッケンブルク調査隊に同行して、一ヶ月
が過ぎたころ。
エリー宛にノルディスからの手紙が届いた。
その内容は例の別れの日の出来事などなかったかのような、淡々とした近況報告だった。グラ
ッケンブルクの街の様子や、疫病の状況、そして……。
「フレアさんもロマージュさんも、無事みたいですね、よかった!」
手紙から顔を上げてエリーが目の前にいたマリーに話しかけると、マリーも嬉しそうに笑った。
「よかったぁ! じゃあ、ディオさんにも教えてあげよう! きっと喜ぶよ?」
「大丈夫です! ハレッシュさんが同じ便で手紙を届けたらしいですから」
「へぇ〜、あの細かいことが苦手なハレッシュさんが、ねぇ」
「はい。ノルディスが誤字脱字を添削してあげたそうですから。……大変だったみたいですよ?」
「あははは、分かる分かる」
エリーも苦笑しながら、手紙の続きを読んだ。
「……そういう訳で、なぜかこの疫病にかかりやすいのは、子どもよりも大人、それも長い間こ
の土地で暮らしてきた人たち、しかも先祖代々この辺りにいた本当の土着の人たちなんだ。フレ
アさんもロマージュさんも元気だよ。二人とも、積極的に救援に当たってくれている。本当に助
かっているよ。それにしても、この土地に馴染みのない人間が不思議とこの病気に感染しないの
は、不思議でならない。でも、分からないことを分かるようにして、原因を確かめるのが僕たち
の仕事だから、頑張ろうと思う。
今、ザールブルグは秋の終わりだね、エリー。僕、今くらい時期のザールブルグが、一番好き
なんだ。空気が澄んでいて、静かで。本を読むにはちょうどいいからね。でも、こっちはまだ暑
いくらいだよ。どうも、夏の次にすぐ冬が来るような気候らしい。以前もここに君と来たことが
あったけど、こんなに長い間街中に留まっていたことはなかったから、その加減はよく分からな
かった。しかも、今時期は昼と夜の温度差がすごいんだ。湖を臨むこの街は、気温の下がった夜
間には夜風がとても冷たい。僕は大丈夫だけど、でも一緒に来た人たちはみんな、一回は風邪を
引き込んだよ。
疫病の状況は一進一退で、正直言うと、僕たちは特効薬の開発どころか、目の前の弱っている
人たちに、とにかく症状をやわらげるための薬を調合することしかできない。歯がゆいけれど、
仕方ない。
それから。ちょっと気になったことがあるんだ。この手紙と同じ馬車便で、サンプルを入れた
手紙をクライス先輩に送っておいた。病気とは一見関係なさそうなことで、あんまり気にするこ
ともないんだろうけど、でも、一応ね。鉱物に関係があることなんだ。僕も気になって調べたん
だけど、何しろここには文献もなければ鉱物に関して詳しい錬金術師もいない。クライス先輩は、
鉱物や土壌などに関しては、賢人会で研究を進めていたような人だからね。きっと、分かるんじ
ゃないかと思って。多分、僕の取り越し苦労だとは思うんだけど。
それじゃ、元気でね。マリーさんたちに宜しく。また、手紙を書くよ。
ノルディス・フーバー」
しかし、ノルディスの手紙はそれきり来なかった。
*
冬が来た。ザールブルグは、例年になく厳しい冷え込みと大雪に見舞われた。
その日も嵐だった。早朝、激しくドアがノックされた、と同時に、シアが工房にやって来た。
「マリー、起きて! ダマールス王国との紛争処理に出かけていた聖騎士隊が、帰って来たわ!」
勝手知ったる何とやら。シアはつかつかとマリーの寝室に入ると、寝ていたマリーを揺り起こ
した。マリーは、寝ぼけ眼で起き上がった。
「ふえ……シア! 本当〜?」
「ええ! それでね、ブレドルフ国王が、あなたを呼んで欲しいって! さっき用事でうちの人
と朝一番の謁見に行ったら、そう言われたのよ!」
お茶を淹れていたエリーは台所から飛んでくると、慌てて尋ねた。
「ダグラスや、エンデルク隊長は無事なんですか、シアさん?」
「そう、そのことなのよ。とにかく一緒に来てちょうだい!」
「……分かった。とにかく、支度しなくっちゃ」
そう言って豪快に寝巻きを脱ぎ捨てると、マリーはベッドからはね起き、工房のテーブルに置
いてあった水差しから盥に水を入れると、ばしゃばしゃと勢いよく顔を洗った。それから腰に手
を当てると水差しの残りの水を、ごっくごっく、と喉を鳴らして飲んだ。
「ぷはぁ〜、夕べ飲み過ぎたかな〜、水が美味いわ〜!」
「マリー、風邪をひくわよ? いいから早く服を着たら?」
「……いつもこうなんですよ。いくらお客さんがいないからって、きちんと服を着ないで歩き回
るのはやめてくださいって、いつも言ってるのに」
そのとき。
慌しく工房のドアがノックされた、と思った瞬間にばたん、とドアが開かれた。
「マルローネさん、分かりました! ノルディスの送ってくれたサンプルから重要なことが、マ、
マ、マルローネさん!?」
慌しく工房に駆け込んできたクライスは、目を白黒させた。
*
「……それは確かなんだね、クライス?」
ブレドルフ国王は、いつになく険しい表情でクライスに言った。
「はい。ですから例の疫病は、通常の人間に対する治療では根本的に解決はしません。グラッケ
ンブルクの土壌に混じっているある成分が百年周期で害悪を成す、と考えたほうがよろしいので
す」
「ふむ。それじゃあ、医学の専門家ばかりを送り込んでも?」
「まったくの無駄とは言いませんが、疫病それ自体の沈下にはあまり有効とはいえないでしょ
う」
「そうか……。分かった。どうもありがとう。ところで、クライス?」
ブレドルフは、くすりと笑った。
「何でしょう?」
クライスが聞き返すと、ブレドルフは一瞬、昔の王子時代のような人懐っこい顔になった。
「……その、頬についた鮮やかな手形は、何?」
「いえ、これはその……」
「まあいいよ。それじゃあ、君たちを呼び寄せた理由について、話そう。ダマールスとの国境紛
争に送り込んだ聖騎士隊が帰ってきたのは、もう言ったよね?」
マリーはうなずいた。
「はい。さっき、聞きましたから」
「それなんだけど……、妙なことが起こってね」
「妙、と言いますと?」
クライスが聞き返すと、ブレドルフは、うん、と言って小さく息をついた。
「混乱を避けるために内密にしておいて欲しいんだけど……。聖騎士たちが、最近の記憶を失っ
てしまっていてね」
「ええっ!」
思わずエリーが驚きの声を上げると、国王は眉を潜めた。
「昨日帰ってきた時は、とりたてて問題はなかったんだ。でも、昨日から今朝にかけて、様子が
おかしくなった聖騎士が大勢出てね……。妙なんだ。たとえばダグラスは、自分がカリエル王国
にいたころのことしか覚えていなくって、ここはザールブルグで、自分が聖騎士だということを
聞いて驚いていたし、エンデルクに至っては、東方の故郷の国の言葉しか話せなくなってしまっ
ているから、何を言っているのか僕には分からないんだ。……まいったよ」
「……聖騎士隊の主力部隊が、みんなそうなんですか?」
エリーがおずおずと尋ねると、ブレドルフは首を横に振った。
「いや、違う。新しく入ったばかりの若い聖騎士には、それほどひどい状態になっていない者も
いる。ただ、古参の聖騎士は……本当に大変なことになっていてね。これは、国の安全対策にと
って問題なだけじゃない。君たちも知っての通り、聖騎士はシグザール王国国民の安寧の要だ。
こんな状態になってしまったことが知られたら、社会不安が広がってしまう。……僕はそれだけ
は避けたいと思う。もちろん、予備兵を集めて当座の任務に当たれるような準備はしたけれども、
一般市民はやはり聖騎士への信頼感や安心感が失われたら、普段どおり生活することができない。
そうなったら物資の流通にも影響が出て、通常ならば売り買いされて順当に回るはずの商品経済
にも差し障る。つまり、景気が悪くなってしまうんだね。近年ではエル・バドール大陸との間の
交易も盛んになって、シグザール王国はようやくザールブルグの街だけじゃなく、近隣の農村部
に住む人たちの生活も豊かになってきたところだというのに、これは本当にまずいんだ」
ブレドルフ国王は、静かに深いため息をついた。
「で、本題だ。君たちに相談したかったことは、他でもない。エルフ族に伝わる宝珠のことを、
聞いたことはないかな?」
「……う〜ん、どっかで聞いたことがあるような……」
マリーが言いかけた瞬間、横からそれを遮るように、クライスが即座に答えた。
「たしか、古文献にそんな記述があったと思います。'時間の果実'と'知識の果実'の二つが、
この世界のなりたちを支えているのだとか、そんなことが」
ブレドルフはうなずいた。
「……王宮の古文書を調べたら、この二つの宝珠の力は交互に弱まるときが訪れるのだけど、そ
の際、力の逆作用に触れた者に災いがある、と記載されていた。僕も半信半疑だったんだけど、
たしかに事例があるんだ。……知識の果実の力が弱まれば疫病が流行り、時間の果実の力が弱ま
れば記憶が吸い取られる人間が出る、と」
「でも、今、両方同時に出てますよ?」
マリーが言うと、ブレドルフは苦笑した。
「それなんだよ。で、これも僕の憶測なんだけど……。ここ数ヶ月、ザールブルグの街中に、魔
物が侵入してくる事件がやたらと増えたんだ。……これも古文書に書いてあったんだけど、どう
やら二つの宝珠の力が弱まると、それだけ魔性のものの力が強くなるという。……土や、木や、
水や、空気に混じっている'魔'の力が、より具現化しやすくなるってね。このことと、疫病や
聖騎士たちの集団記憶喪失は、何か関係がないだろうか? できればこの件について、君たちに
調査をしてもらいたくてね」
ふむ、とクライスは言った。
「荒唐無稽な仮説ですね」
「……ちょっとクライス!」
人を押しのけておいて! と言おうとしてマリーがにらむと、クライスはその薄い唇に笑みを
浮かべた。
「しかし、現実に起きている事態もまた、荒唐無稽です。陛下のおっしゃる仮説も、おそらく大
枠では間違いではないでしょう」
「君も、そう思うかい、クライス?」
「はい。……これも荒唐無稽な仮説ですので申し上げなかったのですが……、グラッケンブルク
の土壌の成分には、よく見ると、古代文字での呪術の誓約の跡らしきものがみられるのです。も
ちろん、現代の錬金術の技法とは大幅に異なる呪法であり、エルフ族の古語を音韻学にのっとっ
た、特殊な解法で読み解かなければ解読不能なものではありますが……」
ブレドルフ王は、にっこり笑って言った。
「君は、分かるんだね?」
「はい。賢人会に属していれば、これくらいの誓約文は解読できなければ研究が進められないも
のですから」
*
四人は、城の外に出た。
「それでは、私もただちにグラッケンブルクに向かいます。支度が済み次第、工房にうかがいま
すので、また後ほど」
門の前でクライスが言った。マリーは小声でブツブツ言った。
「……何よ、研究に差しさわりが出るとかなんとか、いつもだったらブツブツ言うくせに、王様
に頼まれたらすぐさま、コロッと言うこと聞いちゃって……」
エリーは、そんなマリーの声を遮って笑顔で言った。
「助かります! 今回のことは、クライスさんがいないと解決できそうにないですから!」
「いえいえ。研究に従事する者として、当然の勤めですから」
マリーはブツブツ言い続けた。
「……だいたいムカつくのよね。知識ひけらかして、嫌味ったらしくて、黙って手伝ってくれた
ら少しは感謝もするのに、いちいち一言多いっていうか、自慢ったらしいっていうか……」
しかし、そんなマリーの横で親友の声が響いた。
「私も行くわ。ねぇ、いいでしょう、マリー?」
「シ、シア!?」
エリーも慌てて言った。
「でも、シアさん、マリーちゃんや旦那様は大丈夫なんですか?」
「大丈夫よ。夫は今日これからカリエル王国に仕事で出かけて、当分帰って来ないし。それに実
はね、母がしばらく家にいることになったのよ。父と、新しく建てる別荘のことで大喧嘩したん
ですって。当分帰らないから、孫の面倒を見て暮らすって息巻いてたわ」
そう言ってくすくす笑うシアを見て、エリーはため息をついた。
「……で、でも……。それじゃご両親の喧嘩は、話がこじれませんか?」
「いいのよ。私も母の意見に賛成だもの。それにね。……私、フレアさんにも会いたくなっちゃ
って」
マリーは苦笑しながら言った。
「いいわよ、シアがそう言うんなら。でも、寒いわよ? 身体は大丈夫なの?」
「マリーは相変わらずそんなことを言うのね? 大丈夫よ。私、もう昔の病弱な女の子じゃない
のよ?」
シアは、そう言って微笑んだ。
朝方の嵐はひとまず収まってはいたが、大雪が城壁や門の上にもうず高く積もっていた。ふい
に、どさっと雪の塊が落ちてきて、クライスは見事に埋もれた。
「うわっ!」
雪の上には、放り出された眼鏡だけが残り、クライスの身体は完全に雪の塊の下にうずもれて
しまっている。エリーは慌てて言った。
「ク、クライスさん!大丈夫ですか?」
そのとき。
「悪ィ、悪ィ! 大丈夫か!?」
上方から、聞き慣れた声がした。
「ダグラス!?」
エリーが上を見ると、城の壁の上で大振りのスコップを手に雪かきをしているダグラスの姿が
あった。ダグラスは、慣れた足取りで雪の塊の足場を身軽につたい、あっという間に地面の上に
降りてきた。
「人がいるのが見えなかったんだ! 悪かったな? 怪我、なかったか?」
「ダグラスこそ! 大丈夫なの?」
エリーが尋ねると、ダグラスは不審そうな顔で聞き返した。
「……おまえ、どうして俺の名前を……? そうか! 俺がこっちに来てからの知り合いなんだ
な?」
「え……ダグラス、やっぱり、さっき王様が言ってたみたいに……、わたしのこと、覚えてない
んだ……?」
ダグラスは心配そうなエリーの眼差しに、困ったように頭を掻いた。
「悪いな。身体はどこも悪くねぇんだけどよ。……たしか、シグザール王国の聖騎士になるんだ!
って故郷を出ることを決めたあたりまでは、覚えてるんだけどな……。まさか、本当に聖騎士に
なってるなんて、夢を見てるみたいで変な感じなんだ」
ふいに、エリーたちの背後から、低く鋭い声が門前に響いた。
「放掉手(手を放せ)!」
そう言って、誰かの手を振り解き、長い見事な黒髪をなびかせて歩いていたのは……。
「エ、エンデルク隊長?」
エリーが驚いて言うと、マリーも目を丸くした。
「……な、何、あの言葉は?」
エンデルクの足元には、さきほど手を払いのけられた金髪の美青年がうずくまっていた。青年
は、今度はエンデルクの脚にすがりついた。エンデルクは、再び青年の手を払いのけると、うっ
とおしそうに言った。
「……汝是誰(いったいおまえは誰なのだ)?」
「……ううっ、ヒック、グシッ、エンデルク様、僕を、僕を覚えていないんですか……?」
泣き崩れた青年の剣幕にさすがに驚き、エンデルクは言った。
「……別哭了(……何も泣かなくても)……」
「ああ、エンデルク様……。お気の毒に……。でも、でも僕の愛の力で、必ずやもとのエンデル
ク様に戻っていただきますからね?」
そう言って抱きついてきた青年を、エンデルクは無言で容赦なくぶっ飛ばすと早足で歩き去っ
た。
「うぷっ!」
そう言って雪の中に埋まった青年に、一同は駆け寄った。
「大丈夫?」
シアがそう言って助け起こすと、エリーも、
「大丈夫ですか?」
と言ってのぞきこんだ。しかし。
「……この人、笑顔で気を失ってるよ?」
マリーは、あきれ気味に言った。
「どうする、マリー?」
シアが苦笑しながら聞くと、マリーは言った。
「そうね〜、こんなところでおねんねしてたら凍死しちゃうもんね。しょうがない、城内に運ぶ
か! ね、ダグラス、手伝って!」
「……お、おう、分かった。……よっこらせっ、と!」
全員が去った後、門前には雪の塊だけが残された。
その下から、か細い声が響いてきた。
「……誰か………私、も……助け、て……ください…………」
|
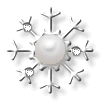 百年前
百年前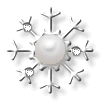
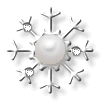 百年前
百年前