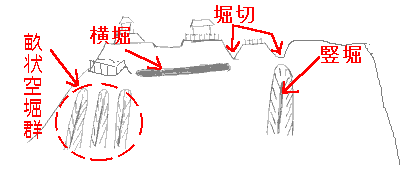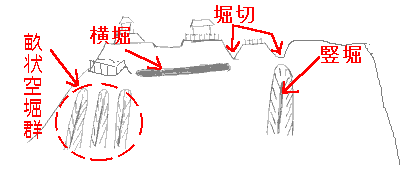竪堀(たてぼり)
特にTABLEなどで文書を整形していませんので、ご自由にこのウィンドウを読みやすいサイズにしてください。
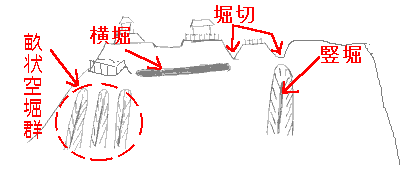
山城において、斜面に沿って掘られた(等高線に対して垂直に掘って)堀のことを竪堀(たてぼり)といいます。(たつぼりともいうそうです。)
尾根伝いに進軍してきた寄せ手(攻城兵)が堀切に遮られると、今度は横の斜面から城内に進入しようと試みます。その横からの進軍を妨げるため堀切の延長線上に堀を縦方向に延ばそうとする工夫が生まれました。それが竪堀の最初だそうです。その時期は15世紀頃だそうです。
竪堀は、その後、16世紀頃には堀切とは別に単独で用いられるようになり、さらに16世紀第2四半期には畝状空堀群へと発展していったようです。
なお、竪堀や畝状空堀群は斜面を登りにくくするために用いたという説もあるようですが、どうしてそのように考えるのかは、よくわかりません。おそらく、緩やかな斜面の勾配を急斜面にするために縦に削って堀を作ったという解釈なのでしょうか?。
しかし、群馬県の岩櫃城や後閑城などで竪堀が城道を兼ねて用いられている場所もあり(私はこれらの城に登城したこともあるし、実際に登りやすかったです(^_^;))、竪堀の用途を斜面を登りにくくするということに絞るのはちょっと無理があるような気がします。竪堀はさまざまな目的で作られたのでしょう。
参考文献
日本城郭大系 別巻2
新人物往来社 編
千田嘉博 小島道裕 前川 要 著
城館調査ハンドブック
新人物往来社 発行
今あなたの見ているウィンドウは正規であるドイツ参謀本部経由からきた方は、新しく別ウインドウとして開かれていますので、もとの本文に戻る場合は、タスクバー(マックの場合はメニューバーっていうんでしょうか?)などをクリックして元のウインドウを呼び出して下さい。(別ウィンドウにした理由は、あくまでも、用語解説のページなのでちらっと見てすぐに本文にもどりたいという人が多いと思いまして、別ウィンドウの方が本文にすぐに戻りやすいと思いまして別ウィンドウ形式にしました。)
あまりたくさんのウィンドウを開けるとメモリーなどが不足する場合がありますので、必要に応じてウィンドウを閉じて下さい。
検索ページなどから来た方の場合はよろしければ、ウィンドウサイズを800*600のサイズ゙にして
 こちらへ(ドイツ参謀本部入り口ページ)
こちらへ(ドイツ参謀本部入り口ページ)