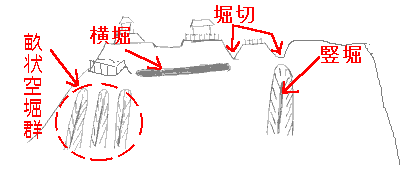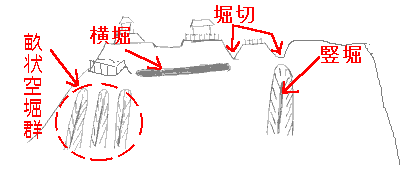畝状空堀群(うねじょうからぼりぐん)
特にTABLEなどで文書を整形していませんので、ご自由にこのウィンドウを読みやすいサイズにしてください。
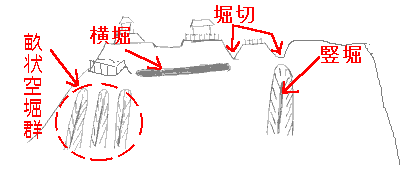
山城において、竪堀を連続に3つ以上並べたものを畝状空堀群といいます。(2つ並べたものは二重竪堀というそうです。)各竪堀の山の部分には竪土塁すなわち土塁を縦に作り鋭利にして、敵が横に移動するのを防ぎ、堀に沿ってしか進軍出来ないようにしたようです。しかし、畝状空堀群の設置の目的は竪堀のような横方向への進軍妨害ではなく、敵を1列に並べて討ち取ることではないかと思います。ようするに妨害ではなくて罠のニュアンスが多少強いような気がします。下のへぼ劇画?(゚_。)?(。_゚)のように、敵を一列に並べて石を落としたり、弓を雨のように降らせば、かなりの寄せ手(攻城兵)を撃滅できるのではないでしょうか。

また、攻撃側が攻城をあきらめて退却しようとした場合、守備側がこの畝状空堀群を使って一気に逆落としに駆け下り、敵を追撃するのといった攻撃的な利用方法もあったように私は推定しています。通常の城道だと、守備のためにうねうねした道になっているので、そんな道を通っている間に敵が逃げてしまうときもあったでしょう。戦意の失った兵に逆落としの攻撃をあたえた場合、壊滅的なダメージをあたえることが出来ると思います。攻城兵に夜襲をしかけるのもいいですね(^_^;)。
畝状空堀群は石垣作りの発達によりすたれたという説もあるようです。(例...兵庫県の光明山城と感状山城の関係など) おそらく、ゆるい斜面に畝状空堀群を設けて防御していたが高い石垣で急斜面をつくることができるようになったので畝状空堀群を使わないようになったという考え方がその説の根底にあるのでしょう。しかしその考え方は畝状空堀群の防御面のみを視点にした考えであって前述のような、畝状空堀群の罠的かつ攻撃的な面を考慮すれば、石垣の発達が畝状空堀群をすたれさせたとは一概にはいえないと私は思います。
参考文献
千田嘉博 小島道裕 前川 要 著
城館調査ハンドブック
新人物往来社 発行
西ケ谷 恭弘 著
「戦国の城」(中)(総集編)
学研 発行
今あなたの見ているウィンドウは正規であるドイツ参謀本部経由からきた方は、新しく別ウインドウとして開かれていますので、もとの本文に戻る場合は、タスクバー(マックの場合はメニューバーっていうんでしょうか?)などをクリックして元のウインドウを呼び出して下さい。(別ウィンドウにした理由は、あくまでも、用語解説のページなのでちらっと見てすぐに本文にもどりたいという人が多いと思いまして、別ウィンドウの方が本文にすぐに戻りやすいと思いまして別ウィンドウ形式にしました。)
あまりたくさんのウィンドウを開けるとメモリーなどが不足する場合がありますので、必要に応じてウィンドウを閉じて下さい。
検索ページなどから来た方の場合はよろしければ、ウィンドウサイズを800*600のサイズ゙にして
 こちらへ(ドイツ参謀本部入り口ページ)
こちらへ(ドイツ参謀本部入り口ページ)