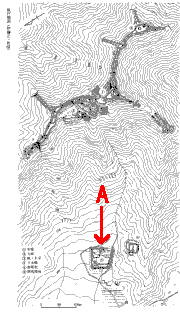| A.....御館(おたて)跡 (御屋敷とも呼ばれているようです) ここは、平時に行政などを行う場所と思われます。山城の多くはこのように、平時に行政などを行う場所として平地に小城、館等を設けています。いざという時は、山頂の山城へ籠城します。(たとえば、武田信玄公が居住した有名な躑躅ケ館にも実は裏手に要害山城という詰めの山城があります。あまりこのことは一般的に知られていないみたいですが。 (^_^;) ) 殿様はいつも本丸や天守閣の最上階にいるなんていうのは、時代劇の世界だけですよ。 (笑) (時代劇と言えば、NHK大河ドラマ「毛利元就」で出てきた城の描写は天守閣が無くて、なかなか戦国時代らしき城に描かれていましたね。進歩したものです。(といっても、黒沢映画の「蜘蛛の巣城」ですでに、そのような描写は使われていたと思いましたが....)ただ、尼子氏の紋章が、隅立四つ目になっていたのにちょっと疑念を抱くのですが、私としては今までの資料から平四つ目だったと思うのですが....地元(出雲地方)の人は何にも言わないみたいだし...地元の人が作ったホームページでもわざと尼子氏の紋章は載せないようにして、論争をさけているようだし...あっ、ここでは関係ありませんか (^_^;)) |