※まず初めに断っておく。私は以前から何度も書いている通りイデオロギーというものを論ずるのを控えている。それは、イデオロギーというものが非常に曖昧なもので、それを自分の主張にするには非常に危険なものであると思うからだ。それはその土地だったり歴史だったり文化だったり、非常に複雑な要素によって組み立てられるものだと考えるのだ。しかし、あえて今回はイデオロギーを論じたいと思う。それは最近私が痛切に感じていることを描いたものに出会ったからだ。
素晴らしい映画に出会った。何ヶ月か前に購入はしたものの今まで見ていなかったドイツ映画「The Edukators」(邦題:ベルリン、僕らの革命)だ。最近行きつけのバーで常連さんと語った資本主義に対する批判や、革命戦士チェ・ゲバラの若い頃を映画化した「Motorcycle Diaries」、フィデル・カストロとチェ・ゲバラのキューバ革命映画「Che Guevara & Castro」を見てゲバラのボリビア革命日記「ゲバラ日記」を読んで以降の革命に対する考えなどをまさに表している映画だった。数年前に見たジョン・トラボルタとヒュー・ジャックマン、ハル・ベリーが熱演した「Swordfish」以来の久々にヒット作だ。DVDジャケットには「理想への純粋な夢を抱き、愛と友情の狭間で揺れる若者たちを描く爽やかな青春恋愛映画」などというコピーが付いているが、はっきり言ってこのコピーを考えたコピーライターはナンセンスすぎる。本当にこの映画を観たのだろうか?そんなもんじゃない。この映画は今の資本主義で生きている人々すべてが見るべきであり、タイトル通りの教育映画だと思う。最近私がプロジェクトで行っているお客様先に来ているリクルートスーツの就職活動組、うちの会社の1階の喫煙所で「最近どうですか?」とか「給料上がらねーなー」なんて言いながらタバコを吸っているサラリーマン、通勤電車で口を開けて寝ているサラリーマン、そして今の状態に何か感じながらも黙々と生活している人々にぜひ観ていただきたい映画だ。
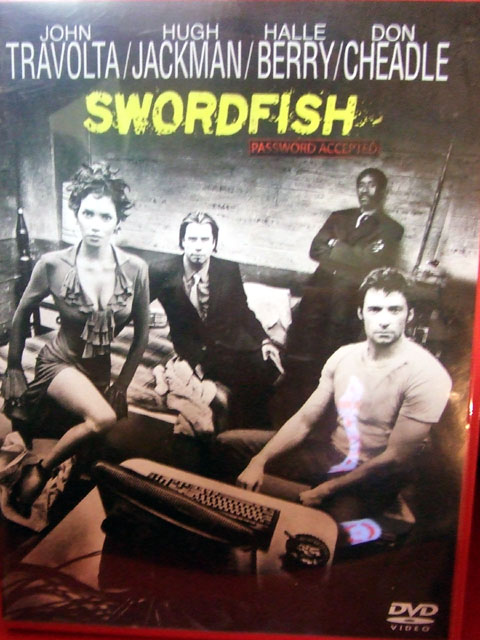
|
主演は「グッバイ、レーニン」でも好演をしたダニエル・ブリュール。はっきり言って「グッバイ、レーニン」は日本人の私にはいまいち飲み込めない映画だったが、本作ではその鋭いまなざしと何かどこか頼りないところがまさにハマっている。この映画の見所はやはり資本主義に対する再考というところだろう。特にただの若者の反逆といういかにも”パンク”と仕立てられそうなベタな構成ではなく、そこには年収300万ユーロの富豪が入り、そして一緒に考えるという構成がリアリティを生んでいる。よくあるニュース、「渋谷で若者がマリファナや覚せい剤にハマっている・・・」とか「日本の中年サラリーマン団体が異国で集団売春・・・」なんていう子供が悪い、大人が悪いなんて理論は一切ないのだ。すべてを巻き込んで、赤子から老人までが同じ土台に立って一緒に反省し、一緒に考えなくてはならない、そんな最近私が相談もののテレビ番組や偉そうに大人が何様のつもりだという感じで批判だけする番組を観ていて、ずっと思っていることを見事に表現していくれている。「今あなたの買おうとしているその靴は東南アジアの12歳から16歳の子供たちが作っているんです。」、そんなどこかで聞いたことのあるようなメッセージからこの映画は始まる。そこにはもちろん若い男女の恋愛事情や友情物語も含まれている。それは当たり前と言えば当たり前だ。主義や理想というものをとったら彼らはただの普通の若者でしかないのだから。
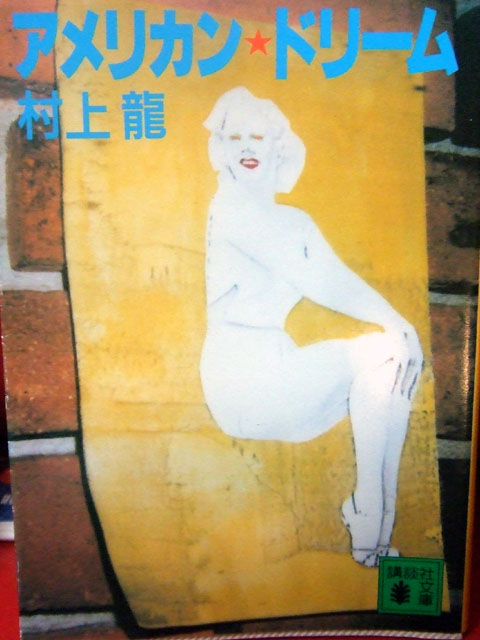
|
特に印象に残っているのはダニエル・ブリュール演ずるヤンと、やはり好演のユリア・イェンチ演ずるユールがベルリンの夜景を見ながら語るシーン。「反逆の難しい時代さ。今は革命さえも商品になる。チェ・ゲバラのTシャツや、無政府主義(アナーキー)のステッカーとかね。」そういう反骨精神さえも飲み込んでしまう、資本主義というものは魔物だ。私がバーで気の合った連中と資本主義に関して話すとき、必ず言う「資本主義は今の人類には高度なイデオロギーすぎる。きっとオレらはそれをコントロールできない」というのはまさにこのことを言っているのだ。例えばある工場が有毒な化学廃棄物を川に流し甚大な被害が出たとする。そのとき、この工場の工場長ははっきり罪を認めるだろうか?きっと自分がやっていることが多くの人を苦しめていることを自覚しながら、自分の生活を守るために弁明するに違いない。これこそ、コントロールできない資本主義というもの、金がなければ生活できないという世界だと思うのだ。本当に自分が正義と思ったこと、これを曲げなければ生きて行けない社会、精神を病む人が多く異常犯罪が増えるのも頷ける。人間が有史以来培ってきた良心というものを真っ向から否定してしまっているのだから。ちょうど読み終わった村上龍の「アメリカン★ドリーム」では、核兵器の出現で偉大な英雄は今後現れないだろうと言っている。これは直接資本主義と結びついているわけではないが、実質アメリカが核における超大国であり、そのアメリカが資本主義においても超大国であることから決して無関係とは言えないだろう。すべてを飲み込んでしまう資本主義、それを最近痛切に感じているのである。
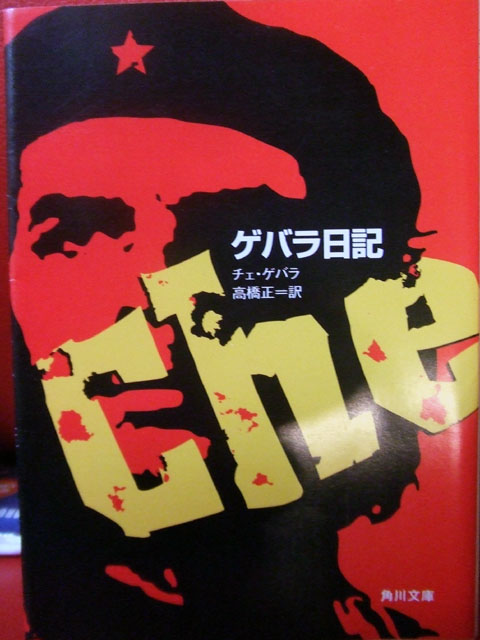
|
「Swordfish」ではジョン・トラボルタ演じるテロリストが「ハリウッド映画の観客はハッピー・エンドを望んでいるのさ」と言い残し、最後に生き残る。この映画を観て圧倒的なリアリティを感じた。スーパーマンにしろ、ロード・オブ・ザ・リングにしろ、水戸黄門にしろ善と悪は明確だ。しかし、この映画には善と悪がない。観客はどちらが正しいのかわからないだろう。そしてそれこそがこの映画の狙いであり、リアリティを造り出す最も大きな要因だと思う。映画やテレビの世界では善と悪が区別されていて分かりやすい。しかし、現実にはどちらが善でどちらが悪と明確に区別できることは非常に少ないと思う。それは国際問題にまで波及するがそれにはあえて触れず、身近なことについて考えても思い浮かぶ。よく恋愛関係で彼氏が彼女をフッタなんてとき、どちらが善でどちらが悪と区別できるだろうか?彼女をフッタ彼はたしかにひどいかもしれない。でもそうさせてしまった彼女にも問題はあるだろう。これは浮気なんてものにも適応されると思う。非常に稚拙な例ではあるが、そのように日常に近い分だけ「Swordfish」はリアルだった。そして今回出会った「The Edukators」もそれに近い作品だと思う。「警察のことは心配するな」そう言った若い頃はは学生運動にも参加した富豪が最後に警察に通告し、警察が見つけた「お前たちは、きっと一生変わらない」という張り紙、そしてこの映画は終わる。これは資本主義というものが魔物であることを感じつつも結局その流れに逆らえない、コントロールできない今の人々の心を表しているようにも思う。この映画が現代の社会主義と民主主義を両方経験しているドイツという国で製作されているのも自然なのかもしれない。DVD特典のインタビューではこれ以外のエンディングもあったようなことを言っているが、これ以外のエンディングはあり得ない。そこに圧倒的リアリティが存在する。そして、この映画を見終わったとき、この映画さえも資本主義なのだと思い複雑な気持ちになるのだ。
もちろん、私は革命思考だったりするわけではない。現に私も日本の資本主義の中で生きるサラリーマンの一人である。しかし、なんだろう、この複雑な気持ちは、と思ってしまうのである。
『僕らの革命』完








