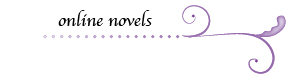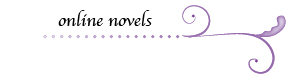
狼殺しの蒼い赤
1
強い西日に照らされて、空は朱に染まっていた。
木々が伸ばす影は長く、濃く。夜の先駆けたる闇が音もなく世界を浸食してゆく。
人の姿すら見分けがつかない誰そ彼時。
逢魔が時の妖しさは、照明の灯された室内にあっても薄れることはないらしい。
否。
たとえ太陽の光に照らされていても、この場所には闇のにおいが漂っていただろう。
ソファに腰を降ろしながら、久瀬鈴華はさりげなく室内を見渡した。
ウグイス色の砂壁も白い建具も日に焼けて、天井には染みが浮き出ている。畳も、かなりの年代物であるはずだ。
だが確かめることはできない。床の間を持つ部屋の造りは純和風。だというのに、足元には色鮮やかなペルシア絨毯が敷かれているからだ。
奇妙なのはそれだけではなかった。鈴華が座るソファは金に光る猫足を持ち、布地に施された刺繍がロココ調を思わせる。ヨーロッパの旧家にふさわしいような品だが、その前に置かれたテーブルは漆黒で、繊細な螺鈿細工がいかにも中国風だった。
床の間を飾っているのは孔雀のブロンズ像やアールヌーヴォー調のガラスランプ。丸みを帯びた飾り棚はベトナム製だろうか。その他の調度品も、ひとつひとつを鑑賞すれば美しい品であるのだろう。しかしどれもが己の個性を主張するばかりで、譲ることを知らない。
悪趣味な部屋だと、鈴華は思う。
とはいえ、すべては演出なのかもしれない。
なにしろここは、堂々と毒草園の看板を掲げる人物の家なのだから。
「私も、ずいぶんと長くこの商売を続けていましてね。取り扱っている商品の性質上、顧客は個性的な人間ばかりなんですが」
穏やかな声に呼ばれて視線を正面に戻す。テーブルのむこう側から、毒草園の主人は物珍しげに鈴華を眺めていた。
「それでも、セーラー服姿のお嬢さんを園内に招き入れたのは初めてですよ」
「学校を出るのが遅くなってしまって。家に寄る時間がなかったんです」
木々の緑が生い茂り、梅雨の入りにはまだしばらくの猶予を残した季節。数日前に衣替えを迎えたばかりで、夏服はまだ鈴華の体に馴染んでいない。腕に直接触れる空気を肌寒く感じて、鈴華は体を強ばらせてしまう。
その行為が、緊張から生まれたものだと思われたのだろう。佐伯七生と名乗った男は、かすかな笑みをうかべてみせた。
「久瀬さんも人が悪い。代理人が来るとは聞いていたのですが、それが実の娘さんだとは思ってもいませんでしたので。少々驚きました」
「わたしも、です」
還暦をすぎた父親の古い知りあいだと説明されたから、毒草園の主人は父と同年代だろうと思っていた。だから七生と会ったときは驚いた。四十歳を越えているようにも見えなかったからだ。
外見だけで判断するなら、二十代でも通用するだろう。しかし落ち着いた物腰は若者のそれではない。もしかしたら、父よりずっと年上なのだろうか。そんな奇妙なことを考えさせる男なのだ。
「父に毒草園へ行けと言われたときは、耳を疑いました。何度聞いても、注文した品を取ってくるだけだとしか教えてもらえなくて」
自分が、何故そんな用事を頼まれなくてはいけないのか。理解できないままに、鈴華は毒草園の門をくぐったのだ。
「久瀬さんらしい言動ですね。なにかに夢中になると、それ以外のことがまったく考えられなくなる。ときに奇行と呼ばれる言動に走っても、彼にはその自覚がまるでない。顧客として接する分には楽しい方ですが、ご家族はいろいろ大変でしょう」
同情めいた視線に否定の言葉を返しながらも、鈴華は心の中で大きくうなずいた。
子供のような人と言えば聞こえはいいが、つまりは幼稚だということだ。周囲の人間を思いやる気持ちなど欠片もなく、物事がすべて自分の思いどおりにならなければ気がすまない。
牟礼禄児の名を日本画家のそれとして記憶している人間は多いだろう。牟礼は父の旧姓で、画壇ではいまもその名で通している。だが彼が新進気鋭の作家として話題にあがっていたのは、二十年以上昔の話だ。とうに忘れ去られた存在だと気づいていないのは本人だけ。大家気どりの変人に門下生などつくはずもなく、ひとりでピエロのように踊り続けている。それが鈴華の父親なのだ。
画家としての仕事も、収入もほとんどない。それでもなんとか食いつなぎ、鈴華が名の知れた私立校に通うことができるのは、亡くなった母が資産家の一人娘だったからだ。
「最近はお父上の名を聞く機会も減りましたね。ですが、ああいう方は打たれ強くもあるのですよ。自分の選んだ道を悔いる人でもありません」
父の姿が脳裏をよぎるたびに、嫌悪感が心に募る。その感情を表に出したつもりはない。だが七生にはすべてを見透かされているような気がして、鈴華は手元に視線を落としてしまう。
「父のこと、よくご存じなんですね」
癖の強い人間だから、交友範囲もかぎられている。落ちぶれた日本画家が何故、毒草園の主人などと知りあいになったのだろうか。
「あの方がはじめて私の元にいらっしゃったのは……そうですねえ。婿養子になる前でしたから、三十年ほど前のことになりますか」
一瞬天井を見上げたのは、過ぎ去った月日を数えるためだろうか。鈴華はうなずくことも忘れて七生をみつめた。
やはり七生は見た目以上に年を重ねているらしい。そう思いかけて、鈴華は静かに息を吐く。薄い笑みをうかべたままの七生は、鈴華をからかっているだけなのだろう。
「母と結婚したのは十八年前です。都が主催する日本画の新人賞を受賞して、画家として認められはじめたのは、二十四、五年前のことだと聞いています。つまり、それ以前からのお知りあいだということですね?」
冗談につきあうつもりはないのだと、鈴華は満面の笑みを七生に返した。
「そういうことになりますねえ。あのときはまだ、運送会社にお勤めでしたよ。配達中にウチの看板に目を止めて、仕事着のまま門を叩かれたのです。私の商品は特殊な品ですからね、飛びこみの客を相手にすることは滅多にないのですが。久瀬さんは、私にそれを説明する暇さえ与えてくれなかった」
七生の顔を見るなり、トリカブトを譲って欲しいと頭をさげたのだという。
「トリカブトはご存じですか? 古くから猛毒として知られるキンポウゲ科の植物なんですが」
「名前だけなら」
鈴華の脳裏をよぎったのは、保険金めあてに妻を殺害した男の話だ。カプセル入りのトリカブトを摂取して亡くなった女性は男の三人目の妻で、前妻たちもみな急死していたのだと聞いた覚えがある。
「この植物には数種類のアルカロイドが含まれていましてね。そのうちのひとつであるアコニチンは、植物の中では一番強い毒だと言われています。アイヌ民族は矢じりにこの毒を塗って狩猟を行っていましたし、ヨーロッパでは狼を捕まえるとき、生肉にトリカブトを包んでエサとしました。そこから、『狼殺し』という名前がつけられたのです。異名の多い植物でしてね、『継母の毒』とも呼ばれていました。夫の連れ子を殺害するために、女性たちが用いた毒。昔は今より簡単に、人が毒殺されていたのでしょう。古代ローマではしばしば栽培禁止令が出されていたとか。逸話の多さも、トリカブトの毒性が人々によく知られていた証拠でしょう」
毒草園を営んでいるのだから、七生が毒にくわしいのは当然だろう。しかし彼の話を楽しむことはできなかった。そんな毒草を手に入れて、父はなにをしようとしていたのか。
「日本画に使われる岩絵の具の原料は鉱物ですからね。なかには毒性の強い物もある。トリカブトの毒に捕らわれる必要はありません。あなたの父上は、絵のことしか頭にない御仁ですから」
「つまり父は、絵の具の材料としてトリカブトを必要としていたのですか?」
「堅く口止めされているのですが、実のお嬢さんにまで隠す必要はないでしょう」
鈴華に毒草園へ行くよう指示したのは久瀬自身。ならば秘密を知られることも覚悟していたはずだと、七生は続ける。
「トリカブトの花は青紫色をしています。ですが久瀬さんは、そこから赤い色を取りだす方法を編みだしたのですよ。ただ毒の強弱によって、その色が微妙に変わってしまうのだそうです。毒が強ければ強いほど、鮮やかな色素が取れる。絵の具として最適な品種を探しだすために、彼は各地のトリカブトを求めていたのです」
北半球の温帯や寒帯に分布するトリカブトには三百以上の種類がある。範囲を日本にかぎっても三十種。そのうえおなじ種類であっても、生育地や季節によって毒性に違いがあるらしい。
トリカブトは茹でると苦みが消えてしまうため、山菜と間違えて食べてしまう事故が毎年のように起きている。だから誤ってトリカブトを摂取しても、かならず死ぬわけではないという。
「しかし有名な毒草ですからね。毒草園ならば当然トリカブトがあるはずだと考える人間は案外多いのですよ。だが殺人以外の目的で、トリカブトを欲した人間は久瀬さんただひとり。自分が絵画の歴史を変えるのだと息巻いていました。その熱意と純粋さに根負けしましてね。数回に分けて、たしか二百種近いトリカブトをお渡ししたでしょうか」
毒草園を名乗っているものの、七生の仕事は植物を育てるだけではないという。正確には、古い時代における薬種商なのだと説明された。医術と妖術の区別もなく、村はずれに住む魔女たちが畏敬の念とともに受け入れられていた近代以前。遠い異国の地から一角獣の角や竜の血を調達してくる薬種商は、人々にとって必要不可欠の存在であったのだ。
そんな七生にとって、各地のトリカブトを集めることはさほど困難ではないらしい。
「そして実験をくり返した彼は、望みどおりの色を手に入れたのです」
「それが、『牟礼の赤』なんですね」
技術はあるが凡庸で、いまひとつ特徴に欠ける。そう酷評されていた父親の絵は、ある色がつけ加えられることで劇的に変化した。
その色こそが赤なのだ。
父が新人賞を獲得したのは、源氏物語の六条御息所を題材とした作品だった。嫉妬の念を押さえきれず、生き霊となって光源氏の正妻や他の恋人を呪い殺し、死後も彼の妻たちにとり憑いた女性だ。自分が生き霊と化したことを知っており、罪の意識に囚われながらも光源氏への気持ちを抑えきれない。
彼女を題材とした作品はいくつもあるが、そのほとんどが鬼女や幽霊のように描いている。
だが父は、高貴な女性として彼女を描いた。東宮と死別しなければ、皇后になっていたかもしれない女性。知的で品のある姿を透明感のある色彩で描きながらも、わずかに青みを帯びた赤い唇だけで彼女の妄執を表現してみせた。
岩絵の具は粒子の細かさや、焼きを入れることでさまざまに色を変える。画家たちはみな工夫して、自身の色を作りあげていくのだ。そんな世界にあっても、父が使った赤は異質だった。油絵の具を思わせる深さと、濡れたような艶。見る位置によって、その色は微妙に変化してみせる。美しいが血を連想させる唇の色は、それだけで貴婦人が生き霊なのだと伝えたのだ。
驚きを持って画壇に迎えられた父は、その後も赤を効果的に使った絵を描き続けた。独特な色を再現できる人間は他におらず、いつしかそれは『牟礼の赤』と評されるようになった。
とはいえ、父が脚光が浴びた時代は短い。
あたり前だ。血のような赤が映える題材などかぎりがある。第一どれほど優れた作品であっても、幽霊や鬼女の絵を自宅の居間に飾ろうと考える人間は少ない。
父が作りだした赤は、物珍しさから人々に注目された。作品数が増えるにつれ、次第に飽きられてゆくのは当然の成り行きといえるだろう。そのうえ、『牟礼の赤』には致命的な欠点があったのだ。
他の絵の具と比べても、異様なほどの速さで退色してゆくのである。
美しさを保っていられるのは二十年ほど。その期間を過ぎると、花が枯れるように色が褪せてしまうのだ。深さを生みだしていた青みは薄汚い茶色に変わり、艶さえも失われた。そのさまは、傷口を濡らしていた血が、かさぶたに変わるようだと人々は噂した。『牟礼の赤』は死んだのだ。
その事実が世間に知れたのは、いまから五年ほど前。もともと、その赤い色だけを武器に絵の世界に留まっていた人間だ。絵の注文もぱたりと途絶え、父は過去の画家となった。
久瀬禄児はその赤をどのように作りだし、何故、かくも早く退色してしまうのか。
謎を解こうと考えた人間が訪れても、実の娘が尋ねても、父は沈黙を貫いた。だが、いまなら分かる。赤い色の正体はトリカブトだったのだ。
植物から取りだした色が、鉱物のそれより変色が激しいのは素人でも知っている。そのリスクを理解しながら、何故トリカブトにこだわる必要があったのか。父の愚かさに鈴華は呆れた。目の前に七生がいなければ、舌打ちのひとつぐらい洩らしてやりたいところだ。
「……父はまた、佐伯さんからトリカブトを購入するつもりなんでしょうか」
そのために、自分を毒草園に寄こしたというのだろうか。苛立ちを心に秘めて、さも不思議そうに問いかける。
「久瀬さんの目にかなったトリカブトは一種だけ。はじめのうちは私が卸していたのですがね。それがどこで採取できるかを、知られてしまいまして。海外なら久瀬さんも諦めたのでしょうが、山形県で採れる種類でしたから。私に払う手数料が惜しくなったのでしょう」
その後は七生を通すことなく、自分でトリカブトを採りに行っていたらしいと七生は続けた。同時に父とのつきあいも疎遠になった。鈴華が毒草園を訪れるにあたり、父が七生に連絡を入れたのは、実に十五年ぶりのことだという。
「あの人も『牟礼の赤』だけで、一生画壇に留まれるとは考えていなかったはずです。そして独特な色を使う以外、自分に生き残る道はないと知っていた。次代を担う画家だともてはやされていた頃から、彼はあらたな色を探していましたよ。そういえば、スズランからも色が取れるのではないかと試行錯誤していた時期もありましたねえ。彼が姿を見せなくなる数年前のことですから、あなたの名前もそこに由来しているのかもしれません」
スズランは春を告げる花だ。花言葉は『幸福の再来』。淑やかにうつむいて咲くさまは、純潔の証として花嫁たちのベールを飾った。
九月生まれの鈴華だが、この名前はスズランにちなんでつけられたと聞いている。
父が養子に入った久瀬家は華族に列せられていたほどの家柄で、その歴史も古い。少女時代の母を映した写真には華やかな時代の痕跡が残っており、鈴華にも名家の娘だという自負がある。スズランの花は、そんな自分にふさわしいとも思っていた。
「可憐なイメージを持つ花ですが、潔癖そうに見えるのは外見だけでしてね。人間を死に至らしめるほどの毒を隠し持っているのです」
トリカブトには劣りますがと、七生は人の良さそうな表情を崩さないままに続けてみせる。
「スズランと聞いて、たいていの人は純白の花を思いうかべる。しかし秋になると、赤い実をつけるのです。鮮やかな色が子供の好奇心を誘ってしまうようでしてね。この実を食べて幼児が死亡する事故は、毎年のように起きているのですよ」
毒があるのは実だけではない。葉や花にもおなじ成分が含まれており、スズランを生けた花瓶の水を飲んだ人間までもが命を奪われているのだ。
その毒性に関連するのだろうか。スズランには、血にまつわる伝承が残されているという。
「イギリスでは、村を襲うドラゴンと戦った男の話として伝えられています。戦いに勝利したものの、男自身も傷を負い、血が地面に滴った。その跡に生えたスズランが、小さな鈴を鳴らして男を祝福しているのだとか。北海道には赤やピンクの花を咲かせるスズランがあるのですが、それもアイヌの娘が流した血に染まったためだと言われています」
「なんだか、イメージが変わってしまいそう」
驚きの表情をうかべながら、鈴華は肩をすくめてみせる。
「スズランには、赤い色はふわさしくないと思います。……血を思わせる赤なんて、特に」
自分の大好きな花が、何故そんな汚らしい色の実をつけるのか。
「赤はお嫌いなようですね。たしか『牟礼の赤』も、血のようだと評価されていたはずですが」
鈴華が毛嫌いしているのは色ではなく、その使い手。心の内を見抜かれたような気がして、鈴華は無言で目を伏せた。
「血を汚らわしいと感じるのは、それが暴力や死を連想させるからでしょう。だが本来、赤は生命力の象徴なんです」
人や動物たちの体を巡り、生命を維持するために欠かせないもの。血液とおなじ色だからこそ、赤は重要視されたのだ。
「吸血鬼が血を欲するのはそのためですよ。血を飲むという行為は、相手の命を飲むことを意味している。彼らは奪った命を己のそれに変えることができるんです。獲物を選り好みする必要はないと思うのですがね。若い女性の血ばかりを求める吸血鬼などもこの世には存在するのです。さながらエリザベート・バートリのように」
彼女は吸血鬼ではなく、十六世紀のハンガリーに実在した公爵夫人だ。美しくありたいという欲望が、人より少し
だけ強かっただけだと七生は言う。彼女は独特な方法で、己の肌を美しく保とうとした。それは若い娘の体から血を搾りとり、その血を満たした風呂に浸かるという方法だった。
犯行が発覚するまで、実に六百人以上の娘が夫人の『美容法』の材料となって殺されていたという。
だがエリザベートだけが特異だったわけではない。人の生き血を飲めば、永遠の若さと美しさを手に入れられる。ヨーロッパやアフリカでは、そんな伝承が密かに伝えられているらしい。
「……父は、あなたに何を注文したんですか?」
痺れを切らして、鈴華は七生に問いかけた。
七生と雑談するために、鈴華は毒草園を訪れたわけではないのだ。想像の産物でしかない吸血鬼の話など、聞いても時間の無駄になるだけだ。
「やはり親子ですねえ。久瀬さんも、私の話を最後まで聞いてくださらない人でしたよ。そういうところも、よく似ていらっしゃる」
自分が父に似ていると思ったことは一度もない。七生の感想は不愉快だったが、表情を変えることなく聞き流した。
日常生活でトラブルを引き起こしても頓着せず、相手の感情を推し量ることもできない。そんな男の娘に生まれて十七年。父のかわりに嫌味を吐き捨てられた回数は数え切れない。少なくとも、そんな言葉にいちいち動揺しない程度には慣れてしまった。
皮肉が通じないと気づいたのか、七生は大げさにため息をついている。だが鈴華の言葉を無視するつもりはないらしい。
「実物をお持ちしましょう。そうでなければ、いくら説明したところで、あなたに信じてもらえそうにありませんから」
少々お待ちくださいと告げて、七生はソファから立ちあがった。鈴華が案内された客間は、母屋とは廊下でつながれた離れ座敷だ。
父が注文した品は、母屋に保管されているのだろう。渡り廊下を歩く七生の足音が徐々に遠ざかってゆき、いつの間にか聞こえなくなる。
客間に残っているのは鈴華ひとり。奇妙な話ばかりを聞かせる男に、多少は緊張していたようだ。無意識のうちに吐息をもらして、鈴華はソファの背もたれに体を預けた。
ふいに強い風が吹きつけて、庭の木々がざわりとうごめく。
音につられて、窓の外へと視線をむける。妖しいほどに空を照りつけていた夕日はいつしか消えて、世界は闇に包まれていた。
自分が毒草園に入って、そんなに時間が経ってしまったのだろうか。
驚きかけて、鈴華は己の考えを否定する。夕焼けは夜への入り口。日没を迎えれば、空が暗くなるのは当然すぎる現象なのだ。七生の話を聞いていたのは三十分程度。それを確認して、腕時計から顔をあげる。
部屋の入り口に立つ人影に気づいたのはそのときだ。その姿を視界に捉えて、鈴華は悲鳴を飲みこんでしまう。
廊下を近づいてくる足音は聞こえなかった。一体いつからそこに居たというのだろう。
柱に手を添えて立つ少女は、紅い唇に笑みを結んで鈴華をみつめていた。
すみれ色の瞳と、金の巻き毛。肌の白さも顔立ちも、毒草園には不釣りあいな異国の少女。年は鈴華とおなじぐらいだろうか。白を基調としたワンピースにはレースがふんだんに使われており、その姿はまるで『不思議の国のアリス』のよう。
だが少女を愛らしいとは思わなかった。天使を思わせる笑みをうかべながらも、鈴華をみつめる視線は蛇のそれだ。天敵に狙われた蛙のように、鈴華は動けない。
「スズランが好きなの?」
唐突に話しかけられて、我知らず体を強ばらせてしまう。
少女から目を離した覚えはない。だがそうと気づいたときには、少女は鈴華の隣りに腰かけていた。
「私も好きよ。あの赤い実が、特に」
息が頬にかかるほどに、その距離が近い。バラを思わせる甘い吐息。しかし鈴華は悪寒に震えた。
「あなた、スズランの実を見たことがないのでしょう? だから花のほうが好きだと言ったのよね。あの美しさを知らないから、そんな錯覚を起こすのよ。可哀相だから教えてあげる」
鈴の音色にも似た笑い声が鼓膜に響く。澄んだ瞳から目をそらすこともできないまま、息を飲む。
指先に鋭い痛みを覚えたのはそのときだ。
いつの間にか、少女に左手を掴まれていた。触れられていると気づいて、はじめて少女の体温の低さに驚かされる。血が通っているとは思えないほどの冷たさだ。
少女は鈴華の手のひらをみつめている。否。その視線がむけられているのは指先だ。針で刺されたような痛みを覚えたのは、人差し指の腹。そこに、赤い血の玉が浮かんでいた。
「ほら、キレイでしょう?」
問いかけとともに、指の付け根を強く押された。圧力を受けて、裂けた皮膚からさらに血が滲んでくる。少女はそれをみつめているのだ。
「ああ、でも違うわ。スズランよりも、あなたの血のほうがよほど美しい色をしている。予想以上よ。とても……気に入ったわ」
白い歯を覗かせて、にたりと笑う。その奥で、唇よりも赤い舌が踊っていた。
そう気づいた瞬間、鈴華は悲鳴をあげていた。逃げようと腰を浮かすが、少女の束縛はほどけない。鼓膜には笑い声だけが響いてくる。冷ややかな声は、自分をあざ笑っているかのよう。
少女に見据えられるのが恐くて、鈴華は堅く目をつむった。
そして一瞬の沈黙。
「お待たせいたしました」
穏やかな声に呼ばれて瞼を開く。
視界に映ったのは、細長い箱を持った七生の姿だ。美術品でも扱うように両手で箱を持ち、ペルシア絨毯の上を歩いてくる。
笑い声は途絶えていた。我に返ってあたりを見渡すが、少女の姿はどこにもない。
「あの子は? いままでここに居たのに」
目を閉ざしたのは一瞬だった。七生は、ソファに座る少女の姿を見ているはずだ。だというのに、七生は不思議そうに首をかしげた。
「金髪の女の子がいたのよ。わたしの手を握って、血がキレイだって言ってたわ。あの子は、なに?」
とても普通の人間だとは思えなかった。その笑みを思いだしただけで、全身に震えが走る。
「ここには少女なんていませんよ。私の他には弟子がひとりいるだけです。いまは外出させていますし、女性に見間違えられるほど可愛らしくもないですから。……顔色が悪いですね。それにずいぶんとお疲れのようだ」
幻覚でも見たのだろうと、暗に告げられた。
「嘘。だって本当に」
血の滲んだ指先を七生に示そうとして、鈴華は言葉を飲みこんでしまう。露のように肌に付着していたはずの血が、どこにもない。痛みも消えて、傷跡さえみつけることはできなかった。
……あれが、幻?
そんなはずはない。少女の姿を、自分ははっきりと思いうかべることができる。だが少女がここに居た証が、何ひとつ残されていないのも事実で。
たしかに、奇妙な少女だった。
足音を聞いた覚えはないし、鈴華の隣りに腰かけても、ソファは沈まなかった。部屋への入り口はひとつだけ。あのタイミングで、七生の目を盗んで逃げだせるはずがない。
そう。彼女が普通の人間なら。
「ごめんなさい。わたし……どうかしていたみたいです」
白昼夢を見たのだとは思えなかった。だが不気味な存在を記憶から消したかったのも事実で。
「それが、父の新しい画材なんですか?」
少女の姿を脳裏から消し去って、テーブルに置かれた箱へと視線をむける。
木目の美しい箱の長さは四十センチほど。真鍮の蝶番もデザイン性に優れており、それ自体が高価な工芸品に見えた。
「久瀬さんは運がいい。これほど質の良い品は、探してもなかなか手に入るものではありませんよ」
もったいぶった言葉とともに、七生の手が箱へと伸びる。驚いたことに、箱には鍵まで取りつけられていたようだ。
鍵をはずしてから、七生は鈴華の手前に箱を移動させた。そして静かに蓋を開く。
余白を埋めているのは濃紺のビロード生地。鈍い艶を放つ布地に守られていたのは、純白に輝く円錐状の物体だった。
ガラス質でも含まれているのか、照明を受けて雲母のように煌めいている。だがこれは鉱物ではないだろう。ダイヤモンドのように澄んだ輝きを見せながらも、その色合いは儚さを感じさせるほどの白さなのだ。
長さは箱より一回りほど短く、円錐の底辺は直径五センチにも満たない。螺旋を描きながら伸びるそれは直線ではなく、木の枝のようにわずかな歪みがある。不対称な形状は、人工物ではない証だろうか。鈴華がはじめて見る物体だった。
「これは一角獣の角ですよ。ユニコーンと言ったほうが分かり易いかもしれませんね。お伽話によく出てくるでしょう」
ロバの体とライオンのたてがみ、そして額から伸びる長い角。幼い頃に絵本で見た一角獣は、たしかに白い体と角を持っていた。美しい姿からは想像もつかないほどに獰猛でありながら、清らかな処女の前ではおとなしく眠りについてしまうという。
目の前にある角は、一角獣のそれにふさわしい形状だと言えるだろう。だが七生の言葉を信じられるわけがない。一角獣は空想上の生き物にすぎないのだから。
「一角獣の角には解毒作用があるんです。中世から知られた薬でしてね、みなこの角を手に入れるために、惜しげもなく大金をつぎこんだ。しかし一角獣の捕獲はとても難しいのです。世間に流通した品の大半は、イッカクという小型のクジラの牙でした。質の悪い商人たちは、セイウチの牙を一角獣の角だと偽っていたそうですよ。同業者としては嘆かわしいかぎりです」
自分こそがまっとうな薬種商だと言わんばかりの口ぶりだ。だが鈴華の前にある品が、本物の一角獣の角だという証拠はどこにもない。
「イッカクの牙と比べて見せれば、あなたの疑惑も晴れるのでしょうがね。あいにく何の効力もない偽物を手元に置く趣味はないんです。それに久瀬さんも、解毒作用に期待して角を求めているわけではない。これが本当に一角獣の角であるかどうかもだ。彼が求めているのは絵の具の材料です。鑑賞者の心を奪えるほどに美しく、誰も見たことがない新しい色。その素材として、これほどふさわしい品はないと思いませんか?」
問いかけられて、鈴華は素直にうなずいた。
正体がなんであれ、きらきらと光を反射させる角は、ため息が出るほどに美しい。これを絵の具として画面に乗せたら、どのような効果を生みだすのか。絵を描かない鈴華であっても、その出来あがりに期待を抱かずにはいられない。
たしかにこれは、父が七生に注文した品なのだ。
そう確信しても、不安が消えたわけではない。
「おそらく『牟礼の赤』を越える反響が起きると思います。父はまた画壇で注目を浴びることができるでしょうね。だけど、それは未来の話です」
岩絵の具の材料は宝石に分類される鉱物もあり、高額な値がつけられている。この角が鉱物を加工した品だとしても、宝石に近い値段での取引が可能だろう。
まして七生は、これを一角獣の角として売りつけるつもりなのだ。空想の産物であるはずの動物が、人知れず実在していたとして。希少性は宝石のそれを遙かに越えるだろう。七生は父に、どれほどの価格を提示しているのか。
「あなたも苦労しているようですねえ」
株価が下落したいま。貯金はほぼ底をついて、あとは土地や建物を抵当にするしかない。そんな経済状態で、父はどこから角の代金を調達するつもりなのだろうか。
「たしかに私は、決して安くはない金額をお父上に伝えてあります。だがその支払いに関して、あなたが頭を痛める必要はありません。どうやらあの人は、裕福なパトロンをみつけたらしいですからね。いくらでも現金を積んでみせると笑っていましたよ」
安心して角をお持ち帰りくださいと、七生は鈴華に笑顔を見せる。だが鈴華の心は晴れなかった。
特別な絵の具を使わなければ見向きもされない平凡な画家。そんな男に援助を申し出た人物は、一体どんな見返りを求めているのか。
一抹の不安を覚えながらも、鈴華は角を収めた箱に手を伸ばした。
2
鈴華が自宅に戻ったとき、時刻は午後八時を過ぎていた。すぐに父を捜したが、外出しているらしく、その姿をみつけることはできなかった。
一角獣の角を美しいと思ったのは事実。しかし時間が経つにつれ、毒草園の怪しさのほうが気になるようになっていた。七生は穏やかな表情を崩さない男だったが態度も話も嘘臭く、鈴華が見た姿が彼の本性だとは思えない。
……父は、彼のことをどれだけ理解したうえで、取引を持ちかけたのか。
おだてられればどこまでも木を登り続けて、己の足元を振り返ることを知らない。父のような小物が、七生と対等につきあえるはずがないのだ。
人気のない家は静まり返っていて、照明も薄暗い。生まれてからずっと住み続けている家だ。暗さにも、ひとりで摂る食事にも慣れている。だというのに、何故か心が落ち着かない。父が帰ってきたのは食事を済ませ、台所の片づけを終えたときだ。
門扉の開く音を聞きつけて、小走りに廊下を進む。玄関ホールの照明を灯すと同時に、父がドアの外から姿を見せた。
「おお、もう帰っていたのか」
鈴華に目を止めて、驚いたように目をみはる。日に焼けた帽子と登山用の長靴。リュックを背負った姿はまるで山から降りてきたばかりのよう。
「佐伯は話の長い男だからな。儂のほうが先に着くと思っていたよ。……まさか、毒草園に行かなかったわけではないだろうな」
「ちゃんと品物を受け取ってきました。あんなものを買うなんて、一体何を考えているの?」
問いかけているのに、父は鈴華の前を素通りしてしまう。おそらく、途中までしか話を聞いていないのだ。いそいそと居間へ移動する父の後ろ姿は、まるでプレゼントを待ちかねていた子供のよう。
だが還暦を過ぎた男がはしゃぐ姿など、みっともないだけだ。我知らず舌打ちをもらして、鈴華は父の後を追った。
一角獣の角を収めた箱は、居間のテーブルに置いていた。鈴華の視界から父の姿が消えていたのはわずかな時間。だというのに、鈴華が居間を覗いたときには父は箱に手をかけていた。
……まるでエサに飢えた野良犬だ。
冷ややかな鈴華の視線に気づかぬまま、箱を開けた父が歓喜の声をもらしている。
「こんなものに、いくらお金を使ったの? この家にはもう、そんな余裕はないって知っているでしょう。佐伯さんは、かわりに払ってくれる人いるから心配ないって言っていたけれど。それは、わたしの知っている人?」
父の前に回りこんで、一息に質問を重ねる。
「話には聞いていたが……これは想像以上だな。この世のものとは思えない美しさだ。鈴華、おまえもよく見ておきなさい」
だが父の視線は角に釘づけられたまま。箱から取りだした角を照明にかざす父は、酔ったように頬が紅潮していた。
「これで、ようやくあいつらを見返すことができる。儂を馬鹿にした奴らの驚く顔が目にうかぶようだ」
「少しはわたしの話も聞いて。父さんのパトロンって誰なの? それにそんな格好して。いままでどこに出かけていたのよ」
こみあげる怒りに比例して、声も大きくなっていたのだろう。父がようやく鈴華を見た。そして不思議そうに首をかしげる。鈴華が何に不満を覚えているのか、まったく理解していない表情だ。
「山形に、ちょっとな。ああ、山菜を採ってきたから、お浸しにでもしてくれ」
周囲を見渡してはじめて、自分が荷物を背負ったままだと気づいたらしい。丁重な手つきで角を箱に戻すと、慌ててテーブルに荷物を広げはじめた。
「そんなことはどうでもいいわ。父さんにお金を出してくれたのは誰なの?」
だが父は応えず、ビニール袋から取りだした山菜をふたつに仕分けている。葉の形はどれも似ていて、何を基準に分けているのか、鈴華には判断できない。第一、自分の話を無視してまで続ける作業だとは思えなかった。
強すぎる怒りに、鈴華は言葉を忘れてしまう。
同時に、心の一部分がひどく冷めていた。
生活のすべてを鈴華に頼り切っているのにその自覚もなく、画家として脚光を浴びることしか頭にない。いまもさっさと鈴華に山菜を渡して、仕事部屋に籠もりたくて仕方がないのだ。
父はそういう人間なのだと、見切りをつけたのは小学校低学年の頃。だが死ぬまでこの男の面倒を見なくてはならないと思うとゾッとした。
「これでいいだろう。儂はこれから大作に取りかかるからな。明日から食事は部屋に運んでくれ。ああ、今朝のアジは安物だったぞ。もう少し質の良いものを食わせてくれ」
無神経な言葉とともに差しだされたのは、ふたつに選り分けた山菜の一方。残りの山菜を戻した袋と一角獣の角だけを持って、父は居間を出てしまう。テーブルには荷物が放りだされたまま。黙っていても鈴華が片づけてくれると知っているのだ。
……わたしはいつまで、あの男に搾取されなければならないのだ?
感情を抑えきれず、鈴華は壁にかけた写真に視線をむけた。無言ですがりついたのは、その中で柔らかに微笑む母親だ。
赤ん坊の鈴華を抱く彼女は、そのとき二十五歳。商才のある祖父に庇護されて育った女性は、いまの十七歳の鈴華より純粋そうに見えた。経済的な苦労など経験しないうちに逝ってしまったのだ。
よく似た顔立ちをしているのに、母と自分の雰囲気はまるで違う。それが家庭環境に起因していると思うと、母のことが妬ましくもある。
……あなたが、あんな男と結婚しなければ。
せめて普通の会社員だったら、自分だけがこれほどの苦労を背負わされることはなかっただろう。
あんな父親はいらない。自分の人生を歪めてしまう存在など、いますぐこの世から消えてなくなってしまえばいい。
だが病気知らずの父が、すぐに死んでくれる可能性は低い。
唇を噛みしめかけて、ふいに鈴華は気がついた。
「……山形?」
その県名は、毒草園でも耳にした。『牟礼の赤』の原料となるトリカブトが採れる地域だ。
色の美しさは、毒の強さに比例するのだと七生は言っていた。トリカブトは茹でると苦みが消えて、そうと気づかず食べてしまう事故が多いのだ、とも。
七生の言葉を反芻しながら、父がいるだろう仕事部屋の方角へと顔をむける。
だが鈴華の脳裏に映っていたのは、目にしたばかりの父の行動。
山菜をふたつに選り分けた父は、何故その一方しか自分に渡さなかったのか。
疑問に思うと同時に、鈴華はその答えを導きだしていた。
古くから猛毒として知られるトリカブトは、『狼殺し』とも『継母の毒』とも呼ばれていた。だがいまは血を分けた親や子であっても、殺人の対象となる時代なのだ。その毒を継母に独占させる理由はどこにもない。
あの老人を、あの世に送りだすために。
自分が取るだろう行動を想像して、鈴華は暗い愉悦の笑みをうかべていた。
3
鈴華がふたたび毒草園を訪れたのは、父の葬儀を終えた翌日。もうすぐ日付が変わろうかという時間のことだ。すでに情報が伝わっていたのか、喪服姿の鈴華を見ても、七生の表情に驚きはない。
「憎まれっ子世にはばかると言うわりに、ずいぶんとあっけなかったですねえ」
父の死を悼むそぶりも見せないまま、平然と言い放つ。
深夜のためか、客間を照らしているのは数個のガラスランプのみ。薄闇に支配された空間には、奇妙な形の光と影が怪しくうごめいている。
「自分で採取した山菜に、トリカブトが混じっていることに気づかないとは久瀬さんらしくもない。老眼でも進んで、区別がつかなかったのでしょう。ほかの山菜と一緒に茹でて水気を絞ったら、私でも選別は難しいと思いますしね」
なかなか上手いやり方です。
さりげなくつけ足された言葉は、鈴華の行動を見透かしてのものだろう。
あやうく素直にうなずきかけて、鈴華は悲しげな表情を取り繕った。
あの晩。父が眠りについた時間を見計らって、鈴華は仕事場に足を踏み入れた。目的は、父が一角獣の角とともに持ち去った山菜。否、トリカブトだ。
父ははじめてみる一角獣の角に夢中になっていたらしく、トリカブトは手つかずのまま机に放置してあった。万が一にも気づかれないよう、手に入れた葉はほんの数枚。しかし猛毒と恐れられるだけあって、トリカブトは簡単に父の命を奪ってくれた。
鈴華は朝食を用意して、父親が眠っているうちに登校してしまった。父は誰に看取られることもなく、ひとりでもがき苦しみながら死んでいったのだ。
あの男には似あいの死に様だと、鈴華は思う。
父の死は変死として扱われて、遺体は解剖に回された。だが鈴華には恐れることは何もなかった。
山菜とトリカブトを採取してきたのは父自身。鈴華にはその違いが判別できず、ただ父の言いつけに従って、山菜を料理したにすぎないのだ。
計画どおり、父は事故死と断定された。鈴華は、晴れて自由を手に入れたのだ。
「目的のためなら手段を選ばす、罪悪感さえ覚えない。あなたは、私の顧客にふさわしい素質をお持ちらしい。さすがにあの人の娘さんだ」
自分は、あの男ほど浅はかではない。
脳裏をよぎった反論を飲みこんで、鈴華は静かに微笑んでみせる。
そう。彼は娘の殺意に気づかぬまま、惨めな姿をさらして息絶えた。父という障害を取り除いたからこそ、鈴華は七生の前にいるのだ。
「佐伯さんに、お願いがあるんです」
むかいあってソファに座る七生をみつめて、そう告げる。七生が扱う毒草に興味を持ったわけではない。彼に会うのもこれで最後だ。
鈴華は携えてきた木箱をテーブルに置いた。真鍮の鍵が取りつけられたそれは、一角獣の角を収めた箱である。
「わたしには不要の品ですから。これを引き取っていただきたいんです」
絵の具としての特性を調べるため、父は角の一部を削り取っていたようだ。だが鈴華がどんなに目を凝らしても、その傷跡をみつけることはできなかった。だから何食わぬ顔をして、返品を求めた。
鈴華が恐れたのは、父に出資した人間の存在だ。葬儀のとき、それとなく参列者を観察していたが、それらしい人物を捜しだすことはできなかった。
一角獣の角を用いて父に絵を描かせようとした人物は、この事態をどう理解しているのか。相手の気配さえ感じられない状況では、その心理を想像することも難しい。
「つまり、取引自体を無効にしたい、ということですか。お気持ちは理解できますが、いまとなっては難しいですねえ。私は、すでに角の代金を受け取っていますから」
鈴華が交渉すべき相手は自分ではなく、金を出した人間でしょうと七生は言う。
「その人を、わたしに紹介してください」
「可哀相に。お父上のせいで、すっかり苦労性におなりのようだ。支払いに関して、あなたが気に病む必要はないと伝えたはずですよ。そう。いまのあなたには、心配すべき未来もない」
鈴華の願いを無視して、七生は楽しげに言葉を重ねてゆく。人が良さそうに見える表情に変化はない。ただ冷ややかに響く声が、静かに鈴華をあざ笑っているようだ。
締め切られた室内に風はない。だというのに、一瞬、ゆらりと照明が揺れる。
背後に立つ人の気配を察したのはそのときだ。
「この方は、絵が欲しくて久瀬さんに近づいたわけではないのですよ。一角獣の角は、彼に取引を持ちかけるエサにすぎなかった。彼の手元に唯一残った宝を手に入れるために、ね」
七生の声とともに背後から響いてきたのは、涼やかな笑い声。両肩をつかまれて、鈴華は悲鳴を飲みこんだ。
体温を感じないこの指には、鈴の音のような声には覚えがある。
鈴華の脳裏にうかんでいたのは、白い服を着た異国の少女。自分の指先に滲んだ血を見て、キレイだとつぶやきながら笑っていた。
すみれ色の瞳にみつめられただけで、全身に鳥肌が立った。少女の正体を知らないまま、怯えた。
そんな恐い存在が、父に何を求めたのか。
「人の生き血には、永遠の若さと美しさを保つ力がある。そんな迷信を実行している人ですよ。とはいえ、すでに数百年は生きているはずですから、その効力も侮れない。しかもなかなか偏食でしてね。極度に潔癖な少女がお好みのようです。自身の清らかさを保つためには、血で手を染めることも厭わない。あなたのような少女がね」
毒草園を訪れた、あのとき。
彼女の目にかなったからこそ、鈴華は一角獣の角を受け取ることができたのだ。
「残念ですよ。あなたのような女性なら、私もぜひ顧客に迎えたいところなんですが。角を渡した時点で、あなたは彼女の所有物となってしまった」
いまさら自分が手を出すことはできないのだと、さも悔しげに肩をすくめる。だが鈴華には分かっている。七生の態度は、すべてが演技にすぎないのだ。
「佐伯。おしゃべりな男はキライよ?」
拗ねたような声に責められても、七生が態度をあらためる気配はない。それどころか、これみよがしにため息をついてみせる。
「勝手に獲物を連れこまれて。あなたの狩りにつきあわされたのは、これで何度目ですかね。たまには愚痴をこぼしたくもなります」
つぶやいて、七生はソファから立ちあがった。すがるような鈴華の視線を無視したまま、絨毯を歩いて廊下へとむかう。
ふと思いついたように七生がふりむいたのは、障子を開いたあとのこと。
「食事の邪魔をするつもりはありませんが、部屋を汚さないでくださいよ。掃除の手間を増やさないようお願いします」
事務的に告げて、七生は部屋を出てしまう。音もなく障子が閉ざされて、客間には鈴華と少女だけが残された。
「手間賃はきっちり請求するくせに。本当に口うるさい男よね」
同意を求められても、うなずけるわけがない。
冷たい指に首筋を撫であげられて、鈴華は恐怖に身を縮ませた。
「あなたのお父様は、この世にふたつとない絵の具の素材を探していた。だから一角獣の存在を教えてあげたの。その角が、どれほど美しいものかをね。あの人、子供のように目を輝かせたわ。本当に無邪気で、あなたによく似た性格をしていた」
角の代金を払うかわりに、あなたの娘が欲しい。
少女の提案を、父はためらう素振りも見せずに受け入れたのだという。
……わたしの行動は、遅すぎたのだ。
自由を得るために、鈴華は父親を殺害した。だがそのとき、鈴華の命は父によって売り払われていたのだ。
よく似た親子だと、他人事のように感心してしまう。自分の欲にだけ誠実で、周囲の思惑には頓着しない。互いに足を引っ張りあった結果が、これだ。
耳元で響く鈴の音色に、意識が遠のく。いつの間にか少女に抱きしめられていた。冷たい肌の感触に、体温さえ<も奪われる。
そして。
首筋に痛みが走ると同時に、視界が赤く染まっていた。それは、わずかに青みを帯びながらも、濡れたような艶を放つ『牟礼の赤』。
毛嫌いしていた血の色に、鈴華は命を飲まれて、消えた。
〈終〉