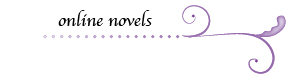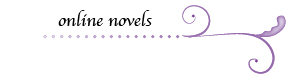
伽羅売りの娘
父が死んだ。
遺体がみつかったのは木々が生い茂る公園の隅。老木に寄りかかって絶命していた父は、全身を何度も殴られて、血にまみれたボロ布のような姿で発見された。そう、殺されたのだ。
それから十日。
わたしは、いまだ父の死を受け入れられずにいる。
春のひざしに満ちた庭では、ソメイヨシノが音もなく花びらを散らしていた。かすかに響く鳴き声は雲雀だろうか。
そんなことを考えながら、支倉(はぜくら)真夜は板張りの廊下に膝をついた。静かに障子を開いて、座敷へと視線を投げる。
しかし喪服姿の男は真夜に気づかぬまま、床の間の前で立ちつくしている。
男に我を忘れさせるもの。
床の間にあるのは名のある器でも掛け軸でもない。あるのは六角形の香炉ただひとつ。男の心を奪ったのは、その内側から立ちのぼる香気なのだ。
産出地によって分類される沈香にあって、最高級の品だけに与えられる称号『伽羅』。希少な伽羅木の中でもこれほどの奥ゆかしさと、凛とした清涼さを併せ持つ香木はふたつとない。
「銘は『十和子』。亡き母を偲ぶためにと、父が選び抜いた伽羅木です」
傍らに立ってそう告げると、ようやく男が振り向いた。
「母の名前を銘に選ぶほど、父が愛した薫り。この香木は、わたしにとって両親の形見なんです。ですから、たとえどれほど札束を積まれようと手放すつもりはありません」
「……この伽羅木には、たしかに札束を積むだけの価値がある」
つぶやいて、男はふいに苦笑をもらした。
「だけど譲って欲しいと言った覚えはないよ?」
「すぐ言いだすに決まってます。製香業者も執拗ですけど、香道の関係者ほど悪質ではありません。あなたたちは、良い香りは自分たちこそが持つべきなのだと無邪気に信じこんで疑わないのだから」
長身の相手をにらみ続けるのも首が疲れる。真夜は相手を促して床の間の前から離れた。
「どうして俺が香道を嗜んでいると?」
「それぐらい、においで分かります」
さまざまな香りを聞き分ける香道において、香木以外のにおいは判定の妨げとなる。香席では香水はもちろん、化粧品や生花のにおいさえ気にかけなければならない。
そのせいだろう。彼らは、一般の人たちよりもにおいが薄いのだ。
「花房流に見雲流。香元を名乗る方々とは、全員お会いしたはずですけど」
座敷机の前に座り、あらためて男と向きあう。男は二十代半ばぐらい。十八歳の真夜とひとまわり以上は離れていないだろう。
「つまり君は、あの人たちの申し出をすべて断ってきたわけだ。こと香りに関してはどん欲な人たちだ。ひとりを相手にするのも骨が折れるだろうに。……だから君は俺をにらんでいるんだな」
「本当に現金を積みあげて見せた方もいらっしゃいますから」
鼻息も荒く香木の譲渡を迫る老人たちの顔など、思いだしたくもない。
「それだけ純粋な人たちだとも言えるんだけど。災難だったね」
同情めいた視線を投げながら、男は名刺を差しだしてきた。しかし泗水(しすい)紘臣という男の名にも、泗水流という流派にも覚えはない。
「明治のはじめに一度途絶えてね。門人をとりはじめたのは五年前だ。君が知らないのも無理はない。だが君のお父上は、泗水流を覚えていてくれたよ」
泗水流を再興した紘臣の父は、しかし病に倒れて一昨年他界したのだという。
香木を商う支倉は古い家柄で、その当主であった真夜の父、影行は歴史に精通していた。どの流派の香元も、知識量では父の足元にも及ばない。
それも当然だ。
香道が成立する以前から、支倉家はこの商いを続けているのだから。
「俺にはまだ学ばなければならないことが多い。だから君のお父上を頼ったんだ。俺にとって支倉さんは、大切な師のひとりだった」
「……父が、あなたに?」
問いただしながら、つい眉をひそめてしまう。
母と、年の離れたふたりの兄を相次いで失ったのは十年前。ただひとり残った娘に、父が家業について語ることは滅多になかった。
だというのに、父はこの男にどんな教えを授けたというのか。
「香に関する知識をいろいろと、ね。香元を名乗るなら当然知らなければならないことだけだ。支倉の秘術を教わったわけじゃない」
真夜の表情を読んで、紘臣は大げさに肩をすくめてみせる。
日本の文献にはじめて香料の文字があらわれるのは飛鳥時代。沈水が淡路島に漂着したという、日本書紀の記述である。沈水は沈香の別名だ。
樹木自体に芳香はなく、傷や枯死、あるいはある種のバクテリアに冒された部分から分泌される樹脂。そこに香の元が隠れている。
正式な名称は沈水香木。
樹脂の重さで水に沈むようになることから付けられた名である。
日本ではもっとも知られた香木だが、東南アジアに広がる密林の奥深くでしか育たない。そんな樹木を見つけだすのは困難を極め、いまでも一度の採集に二十日以上の日数が必要なのだ。
樹脂を分泌するのは樹齢が百を越えた老木にかぎるため、沈香を人工的に栽培するのは不可能とさえ言われている。
だがそれは表向きのこと。
淡路島にたどり着いたのは、沈水を携えた支倉の祖先なのだ。
しかし彼らは香木を売るためだけに日本に移り住んだのではない。ひそかに沈香の栽培方法を編み出した彼らは、栽培に適した土地を求めて海を渡って来たのである。
以来、沈香木の栽培方法は支倉の当主だけが知る秘術として受け継がれている。
香に携わる人間なら誰もが知る、しかし決して一般には口外されることのない事実。紘臣が父に近づいたのも、あわよくばその秘密を暴こうとしたからに違いない。
「お父上は、香の世界になくてはならない人だったのに、残念だ。せめて線香だけでもあげさせてもらおうと思ってね」
「この家に仏壇はありません。故人が生前、最も愛した香を焚く。それが支倉の習わしです」
だから望まぬ弔問者たちも、『十和子』がくゆる座敷に通した。
だというのに彼らは父を悼む言葉も忘れて、『十和子』を欲するばかり。
支倉の後継者である真夜はまだ高校生。そして父、影行の死はあまりに唐突だった。
ゆえに、支倉の秘術も途絶えてしまった。
彼らはそう結論づけたのだろう。
そして現存する伽羅木を買い占めようと、弔問にかこつけて屋敷に乗りこんできたのだ。
兄たちを失ってから、真夜は自分こそが支倉を継ぐのだと自覚していた。
だが秘術を受け継ぐ機会を失った自分は、支倉の後継者として認めてもらえない。客たちの態度で、それを痛感させられた。
「ご遺骨は、もう墓に?」
「本家の墓地に運びました。母と、兄たちがそこで眠っていますから」
正確に言えば、支倉の家に墓はない。葬式すら執り行う習慣はないのだ。だがそれを部外者である紘臣に告げる必要はない。
「犯人はまだ捕まっていないと聞いたけど」
ためらいがちな紘臣の言葉に、唇を噛む。
頭蓋骨が陥没するほどの傷を負っていた父は、おそらく若者たちに狩られたのだろうと説明された。
身なりにはかまわない父だったから、浮浪者と間違われたのではないか。それが警察の見解だった。警察の人間自体、父が古い家柄の当主と知って驚きを隠さなかった。
「ここ数年、市内では似たような事件がくり返し起きていたそうです。父もかなり抵抗して、相手に噛みついた痕跡も残っているそうですけど。犯人の特定には至っていないと聞かされました」
答えながらも、真夜の脳裏にうかんでいたのは変わり果てた父の姿だ。
家族を何人も失ってきた真夜だが、命の尽きた肉体と対面したのはこれがはじめてだった。
冷たく硬直した遺体は恐ろしくもあり、触れることすらためらわれた。
それが敬愛する父のなれの果てだとは信じられず、その死を受け入れることができないのだ。
いまは心静かに過ごしたいのに、次々と訪れる弔問客に感情を揺さぶられてしまう。
ふたたびこみあげてきた怒りに拳を握っていると、紘臣の洩らす咳が鼓膜に響いてきた。
「……すまない。少々体調を崩していてね」
軽く肩をすくめてみせるが、それは香元にあるまじき言動だ。
香のわずかな違いを聞き分けるためには、常に体調を整えておく必要がある。その管理を、紘臣を怠っていたのだから。
「それで、君はこれからどうするの?」
冷ややかな視線に気づかぬふりをしたまま、紘臣は言葉を繋いでゆく。
「ご心配には及びません」
長い歴史を誇る支倉には、代々仕えてくれる人々がいる。真夜が幼い頃と比較すればその人数はわずかとなったが、彼らの支倉に対する忠誠心は変わらない。父の死が伝えられた瞬間から、彼らは真夜を家長と認めてくれている。
そう。外部の人間がどう考えようと、真夜はすでに支倉の当主なのだ。
「たしかにわたしは若輩ですから、しばらくはご迷惑をおかけするかもしれません。けれど、支倉の伝統を父の代で終わりにするつもりはありません」
紘臣を見据えて、何度もくり返した言葉を吐く。
「家業のことを聞いているんじゃないよ。今回のことで、支倉を名乗る人間は君ひとりになってしまった。たったひとりで、その重責を背負い込むつもりなのかい?」
……この男は、何を言いだすつもりなのだ?
紘臣の真意を測りかねて、真夜は眉をひそめた。
「俺も自分の父親を亡くしたばかりだからね。君の心細さは理解できるよ。それに君のお父上も。そう遠くないうちに、君がひとりになってしまうことは分かっていただろう。そして心配もしていた。……俺はね、君と会ってみないかとお父上に頼まれていたんだよ。こんな形で、ではなく」
支倉の人間はみな短命だ。
五十歳を越えた人間など、父の他には数えるほどしか存在しない。平均寿命は四十代前半だと聞かされている。
そのせいだろう。支倉の当主は早婚なのだ。
嫁や婿は分家筋から選ぶ習慣だったが、いまや支倉の血を継ぐ人間などほとんどいない。
そんな真夜の結婚相手として、父が選んだ男が紘臣だと言うのか。
真夜はあらためて紘臣を見た。
香元を名乗るだけあって、その立ち振る舞いに隙はない。顔も整っているほうだろう。弔問客のなかでただひとり、嫌悪感を覚えない男であるのは事実。
だが、それだけだ。
「いまは父のことだけで、頭が一杯で」
「分かっているよ。この話は忘れてくれてかまわない。だけど俺たちは、似たような境遇にいるからね。たぶん、いい話相手になれると思う。これからも、ときどき顔を見に来るよ」
余計なお世話だ。
そう思ったはずなのに、真夜は無言でうなずいていた。
もしかしたら自分は、思っている以上に心細かったのかもしれない。
他人事のように判断したのは紘臣が帰ってからのことだ。
父の遺体をこの目で見てしまったことに、動揺を覚えていたのは事実。それに当主である自分が、いつまでも独り身でいるわけにもいかない。
無名とはいえ香道の家元である紘臣は、たしかに真夜にふさわしい相手ではある。
そんなことを考えながらも紘臣と連絡を取りあうつもりにはなれず、屋敷の書庫に籠もる日々を過ごしていた。
新学期はとうにはじまっていたが、いまさら学生生活を続けようとは思わない。一族が守り抜いた秘術を継承すること。それこそが、いまの自分が最初に行わなければならないことだと信じていた。
漏れ聞いた断片的な知識はある。だがそれだけでは、父が育てた香木を採集することしかできないだろう。支倉の沈香が薫り高いのは、樹木に付着させるバクテリアが特殊だからだ。
だがそれをどのように培養し、管理してゆくのか。
残された書物を読んでも、家中の机や棚の引き出しの裏を覗きこんでも、秘密を伝える書き付けの類は見当たらなかった。
何の成果も得られぬままに時間が過ぎ、ソメイヨシノが葉桜に変わった頃。
真夜に宛てた父の手紙は、十年前まで住んでいた本家の書斎で発見された。
真夜が佐伯毒草園を訪れたのは、その翌日。
古びた木塀に囲まれた園内にはさまざまな植物が生い茂り、平屋建ての母屋は田舎の農家を思わせた。真夜が案内されたのは離れ座敷で、外見は茶室のそれを連想させる。
しかし室内に敷かれていたのは、色鮮やかなペルシア絨毯。中央に置かれた机には螺鈿細工が施されており、机を囲むソファは金色の猫足を持つロココ調のそれだった。
床の間はどこの国のものとも知れない調度品で埋まっていて、悪趣味なことこの上ない。蛇を飲みこもうと首をのけぞらせる孔雀のブロンズ像を目に留めたときは、さすがに踵を返そうとした。
思いとどまったのは、かすかに薫る香が伽羅木のそれと気づいたからだ。
辛みの強い香だが不思議なほど奥深く、幻想的な薫りである。
「これは、父が?」
「おや、よくお分かりですね」
真夜の問いかけに、満足そうにうなずいて見せたのは毒草園の主人である佐伯七生だ。
「たしかにこれは、支倉さんから戴いた香です。この客間で焚くのがふさわしい薫りなのだと説明を受けましたよ」
人が良さそうな表情をうかべる七生は三十代半ばぐらいだろうか。だが七生の年齢など、どうでもいい。
自分が毒草園を訪れた目的を思いだして、真夜はソファに腰かけた。
「突然押しかけて申し訳ありません。だけど、どうしても聞きたいことがあって」
父からの手紙を受け取り、すぐに毒草園に電話をかけた。応対に出たのは子供のようで、七生に取り次ぐこともしてくれなかった。だから明日伺うと一方的に告げて通話を切った。
「こちらこそ。弟子には顧客以外の電話は取り次ぎ不要と教えているのです。だが支倉さんの娘さんとあっては話は別だ。それにしても、彼は不本意な死に方をされましたねえ」
父の死を嘆くように天を仰ぐが、その態度はどこか芝居がかっている。
「支倉の当主が雲隠れできずに、死骸を人目に晒すとは。彼もさぞ口惜しく思ったことでしょう」
さらりと告げられた言葉に真夜は絶句した。
「何故、そのことを」
「支倉の人間は死期を悟ると、自ら死地にむかって遺体を見せない。それを雲隠れと言うのだと、支倉さんに教えてもらったのですよ。あなたの一族は、吐息に混じる甘いにおいで、己の寿命が尽きたことを知るのだ、とね」
父が部外者に支倉の秘密を漏らした。
その事実が信じられず、瞬きも忘れて七生をみつめた。
「あのときは妻と息子を失ったばかりで、消沈してましたから。心が弱くなっていたのでしょう」
「あの父が……」
ひどく寡黙な人だった。
貧相な外見とは裏腹に、鋼のような強い意志の持ち主で。香木の買い付けのため海外に出ることも多く、父が自宅でくつろいでいる姿など見たことがない。
それでもときおり帰ってきては、元気か、と短い言葉をかけてくれた。
そんな父が、憔悴した姿を七生に見せたとは思えない。だが父にとって、七生はただの客ではなかったのだろう。
「昨日、父の遺言がみつかりました」
十年前の日付が残されていたから、殺されることを予期して書かれたものではない。支倉の人間は短命に終わるのが宿命。
いつか訪れるだろう代替わりの時を見越して、父が残した言葉なのだ。
父の吐息に甘いにおいが混じりだしたのは十年前。
家族を失って本家を出て、いまの屋敷に移ったばかりの頃だった。
母や兄たちのように、父も雲隠れしてしまうのではないか。
当時は不安で仕方がなかったが、甘い吐息を吐きながらも、父はかならず真夜の元に帰ってきてくれた。
……それなのに。
「自分が雲隠れをしたら支倉の財産を佐伯毒草園に売り払い、すべてを忘れて生きること。そう記されていました」
父は後継者に真夜ではなく、見ず知らずの人間を選んだのだ。
「それは私も初耳ですね。しかし支倉さんもずいぶんと思い切ったものだ」
おおげさに驚いてみせるものの、降ってわいた幸運を喜んでいるようでもない。
「その遺言を実行するには、相当の代金を支払う必要がある。ためらう気持ちもお分かりでしょう」
真夜の疑問を見抜いて、肩をすくめる。真夜は反射的に首を横に振った。
「わたしには分かりません。父が、何故わたしを選ばなかったのか。わたしの何が父を失望させたのか。いくら考えても、納得のいく答えをみつけることができないんです」
そして何故、父は七生を選んだのか。
七生に感じる怒りは、八つ当たりなのだと分かっていた。それでも、感情を抑えることができない。
「あなたは、支倉の人間が短命に終わる理由をご存じですか?」
真夜が怒りもあらわににらみつけても、七生は穏やかそうな表情を崩さなかった。諭すような口調で、静かに問うてくる。
「……秘術を守るには、避けることのできない代償なのだと。それを恐れたことはありません」
芳香を持たない沈香木を香木に変えるバクテリア。沈香木は細菌から自らを守るために樹脂を分泌し、それが芳香の元となる。
だが支倉が秘匿するバクテリアは樹木だけでなく、人間にも害を及ぼすのだ。
感染力は弱いが、ひとたび感染すれば一ヶ月で人に死をもたらす。
支倉の血族はもともとその細菌に強い体質で、だからこそ沈香の栽培が可能だった。しかし栽培地の側で暮らしていれば、いつかは細菌に冒される。その兆候が、吐息の変化だ。
「抗体を持つ人間を見つけだしては、一族に迎え入れる。それをくり返すことで、バクテリアに強い体質を維持してきたそうですよ。ですが細菌というものは、ときに劇的に変化することがある」
長年飼い慣らされてきた細菌が牙を剥いたのは十年前。
突然その毒性が強まり、抗体を持つはずの一族が次々と菌に冒されてしまったのだ。
母と兄たちの死も、それが原因なのだという。
「本家で暮らしていて、感染しなかったのは真夜さん、あなたひとりだったそうですよ。だから支倉さんは、あなたを連れて本家を出た。そして私の元を訪れたのです」
毒草園を名乗るものの、七生の職業は薬種商なのだという。ただし言葉の意味合いは現代のそれとは異なる。
村はずれには当然のように魔女が住み着き、妖術と医術の区別すらなかった古い時代。
存在するはずのない竜の血や一角獣の角が薬だともてはやされていた時代に活躍していた薬種商の末裔なのだ。
そんな世界においては、香料も薬の一種に数えられるらしい。だからこそ、七生も支倉の家から香木を仕入れていた。
だがそのとき。父は香木を売るためではなく、七生が作る秘薬を求めて毒草園の門をくぐったのだ。
「といっても、毒薬ではありません。服薬を続ければ、死からも解放される不老薬。支倉さんは、それを求めにいらっしゃったのですよ。当時のあなたは小学校にあがったばかり。幼すぎる後継者を残して自分が雲隠れするわけにはいかないと考えられたのでしょう」
声をひそめたのは、決して他人には聞かせたくない秘密だからか。
だがそんな空想めいた話を素直に信じられるわけがない。
「あのときは、あなたもこの客間に見えられたのですよ。人見知りが激しくてね。決して父親の膝から降りようとしなかった」
「そんな記憶はありません」
冷ややかに言い切ってみせるが、七生の表情は変わらない。
……本心の見えない男だ。
そう考えて、真夜は気を引き締める。
七生は欲望を隠さない香元たちとは人種が違う。
芝居がかった態度に騙されていては、七生が告げる言葉の意味すら、正しく理解できないだろう。
真夜は深く息を吐いて、己の感情を鎮めた。そしてあらためて七生と向きあう。
「さすがにあの人の娘さんだ。支倉の名を継ぐ資質は、十分にお持ちらしい」
鳩のように喉を鳴らして、七生が笑う。
小馬鹿にされたとは思わなかった。七生は、ようやく自分を一人前の相手と認めてくれたのだ。
「支倉さんがあなたを跡継ぎに選ばなかったのは、父親としての感情からでしょう。支倉の仕事はけっして綺麗なものではないと仰有っていましたから。そうですね。支倉の人間も、私とおなじ闇の世界の住人といえる」
真夜という名前の由来を父に尋ねたのは小学生の頃だろうか。
真の闇夜に包まれてこそ、見いだせる価値もある。それが父の答えだった。
支倉に生まれた人間は、光ではなく影に生きる宿命にあると父は考えていたはずだ。父の気持ちが変わったのは、家族を失ってからのことだろう。
だが支倉の秘術は一族だけのものだ。それを七生に売り渡すなど、許されるわけがない。
「……父が求めたのは、不老薬だけですか?」
後継者に名をあげた以上、父は七生に秘術を受け継ぐ資格があると考えていたことになる。すでにその秘密を明かしてしまったのだろうか。
「細菌の毒性を弱める方法について相談を受けた覚えはあります。だがその変質によって、沈香木はより多くの樹脂を分泌するようになった。沈香の質が、樹脂の量に左右されるのはご存じでしょう」
それだけではない。バクテリアの変化によって、沈香木はより薫り高い芳香を放つようになったのだ。それに気づいた父は、毒性を弱める研究を止めたのだという。
「以前より管理に手がかかると嘆いていらっしゃいましたが。さすがに秘術中の秘術といえる管理の方法については口を閉ざされていましたからねえ」
真夜の疑惑を見抜いたように言葉を紡いで、天井を見上げる。しかし沈黙の時間は短く、七生は何かを思いついたように真夜を見た。
「お父上に指名された以上、私には支倉の家業を受け継ぐ資格がある。後継者問題に口を挟む権利があるということだ」
「家業を譲るつもりはありません」
「ですが真夜さん。あなたは沈香木の管理方法をご存じない」
冷ややかに言い切られて、真夜は体を強ばらせた。
「とはいえ、いますぐお父上の遺言を実行しろと言うつもりはありません。……そうですね。あなたには、一年間の猶予期間をさしあげましょう。支倉を継ぎたければ、その間に秘術を解き明かしてみせてください」
「ずいぶん一方的ですね。それにあなただって、その方法は知らないのでしょう?」
「おおよその見当はついていますよ。それに一年間という期間にも意味はある。それ以上管理を怠れば、沈香木の質を落としてしまいますからね。そうそう、支倉さんは年に一度、本家に客を招いていたようだ。これがヒントです」
あなたには、お分かりのはずですよ。
肩をすくめる七生の真意を測りかねて、真夜は七生をみつめてしまう。しかし人が良さそうな表情をうかべる七生の本心は分からない。
……七生は、支倉の秘術に興味がないのか?
「支倉の香木は、私の顧客たちにも評判が良い。このまま失うには惜しい商品だ。管理の手間を考えても、十分に利益を生みだしてくれるでしょう。だが私は、あなたの資質にも興味があるのですよ」
毒草園を名乗る七生は、ある基準によって客を選ぶ。七生が客に求める資質は、支倉の当主であれば当然備えていなければならないものだという。
「良家のお嬢さんのふりが板についていますが、あなたは私の顧客になり得る女性のようですから。期待を裏切らないで欲しいものですね」
それ以上は何を聞いても煙に撒かれて、真夜は後ろ髪をひかれながらも毒草園を後にした。
それからの記憶は定かではない。
おそらく何度も道を間違えて、遠回りもしたのだろう。自宅の外見が視界に映ったとき、あたりは夜の闇に包まれていた。
疲れた、と思いながら門扉に手をかける。
しかし重い枷に喘いでいるのは体ではなく心のほうだ。
千年を越える支倉の歴史。代々の当主が守り抜いてきた秘術を、たった一年で解明しなければならない。
そんなことが真夜ひとりの力で成し遂げられるとは思えなかった。だが果たさなければ、秘術を七生に奪われてしまう。
それに、と真夜は唇を噛みしめた。
七生は芝居がかった男だったが、告げられた言葉に偽りがあるとは思えなかった。つまり真夜は、無意識のうちに秘術を引き継いでいるのだ。
おそらくは、断片的な形で。
自分が持つ知識をジグソーパズルのように当てはめてゆけば、正しい絵が浮かびあがるはずだった。しかしいくら考えても、パズルの破片が繋がることはない。
口に広がる鉄の味は、切れた唇から伝う血のそれだろうか。
そんなことを考えていると、真夜の名を呼ぶ声が背後から響いてきた。
「こんな時間まで、どこに行っていたんだ?」
咎めるような声に振り向くと、そこに背の高い男が立っていた。
「お父上が亡くなってから、学校にも通っていないそうじゃないか。なのに行き先も告げずにふらりと出かけて、帰ってこない。みな心配していたよ」
「……泗水さん」
しばらく考えて、父の弔問に訪れた男だと思いだした。その顔も告げられた言葉も、いままですっかり忘れていた。
「父の知りあいに会ってきたんです。……父が、支倉を継がせようとした人物に。交渉のつもりで出かけたんですけど。わたしが敵う相手ではなくて」
久しぶりに出した声は掠れていた。
否。これは涙声だ。
そう気づいたとき、真夜は紘臣に抱きしめられていた。
「何故ひとりでそんな相手と会ったりするんだ。君はまだ高校生なんだ。もう少しはまわりの大人を、俺を頼ってくれていいんだ」
硬直したのは、紘臣の言動に驚いたからではない。
耳元でささやかれる言葉も、真夜の鼓膜を素通りしていた。
真夜の心を奪ったのは、紘臣の吐息に混じる甘い香り。
そのにおいを嗅いだとたん、真夜はすべての答えを導きだしていた。
「支倉の名前は、君ひとりで背負うには重すぎる。俺にも、その荷をわけてくれないか?」
紘臣の申し出に、無言でうなずく。
だが紘臣の胸に額を押しつけたのは、誰かにすがりつきたかったからではない。
すでに涙は止まっていた。
しかし泣いている演技を続けながら、真夜は自分がなすべき行動について考えを巡らせていた。
十年ぶりに訪れた生家は、ひどく寂れていた。
年に数回は父が空気を入れ換えていたはずだが、窓を開け放ってもかび臭いにおいが消えることはない。
とはいえ調度品は真夜の記憶のままで。
脳裏に甦る思い出に、我知らず胸が締めつけられる。だが感傷に浸るなど、支倉の当主にあるまじき行為だ。真夜はため息とともに過去を振り切った。
「それにしても、支倉の本家が本州にあるとは思ってもいなかったよ」
真夜の傍らで、おおげさに肩をすくめてみせたのは紘臣だ。
「もっと南の、離島にでもあると思っていた?」
本来、沈香木は東南アジアに生息する樹木である。支倉の秘術は芳香だけでなく、樹木の性質をも変容させてしまうのだろう。
「それに意外と人里にも近い。こんな場所で、よく千年以上も秘密を守れたものだね」
「大丈夫よ。あの人たちは、支倉の敷地には魔物が住んでいると考えているから」
幾重にも連なる山並みに抱かれた深い谷。その入り口に、支倉の本家は建っている。
付近にはちいさな集落が点在しているが、彼らにとって支倉の人間は悪神の使いだ。
その敷地内に足を踏み入れたが最後、一月後には必ず死が訪れる。それが迷信などではなく事実だと知っている彼らは支倉を恐れ、忌み嫌っている。
その名前を口にすることをも厭う彼らが、よそ者に秘密を漏らすはずがない。
それが秘術を守る煙幕にもなっているのだ。
そう。
支倉の血も引かないくせに、特殊なバクテリアに抗体を持つ人間など滅多にいない。
そんなことを考えていると、紘臣の洩らす咳が鼓膜に響いてきた。
「風邪、なかなか治りませんね」
「そうだな、そろそろ一ヶ月になるか」
長すぎる体調不良に、紘臣自身も疑問を覚えているらしい。だが、それもじきに終わる。
「さすがに山あいは日暮れがはやいね。墓参りに行くのなら、急いだほうが良さそうだ」
正式に婚約する前に、両親の墓に挨拶して欲しい。
そんな真夜の願いを聞き入れて、紘臣はこの地にやって来た。沈香木の栽培地でもある本家の所在地が分かるのだ。真夜の申し出は、紘臣にとって願ってもないものだったろう。
紘臣が真夜に近づいたのは、父の意志ではない。
彼が欲しているのは支倉の秘術なのだ。紘臣が吐く息の甘さに気づくと同時に、そう悟った。
「いいえ。墓地に行くのは夜が更けてからよ。支倉の沈香木には、特殊なバクテリアが欠かせないって話したでしょう? その細菌はね、夜になると蛍のように淡く光るの。今日は新月だから、とても幻想的な光景が見られるはずよ」
真の闇夜に包まれてこそ、見いだせる価値もある。
自分の名前は、その光景にも由来するのだと真夜は信じている。
甘えるように腕に抱きつくと、紘臣は呆れながらも真夜のわがままを許してくれた。
「ああ。でも紘臣さん、どこかに怪我をしていたでしょう。もう傷口は塞がっているのよね?」
ふと思いついたように問いかけると、さすがに怪訝そうに眉をひそめる。
「はじめて会ったとき、消毒薬のにおいがしたから。傷から細菌が入るといけないと思って」
「君は本当に鼻が良いね。たしかにあのとき、腕に切り傷があってね。だけどいまは何ともないよ」
「それならいいけど」
安堵の表情をうかべて答えたが、紘臣の言葉が事実ではないと知っていた。
問いかけ自体がでまかせなのだ。その答えが、真実であるはずもない。
試されたとも知らずに、馬鹿な男だ。
心の内で、吐き捨てる。
彼はいまだ、自分の吐息の甘さに気づいていないらしい。
否。
気づいてもその意味を理解することはできないのだろう。
それが死の兆候であるなど、支倉の人間でなければ分からない。
一族の墓場は沈香木を栽培する森の中にあると聞いていたが、それはすこし違う。
支倉の人間が死すべき場所は、沈香木の根元。
沈香木の栽培に必要なのは、ヒトの肉体を媒介に育ったバクテリアなのだから。
しかし代々の当主が守り抜いた栽培地は一箇所のみ。いままで本家に足を踏み入れたことのない紘臣は、どこでバクテリアに冒されたのか。
可能性はただひとつ。
何者かに殺害された父は、すでに細菌に冒されていた。そして自分を殺した相手に噛みついている。
それは己の身を守るための行為ではない。父は秘術のヒントを残してくれたのだ。
自分の死後、かならず真夜の側に現れるだろう殺人者の体を使って。
紘臣は父の唾液、あるいは血液を介して感染したのだ。
自分の想像はかぎりなく事実にちかいと、真夜は確信している。だが予想が外れていても、別にかまわない。過程がどうであろうと、菌に冒された紘臣の体はあと数日と持たないのだから。
そして七生に示された、一年という期間。
おそらく沈香木の栽培には、常にあたらしいバクテリアを必要とする。父が年に一度本家に招いた客というのは、沈香木のための贄なのだ。
それこそが、支倉が守り抜いた秘術の核。
父が自分の後継者として七生を選んだのは、間接的とはいえ己の娘に殺人を犯させたくなかったからだろう。だがそれこそ不必要な家族愛だ。
支倉の伝統の前では、人の命の重さなど紙切れよりも軽い。
そう言い切れる自分は、七生が見抜いたとおりの人間なのだ。目的のためには手段を選ばず、罪悪感さえ覚えない。彼が顧客に求める資質を、たしかに真夜は備えている。
そう。
秘術に必要とあらば、自分は何人でも贄を捧げてゆくだろう。
激しく咳きこむ紘臣の背中を優しくさすりながらも、真夜の口元には愉悦の笑みがうかんでいた。
〈終〉