PC110(1)
T-ZONEがウェブ上でPC110(YDT)を売り出した。さっそくFAXで注文したけれど、既に完売。残念。 |
お知らせ
| 最近はこのサイト自体が日記化してきている。いたるところに日々の記録が待ち散らされていて、いまさら改めて日記欄に記入することが少なくなった。 そういうわけで、しばらくこの欄の新規書きこみを停止します。あちこちに書きこんだ日々のPCとの格闘は、いずれ記事としてまとめていく予定なので、そのころには、ここに再録する予定。 |
February 17, 2000
保守部品の注文(2)注文していた保守部品が今日、届いた。注文したのが連休明けの月曜で、思ったよりもはやくついた。不必要にどでかいダンボールを開けると、小さなパーツの入った小箱とともに、英語版キーボードが入っていた。 今日はちょうど休みだったので、外出の予定を取り消して、さっそく換装することにした。560Xを分解し、キーボードのコネクタを引き抜いて、交換。設定を英語101キーボードに変えて、立ち上げる。無事完了。 使ってみての感想は、さっそく新しく立ち上げたページに書いたので、ここでは書かない。かなり満足している。 |
February 16, 2000
オークション掲示板がなんだか日記みたいになってしまった。繰り返しになるのでここには書かない。時期を見計らって、掲示板からこちらに書き写そっと。 |
February 11, 2000
保守部品の注文(1)以前から保守部品をIBMから直接購入が可能であると聞いていたので、PCMCIAスロット部分のカバーが取れたのを機会にいくつかの部品を注文した。ついでに思いついて、以前からほしかった英語版キーボードを注文してみた。部品番号も値段もわからなかったけれども、機種名を告げると向こうの側で調べてくれた。愛想のない若い男性で、ほとんど感情の感じられない事務的な声であったが、意外に親切なのか、そういうものなのか、きちっと応対はしてくれた。もっとも送られてきた注文書を見ると個数が間違っていた上に、消費税の計算も間違っていた。これはたんにだれていただけだな。ともかく在庫がなく一ヶ月ほどかかるが、注文は可能であった。 Web上の噂では入手不可能だとのことだったが、単なる在庫切れだったようで、ひと安心。 さて、英語版キーボードだが、これはアメリカに留学している友人が東芝の英語版ノートを持っていて、クォーテーションマークなどがシフトキーを押さずに打てることを自慢していてうらやましかったので、前から交換したいとは考えていたのだ。キーの数が少なくて、エンターキーが細長いのが、なんともいえずかっこいいのだ。 スペイン語版キーボードなども手に入るのだろうか。 |
February 08, 2000
Windows98SEいまさらだけどWindows98SEを先月購入。560X+Windows95OSR2ではなんだかUSB周りが不安定であるのと、PCMCIA管理ソフトであるCardWorks関係のトラブルが多発したため。正直、560+OSR1のほうが安定している。インストールがややこしくて、このあたりの設定に問題があるのだろうけれど、面倒くさくて98をインストールした。意外なくらい安定しているのだけれど、問題がいくつか。ひとつは有名なバグだけれど、電源が落ちない。これはMSのサイトから修正プログラムを導入して、とりあえず解決。それでも時々落ちなくなる。USBのメモリリソースの範囲を手動で変えることにより、これは回避できる。詳細はIBMのサイトにある。 これと関連してか、サスペンドに入らない。これは今のところ、解決できていない。 もうひとつは、グラフィックにあって、表示画面を新しくした際に、以前の表示の一部が残ったままになることである。これも原因は不明。 それでも98の使い勝手は悪くない。フォントが見やすくなっているのが、いまのところ一番のお気に入り。それだけって説もあるけれど。あと、シングルクリックも慣れれば悪くない。 |
January 16, 2000
Internet Explorer5.01以前インターネットエクスプローラ5.0を導入したときに、全体に動作が軽くなった感があって、まっとうなバージョンアップだと誉めたことがあった。しかしながら何回かに一回は起動しないことがあり、すぐに消してしまっていた。起動したとき、たまに例外違反が発生するのである。これは周知のバグであったようで、5.01にバージョンアップされた際に改善された。それを聞いて、さっそく導入。いまのところは正常に稼動している。最近、問題がどんどん解決していくなぁ。パソコンの環境が向上したのか、おいらのスキルが向上したのか、パソコン使用者間の情報が蓄積されつつ広がっていっているのか、おそらくそのどれもが当たっているだろう。 昔、若くして死んだレーサーの東海道をカブで走破した記録を読んだが、当時の車やバイクなんて、トラブルの際の専門知識なしでは乗っていられないというのが常識だった。そのころから現代のモータリゼーションを思えば隔世の感がある。同じことがきっとパソコンにもいえるようになるだろうという気がする。 |
January 16, 2000
Laser5LinuxLaser5Linuxを導入。くわしくは今度。 |
January 10, 2000
LANの問題解決Niftyのフォーラム、FIBMNOTEのFAQで無事解決。以前にここで書いていたLANの障害についてのことである。なんのことはない,ThinkPad560はあらかじめジョイスティックのドライバーを組み込んでおかないとLANが正常に動かないそうだ。ゲームなんかしないから、ジョイスティックなんて組み込んでいない。 あらためてジョイスティックのドライバーを組み込んで再びLANカードを導入。 こんどはあっさりとネットワークに認識された。なんだ、こんなことのためにおいらはいったいどれだけの睡眠時間を無駄にしたのだ。 おかげで我が家のLANは快調。ナイキネットも最早必要なくなり、ようやくごく当たり前の環境が成立した。 これならば560Xを買う必要はなかったかな。まぁ、それなりに楽しんでいるからいいか。 |
December 21, 1999
560X購入二号機の性能には十分満足していたのであるが、HDを換装して以来LANにつながらなくなってしまった。これの原因は後で分かった。Win95の再導入の方法に問題があったためである。しかしそのときは何度インストールされても改善されないため、HDとの相性の問題かと考えて、買い替えることにした。たまたま買ってくれる人が現われたので、中古で560Xを\97kで購入。しかしながら買った後で二号機売却がドタキャンされてしまった。購入前後の経緯はともかく、560Xはけっこう気に入っている。 日本橋のBus&Tugで\99,800。安いけれどもHDに不良セクタがあり、これがいちばんの問題。PCカードの蓋は取れていて、キーボードにはコーヒーでもこぼしたのか食べ物滓のようなものが、奥のほうに多量に付着している。そのためかキーボードが歪んでいたので、これは負けてもらった。-\3k。 買ってきてさっそく分解掃除。その後HDDを6.4Gに換装。メモリーも32MBがあまっていたので増設。前のユーザーはキーボードの汚れかたから判断してもあまり使っていなかったようである。食べ物の滓はあっても、キーボードにテカリがほとんどみられない。雑に使っていたのだろうな。 OSの再インストールが一番大変だった。Windows95のOSR2がついていたので、これをクリーンインストールしようと思ったけれど、自分で作った起動ディスクではうまく行かなかった。結局、付属の起動ディスクのConfigとAutoexecを書き換えて、僕の持っているPanasonicのPD/CD-ROM、LF-1500のドライバを組み込んだ起動ディスクを作った。これで導入。修正ファイルを組み込んで無事成功。 OSR2を入れてみた結果、結局Windowsは95の初期バージョンが一番安定しているという結論に達した。それでもFAT32とUSBを使うためには仕方があるまい。でも考えてみたらどちらも使ってないんだよね。 560Xそのものは満足。動画の動きが滑らかだし、MP3を再生しながらほかのことをしても、ほとんど影響が出ないのはうれしい。 |
September 21, 1999
Plamo Linux 導入成功!Debianの最新版を買いに行ったところ、『ホップ!ステップ!Linux』という本を見つけた。Plamo Linux(1.42LE)が付録で付いていて、本もわりと簡単そうだったので、購入。Plamoで再挑戦。結論から言うと無事インストール完了。XF86の設定には手こずったけれども、XF86SetupではなくXF86Configで必要な情報を書き込んで無事立ち上げることが出来た。問題はモニターの周波数の設定にあったようだ。デフォルトで用意されている設定ではどれもうまくいかない。Web上に公開されていたXConfiguratorを参考に手動で設定。(参考『とことん使えるLinux』)モノクロの画面からいきなりカラーの画面に変わったときには、なんというか長い間の航海の末に新大陸を発見したような気分だった。 いまのところ、問題はCD-ROMのマウントが出来ないこととモデムが認識されないということである。元がslackwareだけにほとんどが手作業であるが、導入に散々苦労した僕としては、手作業であっても自分が現在何をしているのかがはっきりとわかる方がいい。slackwareは、解説の本もWeb上でのFAQも充実しているので、わからないことは容易に調べがつく点もよい。 これからネットスケープをインストールして、インターネット端末としても使えるようにするつもり。最終的にはサーバー環境を構築してもいい。 あとはいろいろ本を片手に勉強するか。 |
September 16, 1999
Debian/GNU Linux or elsoVineはやめ。というわけで、パーテイションを切りなおして、初期化。Debianに挑戦だ。以前に挑戦して出来なかった理由はWeb上で判明。ブートディスクはTP560の場合、東芝Tecra用のディスクを使う必要があるのだ。OK。 今日は休みなので朝から導入。でもインストールのやり方が複雑でいまいちわからない。だいたいインストール本(AIムック200「挑戦!Linux」)はノートへの導入なんてほとんど想定していない。win95との共存も想定していない。発行年月日が古いのだ。使っているバージョンも古い(1.3.1)。わかりやすいことはわかりやすいのだけれどね。仕方がない。またニノミヤに行って適当なデストリビューションがついている雑誌を探してこよう。 ちなみに現在AptivaB86の方は1024x728の画面で動いている。こっちはVineで快適。 |
September 15, 1999
PC Town ニノミヤ西奈良店ぼくんちから歩いて5分もかからないところにニノミヤがある。ここはPC-Townを名乗るだけあって、品揃えは、日本橋並とまではいかないが、なかなかのものである。自作用のパーツまでそろっているのはうれしい。たいていはここでそろってしまう。ここしばらくLinux導入で悩むたびに、ここの書籍売場にヒントを探しに出かけてゆくのだが、平日の昼間からうろうろしているひげ面は、店員の目にもさぞかし怪しげにうつっているのだろうなぁ。 そうは思いながらも便利なので、つい通ってしまう。 考えてみれば、職場から飲み屋から趣味の店まで全て徒歩圏にあるのだ。考えてみたらすごいことかも知れない。 |
September 15, 1999
Vine Linux (3)前述のハードディスクからのインストールなのだが、CD-ROMからハードディスクにコピーするときにファイルの大文字小文字がおかしくなるのが原因と聞いたので、インストールのテキストに書いてある方法でrenameする。しかし状況は変わらない。結局560を分解して、ハードディスクをAptivaに直接繋いでインストールした。X-windowの設定はとりあえずビデオチップなどを指定し、検証はすっ飛ばして、とりあえず導入。改めて560に入れ直して立ち上げた。 しかし、ここでもまた、X-windowが立ち上がらない。Xconfiguratorで設定をやり直すが何度やっても立ち上がらない。 Vineがこの状態だとRed-hat系はダメなのか? 実は以前にDebianを試したことがあるのだが、そもそもインストール用のディスクからブートすることも出来なかったのだ。 plamoは導入できるのだろうか。 今宵もたぶん眠れそうにない。 |
September 11, 1999
Vine Linux on Aptiva気分転換にディスクトップマシンにインストールしてみることにした。Aptiva B86である。グラフィックチップはATIの3D RAGE ll。はじめてみると嘘のようにすいすい導入できる。途中X windowの設定の設定で800x600以上に解像度をあげることが出来なかったことを除けば、特に問題はなし。無事立ち上げることが出来た。感無量。これで僕もLinux User。まだタコだけれど。気分一新、またThinkPad導入に挑戦する気がわいてきた。 |
September 10, 1999
Vine Linux(2)CD-ROMからの導入をいったんあきらめて、ローカルのWindowsのパーテイションからインストールすることにした。なにせFAT16なものだから6.4GBが4つのドライブに区切られているのだ。スペースはいくらでもある。注(Win95の初期リリースはFAT16と呼ばれるファイル形式であるため、最大2GBまでしか一つのドライブとして認識しない)C/D/E/Fの4つのファイルのうちC/D/EをWINDOWSで使うことにする。とりあえずDドライブにCD-ROMの内容を全てコピー。ブートディスクでいったん起動した後、インストールの方法で「ローカルのハードディスクを選ぶ。とりあえず先には進める。 Disk Druid(Vine用のパーテイション設定用ツール)でFドライブを削除。Linuxで使えるようにスワップパーテイションとルートパーテイションを作成。 ところがここから先が行けない。インストール用のファイルの入ったDドライブを選択しても、ファイルが見つからないと表示がされるのだ。 ここから先はいろいろ試してみた。Windows用のブートディスクで直接CD-ROMを指定してもダメだった。 うーむ。もう、やだ。 |
September 09, 1999
Vine Linux(1)先日からVine Linuxの導入に挑戦しているのだけれども、これがなかなか思うようにいかない。まず日本語インストーラーが文字化けする。TP560のグラフィックチップにインストーラーが対応していないようだ。bootのあとにlinux nokonと打ち込んで、konを無効にする。そのあとインストール時の言語の選択画面でEnglishを選んで、とりあえずはOK。問題はそれからで、外付けのCD-ROMを認識してくれないのだ。これがよくわからない。いっそのこと導入もとのCDをハードディスクにコピーして、そこからインストールしようか。うーん。 とりあえず、一眠りして考えよう。それでは。 |
September 06, 1999
HDD換装2号機のHDDは1.0GBしかないので、HDDを換装することにした。Web上で調べた価格は6.4GB、9.5mmで約\26K。Niftyのフォーラムでの換装実績のあるIBMのDBCA-206480を選んだ。(詳細はMy Computing SystemのHD換装ページ)換装した結果、HDBENCHでほぼ3割以上、システム全体としても1割弱のスピードアップである。なかなか快適。 さっそくfdiskをかけてパーテイションを区切る。初期バージョンのWindows95しか持っていないので、2GB以上のパーテイションをつくることが出来ない。 結局2.0G/2.0G/1.0G/1,0Gで区切った。 起動ドライブはシステム関連のみにして、アプリケーションは全て別ドライブと言うことも考えたのだが、インストールの時に面倒だし、これで行くことにした。 C,DドライブはWindows95、EドライブにLinuxを入れることを考えている。 |
August 19, 1999
LAN(2)ThinkPadが2台に増えたので、LANカードをもう一枚買ってきた。前にも少し書いたが、ネットワークへなかなか接続できないという現象が初号機にはあって、原因がPCなのかNICなのか特定できずにいたのだが、2号機に挿してみてわかった。おそらく初号機に問題があるのだ。ドライバーを入れ直そうにもデバイスマネージャーのプロパティで、ドライバーのタブが現れない。なにか問題があるらしいのだが、ちょっとわからない(これは後で気がついたが、SafeModeで起動すれば再導入できる)。 とりあえず、ほっておくことにして、LANカードをもう一枚、近所の家電量販店(弟くんの勤務先)で購入。結局、前に買ったものと同じ物にした。ドライバに若干手を加える必要があるが、Linuxも使えるし、WindowsCEに対応している上に、なによりも安いので、まぁいいや。 それで、実際に繋げてみての話なんだけれど、初号機の調子はあいかわらず悪いし、ちょっと大量のデータを送ると、よくわからないメッセージが出てきて、フリーズしてしまう。確かに多少のデータのやりとりは楽なんだけれども、結局今のところナイキネットには勝てないというのが結論。
|
August 16, 1999
InternetExplorer5.0友人のアトリエでLibllet50を借りて、ネットに繋いだ。pentium75程度なのに妙にサクサク動くなと思ってみるとie5.0を使っていた。ie4.0よりも速いとは知らなかった。さっそく家に帰り、インストール。アクティブ・ディスクトップが導入されるのではないかと少し不安だったけれど、ie4.0で導入されていなければ、その環境が引き継がれるようだ。たしかに軽く感じる。マイクロソフトにしてはまっとうなバージョンアップだ。でも起動が遅くなったようであるのは気のせいか。 |
August 16, 1999
ThinkPad 560 二号機先月の終わりに日本橋のソフマップ中古センターで560FJEが\55kで売られているのを見つけた。pentium133/12.1inchTFT/HD1.0G/memory40MB(32MB増設済)というスペックでこの値段はちょっといい。取り置きしてもらって一週間、少し考えて購入。値段が安いのにはちゃんと理由がある。ACアダプター無し、バッテリーは中古なのでもちろん保証無し、液晶ヒンジ部にひび有りという状態のためである。けれども僕はすでに560を持っていて、大概のパーツは共有できる環境にあるため、別に問題はない。それにACアダプターはサードパーティ製の急速充電器のACアダプターが流用できることがわかっていた。これは以前にT-zoneで\4k程度で購入済み。こんなところで役に立つとは思わなかったけど。 ちなみにヒンジ部のひびは無印560の持つ欠点で、よくあることなのだ。強度的にさほど重要な部分ではなく、単に美観を損ねるだけであるため、気にしないことにした。 バッテリーは案の定死んでいた。うんともすんとも言わない。これは買わなきゃなんないなと思っていたら、しばらくしてバッテリーがいきなり生き返った。しかもバッテリー・メーターで見る限り、カタログ・スペックである3hの数値を出している。バッテリーは個体差が大きく、初号機が2h程度だったので、実にその1.5倍。なんてことはない。なにもしないうちに問題はすべて解決してしまったのだ。 同じようなスペックのノートパソコンを買った理由は予備機として使用するためである。海外の発展途上国で使用することを前提としているので、一台壊れても互いにパーツを共有できるのは力強い。ついでに一台をLinuxマシンにしてしまえっとばかりに買ってしまった。 そう思って買ったのだが、TFTはやっぱりきれい。気がついたら二号機の方も初号機と同じ環境を構築して、メインマシンにしてしまった。こうなると1GのHDが何とも力不足で、次は6Gくらいに増設したろかなんて考えている。 あぁ泥沼だ。 |
June 27, 1999
PC110(4)Be-StockでのPC110(YD0)限定販売、残念ながら抽選にはあたらなかった。お金もないことだし、入手はあきらめようかと思う。IBMから340MB、CFサイズのハードディスクが販売されることだし、手に入れられれば面白いかなと思ったけど、残念。 |
June 24, 1999
バックナンバーLANの調子が悪い。どうも原因はカードのようだ。なかなかネットワークで認識されない。あまつさえ電源が落ちないこともしばしば。使い方が悪いのか?。それはともかく、昨日は休みだったので昔のパソコン雑誌を整理していたら、結構面白くて、結局休みを一日つぶしてしまった。 なんといってもハードの記事が面白い。今は名前が変わってしまったHello!PCなんか読むとオリベッティのパソコンの記事とかが出てくる。エコスなど、今見てもきれいなデザインだと思う(画像などはこちら)。もう手に入らないのかなぁ。LINUXなら今でも使えそうだ。ハードディスクなどが安くなったおかげで、昔のノートなども手を加えれば使えそうな気がする。 最近、PC110等の昔のPCが人気なのもわかる。時が過ぎて振り返ってみれば、昔は見えなかった造り手の想いが見えるような気がするのだ。 |
続き オリベッティ関連のページをざっと流していたら、おもしろいページにたどり着いた(Yamachan's Home Page)。関西弁の語り口調がなんともいえない味をだしていた。それでいて使っているのがイタリアンデザインの極みのようなオリベッティというのがいい。時間があったら覗いて見る価値はあると思うよ。コラム(悪の経典)がおすすめ。 ちなみにオリベッティのパソコン部門はもう実質、存在しないらしい。ブランドは残っているけれど、ほとんど別会社だそう。 |
June 19, 1999
PC110(3)Be-StockでPC110(YD0)が\10kで販売されている。抽選だけど。とりあえずインターネット上で申し込んだ。はたして購入は出来るだろうか。 |
June 15, 1999
DS110とi-mode(2)以前にDS110の簡易ブラウザーでi-modeのリンクが辿れないという現象を書いたが、これについてニフティのフォーラム(SMTELVA)に書き込みがあった(19006)。これは「リンク先CGIと現在表示されているページのURLが一致しているために、ブラウザがページは既にロード済みと判断して、キャッシュを引いているため」とのことで、強制リロードの「3」を押せばOKだそうだ。 これでi-modeのサービスも利用できる。 って今書き込みながら試してみたけれど、ダメだった。なんでだろう。表紙のページしか見ることができないのだ。 |
June 14, 1999
ナイキ・ネットとりあえずディスクトップ(IBM Aptiva B-86)にLANボード、ノートPC(ThinkPad560)にLANカードを挿して無事稼働することを確認した。でもまだケーブルの配線が終わっていないので、家庭内LANはまだ実現していない。仕方がないので職場に持ち込んで、ハブにケーブルを繋ぎ、LANにアクセスしている。 初めの内は繋がっただけで喜んでいたのだけれど、どうもネットワークに認識されるまで、随分時間がかかる。原因はよくわからない。ひどいときには認識さえ、されない。 ナイキ・ネットという言葉がある。 どういうことかというと、パソコンのデータを転送するのに、フロッピーにいったん落としてから、自分の足で転送したいパソコンまで運んでいくことだそうだ。スニーカーを履いて片手間にヒョイッと運ぶのでこの名前が付いた。結局これが一番早いということらしい。うーむ。 |
June 09, 1999
PIAFSDS110で単体でのPIAFS接続(PHSの高速データ通信サービス)がなぜか出来ない。アクセスポイントが大阪なので、繋がらないのかと思っていたが、そうではなかった。単なるプログラムの入れ忘れ(通信モード選択)であったのだ。小さなプログラムだが、これが必要であることが取扱説明書を読んでもいまいちわからなかったため、導入していなかったのだ。まぬけな話だけれども。 ここ2,3日、あらためてDS110と格闘して、無事接続。 あらためてPIAFSの有用性を知った。なにせ家で使っている28.8Kbpsのモデムより速いのだ(PIAFSは32Kbps)。回線の状態もいい。しかも繋がるまでの処理スピードが速い。ほとんど電話待ち程度の感覚で繋がる。通常の接続の場合、モデム特有のピーガー、ピーヒョロロロの音がするけれど、PIAFSだと、その前にあっさり繋がってしまうのだ。すごい! メールのダウンロードもすぐだし、朝日新聞の見出しなどは2分もあればasahi.comにアクセスして、読めるようになる。こんなに便利なものだったとは知らなかった。 でも、よく考えてみるとDS110を購入してから2年近くなるけれども、その全ての機能が使えるようになったのがここ数日のことである。 なんでも現在のDS110のユーザー数は1000台程度で、その大多数が単なるPHS+PIM(スケジュール管理)でしか使っていないそうだけれど、無理もないなってところ。 |
June 02, 1999
LAN31日が給料日だったので、さっそく電気屋へ。LANカードを買ってきた。職場にLAN(ローカル・エリア・ネットワーク)が組んであるので、これでHUBに繋げれば職場のプリンターを自由に使えるし、デスクトップとのデータのやりとりも、いちいちフロッピーを介さなくても良くなる。ケーブルを繋げるだけで、自分のノートパソコンからクリック一つでプリントアウトが可能になるのだ。 ついでに今日は休みの日だったので、東洋陶磁博物館に行ったついでに日本橋まで足を延ばし、LANボードを買ってきた。これで家のデスクトップともLANが組める。予算は結局1万弱。一昔前に較べて、信じられないくらい安く組めるようになった。すごい。
|
June 02, 1999
PC110(2)PC110(YD1)が日本橋のソフマップで、\39,800(中古品)。高い!でもこれをのがすとしばらく手にはいらなさそう。ちょっと考えたけれども、やめた。もっと安く手に入られるはず。次の機会を待つ。 |
May 30, 1999
PC110(1)
T-ZONEがウェブ上でPC110(YDT)を売り出した。さっそくFAXで注文したけれど、既に完売。残念。 |
May 29, 1999
DS110とi-modeDoCoMo i-mode用のページがいくつも出来ているようで、最近はリンク集まで出てきているようだ(i-seekなど)。データスコープの簡易ブラウジングにも使えないかと早速ブックマークに登録してみたが、リンクがうまくつながらない。どちらもテキスト主体のブラウズしか出来ないので、テキスト中心の必要最小限の情報で構成されたページのはずなのだが、i-modeはなにか特殊なhtmlを使っているのだろうか。リンクが<href=>で記述されていることには変わりないようなのだけれども。 それともデータスコープの側の問題なのかなぁ。 |
May 28, 1999
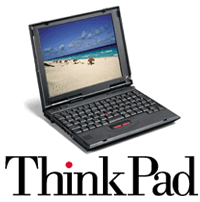 ちょうど夏のボーナス時期に合わせて、各社とも新製品を続々と市場に投入している。興味をそそられているのはIBMの新製品である。 ちょうど夏のボーナス時期に合わせて、各社とも新製品を続々と市場に投入している。興味をそそられているのはIBMの新製品である。ThinkPad570と240(写真)がそれである。詳しく書こうと思ったけれど、眠いのでこの次。 |
May 28, 1999
データスコープの機能(2)前回の続き。 ついにデータスコープの単体メール受信に成功!近所にPIAFSのアクセスポイントがないので2400bpsでの接続。ついでに簡易ブラウザーによるウェブの閲覧も出来た。i-modeなんて使わなくてもほぼ同等の機能が実現したわけだ。 インターネットクライアントという単体での接続ソフトは、以前から購入していたのだけれど、アサヒネットにはつながらないということだったし、試してみてもダメだったので、実を言うとすっかりあきらめていた。結局コンフィグの設定に難があったようだ。といっても説明書にしっかりと書かれていたことなので、ちゃんと読まなかった僕が悪いのだけど。 それにしても京セラは出来ることをしっかり宣伝しない。奥ゆかしいというか、なんというか。商業的にはデータスコープは失敗だったようだけれど、さもありなんと思う。 |
May 25, 1999
データスコープの機能データスコープのシステムバージョンが4.0にアップグレードした。さっそく京セラのホームページからダウンロードする。今回のアップグレードは正式にはWindows98に対応したということであったが、実はWindowsCEにも対応していると、NIFTYのフォーラム上で報告があった。 これ自体はWindows98もCEも持っていない僕にしたら直接は関係ないことなのだが、以前にも書いたとおりThinkPad z50が出たこともあって、これと組み合せれば、かなり使い勝手の良いモバイルシステムが出来るなぁと考えてしまった。いまのところ歯止めはz50に今のところ日本で販売される予定がないことだろう。(笑) それはともかく、もう一点。 データースコープの単体メール機能はこれまでアサヒネットに対応していないとのことなので、ほとんど利用していなかったのだがフォーラムの書き込みで受信だけなら可能であることがわかった。 購入から約2年。ようやく当初の目的が達成できるかもしれない。 それにしても最近いろいろ出回っているPDAのなかでも、これだけいろいろできるものも少ないけれど、これだけ何が出来るのかわからない機種も少ないだろう。京セラ自体がわかっているのかわかっていないのか、あまりアナウンスしないところがおかしい。 |
 |
May 13, 1999
LANボード on AptivaIBMのホームページにフォーラムが出来た。長年の懸案だったAptiva B86にLANボードをつなぐという試みが、ここのコメントであっさり解決した。メーカーは繋げないと言っていたのだ。詳しくはまた書く。 とりあえず、フォーラムは役に立つなぁってとこ。 |
May 12, 1999
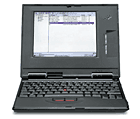 少し前だけれどもIBMからWindowsCEを搭載した薄型ノートが発表された。 少し前だけれどもIBMからWindowsCEを搭載した薄型ノートが発表された。気軽に持ち運ぶことの出来る重さで、なおかつ打ちやすいキーボードを持ったマシンを探していたのだが、ここにきてようやく望むものを見つけたかという気分になっている。WorkPad z50がそれである。 もっとも値段と改造の余地がある点でPC110にも魅力を感じているので、あいかわらず趣味の世界での物欲は限りがないなとも思う。 |