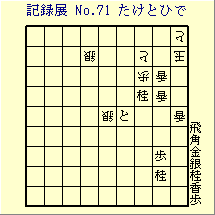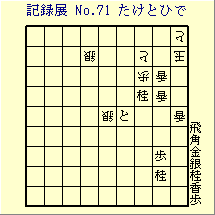
見ての通り、七種持駒。
本作のすごいのは、それを歩、香、桂と最後の飛まで順番に打つところ。
しかもその他の手は一切ない純粋な順列七種連打、ということは理論上の最短手数です。
そう、本作は、順列七種連打の短手数記録(13手)なのです。
順列七種連打をデータベースで調べてみたところ、次の3作がありました。
- 木脇克弘 詰パラ1979年1月 17手 飛打−歩打
- 墨江酔人 近代将棋1979年7月 31手 飛打−歩打 早詰
- 長谷繁蔵 詰パラ1996年12月 15手 飛打−歩打 早詰
いずれも飛打から歩打への順列で、歩打から飛打への順列は本作がはじめて。
*下記参照
飛打から歩打では最後打歩詰になるので15手が理論上の最短です。
なお、本作は七種持駒の短手数記録でもありますが、こちらは13手の作品が既に3作あります(北村憲一、信太弘、信太弘)。
歩打からの順列では強い駒が残るので、余詰防ぎが大変で、本作も修正を重ねてようやく完成。
苦労のあとが偲ばれる配置ですね。
13歩、同玉、14香、同玉、26桂、同香、25銀、同香、
24金、同玉、35角、23玉、13飛 まで13手
手順の方は小駒の5連続捨て駒が見どころ。
13歩と14香の手順前後が成立しないのは当然ですが、この微妙な違いを成立させるため、2手目21玉の変化がかなり難しくなっています。
41飛以下同手数駒余り(分岐棋譜で示します)で詰み。
この変化をとばしした方もいたようです。
形は推敲の余地があるかもしれませんが、史上初の歩から飛の順列七種連打で理論上の最短を実現した本作、記録作として歴史に残る作品になりました。
それでは、みなさんの感想を。 解答到着順です。
- 凡骨生さん:
- 持駒一式順列打ち詰めは初めてでしょうね。
- 長谷繁蔵さん:
- 2手目の変化分かりませんが正解かな。
- ほいさん:
- ★順列駒打ちの最小駒数??
簡単そうに見えて、なかなか難しそうなテーマですねー。
2手目2一王はSkip。信じてます。
なるほど。 最小駒数の記録にもなっていますね。
- やまかんさん:
- 歩〜飛車の順番で打っていく詰将棋ですか?
形、手順とも強引な印象ですが、やっぱり最初は価値がある。
- 中澤照夫さん:
- 持ち駒7色順列使用。
- しろねこさん:
- 盤駒に並べて確かめています。
変化が15手ですと駒余りになるため短手数の13手にしました。
13手駒余りで割り切れています。 柿木将棋なら短手数用で解かせれば最短手順が求められます。
- 隅の老人Bさん:
- 持駒一式、順列打ですね。
2手目に21王の変化、13手以内で詰むのかな?
この暑さ、調べる気持ちはサラサラない。
出題者のTETSUさんを信用してます、ホントだよ。
- 嵐田保夫さん:
- 作者さんの性格(笑)が出ているのか、律儀に歩から飛車まで順番に使っていくのがなんかユーモラス。
- 池田俊哉さん:
- 順列七種打。作意順はひと目でも、2手目の変化が少しややこしい
- 上田大輔さん:
- 下(歩)から上(飛)への持ち駒エレベーターという印象を受けました。
- 占魚亭さん:
- 狙いに気付くまで少し時間がかかりました。うーん、なるほど。
- 鈴木康夫さん:
- 2手目の変化の方が苦労しました。
|