|
12月2日(火)授業 遺伝の復習「伴性遺伝」 |
伴性遺伝の復習をしました。ショウジョウバエでの実験結果は,期待通りになったでしょうか。 今週は試験です。明日も,試験範囲の復習をします。 |
|
12月3日(水)授業 復習「DNA他」 |
試験前の復習をしました。DNA,受容器,効果器,神経系についての復習です。基本的な用語や,覚えることが多くて大変ですが,丁寧に,一つひとつ,理解して下さい。眼や耳は自分で図を描いたりして,まとめてみるのもいいかも知れません。 「明日から試験です。生物は最終日,火曜日ですから,月曜日には,思いっきり勉強しましょう。それまではしなくていい?そんなこと言ってません」(B) |
|
12月10日(水)授業 テスト返し |
期末試験の答案を返し,解説をしました。基本的なことをたくさん出したのだけど,復習が十分でなかった人はあまりよくない点数だったようです。伴性遺伝は,家系図をちゃんと書いて,X染色体の動きを確かめます。DNAは二重らせん構造です。眼,耳の構造はちゃんと覚えておきましょう。ニューロンにおける興奮の伝導は,活動電位により,シナプスでの伝達は,伝達物質によります。体のさまざまな調節を自動的に行なう中枢神経系は,大脳にはありません。ただし,大脳が他の脳に影響はします。 冬休みも宿題を出します。ちゃんと復習して,がんばって課題テストを受けましょう。 |
|
12月16日(火)授業 動物の行動 生得的な行動 |
さまざまな動物の行動はどのようなしくみで起るのか? 動物は生まれつき,誰に教えられたわけでなく,食べ物を探して食べたり,巣を作ったり,異性に求愛したり,生殖行動をしたり,生まれてきた子どもを育てたりできます。このような行動は,「生得的な行動」といわれます。このような行動は,親から子に受け継がれているのです。それでは,行動をつかさどる遺伝子と言うものが存在するのでしょうか。すでに学習したように遺伝子は単に物質(タンパク質)の設計図でしかありません。しかし,時と場合と組み合わせで,物質が作られることで特定の行動が起ったり起らなかったりすることがあることが分かってきました。 「私は高校時代,コンラッド,ローレンツの本を大変楽しく読みました。生物学にかかわるきっかけを作ってくれたと思っています。」(B) |
|
12月17日(水)実習 内臓,感覚器,脳の観察 メギスの解剖 |
メギスはその名の通り,からだの割には「目」の大きな魚でした。 右は,脊椎骨を折り曲げて引っ張ると出てくる,脊髄です。 |
|
12月17日(水)授業,演示 学習,知能行動 |
昨日いわゆる本能行動を学習しました。きょうはカイコガの交尾行動を観察しました。羽化してだいぶん経ったカイコガなので,フェロモンは余り出てなかったようです。先日観察した様子を,別のページに載せてあります。こちらをご覧下さい。 「交尾の最中に無理矢理引き離されて,それは余りにもあんまりや。かわいそうや!」(W君) |
|
12月18日(木)実習 学習 迷路を走ろう |
  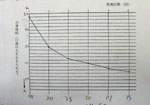 小さな迷路を鉛筆でたどりました。人によってさまざまな学習曲線が描けました。 また,鏡を見ながら図形をたどる作業は,みんなかなり苦しんでいたようです。 教材は大阪府の高校の先生がまとめた作業学習集を利用しています。大阪の先生方いつもありがとうございます。 |
 今日はメギスの解剖を行ないました。この時期,メギスは比較的安価に手に入ります。二人で1体を解剖しました。腹部の肉,えらぶたとえら,頭の肉を取り除くと(下写真)目の上に脳,その下に心臓,食道,肝臓,幽門すい,胃,腸が見えます。白く膨らんでいるのは浮き袋,脊椎骨にそって腎臓がありました。
今日はメギスの解剖を行ないました。この時期,メギスは比較的安価に手に入ります。二人で1体を解剖しました。腹部の肉,えらぶたとえら,頭の肉を取り除くと(下写真)目の上に脳,その下に心臓,食道,肝臓,幽門すい,胃,腸が見えます。白く膨らんでいるのは浮き袋,脊椎骨にそって腎臓がありました。
 頭部を拡大すると,脳の左半球が見えます,大きく見えますが,見えている部分は中脳です。魚の脳は,大脳が小さく,中脳が一番大きいのです。脳の下にある白いものが耳石です。眼を持ち上げると,視神経が見えました。心臓や肝臓,胃,幽門すいがよく見えます。
頭部を拡大すると,脳の左半球が見えます,大きく見えますが,見えている部分は中脳です。魚の脳は,大脳が小さく,中脳が一番大きいのです。脳の下にある白いものが耳石です。眼を持ち上げると,視神経が見えました。心臓や肝臓,胃,幽門すいがよく見えます。
 左は眼から取り出した水晶体です。水晶体は眼から取り出した時,同様に透明なガラス体とくっついて出てきます。ガラス体は柔らかいのですが,水晶体はとても硬いです。新聞の文字がとても大きく見えました。
左は眼から取り出した水晶体です。水晶体は眼から取り出した時,同様に透明なガラス体とくっついて出てきます。ガラス体は柔らかいのですが,水晶体はとても硬いです。新聞の文字がとても大きく見えました。