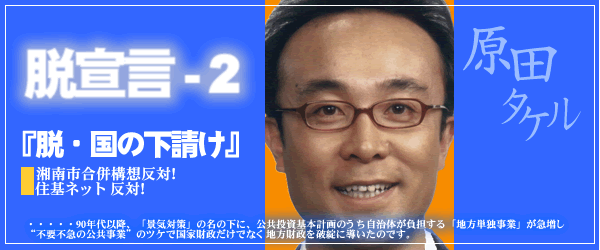
国民の税金は国に6、地方に4の割合で納められ、支出割合は逆に、国が4、地方行政で6に相当する仕事が担われています。
国は、地方への税配分を公平に調整する役割を利用して、地方行政を補助金等で縛り、県は国の下請け機関として、市町村を抑制してきました。
また、90年代以降、「景気対策」の名の下に、公共投資基本計画のうち自治体が負担する「地方単独事業」が急増し“不要不急の公共事業”のツケで国家財政だけでなく地方財政を破綻に導いたのです。
自らの責任を棚上げして、「地方の自立」をうたう国家官僚が「合併への強制」を進めています。「合併で財政強化になる」との喧伝はデマです。経常収支も赤字(下表)となり、合併特例債など借金での不要な公共事業が奨励され、ツケは拡大していくでしょう。
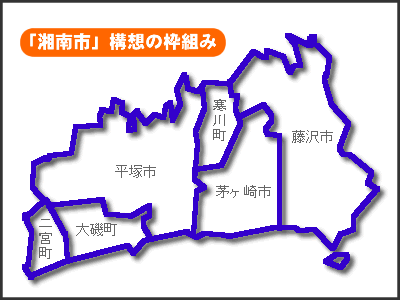
”湘南市合併”は誰のため?
1.「財政強化になる」のウソ
〜以下は、02年度9月議会での私の質問内容と答弁です(「議会報告」既報)〜
(原田)
市長は、「政令市を目指したい」また、「もっと強い財政力を目指したい」と言うが、二つの方向が両立する根拠がわからない。
民意の反映・・・・05年3月の合併特例債を国が認める期限を目標にすると言うが、民意の反映に「住民投票」をやる用意あるか。(茅ヶ崎市は、賛否が拮抗しているようならヤルと市長が表明している)また、仮に合併した場合、行政への市民参画、市民との協働という点でプラス、マイナスどう考えるか。住民投票の請求という点ではどうか。議員定数の削減(用語解説2)という点ではどうか。
(企画部長)
福祉や土木等の分野で県の事業が一部移譲され、行政事務の迅速化や、きめ細かな市民サービスの実施が可能に。財政面では、権限に見合うだけの財源が制度的に確保されることになります。
政令市になれば、区に大幅な権限と財源を付与し、・・・・市民との協働のまちづくりが可能。住民投票請求には有権者の50分の1以上の連署が必要で、一般論として、50分の1が人口規模によって同じで良いのかという指摘はあるが、法に基づくあり方が妥当と考える。議員定数は、議員の方々の活動により十分行われるものと考える。
(原田) 「全然ウソや!」・・・・
と、私の再質問をしたのですが、しゃべり口調では難があるので反論の根拠を、下記に整理しました。
<財政力は逆に低下する!>
「財政力指数」・・・・・・・標準的な行政活動での支出に対して、必要な財源に占める税収入の割合を示す一つの基準。この財政力指数が 1を超えると財政力が強いと言われ普通交付税が不交付となる。藤沢市は00年度、1.075で「全国的に見れば財政力が強い団体」(企画部長)。
現政令市(うち「湘南市」と同規模程度の自治体をピックアップ)01年度の数字は、仙台0.823 千葉0.951 川崎0.941 広島0.754 北九州0.618 これ以外の政令市でも1.0以上の自治体は存在しません。
「権限に見合う財源は来ない」・・・・・ 大阪市(政令市)の00年度の例です。
・政令市になる事で新たに増える業務に掛かる経費=753億円(うち国・府道管理に385億円!)
・新たに措置される税額=203億円(うち道路目的財源が大半)
・税制上の措置不足額=550億円!!川瀬憲子著「市町村合併と自治体の財政」参照
「自治体の人口規模による経済・不経済は」(吉村弘山口大教授調べによる。)
住民サービスの「質」は、必ずしも経済効率では測れませんが、効率のよい自治体の規模を、全国633市(東京23区除く)を対象に比較すると、
・財政力指数を最大にするという意味での最適都市規模は・・・・・・31万7千人
・人口当たり人件費を最小にするという意味の最適都市規模は・・・27〜29万人
・人口当たり歳出総額を最小にするという意味の最適都市規模は・・・22万人
<民意の反映は後退する!>
「市に任命される区役所長=区長。議員は高給お飾り?」
東京23区以外の政令市には区長公選制もなく、区議会議員もいません。そこに「大幅な権限と財源を付与」するそうです。
市議会議員は、現行法の下で、人口が増えるのに反比例して、人口当たりの議員数は減っていきます。定数の上限が決められ、藤沢市は現行40人(法での上限は46人。来年から38人に2人減)で人口千人当たりの議員数=0.105人。
3市3町の現在の議員数合計だと163人=0.17人が、合併で人口が96万人となると、法での上限64人となり、人口千人当たりの議員数=0.07人に。
以下は、定数の上限が60、64、68のランクとなる「湘南市」と規模が同程度の政令市の予算を目的別歳出で見た内訳、その他の指標です。
| 仙台 | 千葉 | 川崎 | 広島 | 北九州 | 藤沢 | |
| 議会費 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 土木費 | 23.7 | 23.5 | 25.1 | 26.6 | 29.9 | 17.22 |
| 投資的経費率 | 27.2 | 26.8 | 18.1 | 22.5 | 34.7 | 18.1 |
| 公債費比率 | 20.3 | 18.4 | 15.1 | 19.7 | 13.5 | 10.5 |
・・・・・これらの指標を見ても、議員数を削減しても、予算のチェックが疎かになり、放漫経営になっているのが政令市の実情です。定数減で、特定の組織の支援を受けた議員以外が、当選しづらくなっている事も要因だと思います。
「住民投票」
有権者の50分の1以上の連署をもって請求できる住民投票。藤沢市で求めるには、約6000人の署名で請求可能です。「湘南市」になると19200人分が必要になります。
大型ゴミ焼却場「エネルギーセンター」計画は、地元住民の反対運動(15000人署名の請願等)や「荏原ダイオキシン流出事件」でいったん凍結されていますが、「合併」後に解凍された場合、一部少数の意見として、圧殺される危険が高いと思います。元々、全市民のゴミ問題なのに、焼却場建設予定地にしか説明会を行わない市の姿勢、産業廃棄物まで、行政で処理しようと計画している国・県の下、みんなで考える問題が、一部住民だけの問題に矮小化されると、「大義無き公共事業」に歯止めを失います。
ちなみに、大震災の傷跡癒えぬ神戸市民は、98年、総事業費1兆円といわれる神戸空港建設を住民投票で問おうと、約30万(法定数2万3千人)の署名を集めながら、既成政党が多数を占める市議会に否決されたのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・等々、反論を試みましたが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
結局、市は、根拠を示さぬまま「スケールメリットがあると思い研究している」と終始し、また、前日の与党議員が質問した際に、市長が「合併について、市民のみなさんに理解を求めていきたいと思っている」と言っていたのに、私への答弁には、助役が市長を制して「湘南市研究会は、合併を前提としているわけではない」と食い違いが露呈。
住民投票等の民意の反映についても、市長が「法定合併協議会が大前提。」と問題発言をすると(※)、助役がすかさず「法定協議会について時期を申し上げる段階ではない」と曖昧にするのに躍起。
※=「法定合併協議会」とは合併の中身を詰めていく場で、それが設置されると事実上、合併は既成事実になる。という事を、市長は判っているのか???
・・・・・・・以上、4月27日投票の市議選で選ばれた新議会の多数決で、恐らく、その「法定合併協議会」
の設置の是非を決める事になるのです。
今度の選挙の結果が「合併」の行方を決めるといっても過言ではありません。
山本藤沢市長は、「合併は県や国からのお話では全くありません」と言いますが本当にそうでしょうか。
95年の「合併特例法改正」以降、合併を推進するためのお膳立てが次々と旧自治官僚によって進められました。
下記のように、主には、05年3月までを時限とした補助金等による誘導政策です。
また、旧自治官僚から都道府県に出された「指針」は「市町村の主体的な取り組みが必要である」とうたう一方、「市町村の合併パターンは都道府県が作成するものとする」と決めつけ、「新指針」では「市町村合併の推進はもはや避ける事のできない緊急の課題」と断じる上意下達のやり方です。
各省庁の官僚の出す「指針」「通達」の類は通知されるだけで、都道府県はそれを「命令」と解釈し、市町村に対して同様の「強制」が行われる仕組みで、中央官僚の意向が法制化を待たずに貫徹されているのです。