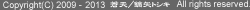神様、お願いっ!<2013梅雨だというのに花火大会小説>
「帆波ちゃん?」
不意に名前を呼ばれてゆっくりと振り返る。
「……浩一さん」
「お待たせ……って……どうかした?」
「え?」
距離を一気に縮めて、目の前に立った浩一さんの指がそっと私の頬に触れる。
「泣きそうに見えた」
「え?」
「大丈夫?」
泣きそう? いや、別に泣きそうなホドでは……え、泣きそう!?
そしてまた、大きな音とともに花火が上がる。
浩一さんは私を橋の手すりに掴まらせて、その隣に並んだ。
「……うん。やっぱり急いで来て良かった」
「……?」
「ちょっと……ね。寂しくなっちゃったっていうか、うん」
何? 浩一さんは何を言おうとしているんだろう。
首を傾げて横にいる浩一さんの方を見ると、浩一さんは花火を見上げたままでこう言った。
「なんで俺、一人でこんなの見てるんだろう、とかさ。そんな事、考えた事もなかったんだけどなぁ」
そのまま花火に視線を残したままで、浩一さんは話を続ける。
「きれいな花火も、一人で見てたってつまんないんだよ。一緒に見たい人がいるのに、なんで俺はここで一人なのよ……とかさ」
「浩一さん……」
「たったそれだけで寂しいとか。大概俺も情けない男だね」
その言葉に私は首を横に振った。情けない事ないよ。そんなの大切に思う人がいたら当たり前だと思うもの。だって私も……私も?
「あぁ」
「帆波ちゃん?」
あぁ、そうか。そういう事だったんだ。
「どうかした?」
浩一さんが心配そうにこっちを見るけど、私はちょっと照れくさくて浩一さんの方は見れそうにない。
だって私は今たぶん初めて知った。そうか。私は寂しくなっちゃってたんだ。
「帆波ちゃん?」
「うん……」
初めて自覚した寂しいっていう感覚。そうかそうか……いや、でもこういうのは何て言ったらいいのかな。私も同じです、かな。
そういえば私は寂しいなんて口では言っても、本当に寂しいと感じた事なんてなかったかもしれない。いや、ずっとそこから目を背けていたのかもしれないけれど……。
だって思い返したらそういう気持ちがいっぱいになる。あの時も、あの時も。私はたぶんずっと寂しかった、と思う。でもその時はそんな事を感じることすらなかった、はず。なかった、んだけどなぁ。
「帆波ちゃん? ホント、大丈夫?」
浩一さんがもう一度声をかけてくれたんだけど、私にはそれに答える言葉がわからない。わからないから……手すりに置かれた浩一さんの腕に手を添えた。
「私も……」
「ん?」
「2人で見た方が、花火、キレイだなって思います」
そう言ったら、浩一さんはちょっと驚いたような顔を一瞬した。でもその後すぐにくしゃっと笑って、ただ一言、そっか……と浩一さんは私の手を握ってくれた。あー、なんだろう。さっきまでのザワザワがおさまってく。すごくあったかで、穏やかな気持ちになってく。浩一さんといるとそんな風に思うことがよくあるのには気付いていた。そうか。私は安心できるんだな、この人と一緒にいると。
メイン会場の方から、演出のためのBGMであろう有名な映画音楽が聞こえてきて、大きな花火が一際大きな音を立てていくつもいくつも夜空に花を咲かせていく。辺りの景色を赤や緑、いろいろな色に照らし出す。
私と浩一さんは特に言葉を交わすでもなく、でも手を繋いだままでずっと空を見上げていたんだけど……不意に繋いだ手に力がこもって、何事かと私は浩一さんの方を見た。
「ねぇ、帆波ちゃん」
「はい?」
浩一さんはこっちを見ない。
「ずっと言いそびれてたことがあるんだけど……」
「言いそびれてたこと?」
「うん」
浩一さんは池の水面に映る花火を見つめたまま言葉を続けた。
「もう随分前から親父には言われてたんだ。でも俺自身どうしたいのかイマイチよくわかってなくて返事をしてなかったんだよ。それをさっき言われてさ……」
「はい。いや、えーっと……何の話?」
「うん……」
言葉を探してるみたいに、何か考え込んでる表情を見せられて、私もちょっと緊張。いったい何を言われるんだろう?
「親父の弟、まぁ俺の叔父さんだね。その人がさ、軽井沢の方で店やってるの、造り酒屋の直営みたいなさ、地酒っていうの? そんなの売ってる」
「観光地のお土産屋さん?」
「今はね、そんなカンジ。で、支店とか出すのはさ、さすがに人手的にも資金的にも無理だけど、通販とかでね、もうちょいいろんな層に……とか、そんなの考えてるらしいんだよね」
「まぁ、多いですよね。有名なんだけど入手経路がないとか……いいじゃないですか、そういうの」
私は正直に思ったままを言ったつもりだったんだけど、浩一さんはちょっと顔を曇らせ、俯きがちにつぶやいた。
「……あんまり、ヒトゴトみたいに言わないで」
え? え? 私、なんか悪いこと言いましたかね???
その答えはすぐに浩一さんがくれた。
「呼ばれてるんだよ、俺が。そういうの、引き受けてくれないかって」
「え?」
あぁ、そういう事か。でもまぁ、浩一さんなら大丈夫そうよね。
そう言おうとしたんだけど、何かが引っかかって言葉にはならなかった。浩一さんが私の方を向く。
「一緒に……来て欲しいんだよ。ゆっくり考えてとか、待つとか言ってたくせにアレだけど……俺、その話を受けようって思った時にね、一緒なら……帆波ちゃんと2人だったら頑張れるんじゃないかなって、そう思ったんだよ」
浩一さんの言葉が頭の中をぐるぐる回り始める。あぁ、それでヒトゴトみたいに言わないでって……あれ? でもそれってここを離れるっていうことだよね。それって……。
「弟さんの事もある。だから難しいのかなっとも思ったんだよ。思ったけど、俺もうこっから先、一人でってあんまり考えられないんだよ」
「浩一さん……」
「今日みたいな特別な時だけじゃない。例えば家でテレビ見てる時とか、そんな時だって……隣にいたらいいのにって思う、一緒ならもっといいのにって。何でもない時間をね、そういう時だってずっと、一緒にいたいって思うんだよ」
いつもみたいに穏やかに話しているけれど、繋いだ手はすごく冷たくって浩一さんがものすごく緊張しているのがわかる。
でも浩一さんの言葉を聞いて、あぁ、私ここから離れるんだって思った時からずっと、頭の中でいろんなものの整理整頓みたいなものが始まってるの。
浩一さんは私にいろんな初めての感情を気付かせてくれた。私にもこんな気持ちがあるんだなって、自分の中の扉がたくさん開くみたいにいろんな事がわかって……でも、なんだろう。このモヤモヤしたカンジ。ここを離れる?
「帆波ちゃん?」
「……うん」
どうしよう。言葉にならない。ただ、本当にここを離れてもいいのかなって、その思いばかりが頭を駆け巡ってる。正直に伝えても大丈夫なのかな。だいたい私はなんでこの場所にそんな拘っているわけ? なんで私は……。
「あー、望月さん。また会ったねー」
不意に名前を呼ばれて我に返る。え、誰?
「おい、やめろって……」
「あ、ごめ……彼氏さん、一緒だったね」
「北村君」
空気を読んだというか、さすがに申し訳なさそうに北村君が浩一さんに向かって頭を下げる。
「いやいや、気にしないで」
浩一さんはいつもの浩一さんに戻って笑顔で返事をしていたけれど、そんな態度とは裏腹に、繋がれた浩一さんの手に力がこもるのを感じた。
「えーっと……?」
そう言って困ったようにこっちを見た浩一さんに、私は高校の時の同級生達だと簡単に説明した。
「そっか。あー、どうも。はじめまして?」
そんな妙に疑問形な挨拶に、北村くんを始め皆が申し訳なさそうに頭を下げた。
「すんません……ほら、いくぞ」
ぎこちない挨拶も早々に、宮司がみんなに蹴りを入れて先を急げと促している。話しかけてきた北村君本人は、何か言いたげな顔で宮司を小突きつつ私の前を宮司と並んで通り過ぎた。
その擦れ違いざまだった。
「お前、大丈夫?」
雑踏にかき消されてしまいそうな、ほとんど聞こえないくらいの小さな声で宮司は私にそう一言だけ言った。何かと思って振り返ったんだけど、北村君に小突き返されながらも宮司は小さく手をあげて、そのままどんどん歩いて行ってしまった。
っつーかダイジョーブってなんだよ、宮司。大丈夫かっていったい何が大丈夫かって……、私のいったいどこらへんが……。まったくあいつはいつもいつも! なんなの!? 私が気が付かんようなそんな細かいコトばかりにまでいつもあいつは!
「帆波ちゃん」
背後から浩一さんが私を呼んだ。ゆっくりと振り返ると、浩一さんはすごく困ったような、何とも言えない笑みを浮かべてこっちを見ていた。
「ごっ、ごめんね、浩一さん。なんか……ホント、ごめんなさい」
「……なんで謝るの? 何を謝ってるの?」
浩一さんの顔がくしゃっと歪む。
そうだよね、私、何を今謝ってるんだろう。
大事な話をしてたのに、あいつらが割り込んできたから?
いや、それは私の謝ることじゃないよ。違う。
口をついて出てきた謝罪の言葉に自分自身でも戸惑ってしまった。私、何謝ってんの?
ほんの少しの沈黙が、ものすごく長く感じられてじりじりする。
遠くからまたアナウンスの声が聞こえてきて、歓声の波と共にまた夜空に大きな花が鮮やかに開く。
「今すぐに返事をくれっていうんじゃないよ。困らせたいわけじゃないんだ」
花火の方に目をやって、そのまま浩一さんはまた橋の手すりに手をかけた。
「うん。そうじゃないんだよ」
ドドンっと大きな音を立てて、一際大きな花火が上がる。
その灯りに照らされた浩一さんの顔は、なぜだか泣きそうに見えた。
「浩一さん?」
すぐ隣から声をかけると、浩一さんは花火を見上げたままで静かに口を開いた。
「言ってる事めちゃくちゃでごめんね。ゆっくり考えろとか言っといて、すぐに答え欲しいみたいな……俺、かっこ悪いね」
「そんな事は……」
「かっこつけたいんだよ。でも焦るっていうか……いや、早く結婚したいとかそういう焦りじゃないよ? 俺、男だしそういうのはないと思ってるんだけど、やっぱ……鬼門だな、あいつは」
「鬼門? 何の話ですか?」
その顔をのぞき込むように、私は橋の手すりの方に乗り出して訊いてみた。
浩一さんはさっき北村君達が消えて行った方をちらりと見やってからこっちを見て言った。
「自分がこんな独占欲の強いヤツだったとはねって、今さらのように驚いてるって事だよ」
目線でわかる。浩一さんはまた宮司の事を言ってるんだ。そんなに気になる? まぁ確かにね、その他大勢とは違うっちゃー違うけど。
「やだねー、嫉妬だよ嫉妬。ヤキモチ妬いてるだけだって自覚はあんだよ。って、それを本人に聞かせてどうすんだよ俺は」
「浩一さん。なんだかいっぱいいっぱい」
「そうだよー? 俺なんていつもいっぱいいっぱいよ。我ながら情けなくって嫌になってくるよ」
「そこまで言わなくったっていいのに」
「言いたくもなるの!」
なるの!ってそう言って、橋の手すりに突っ伏してしまった。
拗ねてる浩一さんは嫌いじゃない。かわいいとか言ったら怒られるかもしれないけど、何だか高いところから降りてきてくれたような、そういう気分になる。いや、もちろんいつも隣にいてくれてるんだけど…でもやっぱり大人だなって思う事の方が多いから。
「浩一さん、顔上げて?」
「……嫌だ。なんかかっこわりーのがじわじわきて恥ずかしくなって来た」
「そんな事ないでしょう」
「あるよー。あるでしょー」
「……じゃ、浩一さんはかっこいい面しか見せたくないような人間にプロポーズしたんですか?」
ちょっとイジワルな言い方をしたら、浩一さんはガバッと顔を上げてこっちを見た。真顔だ。
「そんなわけないじゃない!」
それを聞いて思わず噴出すと、浩一さんは困ったように笑って言った。
「こういうとこ見せられる人だからに決まってるでしょ?」
そう言って私を引き寄せる。
「それでもやっぱ、かっこつけたいんだよ。バカな男心ってコトにしといて」
遠くのアナウンスと共にBGMが一際大きくなる。どっと歓声が上がり、フィナーレの花火が盛大に打ちあがる。
降ってくる火薬の匂いと、連続で轟く大きな打ち上げ音。華やかに幾重にも咲き誇る大輪の花火に照らし出された私達の影が、一つになって足下に落ちる。
「大好きだよ、帆波ちゃん」
肩に置かれた手から、浩一さんの体温が伝わってくる。
だけど私はどうしてなんだか、自分の思いを伝えるピッタリの言葉がどうしても見つからない。
さっきからずっと何かが引っかかってて、素直に好きって答えられない。
「……うん」
頷くことしかできない私に何を思ったのか、一瞬だけ、肩に回した浩一さんの手に痛いくらいの力がこもった。
== The End. Thank You!! ==
創作の励みになります。
よろしかったら感想等お聞かせ下さい。
◆◇ランキング・バナー◇◆