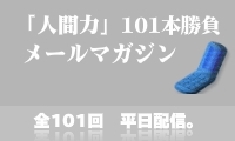Q.1
なぜ外務官僚は真紀子大臣よりムネヲのいうことを聞くのか。
A. 役所の世界の基本は、貸し借りです。なぜかというと、利害の衝突が起きた時に、事の是非の問題ではなく、貸し借りに変換してしまうからです。
理屈じゃないんです。
「江戸長崎」というのも霞ヶ関用語ですが、その場合は借りを返してもらう方が先決で、事の是非は問題ではない。
それもかなり複雑多岐にわたる貸し借りの体系ができていて、その中にいる本人たちも訳がわからなくなっています(「要請主義」というのも、自分たちの戦略的必要性より貸借関係を優先した防衛的発想です)。
取引が一回切りですまなくて、「泣いた」「泣かれた」がずっと連鎖していって、お互いがずぶずぶの身内になっていくという関係性です({ずぶずぶ}も最近はやりのタームです)。だからすぐに敵味方にわかれて派閥ができます。
ムネヲのような政治家は、その派閥の敵対関係と貸し借り関係の中で口利き介入をして、うまくのし上がっていくという点についての卓越したセンスを持っているわけです(それが本来の代議士に必要な能力であるとは、私は思っていません)。
癒着を深める中で、官僚は必ず特定政治家との関係を作っていきます。一流官庁の課長以上は、ほぼ全員、得意先の政治家が決まっているはず。できる奴ほど早いうちに、先輩の引きで新橋とか赤坂の政治家との席に引き出されるわけです。
同様に、関連業界も系列が決まっています。政財官のトライアングルには、ちゃんと色分けがあって、自民党○○派=○○省官僚派閥○○グループ=○○業界と、所管法人、外郭団体、所管企業の隅々に到るまでその癒着ネットワークのすそ野は広がっていて利権を構成しています。政治家はその集金ネットワークの中で、塀の中に落ちないようにバランスを取りながら歩いていくわけです。
そうすると、例えば厚生省で橋本龍太郎にかわいがられている官僚を飛ばすというわけにはいかないわけで、官僚が出世の階段を上るためにはだんだん椅子の数が少なくなるわけですから、その構造から無縁でいることはできない。外務省の場合はムネヲしかいなかったので、かえってバランス感覚を失ったんでしょうね。もし対抗勢力でムネヲと同じようなことをしている奴がいると、だれもムネヲを非難できなかったかも。だって他の役所でも程度差はあれ同じようなことをやっているわけですから。つまり彼は出過ぎたから刺されたということかもしれません。
大臣というのは、族でなければこのネットワークと無縁なので、省内では全く力がないわけです。だから外務官僚がムネヲのいうことを聞くのは当たり前ですよね。
ちなみに族議員がたくさん大臣になった時は「仕事師内閣」などと呼ばれましたが、いったいなんの仕事をしていたのかわかったものではありません。
だから、族議員の利権ネットワークが議院内閣制を形骸化させているということに事の本質があるわけです。
実はムネヲは、その構造の中では小者で、本当に悪い奴は他にいっぱいいるということなんですね。真紀子はそれに抵抗したから切られたわけです。どっちが正しいかは、考えるまでもありませんね。