![]() �r�c���S���g�b�v�y�[�W�ɖ߂�
�r�c���S���g�b�v�y�[�W�ɖ߂�
![]() �Ȃ��Ƃ����w�E���̃��j���[�y�[�W�ɖ߂�
�Ȃ��Ƃ����w�E���̃��j���[�y�[�W�ɖ߂�
| �r�c���S���@�Ȃ��Ƃ����w�E�����@ |
| �O�c�����Y��Ȃ̓��w |
| �@�@�������@�@�@�@�J�@ �@�@�@���Ƃ킷��� �@�@�@�@���R�̂����@ �@�@�@�����̝ꛊ�@�@�@ |
| �@�@�C�����@�@ ��̂ڂ��@ �@�@���̛{�Z�@�@�_�璹 �@�@�@ �@�t��҂� |
| �@�O�c�����Y�����@�@�@�����H�����@�@�������痪�� |
| �@���n�䕗�����@�@�@�@���w�ȕ��W�w���R�̂����x |
| ���w�E���́@���T�@�i�ҏW���j |
�@���ł��̂��p����Ă��镶���ȏ��̂Ɂu��̂ڂ�v������܂��B �@�w�q�포�w���́x��܊w�N�p�i�����ȁj�吳��N�i1913�N�j�܌���\�������s�Ɍf�ڂ���܂����B������܊w�N�p�ɂ́A�u�݂������v�u���������v�u���c�𑗂�v�u�O�ˏ��v�u�֓������v�u���t�c�̉�v�u�C�v�u�~�i�F�v�ȂǑS��\��Ȃ��f�ڂ���Ă��܂����B �@���w���T�ɂ��@�ߑ㏥�̏W���x(�r�N�^�[)�̉���ɁA�u���������̂̌��쒆�̌���v�Ə����Ă���̂͊ԈႢ�B�u��̂ڂ�v�́A�w�q�포�w���́x�吳��N���s�Ɍf�ڂ���܂����B�u���������́v�ł͂���܂���B �@ �@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���u��̂ڂ�v�̎��@�y��
 �@�y��Ȏ҂͒N���H�z �@�y��Ȏ҂͒N���H�z�@ ���c���ō��ꂽ�̂ŁA�쎌�E��ȕs�ڂƂ���Ă��܂����A�O�c�����Y���������y�w�Z�s�A�m�ȍ݊w���i�吳��N��\��̎��j�ɍ�Ȃ����Ƃ����Ă��܂��B�̋��A���m�����|�s�a�m�ӌ����ɂ́A�y���ƎO�Ԃ܂ł̉̎������܂ꂽ�̔肪���Ă��Ă��܂��B�i������N�\���ݒu�E�u���w�̗����|�@�O�c�����Y�v�p���t���b�g�ɂ��j�B�E�̎ʐ^�͍��m�����|�s�a�m�ӌ����́u��̂ڂ�v�̉̔�B �@���c��t�F�E�������q�ҁw���{�̏��́k���l�x(�u�k�Е���)�ɂ́A���̂悤�ɏ����Ă���܂��B �@�g�O�c�����Y�����y�w�Z�̓�N���̂Ƃ��Ɋ��߂��č�������̂Ƃ������Ƃ��A�O�c���g���T�g�E�E�n�`���[���Ɍ�������Ƃ�����A�����Y���S�l�͒��쌠����\������Ă݂����A�܂��w������̍�i�Ƃ������ƂŁA���쌠�̑ΏۊO�Ƃ������Ƃ������Ƃ����h 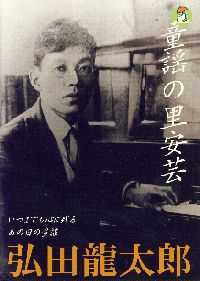 �@������͂��������B�ߓ��{�q�Ƃ����q���̍�i�u�R�q�m�{���v���쎌�҂ƔF�߂�ꂽ�̂ɁA�w��������Ƃ������R�ŋp�����ꂽ�Ƃ����͕̂ςł��B�O�c�����Y�̍�i�Ƃ�������I�؋����Ȃ������̂ł��傤�B �@������͂��������B�ߓ��{�q�Ƃ����q���̍�i�u�R�q�m�{���v���쎌�҂ƔF�߂�ꂽ�̂ɁA�w��������Ƃ������R�ŋp�����ꂽ�Ƃ����͕̂ςł��B�O�c�����Y�̍�i�Ƃ�������I�؋����Ȃ������̂ł��傤�B�@�y�̎��̈Ӗ��z �@ �E�u�O�̔g�v�����i�����j�Ԃ��̉������g�̂悤�Ɍ����邱�Ƃł��B�u�O�E���炩�v�́A�u���낱�v�����u�E���낱�v�Ƃ����ꂩ�炫�Ă��܂����A�����m�炸�ɉ̂��Ă���l�������悤�ł��B �@ �E�u�_�̔g�v�����_���g�̂悤�ɂȂ��Ă���̂��`�e������B �@ �E�u����v���O�Ɖ_�̒��ԂɌ������B �@ �E�u�k�v���݂���̒��ԁB5�E6�����ɔ����Ԃ��炭�B �@ �E�u�M�����ۂ܂�l�����āv���D�܂œۂݍ���ł��܂��悤�Ȍ��C�Ȃ悤���������āB �@ �E�u���ɓ����ʁv���������炢�̂��ƂŁA�т��Ƃ����Ȃ��B �@ �E�u�S���̑��o��Ȃv�������̌̎��A�u�����̑��o��Ɨ��ɉ�����v�Ƃ������̂ɂ�����B���h�ɐ��l���邱�Ƃ̚g(����)���B�u����v�Ƃ́A�����̉��͒����̎x���ɂ��鋬�J�̂��ƁB���ɋ}���Ȃ̂ŁA�����Ȃ��Ȃ������o�肫��Ȃ��B���̗����o�����������Ȃ�A���ɂȂ�Ƃ��������`������A�l�̗��g�o������ւ֖̊���u�o����v�Ƃ����悤�ɂȂ����Ɠ`�����Ă���B �@ �E�u�S���v����������̗���̑������B �@ �E�u�Ȃ�ʂׂ��v���Ȃ邾�낤�B �@ �E�u�킪�g�Ɏ����v�����̂悤�ɂȂ��Ăق����B �@ �E�u�j�q�Ɓv���j�̎q������Ƃ�т����āB �@�O�Ԃɂ́A�����́u��̑�o��v��g���ɁA���C�ŗ��h�ɐ������Ăق����Ƃ������b�Z�[�W�����߂��Ă��܂��B �@ �y�̂����ɂ��āz �@�Ȃ̓w�����B�l���߂��l�̃t���[�Y�ł܂Ƃ܂��Ă��܂��Ba�i4�j a�L�i4�jB�i8�j�BB�������^�ɂȂ����`���ł��B�Z�����K(�V�������j�B �@ �u�^�b�J�@�^�b�J�v�̃��Y���ŁA���C�Ȓj�̎q���]����̂ɂȂ��Ă��܂��B �@�u�����Ɂv�́u���[�����v�ƁA�u��̂ڂ�v�́u���[�����v�����́A�u�^���@�^�^�v�̓������Y���ł��B�u�^���@�^�b�J�v�ɂȂ�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��ĉ̂��܂��傤�B �@�u�����v�̏��́A�͋����̂��܂��B���̉̂ň�Ԗ��͓I�ȕ����ł��B �@�u�k�����钩���ɁA�v�̓w�����̕��s���ł����Z���ɓ]�����Ă��܂��B���̕��������邱�ƂŁu�����j����A�v�����X�Ɛ����Ă��܂��B���{�l�́A���̂悤�ȋȂ���D���ł��B �@ �y���ȏ��ł̈����z �@ �E�w�q�포�w���́x��܊w�N�p(������)�吳��N(1913�N)�܌���\�������s�Ɍf�ڂ���܂����B�^�C�g���́u��̂ڂ�v�B��Ԃ���O�Ԃ܂Ōf�ځB �@ �E�w�V���@�q�포�w���́x��܊w�N�p(������)���a���N�\�\�����s�ɂ��f�ڂ���܂����B��Ԃ̉̎��́u�U��Ӂv�ɂȂ��Ă��܂��B �@ �E�w�����ȉ��y�@�O�x�����w�Z�|�\�ȉ��y��܊w�N�p(������)���a�\���N�\�O�\������s(���a�\���N�ꌎ�Z�������Ȍ�����)�ɂ͌f�ڂ���Ă��܂���B �@ (��)�w�����ȉ��y��x�����w�Z�����ȑ�O�w�N�p(������)���a�\���N��\�l�����s(���a�\���N�O����������Ȍ�����)�Ɍf�ڂ́u��̂ڂ�v�͈Ⴄ�Ȃł��B �@ �E�w�ܔN���̉��y�x(������)���a��\��N�Z���ܓ����s(���a��\��N�܌���\����������)�ł́A�u�����̂ڂ�v�̃^�C�g���ň�ԂƎO�Ԃ��f�ڂ���܂����B��Ԃ��폜���ꂽ���R�͕s���B �@�����H�͕ҁw���{���w���̑S�W�x(�h���~�y���o��)�̋L�ځA�g���u�l�N���̉��y�v�ł͍Ăэ̗p����܂����B�h�͊ԈႢ�B�u�ܔN���̉��y�v���������B�u�l�N���̉��y�v�ɂ͌f�ڂ���Ă��܂���B���̖{�ɂ́A�����̎�����F������܂��B �@��2006�N5�����s�̗���R�����Z���E�ҁw���{�̏��́y����Łz�x(���y�V�F��)�y�ȉ���́g���a22�N�ł̋��ȏ��Œ����������h�͊ԈႢ�B���a22�N�ł̋��ȏ��ł����͏��o�Ɠ����w�����̂܂܂ł��B���̉̂́A�����蒲��������ƁA�u�����j����v�̕����ŁA����グ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B 1997�N6�����s�̗���R�����Z���E�ҁw���T�s�A�m���t���ɂ����{�̏��́x(���y�V�F��)�ɂ́A�g���a22�N�ł̋��ȏ��Œ����������h�̋L�ڂ͂Ȃ������̂ɁA�y����Łz�ŊԈ�������M���������Ƃɂ��A�c�O�Ȃ��ƂɁy����Łz�łȂ��Ȃ��Ă��܂��܂����B����R���̖{�ɂ��P���Ȏ�����F�������̂ł��B �@ �E���a�O�\�O�N�ɋ��ʋ��ނ��J�݂����܊w�N�p�Ƃ��āu�����̂ڂ�v�u�C�v�u�~�������v���I��܂����B���a�l�\�O�N�������B �@�@�@�@�@�@�����a35�N12��25�����s�w���w���̉��y5�x(���y�V�F��)�f�ڂ́u�����̂ڂ�v�B �@�@�@�@�@�@�@�@��Ԃ��폜����A�O�Ԃ���ԂƂ��Čf�ڂ���Ă���B
�@ �E�������A���a�\��N�̕����Ȃ̎w���v�̉����ɂ��u�����ނ�v�u���v�u��v�u���Ձv�u���E�v�u���̒b�艮�v�u�C�v�u���͊C�̎q�v�Ƌ��ɁA���ʋ��ނ���폜����܂����B�̎��ɁA�u�O�̔g�v�u���ɓ����ʁv�ȂǏ��w���ɂ́A����Ȃ��Ƃ��g���Ă������߂ł��B�܂��A���̋Ȃ́A�܌��̐ߋ�̓��ɂ����̂����Ƃ��Ȃ��ƌ������R������܂����B �@ �E�������N����́A�u�����ނ�v�u���͊C�̎q�v�Ƌ��ɍĂы��ʋ��ނƂȂ�܂����B �@ �E������\��N�\�����s�w�V�ҁ@�V�������y5�x(��������)�ɂ́u�����̂ڂ�v�̃^�C�g���ŁA��Ԃ���O�Ԃ܂ł��f�ڂ���Ă��܂��B�֒����B �w���y�̂��������5�x(����o��)�A�w���w���̉��y5�x(����|�p��)�������B �@�y���̑��̌�̂ڂ�@�T�@��l�C�������u��̂ڂ�v��z �@ �@����قlĵ��l�C�������̂ɁA���łɈ�ʓI�ɂ͉̂��Ă��Ȃ��u��̂ڂ�v�̉̂�����܂��B �@�w�����ȉ��y��x�����w�Z�����ȑ�O�w�N�p(������)���a�\���N��\�l�����s(���a�\���N�O����������Ȍ�����)�Ɍf�ڂ���܂����B�^�C�g���́u��̂ڂ�v�B�O�Ԃ܂ł���܂����B �@�l���߂��l�̃t���[�Y�ň�ɂ܂Ƃ܂��Ă��܂��B�n�����A�l�������Ǝl���x�������̂͂����肵�����Y���ɂȂ��Ă��܂��B�g���L���̎���2�Ə����Ă���͎̂l���̓q�̂��Ƃł��B �@�@�@�@�@�@�@�@��̂ڂ�@�쎌�s�� �@�@�@�@�@��ȁ@��㕐�m �@�@�@�@��A�������܂̂ڂ�A �@�@�@�@�@�@�������݂ǂ�B �@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�܂��Ђ����悮�A �@�@�@�@�@�@�@�@�Ђ��Ђ����悮�B �@�@�@�@��A�̂ڂ�𗧂ĂāA �@�@�@�@�@�@�݂�Ȃ����͂ӁB �@�@�@ �@�@�@�@�@�悢�q�ɂȂ���A �@�@�@�@�@ �@�@�@���ق����Ȃ���B �@�@�@�@�O�A�̂ڂ�𗧂ĂāA �@�@�@�@�@�@���Ƃ��̎q�ǂ��A �@�@�@�@�@ �@�@�@���ق����Ȃ��āA �@�@�@�@�@�@�@ �@�ɂ��ۂB �@�y�O�Ԃ͏Ȃ��ĉ̂��z �@���ꂽ�����͑��풆�ŁA���̋Ȃ̃e�[�}�ł���O�Ԃ́A�q���������܂��A�����S��{�����e�ł����B  �@���̕����Ȃ̋�����j�ɂ��������A���݂͎O�Ԃ��Ȃ��ĉ̂��܂��B�e�[�}���Ȃ����̂ŁA��̂ڂ�̎����̂������a�ȉ̂ɂȂ�܂����B �@���̕����Ȃ̋�����j�ɂ��������A���݂͎O�Ԃ��Ȃ��ĉ̂��܂��B�e�[�}���Ȃ����̂ŁA��̂ڂ�̎����̂������a�ȉ̂ɂȂ�܂����B�@��Ԃ̉̎��́u�܂��Ёv�́A������B��̂ڂ�̒��ň�ԑ傫����ł��B�u�Ђ����v�́A�Ԃ��F�̌�ł��B��Ԃ̉̎��́u�悢�q�ɂȂ���A���ق����Ȃ���B�v�̕����́A���݂������������ĉ̂��܂��B�݂�Ȃ̊肢������ł��B �@ �y�u�̂ڂ�v�ɂ��āz �@ ���̂悤�ɕz�Ȃǂ��Ƃɕt���č����������镨���u�̂ڂ�v�Ƃ����܂��B�u�����̂ڂ�v�́A�j�q�����C�Ɉ�悤�ɂƊ���ė��Ă�ꂽ�u�̂ڂ�v�ł��B�������S�N���炢�O�ɁA�u�����̂ڂ�v�𗧂Ă�K�킵���n�܂����ƌ����Ă��܂��B�u�����̂ڂ�v�ƈꏏ�ɗ��Ă�ꂽ�u����E�̂ڂ���v�ɂ͗E�܂������ҊG��A��A�j�q�̖��O��������Ă����i���j�B �@ �@ �y���ȏ��ł̈����z �@ �E�莝���̋��t�p�̓�N���p���ȏ��f��(���o�ŎЁE���s�N�����E�s��������)�́u�����̂ڂ�v�B�g���L���̎���2�Ə����Ă���̂ŁA��シ���̋��ȏ��̂悤�ł��B�O�Ԃ͍폜����A��ԁA��Ԃ������f�ڂ���Ă��܂��B�n�����Ȃ̂ŁA�\�\�h�h�V���\�ƊK���ʼn̂��悤�ɂȂ��Ă��܂��B�؋Ղ�n�[���j�J�ł����t���Ċy���Ȃł��B��㕐�m��ȂƏ����Ă���B�}�G�ɂ́A�u�傫�����������v�Ɓu�������Ԃ������v�̓�C���`����Ă��܂��B �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����t�p�̓�N���p���ȏ��f�ڂ́u�����̂ڂ�v�B
�@ �E���a�O�\�O�N�\�\�ܓ����s�w�����ł��傤���������̂���2�x(���y�V�F��)�f�ڂ́u�����̂ڂ�v�ɂ́A�l���̓q�̐����������Ă���܂��B��ԁA��Ԃ������f�ځB�}�G�́u�I�����W�̂����v�Ɓu�O���[���̂����v�̓�C���`����Ă��܂��B����ł́A�u�܂����v�Ɓu�Ђ����v�̐����ɂȂ��Ă��܂���B �@ ���u��㕐�m�@�쎌�A�����ȏ��́v�Ə����Ă���܂��B��㕐�m�͍�ȉƂȂ̂ŁA�u��㕐�m�@��ȁv�̊ԈႢ�ł��B���t�ɂ͕ҏW�Q�^�@�����Y�p��w�u�t�@��㕐�m�̖��O������܂��B�����ŊԈႢ�ɋC�����Ȃ������̂ł��傤��? �@�@ �@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����a�O�\�O�N���s�f�ڂ́u�����̂ڂ�v
�@ �E���a�O�\�ܔN�\��\�ܓ����s�w�������傤���������̂���2�x(���y�V�F��)�f�ڂ́u�����̂ڂ�v�ɂ́A�l�������Ǝl���x���̐����������Ă���܂��B��ԁA��Ԃ������f�ځB�쎌�ҕs���@��㕐�m��ȂƐ����������Ă���܂��B�ďC�E�ҏW�Ɉ�㕐�m�̖��O������܂���B�폜����Ă��܂��B�}�G�ɂ́A�u�傫���Ԃ������v�Ɓu���������������v�̓�C���`����Ă��܂��B�u�Ԃ������v�̕����傫���`����Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����a35�N���s�f�ڂ́u�����̂ڂ�v
�@�y���̑��̌�̂ڂ�U�@��u���v��z �@�@�w�V���@�������w���́x���w�N�p�@�j�q�p(������)���a�\�N�O���O�\������s�ɂ́u���v�̃^�C�g���Ōf�ڂ���Ă��܂��B �@����f���Ēj�q���j�������̂ڂ�̌��C�Ȃ悤�����̂��Ă��܂��B���͉̂��Ă��܂���B �@�@�@�@ ���w�V���@�������w���́x���t���@ �@�@�@�@�@���w�N�p(������)���a�\�N�l���\�ܓ����s�B�j�q�p�Ə��q�p�̋Ȃ��f�ڂ���Ă���B �@�@�@�@�@����͋��t�p���B
�@�@�@�@�@ �@�@�y���̑��̌�̂ڂ�V�@��T�g�E�n�`���[��u�����̂ڂ�v��z
�@�T�g�E�n�`���[�炵�������̎��́u�����̂ڂ�v�̉̂ł��B��N���̋��ȏ��Ɍf�ڂ���̂�ꂽ�悤�ł� �@(���o�ŎЁE�o�ŔN�����E�s��������)�B �@�@�@�@�@�@�@�����̂ڂ� �@�쎌�@�T�g�E�n�`���[�@��ȁ@���`ᨈ� �@�@�@�@��A�����Ƃ͂ꂽ�@��������� �@�@�@�@�@�@���悢�ł��܂��@�����̂ڂ� �@�@�@�@ �@�@�߂�������@����ɂ��� �@�@�@�@��@�����邢�����́@���悩���� �@�@�@�@ �@�@���悢�ł��܂��@�����̂ڂ� �@�@�@�@�@�@�����߂���˂���@����ɂ��� �@�y���̑��̌�̂ڂ�W�@�@��і��g��́u��̂ڂ�v��z �@�@�w���E���ّS�W17���{���̏W�x�{��������(�t�H��)���a�ܔN�\�ꌎ�\�ܓ����s�Ɍf�ڂ́u��̂ڂ�v�B��Ȃ͖{�������B�������ҏW����{�̏o�łɂ�����A�і��g�ɍ쎌���˗������̂ł��傤�B �@�u�����悭�A�����ɉS�͂ꂽ���A���ɏ��w�Z��O�N�̒j�q�����ށv�Ƃ����R�����g���t���Ă��܂��B�O�Ԃ́A����f�����̎��ɂȂ��Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@��̂ڂ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�쎌�@�і��g�@��ȁ@�{������ �@�@�@��A ���킳�킳�킳���̂ڂ� �@�@�@�@�@�@���ɐ�����ĊƂ̂��� �@�@�@�@ �@ �����̑��܌����� �@�@�@�@�@�@�������j���ł� �@�@�@��A ���邭�邭�邭�镗�� �@�@�@�@�@ �ܐF�ɂȂт������� �@�@�@�@�@�@���������Ă钩���� �@�@ �@�@�@ �܂Ă�܂Ă鐁����Ă� �@�@�@�O�A �܌����̂ڂ� �@�@�@�@�@�@�l�͓��{�̒j�̎q �@�@�@�@�@�@���ɂ̂ڂ邼���� �@�@�@�@�@�@���Ă�댩�Ă���̂ڂ�
�@����̗v���ɉ����āu�ӂ��̎R�v���l�A��R�́u��̂ڂ�v�̉̂�����A�q���������̂��܂����B �@�̂��A�������{����邽�߂ɑ傫�ȗ͂ƂȂ�܂����B �y���҂����p�y�ђ��쌠�ɂ��Ă��肢�z�@�@ �ᒘ�ҁ@�r�c���S���� |
�@�y���\���z �@���́A�G���w�Ԃ����x(�Ԃ����Ёj�吳���N�i1918�N�j�㌎���Ɍf�ڂ���܂����B�q�ǂ��̐���������ɂ���p�����琶�܂ꂽ���H���w�̑�\��ł��B �@�y���̂���̔��H�́z �@�吳���N�O���ɍȁE�͎q(���₱)�̕������̗×{�����˂ď��c���ɗ������H�Ə͎q�́A��K�̕l�ɂ���{���قɉ������āA �l���Ɍ�Ԕ�(���E���c���s�쒬)�ɕ�炵���B���Ɂu���Ԕ��v�ƌ����B�C���߂��B�Z���͑��B���c���\���l���ڋ�S�\�B �@�y���̉����z �@���o�̎��́u�g��(�ׂɂ�)�̂�����(����)�v�ł����B �k�����H�̓��w�W�w�g���{�̊�ʁx(�A���X)�吳���N���s�Ɏ��^�̍ہA �u������(����)�v�ł͌��t�̋����������̂Łu�ؗ�(����)�v�ɂ��܂����B���킢�����̎q�̃C���[�W�ɂ҂�����ł��B �u�g���v�́A���ʂ̍g�F�̕R�B�u�ؗ��v�Ɓu���ʁv�͓����B�u�ؗ�(����)�v�́A���炱��A�Ƃ������ɔh�������c����B �@ �@ �y���ނ̎��z �@�ȏ�ł킩��悤�ɁA���G���u�Ԃ����v�吳���N�㌎�����Ƃ��āw�J�x�̎��������ꍇ�́A�u�g���̂����ʂ������ꂽ�B�v�̎����f�ڂ���̂��������B ���̂��Ă���̂́A�k�����H�́����w�W�w�g���{�̊�ʁx(�A���X)�吳���N���s���Ɏ��^�́u�g���̖ؗ��������ꂽ�B�v�ɉ��삳�ꂽ���ł��B
�@�y��ȔN�����z �@�u�吳�\�N�����ܓ��ɍO�c�����Y����ȁv���͓��I�@�������q�E�����w���{���w�W�x(���y�V�F��)��㔪�Z�N���s�ɂ��B �@ ���w���H�S���w�W�X�x������(��g���X)����O�N���s�ɂ́A�g�吳5(?)�N8��5����ȁB�w�O�c�����Y��i�W�P�x�Ɏ��^�k�w��i�W�x�ɂ͑吳5�N�ƂȂ��Ă��邪�A���H�́u�J�v�́u�Ԃ����v�吳7�N9���������o�l�h�Ə����Ă���A�吳5�N���^���Ă���B �@ �����c�\�Y�E�ҁw���H�����̏W�x(��g����)����ܔN���s�ł��A�g�O�c�����Y�̋Ȃ́A�w�O�c�����Y��i�W�P�x�ɂ́u�吳�ܔN�����ܓ���v�ƂȂ��Ă��邪�A���H�̓��w�͑吳���N�㌎���ɍڂ��Ă���̂�����A��ȁu�吳�ܔN�����ܓ��v�Ƃ����̂͏����ς��B�h�ƁA�吳�ܔN��Ȃ��^���Ă���B �@���������A��ȔN�������A���̔��\�̓�N���O�Ƃ����̂́A���������B����ɁA�̎��́u�ؗ�(����)�v�ō�Ȃ����̂ŁA��Ȃ͎����������Ď��^�����w�g���{�̊�ʁx�吳���N���s�ȍ~�łȂ��Ƃ��������B���������āu�吳�ܔN�����ܓ���ȁv�͊ԈႢ�B���̊ԈႢ�́A���łɑ����̏o�ŕ��Ŏg���Ă��܂��Ă��܂��B �@ �����|�s����ψ���U�w�K�ہE�̋������w�O�c�����Y�ӂ闢�̐S���������x�ł́u�吳�ܔN�����ܓ���ȁv�A�V�����w���w�̗��E���|�@�O�c�����Y�x�ł́u�吳���N�����ܓ���ȁv�ƕύX�ɂȂ��Ă���B �@�܂��A�������͑O�L�́u�吳�ܔN�v�����̂܂ܐM�p���Ďg�����B�������A1995�N�P�O���ɍĔł��ꂽ�w�O�c�����Y��i�W�P�x������Ɓu�吳�V�N�W���T���v�ɂȂ��Ă���̂ŁA�V�����ł́u�吳���N�v�ɕύX�����̂ł��傤�B �@ ���O�c�����Y�̑��̍�i�ɂ��Ă��A���m�ȍ�ȔN�����ł͂Ȃ��A�w�������x�����N�����L�������̂Ȃǂ�����A�w�O�c�����Y��i�W�x��S�ʓI�ɐM�p���邱�Ƃ͓���ƌ��킴��Ȃ��Ǝv���܂�(��������̌����҂̕ʕ{���Y����̏���2011�N3��14��)�B
�@�y�̎��Ɖ̏��̍l�@�z �@������A�Â��ɍ~�葱���J�̗l�q���ڂɕ��Ԃ悤�ȗD�ꂽ��i�ł��B�قڎ����܉��A�܂��͔����܉��̒�^���ɂ܂Ƃ߂Ă��邽�߁A�Ȃ��t���₷���Ȃ��Ă��܂��B���c�O�⍲�X�����铙�A��������̍�ȉƂ��Ȃ�t���܂������A�ł��悭�̂��Ă����̂��A�O�c�����Y�̂��̋Ȃł��B �@���O�c�����Y�̊y���� �@�J�̓��̎₵���ɂ҂�����ȃn�Z���̋Ȃł��B�߂̑O�t�̌シ���̂��o���܂��B���킢�炵���C���ʼn̂��܂��傤�B���܂�߂������ɈÂ��Ȃ�Ȃ��悤�ɉ̂��܂��B ��Ԃ́u�s�������v�́u���������v�Ɖ̂��܂��B����́A���w�̈�ʓI�ȉ̂����ł����A�y���̒��ɂ́A�u���������v�ƌ���Ĉ������A�����̂��邱�Ƃ�����܂��B�������A�Ȃ̒��ň�ԍ��������u���������v�Ɖ̂��ɂ͖���������܂��B�܂��A�u���������v�ł́A�u���������v�u���������v�u���������v�ȂǑ��̈Ӗ��ɂƂ�ꂩ�˂܂���B�O�Ԃ́u�₵����v�́A�u����������v�Ɖ̂��܂��B �@�s�A�m���t�̒ቹ���͉J�̗����郊�Y���ł��B���܂ł������܂��B��t�A�s�A�m���t�̏I���ɂ����Ă���calando(�J�����h)�́A����x���A�キ���t����Ӗ��ł��B�Ō�̓n�����̎�a���i�h�~�\�h�j�Ŗ��邭�I���܂��B�J����݂܂����B�E�E�E�E�O�c�����Y�́A���̂悤�Ɏ������߂��č�Ȃ��܂����B �@�e���r���ςĂ���ƁA���鉹�勳���́u�J���~���Ă��ĊO�ŗV�ׂȂ��Ă������肵�Ă���悤�ɁA�Â��̂��Ă��������B���܂ł��A���܂ł��J�͑����܂���B�͂��Â��A�Â��A�����ł��Â��I�v�Ǝw���B�����������߂̂ЂƂ����܂��B �@�����H�̎��� �@���H�̎��ɂ��Ă͐�{�O�Y�̉��߂��A�Q�l�ɂȂ�B �@ �g���H�̓��w�́A���Ƃ��ēǂ�ł��L���Ȗ��킢������B�u�J�v�Ƃ����u�A�v�������C�ɂȂ��Ă��āA�J�Ԃ���邱�Ƃō~�葱���J�̗l�q���悭����킵�Ă���B�u�J���ӂ�܂��v�́u�܂��v�Ɓu�J���ӂ�v�́u�ӂ�v�̎g�������ł����ʓI�ŁA��J�Ƃ������J�̐Â������`����Ă���B�J�̂��߂ɊO�ɏo���Ȃ��q���͎₵�����̂��낤���A����ł��A���̏��̎q�́A��㎆��܂�����A�l�`�ƗV��A�J�̓��Ȃ�ł͂̂Ђ�����Ƃ����V�т��y����ł���B���傤�ǁA�q������̔��H�����͂̐��Ƃ̑��̂Ȃ��ŗV�悤�ɁB�吳�\�l�N�́u�J�ӂ�v�ŁA��e���ւ̖ڎP�������Č}���ɗ��Ă��ꂽ�̂ł��ꂵ���Ȃ��ĉJ�̂Ȃ����u�s�b�`�s�b�`�@�`���b�v�`���b�v�@�������������v�ƌ��C�ɕ����j�̎q�ƑΏƓI�ł���B���H�͎q���̐ÂƓ��̓�̖ʂ��킩���Ă����Ƃ����邾�낤�B �@ ��O�A�ŁA���������C�ɊO�̐��E���J����W�J���݂��ƁB��㎆��܂��Ă������̎q���O�̏�賎q�̚e�����ɋC�����A�u��賎q��������A�₵����v�Ɗ���ړ�����B�J���A���̎q�Ə�賎q�����т��Ă���B�����ȃA�j�~�Y���̐��E�B �@ �����čĂсA�����ɖ߂�A�l�`�V�т��I���悤�Ƃ��鏗�̎q���Ƃ炦��B�l�`��Q�������q���͂₪�Ď������Q����̂��낤�B�Ō�A���傤�ǃJ���������ړ����Ă䂭�悤�ɁA���_�͎q���𗣂�A������O�ւ��L�����Ă䂭�B�����ł́u�J���~��܂��B�J���ӂ�B�v�́A�����q���̉Ƃɗ����Ă���J�ł͂Ȃ��A����L������������A����ΉF���ƂȂ����Ă䂭�J�ɂȂ��Ă���B�݂��ƂȎ��Ƃ���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��h�i��{�O�Y�w���H�]�i�x�V���ق��B�Ԏ��͒r�c���S���ɂ��j�B �@ ���́u���ߖ@���g�������v�́A���H�́w���̓��x�ł�������B �@ ���J�̓��ɂ͏�賎q�͚e���Ȃ��� �@ 2014�N�A���c�R�ɉ͒Í����炢�����{�A�����̂悤�ɃL�W�������B�u�P���P���v�ƌ�a����̐��H�ނ����̓c��ڂő傫�Ȑ��Śe���̂ŁA�����u���������v�Ɣ�������B���A�Z���O����u�P���P���v�u���������v�呛�����B���̓��A���͂�����߂��悤�ŁA�e���Ȃ��Ȃ����B �@�O����\����͐���āA�L�W�́u�P���P���v�ƌ��C�ɚe�����B�����͒�����J���~�����B�J�͈�����~�葱���A�O������B�J���~���Ă���Ԃ͚e���Ȃ������L�W���A�J��������̂�҂��Ă������̂悤�ɚe���������B�[���܂Śe���Ă����B �y�u�₵����v�ɂ��āz�@ �@�w�J�x�ł́A�u���т�����v�Ə����Ă���܂�����A���̂悤�ɉ̂��܂��B �@�ޗǎ���̉̏W�E���t�W�ɂ́u���Ԃ��v�Ƃ������t���o�Ă��܂��B���ꂪ��������Ɂu���т����v�ƂȂ�A����ɁA�u���݂����v�ƕω����܂����B �@�o�s�ƃ}�s�̉��͓���ւ��₷������������܂��B�u���E���ނ�v���̂́u���Ԃ�v�ł����B�u�ڂ��Ԃ�v�́u�ނ�v�Ƃ������܂��B �@�]�ˎ���ɂ́u���т��v�u���݂��v�́A�ǂ�����g���Ă��܂����B�����u���т����v�u���݂����v�����Ƃ��g���܂����A���j�̌Â��u���т�(��)�v���A�ǂ��炩�Ƃ����ƕW���Ƃ���Ă��܂��B �@���̕ω��ɂ��A��ʂ�ɕ����ꂽ�������Ȃ̂ŁA���Ƃ��ƈӖ��̈Ⴂ�͂���܂���B �@ (��)�ȏ�́A2010�N10��15���A�ǔ��V���f�ځw�Ȃ��Ȃɓ��{��x�p��ψ���E�֍�������Q�l�ɂ��܂����B �@�y��̕��͂����z �@�Ⴂ�����𒆐S�ɑ�l�C�̐�Y�ǎ}�E���u����v�V���[�Y�B�w����Ɠ��w���̂����x(�����)�����\���N�O�����s�E�y�ȉ���@���ːT��Y�B��Ȗڂ́w�J�x�B����`����s�ڂ̕��͂́A����ǂ�ł��ւ�ł��B�u�͕̂����̉��܂������ɔ�u���A�������̓��w�����c�����k�����H�̍�i�ʼnJ�ƌ����E�E�E�w�A���t���x�����܂�ɂ��L���v�B����́A���������B�₢���킹�܂������A�o�ŎЂ���͕Ԏ������������܂���ł���(�����\���N�l���O��)�B �@������\�N���������A�v���[���g�p�ɒ����ŁA�܂����̖{���܂����B����͕����\���N�O����\�� ��O�����s�ŁA�u�͕̂����̉��܂������ɔ�u���A�v�͏Ȃ���Ă��܂����B�Ԏ����������������c�O�ł��B�����ł�m��Ȃ���A��̕��͂̂܂܌��p����Ă��܂��܂��B�u����v�ւ̃t�@�����^�[�́A��ɂ��Ă������������B�S��a�܂��Ă����u����v�́A�݂�Ȃ���D���B
�@�y�܂����c�O����ȁz�@ �@���݂܂ŁA�O�c�����Y��Ȃ́u�J�v���̂��p����Ă��܂����A �ŏ��ɔ��H�̎��ɋȂ�t�����̂͐��c�O�ł����B �@ �E�G���w�Ԃ����x(�Ԃ�����)�吳���N�Z�����Ɂ@(�u�Ԃ����v�ȕ����̓�)�@�Ƃ��Ĕ��\�B �@�@�@�@����؎O�d�g�劲�w�Ԃ����x(�Ԃ�����)�吳���N�Z�����@ �\���G�u����ڂ�ʁv�����ǗY
�@�@�@�@���J�@(�u�Ԃ����v�ȕ����̓�)�@ �̎��́u�g���̂����ʂ������ꂽ�B�v�ƂȂ��Ă��܂��B �@�@
�@�@ ���J�@(�u�Ԃ����v�ȕ����̓�)�@ �y���́u�x�j���m�@�I�Q�^���@���K�L���@�^�v�ƂȂ��Ă��܂��B �@�@�@ �@�@�y�w�Ԃ�����揁x(�Ԃ�����)���W�Ɏ��^�z �@
�@�y���R�[�h���z �@�ȉ��́A�k�C���ݏZ�̃��R�[�h�R���N�^�[�k�����v���L�B �@�ᐬ�c�O��Ȃ́u�J�v�� �@ �@ �吳9�N(1920�N)�����̓�揃��R�[�h��ꍆ�B �@�E�j�b�|�m�z��3978�u���Ȃ��v�A3979�u�J�v�u�肷�肷���肷�v�B �@�̂͐Ԃ����Џ������̉����^�s�A�m�͐��c�O�^�艿1�~80�K�B �@���̂���̃j�b�|�m�z���͕Жʂ��Ƃɔԍ������Ă���B �@����܂ł͏��̂���B�吳8�N(1919�N)�ɁA�����̌��u���ڎq�̈���v(�j�c �|�m�z��3657.3658)���������B���w�ł͂Ȃ��B �@ �E�L����K552�^�̎�@���R�j�q�B �@��O�c�����Y��Ȃ́u�J�v�� �@ �E�L���OA3-2�^�̎�@�ߓ��\�q�B�^�C�g���́u�J���~��܂��v�B �@ �E�R�����r�AC63�^�̎�@��c�F�q�A�����q�B �@ �E�e�C�`�NT517�^�̎�@�c�[���Ƃ݁B
�y���҂����p�y�ђ��쌠�ɂ��Ă��肢�z�@�@�@�ᒘ�ҁE�r�c���S���� |
|||||||||||||||||||||||||||||
�@ �y�t�ɌĂт�����́z�@ �@��[���k���ł͏t���҂��������B�₽����̒��ł��A�A���͏t�̏��������Ă��܂��B�������������A�V�肪�萁���t��҂���т�C�����́A�q������l���ς��܂���B �@���̉̂́A��l���q���Ɋ�肻���ă��Y�������A�݂��ɐS�e�܂��̂������ł��鈤���̂ł��B���������A�e��g�߂ȑ�l�ɉ̂��Ă��������A��l�ɂȂ��Ă���́A�q���⑷�ɉ̂��Ă�����肵���v���o���S��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�쎌�҂̑��n�䕗�́A�ፑ�̐V����������̏o�g�ł��B���́u�t��҂��v�́A�܂��t�����Ȃ��G�߂ɁA����Ԃ��u�t��҂��@�͂₭�҂��v�ƌĂт�����̂ł��B�~�A��̍~��Ȃ��n���ł��A�t���߂��Ȃ�Ɖ̂������Ȃ�y�����̂ł��B �@ �y�c����̉̎��z �@���Ԃ̉̎��ɂ��ā�@�~�̊Ԃɕ����̒��ŕ�����悤�ɂȂ�������̗c���u�݂������v���A�e�ɔ����Ă�������u�Ԃ��@���̃W���W���v���͂��āA������̊O�֔�яo�������Ƒ҂���т�C�������̂��Ă��܂��B�����Ȏq�ǂ����t��҂��]��ł���Ƃ�����]�̉̂ł��B �@ �u�t��҂��@�͂₭�҂��v�Ƃ����Ăт����́A�����ȁu�݂������v�̊肢�ł������ł͂���܂���B�q���́A���������Ɛ������Ăق����Ƃ����e�̊肢�ł�����܂��B �@�y��������ƁA�u�t��҂��@�͂₭�҂��v�́A���t�ɏd����u�������ʂȃ��Y���ɂȂ��Ă��܂��B���̕����́A�^�^�^�^�̃��Y���ŁA��i�����̃��Y���ɂȂ��Ă���̂ŁA���̉̂��o���̓��ق��͂��킾���Ă��܂��B���������āA�ŏ��́u�́[�@���@�����v�́A�t�ɌĂт�����悤�Ɂu�����v�͒Z���l�߂āA�͂��͂��Ɖ̂��܂��B �@���̉̂̍ő�̓����́A�����ւ�J���I�ȋC�����ʼn̂������ł��邱�Ƃł��B�̂��Ă���l�����܂�ӎ����Ă��Ȃ��ꉹ�ɓ���������܂��B����́A�Ȃ�����قNJJ���I�ȋC�����ʼn̂����Ƃ��ł��邩�Ƃ������ƂƊW������܂��B�ꉹ���ӎ����ĉ̂��Ă݂�킩��܂��B�u�̓A�[�@���@�����@�̓A�[�@�₭�@�����v�ƁA�̂��o���̕ꉹ���u�A�v�ł�����A����傫�������Ė��邢���ʼn̂����Ƃ��ł���̂ł��B �@�܂��A�u�݂������v�Ƃ������̎q�̖��O�ƁA�u�W���W��������(������)�v��u��������Ƃ̊O�B�����āB����(��)�̕ω��������t�v�Ƃ������c���ꂪ�A�̑S�̂����킢�炵�����Ă��܂��B �@�u�Ԃ��@���v�́A�������F�����������Ă��܂��B���̂悤�ȕ\���͓����Ƃ��Ă͔��ɒ������������Ƃł��B �@���Ԃ̉̎��ɂ��ā�@���R�ɖڂ������Ă��܂��B���̉Ԃ́A�܂��Q�ł��B�Q�͗c���̃C���[�W�ł�����A��Ԃ���ԂƓ��l�ɗc���q�ǂ��̈�ۂ��d�˂ĕ`���Ă��܂��B�������D�����\���ł��B�O���O���͓��̐ߋ�Ƃ����鐗�Ղ�ł��B�u���̖v�͏t�̋G��B�u�͂恁�����v���c����ł��B �@�Ō�́u�܂��@�Ă��@��v�̃��Y�����A�u�́[�@���@�����v�̃��Y���Ɠ����ɏ�����Ă��܂��B�������A�d�v�ȕ����Ȃ̂ł��B�u�܂��v�͉����l�߂āA�Z���͂�����̂������߂܂��B �@�y�e�̊�]�z�@ �@���̂悤�ɁA�q���̎��_�ɂ����ꂽ�悤�Ɍ����܂����A���ۂɂ͎q���̌����ɂ���e�̊�]���`����Ă�����̂ƁA�Ƃ炦�邱�Ƃ��ł��܂��B�u���邫�͂��߂��v�q���ɂ́A���Ɂu������֏o�����v�u�͂�炫�����v�Ƒ������C�ɑ傫���Ȃ��ė~�����Ƃ����؎��Ȑe�S�����������܂��B���������āA��Ԃ���Ԃ��Ō�͋C���������߂ĉ̂��܂��B �@�y�����̖��O�ʼn̂��z�@ �@�l�C�̈����̂ł��������̗��R�́A�q���������̖��O���A�u�݂������v�ƒu�������ĉ̂����Ƃ��ł���Ƃ������Ƃł��B���̂悤�ȉ̂́A����ȑO�ɂ͂���܂���ł����B �@ �y���f���͕��q����z�@ �@�u�݂������v�ɂ́A���f��������܂����B����́A�쎌�ҁE���n�䕗�̒����̕��q�i���₱�j����ŁA�吳�\�N��\���ɐ��܂�܂����B�u�t��҂��v�͂��̓�N��A�吳�\��N�O���ɔ��\����Ă��܂��B �@���q����́A������N����������s�̎G���w�T���C���W����15�x(���w��)�̃C���^�r���[�Ŏ��̂悤�Ɍ���Ă��܂��B  �@ �u���́A�������f�����Ƃ͈�x�������܂���ł����B�������A��̓�l�̌Z����(���j�̏���E�܂��̂�)�A(�O�j�̝�E������)����"���܂������f������"�Ƃ����b�͕�������Ă��܂����v�B �@ �u���́A�������f�����Ƃ͈�x�������܂���ł����B�������A��̓�l�̌Z����(���j�̏���E�܂��̂�)�A(�O�j�̝�E������)����"���܂������f������"�Ƃ����b�͕�������Ă��܂����v�B
�@�u�̎��ł́A"�Ԃ��@���̂������"�ɂȂ��Ă��܂����A�������������͑S�̂��Ԃ������ł����B�傫����6�`7�Z���`���炢�ŁA�����ƂɕR�����Ă����ƋL�����Ă��܂��B��ɐq�˂���"����́A���܂��ɏ��߂Ĕ����Ă�������������"�ƌ����܂����B���̂��Ƃ������Ă���A���̓��w�̃��f���͎����ȂƎv���悤�ɂȂ�܂����v�B �@���q�����w�Z��N���̍��A����̉��ʔ��̋��Ō����Ƃ����Ԃ������́A���a�O�N�����̉Ύ��ŊD�ɂȂ��Ă��܂��܂����B���n�@�͌��Ē�����A���݂͐V�����w�蕶�����Ƃ��Ĉ�ʌ��J����Ă��܂��B �@�u�����ƂɕR�����Ă����v�Ƃ����،�����ۓI�ł��B�̂̎q�������͊F�A�e�ɂ������Ă�����ė����Ă��܂����B���A�r�c���S�������l�ł����B���������ł��B
�@ �y�q�ǂ��̖��O���u���₿���v�ł͂Ȃ��u�݂������v�Ȃ̂́z �@�u�ŋ߁A���f�����Ƃ����Ă����܂�s���Ƃ��Ȃ��Ȃ�܂����B����́A�����܂ł����̑n��ł�����ˁB�Öق̂����ɕ����ŗ��������������ƂȂƎv���Ă��܂��v�i�w�T���C���W����15�x���q����68�j�B �@�ȏ�́A68�̎��̃C���^�r���[�̕��q����̘b�ł����A�_�ސ쌧�ɕ�炷85�ɂȂ������q����͓����̎�������̂悤�Ɍ���Ă��܂��B �@ �u���̉̂̉̎��͍ŏ��A"���邫�͂��߂��@���₿���"�ƂȂ��Ă����ƕ����Ă��܂��B���ꂪ��Ȃ����Ă����������O�c�����Y���A���₿���ł͉̂��ɂ�������A�݂������ɕς��悤�ƒ�ĂȂ����������ł��v�@ �@������̎���̑O�ɂ́A�̎����̂܂܂ɓ��̖��������Ƃ����B�܂��A�u���̎q�͎��ЂƂ肾���ł�������A�ƂĂ��������^�����܂����v(�w�T���C����18�N13�����ʕt�^�@������x�������݂������́x���q����85��)�B �@�䕗�̎q�������ܒj�ꏗ�̂Ȃ��ŁA���j(�����E�܂��̂�)�A�l�j(���Y�E���Ƃ�)�́A���q�����܂��O�ɖS���Ȃ��Ă��܂����A���a�ܔN�ɐ��܂ꂽ�ܒj(�E�Ƃ�)�́A������������ɖS���Ȃ��Ă��܂��B���߂Ă̏��̎q�̒a���ŁA�����������������Ƃł��傤�B�u�����v�ƌĂ�ł��킢����܂����B ����Ȏ������l���Ȃ��炱�̉̂��������ƁA��������l�̏��̎q�̐�������ԁA���e�Ƃ��Ă̈�������Ƃ�Ɠ`����Ă��܂��B�u�t��҂��v�́A�܂�ŕ��q����̖���̒a�������j���̂̂悤�ł��B �@�t�Ɍ��炸�A���͉̉̂̂��l���ꂼ��̊�]�▲������ĉ̂����Ƃ��ł��܂��B���������A���n�䕗�ƍO�c�����Y�̓�l������Ă��ꂽ���킢�����w�u�t��҂��v����������ŁA���ꂼ��̊�]�̏t��҂��������̂ł��B �@ �y�䕗�̎q�������z�@ �@���n�䕗�͑S���Ōܒj�ꏗ���������܂����B �@���j:����(�܂��̂�)�@ ����43�N2��8�����`����44�N5��20���v�B �@���j: ����(�܂��̂�)�@����44�N11��1�����`���a52�N12��31���v�B �@�O�j: ��(������)�@�@�@�吳3�N6��19�����`���a54�N2��12���v�B �@�l�j: ���Y(���Ƃ�)�@�@�吳4�N9��10�����`�吳8�N8��13���v�B �@����:���q(���₱)�@�@ �吳10�N2��20���` �@�ܒj:��(�Ƃ�)�@�@�@ ���a5�N5��30�����`���a5�N7��18���v�B �@ �u���j�Ǝl�j�A����Ɍܒj���S���Ȃ����̂ŁA���낢��ȕ����ŌZ����l�Ƃ��A�l�l�Ƃ����悤�ɁA��������Ă���̂��Ǝv���܂��B�v (�ȏ�́A�w���n�䕗�L�O�فx��苳���Ă��������܂����B����15�N12��17��) �@�i���j�����F���q����͕�����\��N�i2009�N�j�ɖS���Ȃ��܂����B �@�y���\�ɂ��āz�@ �@���̔��\�͂��ł��傤���B �@ �E�吳�\��N�ꌎ��\���A�䕗�̎��ɍO�c�����Y����Ȃ��܂����B �@ �E�ȂƎ����ꏏ�ɑ吳�\��N�O��������s�̕������b�G���w���̒��x(���̒���)�O�����Ŕ��\����܂����B �@ �E���n�䕗���w���n�䕗�̗w�W�x(�����t)���a�\��N�܌����s�́u���w�̕��v�Ɏ��^�B �@ �E���͖��N�t�ɂȂ�ƃ��W�I�ŕ������ꂽ�̂őS���ɍL�܂�܂����B �@ �E�r�N�^�[���R�[�h�̋g��͎q�̉̐��́w�S���银�w�̎��S�W�x(�R�����r�A�t�@�~���[�N���u)�Œ��������ł��܂��B
�@�y����?�@�u�͂搁�������v�z�@ �@�w���̒��x�f�ڂ̎��́u�͂搁�������Ɓv�ƂȂ��Ă��܂��B�u�萁���v�Ƃ��������炱�̂悤�ɏ������̂ł��傤�B�ƂĂ��Â������w�I�\���ł��B���̕\���͑��ɂ͂���܂���B �@�������̌��e�ׂ�K�v������܂��B �w���n�䕗�̗w�W�x���^�̎��́u�͂�炫�����Ɓv�ƁA���̂��Ă���悤�ɕς��Ă���܂��B����ɁA���o�́w���̒��x�ł́A��s�ڂ��u�t��҂��v�������̂��A���^�́w���n�䕗�̗w�W�x�ł́u�t�悱���v�ƕ������ɂȂ��Ă��܂��B���̏o�ŕ��ł����������ɕς��邱�Ƃ́A�悭���邱�Ƃł��B �@ �y�^�C�g���́u�t��҂��v�z �@ �E�w���̒��x(���̒���)�吳�\��N�O�����̃^�C�g���́u�t��҂��v�Ɣ��\�B �@ �E�䕗�쎌�̏W�听�w���n�䕗�̗w�W�x(�����t)���a�\��N�܌����s�ɂ��u�t��҂��v�ƋL�ڂ���Ă���B���������āA�u�t��҂��v�����������̂ł��B �@(�ȏ�́A�w���n�䕗�L�O�فx��苳���Ă��������܂����B�w���n�䕗�̗w�W�x���u�t��҂��v�̉̎��R�s�[�������Ă��������܂����B����15�N12��17��) �@�y�w�����x�ɔ��\�͊ԈႢ�z �@���H�R�����̉���@�w�ʍ����z�q�ǂ��̏��a�j�@���w�E���́E����100�x(���}��)�ɂ́u����O(�吳�\��)�N�A�䕗���g�D���Ă����؈���̉̂̎G���u�����v�̈ꌎ���ɏ��߂Ĕ��\���ꂽ��i�v�Ə����Ă���܂��B �@�����H�͕ҁw���{���w���̑S�W�x(�h���~�y���o��)�ɂ��u�吳�\��N�́u�����v�Ŕ��\�v�Ə����Ă���܂��B���̑吳�\��N�u�����v�ɔ��\�̌�����L�ڂ́A�ǂ̏o�ŕ��ł������܂��B �@���R������܂��B����́A�����҂���̐M�����Ă��铡�c�\�Y���w���{���w�j�T�x(�����ˏ��[)�ɂ��������Ă��邩��ł��B�������A����͌��ł��B �@�����c�\�Y���w���{���w�j�T�x(�����ˏ��[)�ɂ͎��̂悤�ɏ����Ă���܂��B �@ �u�䕗�̓��w�ŁA�����Ȃ��̂��Ă���̂́A�吳�\��N�A�w�����x�ɔ��\���ꂽ�u�t�旈���v�ł���B�O�c�����Y�̃����f�B�[�ɂ���āA�e���r��W�I�́A�t��ɂȂ�ƁA�n���̈�o���̂悤�ɁA���̉̂𗬂��B �����̂ł͂Ȃ��B�������u���傶��͂��āv�ȂǂƂ����c����ɂ���Ă���킳��Ă���悤�ɁA�Õ��ȁA�O����I�ȓ��w���v�B �@ ��吳����Ɂu�����v�͑��݂��Ȃ��� �@ �E�䕗���吳�ܔN������ɋA���B �@ �E�吳�ܔN�Z���A���싱����̋��̗L�u��m�l���W�܂�A�u�؈���v�Ƃ����Z�̉��g�D���܂����B �@ �E���a�O�N�A�u�؈���v���Z�̌��Ђ��N�����A�Z�̂̔��\�@�֎��Ƃ��ď��a�O�N�l���Ɂu�؈��̏W�v��n���B �@ �E�G���u�؈��̏W�v���������N���}�������A����V���ɂ��đ�5����P�S(��U�N��5�����A�ʊ���S�U�S)�Ƃ��A���O���u�����v�Ɖ��肵�A�ҏW�̓��e������V���čďo�����܂����B���������āA�G���u�����v�́A�吳����ɂ͑��݂��܂���B �@���̏��o���u�����v�͊ԈႢ�ŁA���o�͑吳�\��N�O��������s�̎G���w���̒��x�O�����Ɠ��قł͔F�����Ă��܂��B �@ (�ȏ�́A�w���n�䕗�L�O�فx��苳���Ă��������܂����B����15�N12��17��) �@�����c�\�Y���w���{���w�j�T�x(�����ˏ��[)�̑O�L�Ɠ���452�y�[�W�ɂ́A���̂悤�ɏ����Ă���܂��B �@�u���a�O�N�A�䕗�𒆐S�Ɂu�؈���v������w�����x��n���B�ܔN�\���ɂ͌l�G���w�����ގҁx��n���B�w�����x�͏\���N�p���ɂȂ������A�w�����ގҁx�́A��\�ܔN�܌������A�Z�\���Ŏ�������O���܂Ŕ��s���ꂽ�v�����Ƒ����قȂ�܂����A�Ƃ������G���u�����v�́A�吳����ɂ͑��݂��Ȃ��Ə����Ă��܂��B���c�\�Y�͎G���u�����v�̎���m���Ă����ɂ�������炸�A�Ȃ��u�吳�\��N�A�w�����x�ɔ��\�v�Ə����Ă��܂����̂ł��傤�B�{���́A�u�吳�\��N�A�w���̒��x�ɔ��\�v�Ə����ׂ������ԈႦ�Ă��܂����̂ł��B���̂��߁A���̊Ԉ�����L�q�����X�o�ŕ��Ɏg���Ă��܂����̂ł��B �@��̏o�ŕ��̒��҂����́A�����Œ��ׂ�A�����킩�鎖�ł����B �@�y�w��̗�x�ɔ��\���ԈႢ�z �@���n�䕗���w��̗�x(�t�z��)�́A�G���w���̒��x�Ȃǂɔ��\�������w���܂Ƃ߂āA�吳�\��N�܌��ɏo�ł������w�W�ł����A�u�t��҂��v�͎��^����Ă��܂���B �@(�ȏ�́A�w���n�䕗�L�O�فx��苳���Ă��������܂����B����15�N12��17��) �@���^�c�È�ҁw���{���w�W�x(��g����)�ɂ́A�u�t�旈���v�̎��ɑ����āu�\�w��̗�x��12�E4�v�ƏЉ��Ă��܂��B�������A������ԈႢ�ł��B����ɁA���̖{�́u�܂������v�̃��X�g�i���a�\���N�ꌎ�����ɂ�������M�j�ɂ́u���n�䕗�u�t�旈���v�̏��o�͓��w�W�w��̗�x�Ɣ����v�ƁA��d�ɊԈႢ�������Ă���܂��B���̂��߂��̊Ԉ�����L�q�������̏o�ŕ��Ɏg���Ă��܂��܂����B�������́u�\�w���̒��x��12�E3�v�ł��B �@�Ȃ��A�䕗�́w���̒��x�ɏ��������w�̉ߔ����W�߂����w�W�w��̗�x�Ɂu�t��҂��v�����Ȃ������̂ł��傤�B�吳�\��N�O���A�G���w���̒��x�ɔ��\�����u�t��҂��v�́A�吳�\��N�l�����s�̑��n�䕗���w��̗�x(�t�z��)�̎��^�ɊԂɍ���Ȃ������̂��Ǝv���܂��B�^�c�È�́A�u�t�旈���v�͓��R���̓��w�W�Ɏ��^����Ă�����̂Ǝv�����݁w��̗�x�Ə������̂ł��傤�B �@��N�o�ł������n�䕗���w���n�䕗�̗w�W�x(�����t)���a�\��N�܌����s�́u���w�̕��v�Ɏ��^���܂����B �@�����������āA�w���̐S�̉́\�t�@���ڂ댎��x(�w�K������)�́u�吳�\��N�w��̗�x�ɔ��\�v�͊ԈႢ�B �@��������N����������s�̎G���w�T���C���W����15�x(���w��)�ɂ́u�吳11�N1���ɔ��\���ꂽ�v�Ə����Ă���܂��B������ԈႢ�B������܂ōs���Ď�ށE������������c��Y�́A�u�ǂ��ɔ��\���ꂽ���v�������Ă��Ȃ��B���̎���������A���n���q����ɒ��ځA���\�N�����Ɣ��\�G���܂��͔��\�����ɂ��ĕ��������ł����͂��ł��B �@ �y�u�䕗�v�Ƃ������ɂ��āz�@ �@���˂͗c�����G�ŁA�g���������쏬�w�Z����ɂ́u���|(��������)�v�ƍ����Ă��āA���c���w�Z�݊w����A�\��������u�䕗�v�Ƃ��������g���n�߁A���łɒZ�̂��r��ł��܂����B�����ؐM�j�̒Z�̌��В|����i�u�S�̉ԁv�͉�̉̎��j�ɓ���A�n�����c�V���̑I�҂߂�ȂNJ��Ă����B �@���̂߂��炵�����́A�k�v�̕����A�h����(���Ƃ���)�́u�ԕǕ�(�����ւ��̂�)�v���́u�g���䕗���s�m�����~�v����̂������̂ł��B �@(�ȏ�́A�w���n�䕗�L�O�فx��苳���Ă��������܂����B�w���n�䕗�L�O�فx����́A�[�����������R�����������Ƃ��ł��܂����B���̋L�O�ق⎑���ق����l�ɂ��肢�������Ǝv���܂��B��ʂ̐l����̎���ɂ́A���̊w�|����w���̎�C�厖��u���āA�Ή����Ăق����Ǝv���܂��B�݂�Ȃ̕��ɐ����������Ăق����Ǝv���܂��B����15�N12��17��)
�@ �y���n�䕗�̗����z
�@ �E�����O�\�l�N�A�������c���w����(���E��z�s�̍��c�����w�Z)�A���얢���Ƃ͓������B���w���ƂƓ����ɗ^�Ӗ�S���́u�V���Ёv�ɓ���A�w�����x�̓��l�ɂ܂łȂ�܂��B �@ �E�����O�\�ܔN�A����c��w�p���Ȃɐi�w���܂����B �@ �E�����O�\�Z�N�A�u�V���Ёv��E�ނ��A���A��(����̂ق��߂�)��ƁA�u���������Ёv���������A�G���u���S��(������)�v��n���B�Q����`���|�̐i�W�Ǝ��̂̊v�V���Ăт�����B �@ �E�����O�\���N�A����c��w�𑲋Ƃ����N�O�A�������ŏ��̉̏W�w���@�x�𓌋������Ђ���o�ł��܂����B �@ �E�����O�\��N�A����c��w���ƌ�́u����c���w�Ёv�ɓ��Ђ��A���������̉��Łw����c���w�x�̕ҏW�ɏ]�����܂����B�����̗��s��ł��������R��`���|�^���̐�N�Ƃ��ĕ��|�]�_�̖ʂŊ��܂����B �@ �E�����l�\�N�A�O�ؘI���A�l�������A����J���ƂƂ��Ɂu����c���Ёv�������B���ꎩ�R�����i�̒��S�ƂȂ�w�䕗���W�x(�l�\��N)�����s���܂����B�܂��A����c��w�n����\���N�ɍۂ��A�Z�́u�s�̐��k�v(���V�S�J�E���)���쎌���܂����B��\�l�̎��ł����B �@ �E�����l�\�l�N���瑁��c��w�u�t�ƂȂ�A���B�ߑ㕶�|�v�����u�`�B �@ �E�吳�O�N�ɓ��������Ƃ̍���Ŕ��\�����u�J�`���[�V���̉S�v(���R�W���E���)���嗬�s���܂����B�̂����̂͏���{���q�B �E�E�E�����ʼn߂������N����́A���w�ᔻ��l�ԊW�ȂǂŔg���ɖ������\�l�N�Ԃł����B �@ �E�吳�ܔN�ȍ~�͌̋��̎�����ɋA��(�O�\�O�̎�)�A�����̋��_�������Ɉڂ��A�I���㋞���邱�Ƃ͂���܂���ł����B�ܔN��A���q���a�����A��N��A�u�t��҂��v�\���Ă��܂��B �@ �E�ӔN�͑T�m�ʼn̐l�̗NJ�(��傤����)�̌����ɖv�������B�䕗�͌̋��A���Ԃ̒��ŁA���R�A����c��w�̓����̉�Ô���ɏo������B����́A�̐l�A���ƁB�����܂��]���̒�܂��Ă��Ȃ������NJ��̌|�p��F�߂Ă����m���l�Ƃ��Ēm���Ă���B���̌�A�̋��ŗNJ������f���ɂ��Ȃ���A���z�Ƃ����������������B�NJ�������\��w���NJ��x(�吳���N)���s�B�q�������́w�NJ����܁x�w���s���܁x�w�ꒃ����x���A�w���̂������ցx�Ƃ������b�W���o�ł��Ă��܂��B �@ �E���a��\�ܔN(���܁Z�N)�܌������A�ˑR�]�쌌�œ|��A�������Z�\�Z�ŖS���Ȃ�܂����B���w��ł��A�l�ԊW�ł��������D�܂��A�̋��������A���̂�̕��w�ƌ��������ǓƂȐl���ł����B���l�A�̐l�A�]�_�ƂƂ��Ċ���B��i�́w���n�䕗����W�x�S�\��(��㔪��N�E�������s��)�ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B �@ (��)�@�V���������(�ɂ����т�)�S������(���Ƃ�����)���厚�咬(���E������s�咬��)�ɂ��� �@���a29�N�Ɏs��������������A������s���a�����܂����B�����쒬�́A���݂̎����E�咬�E�V���E���ԁE�����E�V�c�E�S�C�E����E��̋{�E�@�䎛�E�㊠�E�������w���܂��B �@(�ȏ�́A�w���n�䕗�L�O�فx��苳���Ă��������܂����B����15�N12��17��) �@ �y�O�c�����Y�̗����z�@�ʋL �@ �y���ꂩ����̂��p�����悤�Ɂz �@���́A���̉̂���D���ł��B���̉̂��̂��ƁA���������̎������S��܂��B�������ҁw�e�q�ʼn̂��������{�̉̕S�I�x�ɂ͑I��Ă��܂���B �y���҂����p�y�ђ��쌠�ɂ��Ă��肢�z�@�@�@�ᒘ�ҁE�r�c���S���� |
|||||||||||
�@��������̌����҂̕ʕ{���Y���L�̓��w�ȕ��W�w���R�̂����x�O�c�����Y��Ȃ�S�y�[�W�R�s�[�����Ă��������܂���(2011�N2��16��)�B���̖{�͑吳�\�N�\�ꌎ��\�ܓ����s(����)�ł��B�������y��w�����}���ُ����́w���R�̂����x�͑吳�\�l�N�O����\�ܓ����s(�l��)�ł��B�\���G�⒆�\���̊G���ς��Ă���܂��B�y����̎��A�}�G�͓����ł��B
�y���҂����p�y�ђ��쌠�ɂ��Ă��肢�z�@�@�@�ᒘ�ҁE�r�c���S���� |
| �@�y���҂�蒘�쌠�ɂ��Ă̂��肢�z �@���͂��g�p����ꍇ�́A���E�F�b�u�w�r�c���S���Ȃ��Ƃ����w�E���́x�ɂ�遄�Ə����Y���Ă��������B |
���[�� �i�{�����ɕς��āj |
�g�b�v |
![]() �Ȃ��Ƃ����w�E���̃��j���[�y�[�W�ɖ߂�
�Ȃ��Ƃ����w�E���̃��j���[�y�[�W�ɖ߂�