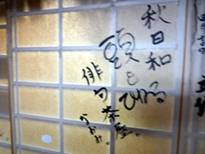|
天恢の霊感遍路日記 (松山〜結願編)
遍路も6日目、疲れもピークに達した。足にマメができて、それが破れて出血し、痛みもある。最終ステージ「涅槃の道場」の2日目は、8つの札所を一日で回る超過密・強行軍である。宿の朝食を待っていたら遅れるので、昨日スーパーで調達したものですませて、早々に出発するが、幸い宿の「ふれあいパークみの」は弥谷寺の門前にあるため、職住接近と同じで助かる。今日は晴天のようであるが、まだまだ辺りは薄暗い。荷物を「俳句茶屋」に(不在だったが無断で)置かせていただき、石段を上れば仁王門はすぐそこである。
第71番 弥谷寺
仁王門をくぐって262段の石段を上りきると、高さ5mの金剛拳菩薩像が大きな藪椿と並んで迎えてくれる。さらに大師堂までは、108段の石段を上がる、大師堂から奥の石段を上がると、岩壁に浮き彫りされた阿弥陀三尊の「磨崖仏」が見えてくる。本堂はさらにその先に建つ、参道はくねるように細く、長く延び、濃い緑の樹木に覆われている。本堂も大師堂も岩壁と一体となり、岩山全体が寺とも思えてくる。あたりには霊気が漂い、霊界に踏み込んだような、不思議な気持ちにさせられる霊場で、天恢もすっかりこの弥谷寺に魅せられてしまった。 そんな気持ちさせるのも、そもそも弥谷寺は、古くから「弥谷参り」と呼ばれる風習が伝わり、地元では死者の霊魂が向かう先だと考えられてきた。四国霊場の中で死霊が帰る札所として、お遍路たちにとくに恐れられた寺だという。昔は死者が出ると、その身寄りの人が、両手を背中に回し、死者の「霊を背負った」格好でお参りを終え、「霊をおろした」後、本堂から山門に辿り着くまでは、決して後ろを振り向いてはならないといわれている。
さてさて、ここの見所は? 先ず、仁王門をくぐると、石段脇には石仏や五輪塔が数多く置かれ、樹木の影には古い墓があったりして、法雲橋を渡る。ここが地獄極楽図に出てくる賽ノ河原だといわれている。死者はこの賽ノ河原を渡って、三途の川へ行くのだという。 次に、大師堂は、四国霊場の中で唯一、靴を脱いでお参りする大師堂であるが、その奥にある「獅子の岩屋」は、大師が真魚(まお)と呼ばれた少年の頃に修業した場所で、十畳ほどの広さの獅子が口を開いた形の岩窟で。獅子の遠吠えは仏の説法と同じものと考えられていることからも、この名がついた。 おまけで、本堂に向かう途中、岸壁に刻まれた阿弥陀三尊像。像高約1m。舟形光背をバックに崩れかけた姿が、長い歳月の風雪に耐えてきたことを偲ばせる。この磨壁仏を刻んだのは弘法大師とも一遍ともいわれる。 そして、ご利益は? 阿弥陀三尊像に念仏を捧げると、未来に極楽往生が約束されるとか。 本堂で、天恢も人生での「霊をおろした」後、(大師堂の中にある納経所でも無言で、)山門に辿り着くまでは、決して後ろを振り向かず、下りてまいりました。天恢にとって、弥谷寺は四国霊場88ヵ所中、もっとも霊的な雰囲気をここかしこに漂わせている神秘的な霊場であった。弥谷山は,昔から山全体が死者の霊が帰り集まって住む山として信仰されてきた所で、寺信仰のはるか昔から岩崖に刻んだ五輪塔内に遺骨・遺髪等を葬るという「弥谷参り」の風俗発祥の地であった。天恢も別途ページを割いてこの風習を紹介し、弥谷信仰の共感を求めていきたいと願っています。
荷物を預けた「俳句茶屋」で、お礼を述べて、コーヒーと蓬餅をいただく、オヤジさんの紹介で2006年放映のNHK土曜ドラマ「ウォーカーズ迷子の大人たち」の面々やNHK「街道てくてく旅」の卓球の四元奈生美ちゃんの俳句をじっくり鑑賞させてもらった。楽しいオヤジさんで、「男は75歳過ぎると遍路は無理、その点女性は80歳過ぎても元気に歩いている人が多い!」とのご意見、毎日、遍路さんを相手にされている方ですから、やけに説得力があるのです。今日は、これから 先が長いので・・・。いつまでもお元気で・・・。 次の札所への遍路道は、いきなり竹藪の中を通って高松自動車道をくぐるまで、なかなかの趣がある小道である。
天恢は、順打ちにこだわらないので、歩きやすさを優先して第72番札所曼荼羅寺を通り過ぎて、その奥にある出釈迦寺を先に参拝することにした。なだらかな坂道を上がっていくと、ミニ公園があって、大小の修行大師像の前に山頭火の「山あれば山を観る」の句碑があって、石段を上りきったところに真新しい山門が見えた。 確か以前は鐘楼付きの重層の山門であったが・・・。
第73番 出釈迦寺 本堂よりも大師堂のほうが大きいこの寺の境内は、全体的には小ぶりだが、霊山・我拝師山を望む山麓にあって、霊気に満ちた札所である。 そもそも出釈迦寺は、この寺の奥之院、我拝師山の山頂に、捨身ヶ嶽禅定がある。弘法大師は七歳のとき願を立て「私は将来仏門に入って、仏の教えを広め、多くの人を救いたい。もしこの願いが叶わぬなら一命を捨ててもよい。お釈迦さまのご意思を示されたい。」といって、断崖絶壁より谷底へ身を投じたという。すると突然釈迦如来が現れ、天女が大師を雲上に抱きとめて、願いが成就する「一生成仏」を告げられた。感激した大師は、後に釈迦如来像を刻んで本尊とし、我拝師山の山上に寺を建てられ、出釈迦寺と名づけられた。出釈迦寺が現在の地に下りてきたのは300年も前の江戸時代になってからのことである。
さてさて、ここでのご利益は? 山上にあった出釈迦寺は、捨身ヶ嶽禅定と呼ばれる奥の院となり、大師のお人柄を偲ぶ信仰の場となっている。奥ノ院までの急な山道を登るのは無理という人のために、本堂の左側にある石段を上がったところに「捨身ヶ嶽遙拝所」がある。ここで念仏を唱えれば、捨身ヶ嶽禅定に参詣するのと同じ御利益が得られるという。先を急ぐ天恢も、ここでお参りさせていただいた。 もう一つ、出釈迦寺は大師が虚空蔵菩薩を刻み、求聞持法を修めた場所であることから、求聞持院という院号が付いた。虚空蔵菩薩の真言を百万回唱える法を求聞持法といい、すばらしい記憶力が得られるという。そのためこの像を拝むと学業成就や物忘れにご利益があるとされている。 おまけで、ご利益限定付きであるが、山門の前に「子宝の三鈷の松」と名付けられた松がある。これも先端が三つに分かれている松の葉で、この葉を身につけていると子宝に恵まれるそうである。 山門を出て、曼荼羅寺へ下りていく途中に出会ったお遍路さん、「出釈迦寺から打たれたのですか?」と挨拶されたが、昨日、本山寺で声を掛けられたお遍路さんだったのです。その時も挨拶だけでした。500mも下りれば 曼荼羅寺です。その手前で、「歩き遍路さんのみ・さぬきうどん・お接待致します うどんの里丸正」の看板がありました。お気持ちだけいただいて、これからの商売繁盛を祈らせていただきます。 第72番 曼荼羅寺
仁王門をくぐり、小さな掘に架かる石橋を渡ると、すぐ右に延命地蔵の銅像と修行大師の石像が立っている。まっすぐ参道を歩き、正面に建つのが本堂である。本堂に向かって左には、護摩堂、大師堂、鐘楼があって、鳥居のある八幡宮もあって、静寂の中で落ち着きのある札所である。 そもそも曼荼羅寺は、密教の根本原理を象徴する「マンダラ」を寺号とし、平安末期の歌人・西行も訪れた、弘法大師の母御前の菩提寺である。 さてさて、ここの見所は? 本堂内は、密教の宇宙観を具現化したしたという「マンダラ」となっている。とりわけ370枚の板絵で構成された格天井は、実に壮観とのこと。内陣には天空を意味する二十八宿の星座、外陣には法界(全世界)の荘厳花である量繝彩色の花が描かれているであるが、有名なわりに観た人は少ない天井画である。
もう一つ、本堂前には、平安時代末期の歌人・西行法師ゆかりの「昼寝石」と「笠掛桜」の碑が残る。保元の乱で敗れ、讃岐に配流されて、失意のうちに46年の生涯を終えられた崇徳上皇を偲び、西行が崇徳上皇崩御後に讃岐を訪れ、白峰の墓に参り、その霊を慰めた後、この札所の近くの丘に草庵を結んでしばらく暮らしたという。その間、曼荼羅寺にも時折訪ねて、本堂前の分厚い大きな平石の上でよく昼寝をしたと伝えられている。これが「昼寝石」である。「笠掛桜」は、西行が都に帰る人と連れだって曼荼羅寺を訪れたが、同行したその都人は、笠を本堂前の桜の木に掛けたきり、忘れて行った。そのままになっている笠を見て西行は「笠はあり
その身はいかに なりぬらん あはれはかなき あめが下かな」と詠んだ。 その歌碑も昼寝石のそばにあって、ちょっと寝そべって、西行の歌心を偲んでみるのもこの札所ならではの一興である。時間の許す方は、ぜひお試しあれ! おまけで、大師御手植えといわれ、お遍路の被る菅笠のように、大きく円形に広がった巨大な松「笠松(不老の松)」があったが、松食い虫の被害に遭い、平成13年に枯れてしまったとのこと。返す返すも誠に残念なことである。 先を急ぐ身として長いはご法度である。延命地蔵に病に苦しむ近親者の無事をひたすら祈った。甲山寺へ向かう道で、讃岐富士と呼ばれる飯野山(422m)が見えてきた。途中に大きなため池があったので、堤防の上を歩くことにした。
弘階池で、ここからの我拝師山も心を和ませてくれる。田んぼの畦道を歩きながら、つい道筋を間違えたらしく、向こうにお遍路さんが見えたので追いつくように急いだ。先ほどのお遍路さんで、連れだって甲山寺まで歩くことになった。定年前で退職し、通しの遍路だそうで、北海道の伊達さんである。小さなパソコンを携帯したそうだが、すぐに送り返したそうだ。フェリーで舞鶴港へ、それからの四国入りでご苦労が伺われる。話が弾んで、弘田川に沿って歩いて行くと、木の香漂う真新しい山門と塀に囲まれた甲山寺が現れた。
第74番 甲山寺 甲山寺は、甲山にへばりつくように建っており、山門からは、すぐ正面に本堂が見える狭いながらも窮屈さを感じさせない札所である。ただ、古い風情のある本堂や大師堂に比べて、新しい山門や白壁の塀が余りにアンバランスで、どうもしっくりしない佇まいである。もうしばらく歳月の過ぎるのを待つしかない。
そもそも甲山寺は、善通寺と曼茶等寺の間に伽藍を建立せんとして霊地を探していた大師は、この山麓の岩窟から一人の老翁が現われ、「ここが探し求めている霊地なり。一寺を建立せよ!」とのお告げがあった。歓喜した大師は早速石を割って毘沙門天を刻んで安置し、堂宇を建てたのが始まりだと伝えられている。その費用は、嵯峨天皇から満濃池の修築を下命され、工事を完成させた報奨金が当てられたといわれる。甲山寺の名前は山の形が毘沙門天の甲冑の形に似ているところからつけられた。 さてさて、ここでのご利益は?
子宝を願う女性の信仰が篤い「子安地蔵尊」 大師堂へ登る石段の隣りに祀られているお地蔵様。ある時、子供に恵まれない女性がお参りし、地蔵の前掛けを持って帰ったところ、願いが叶って授かった。そのお礼に新しい前掛けを作ってお供えした。それ以来、子供を授かるありがたいお地蔵様として信仰されるようになった。今でも子宝を願う女性が前掛けを持って帰り、願いが叶ったら新しい前掛けをお供えにくるという習慣が続いているそうだ。お地蔵様のそばに「ありがたやめぐみもふかき血をわけて、家のよつぎを守るに仏」とある。 もう一つ、74番は『なし」』なので、病気なし・事故なしなどを拝む人が多いとのことである。 伊達さんと連れだって、いよいよお大師さまのお生まれになった善通寺に向かう。わずか20分ほどで善通寺の大きな門の前に着いた。どうやら遍路道は善通寺の東院と西院を隔てる道で、仁王門と中門が対峙する場所である。 第75番 善通寺 善通寺は何しろ広大な敷地である。仁王門で、回廊があって、その奥に御影堂があるので、こちらが西院である。先ずは西院の方から入ることにした。
そもそも善通寺は、弘法大師の生誕の地であり、真言宗善通寺派の総本山である。また、高野山(和歌山)の金剛峯寺、京都の東寺とともに、弘法大師の三大霊場の一つである。唐から帰国した大師が、先祖の菩提供養のため建立したのが善通寺で、山号は、西に向かって連なる5つの山(香色山、筆山、我拝師山、中山、火上山)にちなんで五岳山とし、寺号は大師の父の名である佐伯善通(よしみち)の名前から号したとされる。
境内は東西二つの院に分かれ、東院には、金堂・五重塔・釈迦堂・五社明神などがある。西院は、誕生院と呼ばれる大師個人にまつわる空間で、仁王門を入ると正面には御影堂(大師堂)が建ち、聖霊殿、地蔵堂、本坊、宝物館などがあり、納経所もこの院にある。 さてさて、ここの見所は?
さすが、お大師さま誕生の地であるので紹介しきれないほどたくさんある。境内でひときわ目立つ五重塔は、江戸時代から明治時代に再建されたもので、相輪が天を突くようにそびえる高さ45mの総檜造である。その塔の前には樹高30m、お大師さまとともに育ったと伝えられる樹齢1000年を超える大楠の枝葉が四方に大きく広がる。また境内には、唐へ留学する前に弘法大師がその水面に映る自分の顔を描き母である玉依御前に贈ったという「御影の池」や、大師誕生の時に使ったという「産湯の井戸」もある。 修業の一つとされるのが「戒壇巡り」である。御影堂の地下の胎内のような真っ暗闇のなか、約100mの距離を左側の壁を伝わって「南無大師遍照金剛」を唱えながら1周する。灯りのない通路はかなりスリリングなもので、悪行のある者は出られないといわれている。 善通寺での滞在は1時間で、本日は8札所を打たねばならないので、未練は残るがお暇せねばならい。
伊達さんが門前の熊岡菓子店で買われた名物「堅パン」を1枚いただいた。手焼きで丁寧に焼かれて、香ばしい香りがする。お礼を言って、ここで別れることになった。残り少なくなった道中と北海道帰還の無事を祈った。 これまでの無理と今朝からの歩き続けで、痛めていた足の指のマメがジンジンと痛みだした。休憩を兼ねて、ちょうど昼時なので、途中にあった「すき家」で牛丼1.5人前をいただいた。足の痛みは我慢するしかない! 歩いて行くと、正面に金倉寺のどっしりとした仁王門が見えてきた。 第76番 金倉寺
単層の大きな仁王門をくぐると、一直線に参道が伸びており、広い境内の正面に本堂が建つ。本堂は鎌倉建築様式の建物で、簡素ながら荘厳さを備えている。その左手に、造りが本堂とそっくりの小ぶりな大師
堂が建っている。境内には楠の大樹が茂り 兵火を免れた古い鐘楼がある。 そもそも金倉寺は、弘法大師の姪の子で、天台宗寺門派の開祖、智証大師円珍が生まれた寺として知られる。ここは日本で初めて鬼子母神(訶梨帝母尊)が現れたという寺。智証大師が5歳のときに天女が現れ、仏道に入るならずっと護ってやると言って去った。この天女こそが安産や育児の神とされる鬼子母神だといわれる。 さてさて、ここでのご利益は?
数ある中での一押しは、時折この寺特有「バチ、バチ、バチ」という音が、境内に響くのは、願を掛けながら引いて回すと叶うという巨大な「願供養念珠(がんくようねんじゅ)の音である。参拝者がワイヤーに通した大きな数珠を引くと、数珠が回り、上に上がった数珠が落下する。その時に下方にある数珠に当たって、音がはじける仕組みである。天恢も願を掛けてやらせていただいた。「バチ、バチ、バチ」と小気味よい音が鳴り響き、天まで願いが届いたようなきがした。 その他、鬼子母神を祀る訶梨帝堂、「一願一杓」の水掛け地蔵菩薩、子育地蔵、不動明王の石像、四国霊場の各札所の砂を踏んで礼拝する「お砂踏み道場」などのご利益と、「乃木将軍妻返しの松」の見所もたくさんある。 参拝が終わって「もう来(こ)んゾー」と帰る人もいるそうだが、ご利益盛りだくさんの札所である。「また来るゾー」で後にした。 痛む足を引きずりながら、4km先の道隆寺を目指して歩く。途中に、鬱蒼とした「鎮守の森」の厳かな雰囲気の中に建つ山門が現れた。しめ縄があるので神社と判るが、(後で調べたら)葛原(かずはら)正八幡神社であった。
このような豊かな樹木に囲まれた「鎮守の森」は、昔の郷土の姿を偲ばせてくれる、後世に残したい貴重な自然遺産である。葛原あたりからは多度津町で、のんびりした田園地帯であるが、古くから開けたところである。豊原小学校を過ぎて、予讃線の踏切の手前で右折すると、ほどなく壮大な構えの道隆寺の仁王門が現れる。 第77番 道隆寺
仁王門も仁王像も四国霊場で最大級といわれ、門をくぐれば、その前方には、高さ1mほどの、優しい笑みを浮かべた観音像がずらりと並んで、参拝者を出迎えてくれる。 そもそも道隆寺は、奈良時代に起源をもち、霊験あらたかな眼なおし薬師を祀る多度津の大寺である。境内の正面に本堂、右手に大師堂、鐘楼、多宝塔、妙見宮、地蔵堂、観音堂などの伽藍が建ち並び、200mほど離れたところに本坊と護摩堂があって、繁栄時の面影が偲ばれる。 さてさて、ここの見所は?
境内には優しく美しい観音さまたちが、これほどたくさん並んでいる札所は珍しい。境内の観音像は、正確に数えるのは難しそうであるが二百七十余体あるそうだ。西国三十三、坂東三十三、秩父三十四観音、これに四国八十八ヵ所など日本全国の霊場ゆかりの観音、水子の霊を供養する観音像、交通安全の千体観音像。それに変わり観音?として、生死の境をさ迷う人を生に戻す、といわれている「戻り観音さま」までいらっしゃる。他に、大師堂の前には弘法大師像と、その前に膝まずき両手をさしのべる遍路の開祖衛門三郎の像があり、右手を耳にあてている姿がかわいい「愚痴きき地蔵さん」には、日々、愚痴がある方は、この際ぜひ聞いてもらってはいかがでしょうか。それにしても、観音さまや、地蔵さまや、石像のオンパレードで、壮観な光景が境内には広がっている。 そして、ご利益は?
何たって!「眼なおし薬師さま」である。目の病に霊験があるという潜徳院殿堂は、本堂裏手の左奥に建ち、丸亀京極藩の御典医京極左馬造公を祀っている。公は幼少の頃かは盲目だったが、薬師如来の慈悲によって光を得、その後医学を学んで御典医となり「眼科の達人」と言われた。公は死に際にして「我魂魄を道隆寺に留め世人を救わん」と誓願し、境内にある潜徳院殿堂に祀られた。その後、自分の年齢だけ「め」の字を列記した眼病平癒の祈願札を堂内に納める人が絶えず、「眼なおし薬師さま」として、眼病に霊験あらたかな札所との信仰を集めている。 これで、今朝から7札所をお参りしたことになる。あれほど痛かった足マメも、有難いことに、いつしか痛みは遠のいていた。欲張りだが、本日はもう一札所頑張ることにする。春とはいえ、日も暮れかかる、急がねばならない。
多度津は、古来より交通の要衝として栄えた町で、四国鉄道の発祥の地、高松と松山を結ぶ予讃線と、高知へ向かう土讃線の分岐・中継点であるため広い操車場を持つ駅である。線路を跨ぐかたちで多度津駅へ。さすが四国鉄道の発祥の地だけあって、SLが駅のシンボルとして飾られていた。予讃線は運行本数も多く、快速まで運行されており、高松との駅間ではかなり便利な交通機関である。列車の待つ間、今日の宿、ホテルサンルート瀬戸大橋に予約を入れた。駅の列車発着時には「瀬戸の花嫁」がメロディーとして使用されており、宇多津駅へと向かった。 宇多津駅前の予約ホテルに荷物だけを置いて、郷照寺へ向かった。午後4時過ぎで納経には十分間に合いそうであるが、突然ポツリポツリと雨が降り出してきた。雨具は持参していないので心配したが、幸いすぐに止んだ。ホテルから1kmあまり、ほどなく山門に着いた。
第78番 郷照寺山門をくぐって、坂道や石段を上って行くと納経所があったが、はやる気持ちを抑えて、右折して本堂へ向かう。本堂の二層の屋根の形は、東大寺などの奈良の寺院によく見られる奈良様式の造りで趣をそえる。大師堂は、本堂脇の石段を上がったところにあって、お堂の中に入れるよう開放してあるので、大師像を間近で参拝できる。
そもそも郷照寺は、一遍上人により中興され、真言宗とともに、時宗の両宗派を奉持することになり、札所中で唯一の宗派を超えた寺として、弘法の法灯を絶やすことなく人々の信仰を集め、「厄除けうたづ大師」として親しまれている。 さてさて、ここの見所とご利益は?
金色の観音像の足元にある階段を下りると「万躰観音洞」、冷気と霊気を感じる地下洞の奥行は、大人の足で100歩前後か。壁には、信者から奉納された1万体を超える観音像が整然と並び、暗闇の中でにぶい光を放っている。 もう一つ、本堂に向かって右側にある、やさしい表情をした石仏は、「さぬきの三大ぽっくりさま」の一つといわれている。その顔は下向き加減で、目を閉じて眠っているようにも見える。三大とあるので、他の二つのポックリさまを讃岐で探したが、どこにも見当たらないのである。多分3体並んでいる石仏が3大ぽっくりさまと思われる。 おまけで、「お身体におさすり下さい。 病気平癒及びいろいろなお願いをかなえて下さいます。」と説明書きがある「撫で仏さま」がいらっしゃった。 境内からは宇多津の町並み、瀬戸内海が一望できるのでゆっくりしたいが、納経時間の制約もあるので、すませて札所を早々にお暇した。これで無事に8札所を回り終えたが、これで良かったのか、どうか反省だけは残る。宿に戻ってお風呂に入って、気になる足の指のマメを調べたらつぶれて、固まりかけていた。「これで遍路もお終いかな?」と、覚悟したときもあったが、どうやら明日も大丈夫のようである。ビジネスホテルであるが、お遍路さんには、いろんなサービスが付いていた。夕食をすませて、コインランドリーで洗濯をすませて、明日も早立ちなのでコンビニへ買出しに。忙し過ぎて、楽しい夜の宇多津はとても望めそうもない。
参考文献『週間四国八十八ヵ所遍路の旅』(講談社) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|