扉から少し離れた暗がりに、鎌足が立ったまま、うな垂れていた。
中大兄皇子が出てくると、黙って礼を取る。
「鎌足、すべて終わった」
「はい・・・ 皇子さま、大変なお役目を押し付け、申し訳ありませんでした」
「本当に、難儀なことを押し付けてくれたものだ」
中大兄皇子は、笑いを浮かべようとしたが、それは途中でぎごちなくゆがんだ。
「これしか、道はなかったのだな、やはり」
慌ててそらした瞳に、きらりと何かが光ったような気がして、鎌足はますます深く頭を垂れた。
中大兄皇子は、足早に立ち去る。
鎌足は、その姿勢のまま、扉の向こうに取り残された、か細い姿を思った。
心の中で、中大兄皇子にも、有間皇子にも詫びていた。
しんとした闇が、すべての音を吸い込んで行く。
|
| * * * * * |
有間は、一人座ったまま、目を閉じていた。
ようやく終わった・・・そう感じた。
これで、すべての楔から解き放たれる。
もう、自分の中の恐怖や怒り、哀しみと戦わなくてもいいのだ。
まるで、硬い殻に閉じ込めるように、感情を抑え、人の心を操り、冷酷な策士になりきる努力をしなくてもいいのだ。
ふわりと微笑んだ有間の顔は、静かで、儚く、そして驚くほど幼く見えた。
表情を固く覆っていた氷の仮面が溶け出し、傷つきやすくやわらかい素顔が覗いたようだった。
自分は、何者として死んでゆくのだろう。
そう考えた時、突然、頭に歌が浮かんだ。
ここへ来る途中、磐代の浜で詠んだ歌だった。
「・・・ ま幸くあらば、・・・ また還り見ん」
ぽつりとつぶやいたとたん、膝に置いた手の上に、何か暖かいものが滴り落ちた。
はっとして目を開ける。
涙が、幾筋も頬を流れていた。
有間の記憶に、松の葉の緑が、そしてその砂浜の向こう、海原の青が、くっきりと鮮やかに蘇った。
「美しかったな・・・ なぜだろう、今になって、ようやく思い出した」
有間は、涙をぬぐうこともせず、ひたひたと胸に寄せてくる様々な思いに、身を任せていた。
|
| * * * * * |
数日後、額田王のもとには、有間皇子が最後に遺した歌があった。
監視の者は、頼まれた通り、有間の歌を紙に書きとめ、それを額田王に届けてきたのだ。
同時に、有間の最期についても、知らされた。
藤代の坂で、絞首されたのだと・・・
「皇子さま・・・」
額田王は、涙ながらに、有間の歌を読んだ。
二編あった。
どちらの歌も、さりげない調子で、旅の無事を願っている。
けれど、その底に、どれほどの切なる思いがこもっていたことか。
有間が、旅立つ時すでに、死を覚悟していたのだろうことは、額田王にも容易に知れた。
いや、もっとずっと前からかもしれない、と思った。
「皇子さま、すばらしい歌をお遺しになって・・・ きっとあの方も、この歌を見て、どれほどしみじみなさることでしょう」
額田王は、有間が目の前にいるかのように語り続けた。
「皇子さまはご存知なかったでしょうけれど。あの方は、ずっと、皇子さまの歌を愛でておいででした。お忙しい方なのに、私を見かけるたびに、皇子さまの歌をお聞きになりたがった」
有間の歌が記された紙を、やさしく指先で撫でる。
まるで、そこに逝ってしまった人の魂が宿っているとでも言うように。
「私が皇子さまに、あんなに歌をねだったのは、あの方にお聞かせしたかったから」
白い頬が、微笑みにやわらいだ。
「もっともっと、皇子さまのすばらしさをお教えしたかった」
額田王の目に、新たなる涙が溢れる。
「あの方、中大兄皇子さまに・・・」
額田王は、細い指先で、涙をそっとぬぐうと、有間の遺した歌を、ゆっくりと読み上げた。
ふくよかな美しい声が、晴れ渡った空へと流れてゆく。
磐代の 浜松が枝を引き結び ま幸くあらば また還り見む
ふいに、額田王の脳裏に、緑濃い松の樹が、そして青い広々とした海原が浮かんだ。
その海の面を、まっすぐ滑るように有間の姿が進んで行く。
ああ、行ってしまう、と額田王は思った。
声をかけようとしても、何の言葉も浮かばなかった。
ただ、ひどく美しい光景が、胸をしめつける。
ぽろぽろと、額田王の瞳から涙が零れ落ちた。
果てしない瑠璃の海の向こうへと、なつかしい有間皇子の、たおやかな後ろ姿が消えて行くのを、今、額田王は見送っていた。
(完)
|
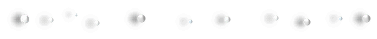 |
  後書きはこちら 後書きはこちら  |