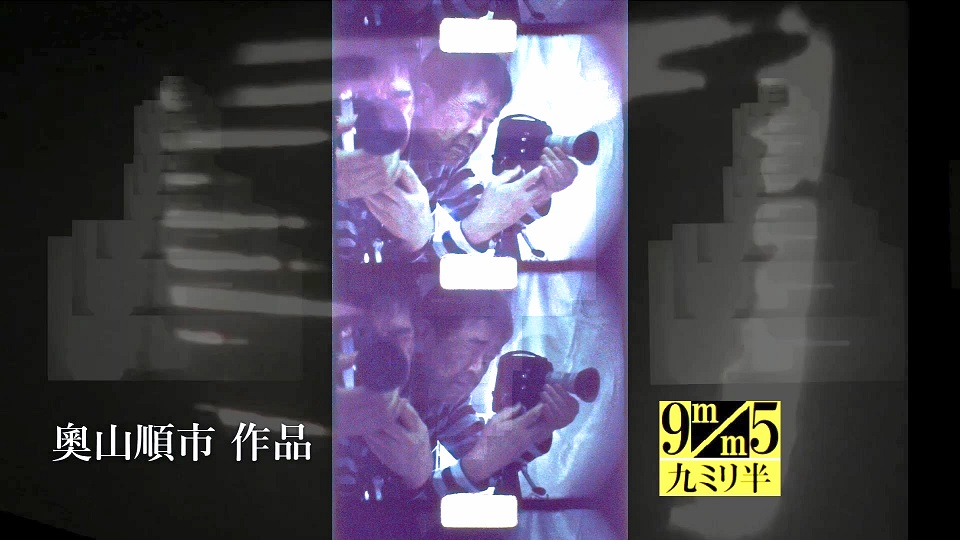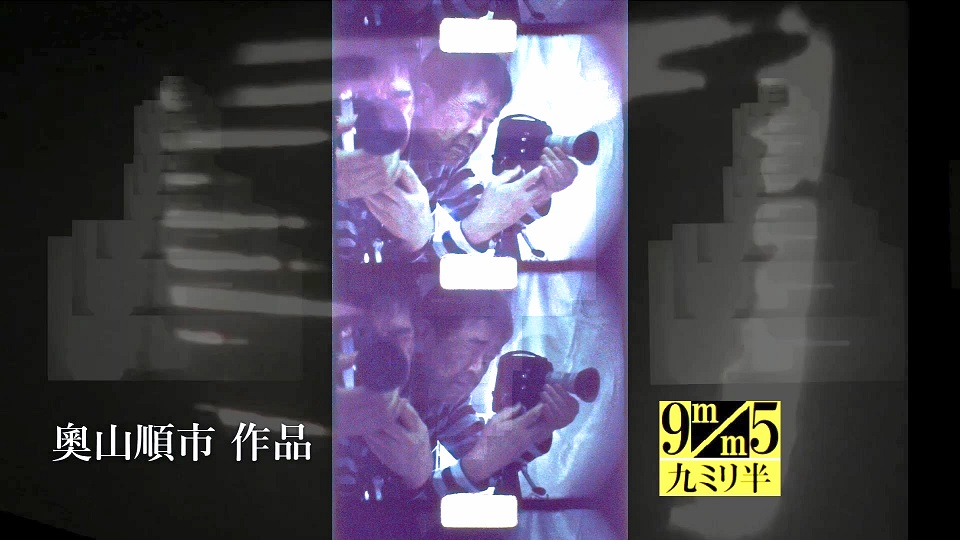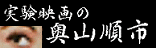�@�@
�@�@
�@�@
�@
|
|
|
|
|
|
���̐́A�܂��f��ɉ���������������A
9,5�~���E�t�B�����́A���{�ł͋�~�����ƌĂ�e���܂�Ă����A
�W�~���E�t�B�������o�ꂷ��܂ŁA���^�f��̑㖼���ł������B
�@�@�@�@�@
|
����i�R�����g��
|
2019�N�ɊJ�Â��ꂽ��9,5mm�����}���t�B�����E�t�F�X�e�B�o��2019��
���̍�i�́A���̃t�F�X�e�B�o���̗l�q���A�f�W�^���ł܂Ƃ߂��B
|
���ł́A�قƂ�ǂ̐l���m��Ȃ����̃t�H�[�}�b�g�ɂȂ��Ă��܂�����~�����B
�S������80�N�ȏ���O�Ȃ̂ŁA�������Ȃ��B
��㐶�܂�̍�҂��A���炭�́A���Ђ����̏�����B
|
�������A�t�B�����̒����ɑ��茊������ׁA��ʂ̃T�C�Y���A16�o�ɔ���قǂ̑傫���Ȃ̂��B
���̓Ɠ��̍\�����A�傫�Ȗ��͂ɂȂ��Ă���B
|
<9,5mm One-man Film Festival 2019>�ł́A�n���h�N�����N�̋@�ނ��g�p�B
����ŃL�[�L�[�Ƃ��Ȃ�A��������~�܂�����̃��[�^�[��A
�ڐG�s�ǂœ_�������������̃����v�ȂǁA
�Ђ�Ђ�̏�f��ł������B
|
9,5mm one-man film festival 2019�̃v���O����
|
�w�l�Ƌ�~�����x�ӏ܂̂����� ___ ���R���s
________________ ________________
��~�����Ƃ́F
�t�����X��PATHE�Ђ�1922�N�ɊJ��������~�����f��́A��O�ɉh�����z�[�����[�r�[�ŃT�C�����g�ł������B
�J�����͎�i��Ƀ[���}�C�ɕς��j�A�f�ʋ@����i��Ƀ��[�^�[�ɕς��j�B
�J�^�J�^�Ɖ�鉹�����Y�������މƒ�f�ʉ�ł́A�~���@�ōD���ȃ��R�[�h�������Ȃ���A�Ϗ܂��邱�Ƃ��������悤���B
��~�����Ƃ́A�t�B�����̒����ɑ��茊���J���Ă���A��ʂ��L���m�ۂł��邱�Ƃ��傫�ȓ������i��ʃT�C�Y��8.5�~6.5mm�j�B����́A16�~���̉�ʃT�C�Y(9.6�~7.01mm)�ɕC�G����B
���́A����Ȏ���̏��^�f��Ɏv�����͂��A���̃t�H�[�}�b�g���A�t�B�����Ő��삷��Ō�̎����f��ƌ��߂��B
��~�����ō�i����鎖�ɂ���F
���A�o����͈͂ŋ�~�����ɓ������鎖�B�e�[�}�͂��ꂪ�S�āB
�����������ɓ����@�ނ͌����Ă���A���t�B�����������B
�ǂ�������t���邩�A�C�̒����b�������B
�ł炸�A�@�ނ̊m�ۂƐ��t�B�����̓���Ɏ��Ԃ������A�Â��B�e�ς݃t�B���������I�[�N�V�����ōw�������B�����Ƃ����ԂɎO�N���߂��Ă������B
�Ă̒�A�Â��f�ʋ@�͓��肵�Ă������ɓ������A�ł܂��Ă����B
�ŏ��͊����i�ł��A�����ɕ��i�����A�����Ȃ��Ȃ�B
�d���R�[�h���z���R�[�h���{���{���A�f�ʃ����v���ʓd���ē_�������Ǝv������A�����Ƃ����Ԃɐ�Ă��܂����B
�����������������Ƃ��Ȃ��A��������̎�f�ʋ@�́A���K�ɓ����Ă���Ǝv������A�����ȃ{���g���O��Ă��܂����B
�U���Ńi�b�g�������Ɋɂޏ�Ԃ������̂��B
��͂�u���L�̈������Ǝ����B�����ɂ˂����b�N�Ōł߁A�Ƃ肠�����́A���݂��~�߂��B
���Ȃ݂ɂ��̓����̃l�W�R�̋K�i�͌���̂��̂ƈقȂ邽�ߓ���͂قƂ�Ǖs�\�B�������Ȃ��ėǂ������Ƌ����Ȃł��낵�����̂��B
�J�������������B�{�f�B�[�͒ɂ݂����Ȃ��������A�����Y���܂��Ă�����A�t�B��������⊪���ɓ��������ƈ�ؓ�ł͂����Ȃ��Ǝv�����B
�����̏C���Ǝ҂͏��Ȃ��A�����Ă��A�d�b�ł̌��ς���͂��Ȃ荂�z�������B
���t�B�����́A�����炭���{�Ō�̈�{�炵����~�����̃J���[�E���o�[�T���E�t�B�����i�����s���̍ɕi�j���A���g���ʔ̂œ��肵���B
�������A������100�t�B�[�g�i���x16�R�}��4���قǁj�Ȃ̂ŁA�B�e�ł�����e�͌����Ă��܂��B
�l�����3�����x��16�~����i�ł��A100�t�B�[�g����{�ł͑���Ȃ��B�e�X�g�B�e�ŏI����Ă��܂��������B
���肵���J�����̒��Ɏc���Ă����A�Â����m�N���̐��t�B�������A�f�ނƂ��Ďg�p���邱�Ƃɂ����B�I�[�N�V�����œ��肵���z�[�����[�r�[���A���p���邱�Ƃɂ���B
�������ƏW�߂��@�ނ̑����͐Ƃ��f���P�[�g�ȃK���N�^�ŁA�тɒZ���F�ɒ����Ȃ̂����A�Ƃɂ����i�߂邱�Ƃɂ���B
��҂��A�ϋq�Ƃ��Ă̍�҂����Ɍ������i�Ɍ������F
�����āA��Okuyama Jun�fichi�fs 9,5mm One-man Film Festival 2019>�Ƃ��Đ��삪�X�^�[�g�����B
������ޗ��ō��ƌ��߂Ă����̂ŁA�ۉ��Ȃ��Ƀ��[�v�E�t�B�����ō\�����鎖�ɂȂ�B
�����Y�����œ��肵���J�����́A�p�����i���[�J�[�s���j��C�}�E���g���B
�����16�~���J�����̃����Y�����p�ł���̂ŁA���p�̍L�p�����Y���Z�b�g�B
���C����i�w��~�����̑��茊�x�́A����ŎB�e���邱�Ƃɂ����B
�f�W�^����i�w�l�Ƌ�~�����x�̃g�b�v�J�b�g�i�Z���t�|�[�g���[�g�j������ŎB�e�B
16�~���J�����ɋ�~�����t�B�������Z�b�g���ĎB�e�����i�wFrameless 9,5�x�ł́ABOLEX 16�ƁA��������KODAK 16 model E�i���P�j���g�p�B
���t�B�����͂����Ŏg������B
�c�O�Ȃ���A�|�s�����[��PATHE���̋�~�����J�����i�Œ背���Y�j�̏o�Ԃ͖��������B
�����I�Ȋ��ŁA�Ō�̃t�B������i�������F
�t�B�����̓��܂�n�����ĉf�����������i�́A�w�c���9,5�x�A�w�`���t�H�[�J�X��~�����x�B
�t�B�����̓��܂��X�v���C�T�[�ō���ăC���[�W�ݏo������i�wSon optique 9,5�x�́AELMO��16�~���f�ʋ@�Ƒg�ݍ��킹�ăT�E���h��i�Ɏd�グ���B
�t�@�E���h�t�b�e�[�W����������i�w�p�ӁI�x�Ɓw�旬��9,5�x�́A��f�ʂŏ�f�B
�w9,5��16�x�́A�X�k�P�̃_�u��8�t�B�����i16�~���Ёj�ɓ\��t���A
�J���[�B�e�����w��~�����̑��茊�x���X�k�P��16�~���ɓ\��t���āA
�f�ʑ��x���R���g���[���ł���NAC���̉�͗p16�~���f�ʋ@���g�p���ĉf�ʁB
16�~���J�����ŎB�e�����wFrameless 9,5�x�́A���[�^�[�ƃn���h�N�����N���p��PATHE���̉f�ʋ@�ŏ�f�B
�Â��t�B�����̒[�ꂩ��������i�w������~�����x�́A��̋�~�����f�ʋ@�ƌ����ɂ�60�N���炢�O��8�~���f�ʋ@���g�p�����B
���[�^�[������Ă����̂ŃX�s�[�h�����X�ɐ����A�ւ����Ă䂭���܂���ۓI�������B
���[�v�E�t�B�������Z�b�g�����f�ʋ@�́A���ɂ������ē��i�i��{�j��S���B�f�ʋ@�̌��ƁA���e�ɍ��킹�ĐU�蕪�����B
������ċꂵ�����ȃ��[�^�[���̉f�ʋ@�A���ƃX���[�X�ȃ��[�^�[���̉f�ʋ@�A��̌y���Ȏ��ԉ��̉f�ʋ@�A���i������Ă���悤�ȃK�T�K�T���̉f�ʋ@�ȂǁA�l�X���B
��f���@���f�ʋ@���F�X�B�f�ʋ@�Ƃ̃R���{����������A�t�B�������X�N���[���ɎN������ƍQ�������������B
�܂��ɁA���C�u�������Ղ�̃����}���E�t�F�X�e�B�o���ł������B
�f�W�^���Ŏc���Ƃ́A���ォ�F
�f�W�^����i�w�l�Ƌ�~�����x�͍��̏��A��~�����t�B�������g�p�����A�Ō�̎����f�悩������Ȃ��B
�Q�ƁF
�i���P�j�����A���X���Ȃǂ��g���ăA�p�[�`���[�Q�[�g������čL���A�T�E���h�g���b�N�����ɂ��I���o����l�ɉ��������J�����ł���B
2001�N��16�~����i�wSync pic �����I������Ă��特����������x�𐧍삷�邽�߂ɉ����B
�NjL�F�[�[�[
|