 |
 |
|
第一小学校裏の水路…サラサラときれいな水が流れています
|
清楚なシャガの花
|
本日は議会運営委員会(議運)が開かれました。案件は3月議会開会中の民生消防常任委員会および本会議(後半)における発言についてです。昨年9月(そもそも、えらい前の話!)○○議員が「自民党・公明党の悪政について行政はどう考えるか」と発言したことにわだかまりが残っていたのかどうか知りませんが、△△議員が今議会で発言された「暴挙」と「差別」の言葉はけしからぬと言い出したことから、議運が開かれたというわけです。
「暴挙」が指している事象は「就学前の子どもの教育と保育環境の整備について(基本方針)」に係る請願審査において、第2号請願の紹介議員出席を民生消防常任委員会が拒んだことです。また「差別」については私が請願者であり紹介議員を務めた第1号請願に比して、2号請願の紹介議員が出席を果たせなかったことを指しています。私は二つの請願が紹介議員の下で慎重審査を行うのは当然だと思っていましたから、「暴挙」の文言には全く抵抗ありません。
一方の「差別」については紹介議員としての役目を果たした私としては、正直あまりよい気分はしません(私の預かり知らぬことなのに、「なんで南部だけ紹介議員になれたん?」といわれているようで)。しかし、まあ○○議員がそう感じて発言したのなら、それは仕方がないことです。議員は自らの言葉がどのような影響力を持ち、どう波及していくかを踏まえて発言しているはずですから、自身への評価も覚悟の上で行っているはずです。それだけ議員の発言は重いものです。従って今回のように△△議員が、気に入らないから不適切だからと拳を振り上げても仕方がないのです。議会の“決まり”では次の2つの理由に合致しなければ、拳は空を切るのみで終らざるを得ません。
理由は2つあります。1つは議会の開会中にのみ、発言の訂正や削除が可能なことです。しかも発言者自らが訂正等具体の文言を会議の中で議長に申し出を行い、議長が全議員に諮って「異議なし」と認められて、初めて発言の変更が可能になるのです。この点からすると3月議会が閉会した今頃になって、問題にすること自体が可笑しいのです。「暴挙」の発言時も「差別」の場合も議場で野次はたくさん飛んだけれど、議長は休憩を取り議運を開くように求める正当な手続きを行いませんでした。
もう1つは「暴挙」も「差別」も、それらの言葉自体は他者を侮蔑したり差別を表す言葉(差別用語)ではないということです。発言者の申し出がなくても議長の権限で整理が出来るのは差別用語・侮蔑用語のみですから、この点においても今回△△議員が指摘する「けしからぬ発言」は削除等には当たらないのです。
ちなみに3月議会で「暴挙」と発語したのは、○○議員のほかに囗囗議員もいました。囗囗議員は本日の議運で委員外議員として発言を申し出ていましたが、私とK議員が賛成したのみで後の3議員が反対したため叶いませんでした。ということで議運は終了しましたが、委員長が言った「本会議での発言について、よく考えていただきたい」との“お説教”が目的なら、それは議運の役割ではないんじゃないの?と言いたいです。
「あの発言はどうかと思うよ」とか「訂正を申し出たほうが良いのでは?」とか、そんなアドバイスは個人的にヒラバで直接出来ること。どうしても全員の問題としたいのなら、議員全員協議会或いは会派代表者会議で話すことでしょう。それらをすっ飛ばして、いきなり議運とはならないはずです。議運は法制化された正規の委員会ですから、振り上げた拳を自ら直ぐ降ろすことになるような、あやふやな提言は行わないで欲しいと思います。
結局のところ、委員長の「結果は取り消しや罰則は出来ない。扱いそのものは言葉について、今後十分注意して発言していこうということしかない」が結論です。そんなことは最初から分かりきった話です。私が会議の最初に発言したでしょう。「今日の召集の意味が分からない。発言の是非を含めての議論を行い、結論が出たところでどうするのか。(「暴挙」「差別」が載った)会議録の訂正も出来ない。これは議運ですることなのか。全員協議会の場でもすればよいことだ」と。昨今どうも安易な“揚げ足取り”や“言葉狩り”が横行しているような気がしてなりません。
さて、会議の終わりにまた新たな提起がありました。「3月議会一般質問の中で行われた『それは嘘ではないか』という発言は、相手の人格を損なうものであると思う。確たる証拠を持って発言に望むべきで、推測で発言すべきではない」と、またまた△△議員が発言しました。この件については、私も議場の質疑応答を聞いていて違和感を持った記憶が残っています。住民から提出されたある文書を巡って、「渡した」「いや貰っていない」の問題が生じている事象ですが、後日のご報告にしたいと思います。
 |
 |
|
第一小学校裏の水路…サラサラときれいな水が流れています
|
清楚なシャガの花
|
本日の本当の日付は5月29日です。あと2日で1年の後半に突入とは!月日の速さに比して日記の遅々とした歩みには、今更ながら愕然(ちょっとワザとらしいですね)とします。ただ今日記は5月分と4月分を混ぜこぜでお届けしていますが、これから暫くはタ〜ッと走り書きで、とにもかくにも4月分を終了してしまいたいと思います。ちなみに4月は11日・12日・16日がアップ済みです。月の前半は栃木県の次男宅へ行っていましたから、余り書くこともありません(3月10日分として、4月12日の日付でミニ旅行記を載せています)。そこで4月後半からの日記を再開することにしました。50日も前の“日記”にお付き合いいただくのは、なんともはや心苦しき限りですが、どうかお許しください。
私は島本町の小学校および中学校は狭い町域に存在していることもあり、また教職員の日頃の取り組みからも結構連携が取れているほうだと思っています(勿論今後幼稚園・保育所も含めて、より連携を深める必要性はまだまだありますが)。教育委員会は2006年度と2007年度において文部科学省の研究指定を受け、一中と一小および四小における小・中連携教育の実践研究を行ったところです。今後は二中校区(二中と二小および三小)における連携の実践を目指すと言いつつ、いつの間にか「連携」が「一貫」に変わってきました。
もっとも昨今議会での自由民主党クラブ議員や山吹民主クラブ議員の小中一貫教育に係る発言を聴いていると、校種間の連携ではなく小中9年間のカリキュラムに則った新たな一貫校の創出を求めているように思われます。また学校の大規模改修等に伴う支出削減のために、学校数の減を図る目的で小中一貫校の実現を質しているのではないかとも感じています。
勿論未来永劫2つの中学校と4つの小学校が保障される根拠を、今私が示せるはずもありません。しかし少なくとも前述のような議員たちの発言に急かされて、小中一貫校の実現に向かってバタバタと事を進めてはならないと思っています。一貫校は教育内容の根幹に手をつけることです。教育委員会や学校の内部のみで制度をいじるだけでは済まない大きな変革です。時間をかけた丁寧で慎重な、なおかつ広範囲にわたる検討が必要です。
とまあ、こんなことを考えつつ協議会を傍聴していました。ところがこの会議の内容が、私にはよく解からなかったのです。教育推進課の職員と小・中学校の先生たちが出席しているのですが、「連携」が「一貫」に変わった理由やそれぞれの違いや子どもたちにどんな影響があるのかとか、保護者はどう思っているのか等々の片鱗でも知りたいと思ったのですが、残念ながら的外れでした。会議は傍聴人のためにあるのではないのですから、“身内”同士で解かれば良いということなのでしょう。おまけに会議開会の時間が直前に1時間繰り上がったり、会議の部屋を開会時に変更したりで、私としては少々「ムムッ?」と感じてしまった傍聴でした。
しかし例え居心地が悪くても小中一貫教育や一貫校に係る情報は大切ですから、今後も傍聴は必要だと思っています。なぜなら先に述べた“大会派”議員たちの“お尻たたき”もありますが、教育委員会の事務局トップが4月の人事異動に際して書き残した引継ぎ書には次のように記していることから、「要注意」と私は感じているのです。
引継ぎ書の文章には「平成20年度に向けた懸案事項に関する連絡調整と取りまとめ」の項目中に「学校施設の耐震化工事および外壁塗装や屋上防水工事に関する大規模修繕計画を、学校施設の現状と課題を的確に把握した上で学務・施設担当に作らせる必要がある」と書かれています。これはこれで当たり前の内容なのですが、次に続く文章が引っかかります。「(前段の内容)に絡んで、今後の適正な学校数や学校を整理統合する際の方向性=小中一貫校を作るなどを明らかにするための、教育委員会の諮問機関としての『(仮称)今後の学校教育のあり方に関する審議会』を設置し、検討を始める必要がある」と示しています。
引継ぎ書にどれほどの拘束力があるのか分かりませんし、現教育次長のもと教育委員会の意思がどのように変わるのかも未知数ですが、少なくとも学校現場にいた元校長であり、再び小学校校長にもどった前教育次長が書いた引継ぎ内容です。注視せざるを得ないのは当然でありましょう。
 |
|
来客にも気持ち良く整えられている第一中学校の玄関
|
新年度に入って初めての代表者会議です。4つの案件について話し合いましたが、議論が集中したのはやはり「会派室の設置について」でした。私は会派室については一貫して反対をしています。町の財政が厳しいのに、なぜ自・公・民は会派室を求めるのか?なぜ当局は、こうまで3会派の言いなりなのか?おまけにパソコンもプリンターも会派ごとに支給するなんて。大阪府内でそのような大判振る舞いをしている町村はありません。しかも来春は選挙です。1年を待たずして、議員数も会派数も変更する可能性があります。
本件については3月11日の日記に詳しく書いていますが、3月後半議会の2008年度予算の採決直前に、私は予算から会派室に関する費用の削除をすべきと会派名で修正動議を提出しました。残念ながら動議は通らず、450万円を含む新年度の予算は可決してしまいました。
そこで4月3日、私は町長に対して「申し入れ書」(日記の末尾に掲載)を提出しました。「予算通りに会派室設置がされても、私の会派は使用しません。当然パソコン等の機器類も必要ありません」と申し入れたわけですが、「予算が可決すれば渋々でも従うだろう」と思っていた3会派は見込みが違ったのでしょう。本日の会議で再三の確認を行うことになったと思われます。
私は今日の会議では、3会派から450万円を縮小するとか或いは次期改選後にするとか、そういう改善策が出されてくると思っていました。ところがS議員は「会派室を造ったら(反対した議員は)会派室を使うのか。使わないのであれば造る必要がない」と発言しました。そりゃその通りなのです。現に私の会派は「使わないから造るな」と自発的に申し出ているのですから・・・。でも、なんというか・・・、「あなた達から言われたくないわ!」「そこまで言うか!」と非常に気分が悪かったです。
このような発言には、自分たちと異なる意見を持つ少数者に対しての配慮は全く感じられません。私が十数年間議員をやってきた中でも、昨今は特にその傾向が強くなってきているように感じます。悲しいことですし、大いなる危機感を感じています。
それでは最後に「申入書」の内容をお知らせします。
|
2008年4月3日
島本町長 川口 裕様 「人びとの新しい歩み」 申し入れ書 「人びとの新しい歩みに対する会派室整備工事費及び備品購入費の支出は行わないでください」
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ただ今日記の進行状況は、3月分が10日あたり2月分は20日あたりを漂っております。ちなみに本日の本当の日付は4月16日です。もとよりあっち飛びこっち飛びの“時空を超えた”雑記帳みたいな日記ですが、今回は最新日、つまり「本当の日付」のもとお届けします。
今日16日は午後から議員全員協議会が開かれました。町から数件の報告事項がありましたが、その中でトンデモナイ事故が15日に起こったことがわかりました。町立第四保育所で朝のお茶の時間に、牛乳アレルギーを持つ2歳児に保育士が牛乳を与えてしまったというのです。
子どもはすぐさま開業医の診察を受けましたが、点滴中に嘔吐症状と発疹が現れたため、救急車で高槻病院に搬送され入院となりました。子どもの症状が気がかりなのですが、母親は怒りのためか職員と会話を交わすこともなく「症状は安定している」としか話さなかったそうです。
実は第四保育所では昨年の1月に、今回と全く同様の事故が発生しています(先回は痙攣を起こした子どもが3晩入院しました)。私たちの頭をよぎった不安が的中してしまったのですが、あろうことか、同じ子どもが同じ保育士の同じ誤りによって再び被害にあってしまったのです。議員全員が一瞬言葉を失いました。
民生部長以下担当職員はただただ頭を下げ「申し訳ない」と繰り返しますが、議員たちの怒りは相当なものでした。またこのような重大事の報告に際して、文書の1枚も用意せず口頭で済ませている姿勢も大いに問題があります。さらには迅速な報告という点においても、昨日のうちに議会への第一報があってしかるべきでした。
大人の、しかも保育の専門職に小さな子どもが苦しい目に遭わされ、一歩間違えば命の危険にさらされる状況にあったことを思うと、かわいそうで胸がつぶれる想いで一杯でした。昨年の事故後作成した「改善マニュアル」は何の役にも立っていなかったと、私は怒りを通り越して情けなくなりました。
「組織のタガが緩んでいる。同じことが起こるということは考えられない」との声に、町長は「申し訳ない、悔しい。重大な任務を担っている認識が希薄になっている」と詫びました。私は事故の詳細な経緯を記載した文書及び保育所における全ての事故内容が分かるものを至急提出することを求めました。
正式な報告書がない中で誰が何をして、或いは何をしなかったかを特定することはしないほうが良いと思いますが、当日の職員体制は次のような形になっていました。当該の2歳児クラスは14名ですが、2名がお休みで当日は12名の子どもがいました。うちひとりが障がいを持つ子どもでした。職員は1名が3月に退職したベテランの再任用職員で、後の3名は臨時職員です。ちなみに当日は障がい児加配の臨時職員が休んでおり、フリー保育士が障がい児の担当についていました。
緊急のお知らせもうれしいことならお届けのしがいもありますが、ため息をつきながらキーを叩くのはつらいものです。今は何よりも、お子さんの一日も早い回復を願うばかりです。また詳細が判り次第後報告いたします。
 |
 |
| ふれあいセンターの桜は今が見ごろです | JR島本駅西側のレンゲ畑は19日から開園します |
日記を書いている本日は6月5日です。立夏も過ぎ、一昨日は近畿の梅雨入り宣言が出されています。しかし日記は、いまだ春爛漫の4月中旬あたりをさまよっています。季節はずれになってしまいましたが、レンゲ畑開園式の様子や鯉のぼりが泳ぐ田園風景の写真を撮っていますので、見てくださるとうれしいです。
11時から、桜井西側の農地でレンゲ畑の開園式がありました。私は毎年行っていますが、年々参加者も増えて春の一大セレモニーになってきたように思います。テープカットだけはなんだか大げさで、見ていて未だに恥ずかしい気がします。しかしレンゲ畑を開放してくださる農家の方々を始め、レンゲ畑実行委員会の皆さんの尽力に応えるためにも、華やかに盛り上げる演出も必要なのだと思うことにしましょう。
関係団体の委員方や議員たち、そして何故か?当セレモニーには律儀に勢ぞろいする役場の三役(町長・副町長・収入役)と、教育長はじめ部長・次長たちを後ろから眺めながら「“レンゲの力”は大したもんやなあ〜!」と、私は改めて感じました。まあ、これらの人たちもさることながら、今年はとてもうれしい大歓迎の参加者たちが来てくれました。島本高校ブラスバンド部の生徒たちと第一幼稚園の園児たちです。軽快なバンドの響きと元気一杯の園児たちの歌声が、のびやかな田園の春空に舞い上がっていきました。
開園式の後は近くの桜井公会堂で「皆さん、採れたて筍を召し上がれ」とお誘いがあるのですが、食い意地の張った私はふらつく思いを断ち切って(やっぱ、タダで飲み食いはできませんから)、新駅の自由通路に掲示してある第三小学校の子どもたちの作品(昨年のレンゲ畑を描いた絵)を観に行きました。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
午後は1週間前に開館した歴史文化資料館へ行きました。2時から開館記念講演会「天平の時代と島本」が開かれます。講師は大阪府文化財センター理事長であり奈良大学名誉教授でもある水野正好さんです。参加者約80名は事前申し込みし、抽選で当った人たちです。私もその中の幸運者の一人でした。
講師の水野先生は大変有名な学者さんですが、さすがにそのお話しぶりは全身から“歴史物語”がほとばしるといった印象を受けました(ちょっと早口なので、ついていけないところも多々ありましたが)。参加者の満足度は講演後のアンケートにも現れていました。
わが町の資料館については「他自治体では歴史資料館を閉じようかというところが多い中で、島本町での資料館開館は大きな朗報です」と言われた言葉が印象に残っています。先生はきっと「だから上手く運営して、充実した資料館のお手本になってくださいね」との心配と激励の気持ちを込めて発言されたのだと思います。
写真は、4月12日に行われた開館式典の様子を主に掲載します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
暗くなってからは、ふれあいセンターの夜桜見物に出かけました。今夜は竹工房の皆さんが、竹灯ろうで散策道を照らしてくれました。
 |
 |
今日の本当の日付は6月10日です。日記を更新しない数日間も、毎日30人前後の方々がアクセスしてくださっていました。申し訳なさとありがたさで一杯です。そしてなんと!なんと!このような気まぐれな日記でも、昨日には訪問者数が4万人を超えました。
2004年12月にホームページを開いてから1288日を経ましたが、そのうち日記を書いたのは870日です。本来なら毎日更新し100パーセントであるべきなのですが、達成率は68パーセントです。書いた(打った)文字数は約83万2千文字です。400字詰め原稿用紙では、2080枚書いたことになります。3年半で、この数字が多いと胸を張ることはとても出来ませんが、それでもボチボチと続けてきてよかったと思います。
ちなみに上記の数字は、私のパソコンの“管理人”が記録してくれていたものです。アクセス数はトップページのカウンターが知らせてくれますが、文字数のカウントまでは思いもよりませんでした。100万文字達成はいつになるのかな?と、少々意欲が湧いてきたような・・・。
それでは4月の日記に戻ります(早く4月を脱出したい!)。
標題の「ボランティア情報センター設立準備委員会」(以下準備委員会と言います)は、町長の施政方針にも述べられている「ボランティア情報センター」(以下センターと言います)を立ち上げるための検討を行っています。H21年度の設立を目指して、本日まで9回の会議が重ねられてきました。委員は社会福祉協議会(2名)、学校�・園ボランティア支援ネット(2名)、緑と花いっぱいの会、学校協議会、婦人協会、社会教育委員から各1名の計8名で構成されています。
本日の私の傍聴申し出が、会議9回目にして初めてだったようです。大抵の会議を傍聴している私ですが、当準備委員会のことはまったく分かりませんでした。分からなかったのは、知らされていなかったからです。公開の対象になる会議であるのに、庁舎内の掲示板及びホームページにも一切掲載されていませんでした。
また閲覧可能な会議録等も全くファイルされず、私が偶然会議日程を知り傍聴を願い出るまで、いわば閉ざされた会議であったのです。これらは担当課である生涯学習課の大いなる過失であり、私は強く反省を促しました。でも未だに改善されてはおらず、その認識度にはあきれてしまいます。ちなみに私は会議録8回分を、わざわざ情報公開請求で手に入れなければなりませんでした。
さて傍聴した肝心の議論の中身が、これまた良く分からないことといったら・・・。既に9回目の会議を迎えているというのに、「情報センターで何をするのかを明確にしていないのではないか。当町が暮らしやすく人に優しいまちになるには何をすれば良いのかを、まだ話し合っていないのではないか」といった意見が委員から出るほどでした。
かたや委員長は「情報センターはあくまでも情報の一元化を図るためのもの」とし、情報の収集�・提供に係るシステムの構築に重きを置いた発言を繰り返されていました(もっとも次回の会議における委員長の発言及び会議の進行は、随分改善されましたが)。センター設立の真のねらいが、生涯学習推進本部事務局のいう「住民参加の活力あるまちづくりのためには、町内各地域において住民が主体的にボランティア活動に勤しむ状況を創り出すこと」であるのなら、住民への情報提供は単なるネットシステムの構築で済む話ではありません。
今日は午前中が文化推進委員会、午後がボランティア情報センター設立準備委員会の傍聴と、教育委員会関係の2つの会議を傍聴した一日でした。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「桐が原」は若山台団地から尺代の集落に向かう途中にあります。かつては尺代地区の里山であり、今も小高い地形をなしています。ところが17年前にゴルフ練習場の建設計画が持ち上がり、「桐が原」の木々は殆ど切り倒されてしまいました。結局ゴルフ場は造られず、跡には土石がむき出しの広大な“禿山”が残されました。
事業者はその後採石許可を取っていますが、営業の実体も定かでなく「桐が原」はほって置かれたまま今に至っています。しかし、ほったらかしにされているのは土地の形状だけではありません。「桐が原」にかかる特別土地保有税が、なんと!4億9千万円近くも滞納になっているのです。
このような状況下にある「桐が原」に、昨年は地元尺代自治会から住宅開発の要望が出されました。町の回答は「開発には総合計画の変更が必要である。JR新駅開業に合わせて総合計画の見直しを行うが、桐が原の住宅開発についても新駅にあわせて検討を進めていく」というものでした(この内容については、昨年の6月14日付の日記で紹介しています)。
今年度から前倒しで始まった新総合計画策定に係る審議の中で、「桐が原」を含む市街化調整地域の線引き(調整地域を市街化地域に編入)が明確になるのかどうかは分かりませんが、新駅開業に“便乗”して開発が進むようなことはよくないと思います。
ところで「桐が原」には毎年大阪府の立ち入り調査が入っています。採石許可を与えている府と町と高槻警察署が合同で、今年は4月25日に実地検分を行いました。直ちに土砂災害を引き起こすような兆候は見られなかったものの、樹木の伐採や切土による弊害は十分に想定しておかなくてはならないと思います。写真は町職員が撮影した「桐が原」の現況です。
 |
 |
すみません、「一週間のご無沙汰でした」(昔々、テレビの司会者が番組の始まりで毎週言っていたような?)。この間は6月議会に向けての会派説明会があり、議会運営委員会が開かれ、一般質問の通告に四苦八苦しつつ、議案の下調べにも気がせいて、バタバタと日が過ぎてしまいました。
また6月議会の準備の合間を縫って傍聴可能な会議は殆ど出かけましたし、情報公開請求と公開された情報の閲覧・コピーにも結構時間がかかりました。ちなみに情報公開における文書のコピー代は月平均5〜6千円、いつぞやは1万9千円!なんて月もありました。この時は金額の多さよりも、エコじゃない自分に後ろめたさを感じてしまいました(必要とはいえ1,900枚も紙を使ったのですから)。
更には水無瀬一丁目で計画されている医療テナント入居ビル建設に係る問題(隣接住居の目と鼻の先に16メートルの建物がそそり建つ)に、いま微力ながら係っています。そしてそして、日記の更新を一番妨げているのはニュースの配布です。未だに5月の中旬に発行した議会報告を配っているのも恥ずかしく情けない話ですが、今回は“一人配布”を貫徹!と決めたので町内をテクテクと行脚の日々というわけです。昼間の運動が足りると夜は睡魔に勝てず、ウトウトしている間に一日が終ってしまっています。
アララ、これでは言い訳だけで1日分の日記になりそうです。本題に戻して、4月26日に開かれた「ことしの予算」について、私の「感想」を簡単に書いておきたいと思います。当日の発言記録は既に担当課が作成した要点録が公開されていますので、質疑応答の詳細はそちらの方をご覧ください。
さて、町長は自らが常々口にする「住民との距離が近い役場」「説明責任を果たす行政の努力」等々が、「ことしの予算」や「きょねんの決算」の開催で“事たれり“と思っているとすれば、それは間違いです。そりゃ説明会をやらないよりはやったほうが良いに決まっていますが、「予算と決算の年2回では不足、回数を多く」「質問時間が少ない」「地域に来て開いて」等の意見が今回も複数ありました。総合政策部長は「今後はタウンミーティング的な会も考えていきたい」と答えましたから、町長の任期中に是非実行してもらいましょう(と言っても、任期は後1年しかないです)。
現在の1年に2回、“よらしむべし”スタイルの会場設営はケリヤホールということもあって、住民は舞台に上った町の職員たちから見下ろされています。これが先ずよろしくありません。首長自らが地域に出向き住民の間に入って対話をする、このような形はもう珍しくありません。町長も遅まきながら、せめて小学校区単位で始めてみてはどうですか?
かつて介護保険制度の導入に当たっては、町は自治会ごと地域に出向いて説明会を行った実績があるのですから、予算・決算の説明会もできるはずです。要するに町長のヤル気とリーダーシップの問題でしょう。それに“よらしむべからず”スタイルなら気軽な雰囲気が生まれるため、堂々の(というか大げさやなぁ〜と感じる)演説調の長い質問もなくなり、より多くの住民が気後れすることなく口を開きやすくなるメリットもあります。
また当日配布された資料(映像も含めて)について、質問者からは芳しい評価をいただけませんでした。勿論完璧な資料とは言えませんが、私は努力のあとは見られたと思います。ささいな試みでしたが、スクリーンには事業に関連ある映像が映し出されて、各施策を身近に感じることができました。また質問では不評の声があがった「町の予算を家計にたとえてみました」は現実的でない例えもありましたが、「なんとか分かりやすい形で住民の皆さんに知ってもらいたい」との担当者の心意気は買ってもいいと思っています。
まあいずれにしても300近いホールの座席に、いつも60人足らずの参加者数では改善・工夫をする必要があることは自明です。余談ですが、今回初めて2人の女性職員(収入役と民生部長)が壇上に並んでいることに、私はうれしさと「まだ2人しかいないのか」との落差が入り混じって少々複雑な気持ちになりました。
今後ますます三役(収入役のポストはなくなるので二役ですが、教育長のポストも含めて“三役”といってもいいでしょう)を始め部長クラスへの女性登用が進むことを願っていますが、収入役は9月のはじめに退任ですし民生部長もあと1年で定年を迎えることを考えると、役場の人材育成(特に女性管理職への育成)に心細さを覚えてしまいました。ただあと十数年を経ると、一気に女性管理職は増えるでしょうね(男女同数、或いは逆転かも)。今育っている若い女性職員は、なかなか力がありますから。そのためには女性が働く制度の更なる改善や、トップの意識改革が急務だと思います。
 |
 |
|
挨拶する川口町長
|
パワーポイントを使っての説明
|
4月15日第四保育所において、食物アレルギー児に牛乳を与える事故が起きたことは、先の日記(4月16日付け)に書きました。昨年1月と全く同様(同じ保育士が同じ子どもに牛乳を)の事故が再発したことは、非常に重大な問題です。町長が翌日午後見舞いと謝罪に自宅を訪れ、副町長が事故が起きた保育室を視察しているのも当然の行動だといえます。
しかし再発させてしまった事態への対応は、町長の「すみません」だけでは済まないと誰もがわかっていたはずです。前回の事故後に作成された「再発防止改善策」は実に簡単で、ごく当たり前になすべき行為3点が記されているに過ぎません。
(1) テーブルには、座っている子どもの分だけを担当保育士が運び、子どもの顔を見ながら配る。
(2) 割分担を明確にするとともに、何より配慮の必要な幼児の場所(位置)を確認する。
(3) (1)(2)について複数保育士によるダブルチェックを行い、事故の発生を未然に防ぐ。
議会への事故報告については翌日(4月16日)に知らされましたが、その後6日を経て時系列に記載された詳細な記録が上がってきました。本来なら配膳担当保育士が用意すべきお茶・牛乳を、当日は障害児加配保育士が担当したこと、また飲料の手渡しも配膳保育士が担うべき役割でしたが、実際渡したのはクラス担任保育士であったこと等が記されていました。
「二度と同じ事故を起こさない」ことを誰よりも強く誓っていたはずの当該保育士が、「普段から役割分担はきっちり把握していた」と事情聴取において述べてはいるものの、実際は「何故牛乳を手渡したのか自分でも分からない」(同じく事情聴取での発言)というのが現実です。そして事故から半月後の4月末日をもって、当該保育士は退職しました。
二度に渡る同様の事故において、直接の原因者は当該保育士であることは明白です。しかし彼女一人が身を処すことによって解決する問題ではないと、私は感じました。「注意していたけれど事故が起こってしまった」、この乖離を引き起こした真の原因をこそ、町は究明しなければならないはずです。町は「今後の対応」として、「暫定措置として、飲み物及び給食配膳並びに午後のおやつの時間帯に所長もしくはフリー保育士1人をチェックのために配置する」と示したものの、抜本的対策については「島本町適正業務検討チーム」(以下「検討チーム」と言います)にゆだね「早急に対応策をまとめる」としています。
しかし検討チームは5月の末にようやく第1回目の会議を開き、原課より提出された「アレルギー事故防止策」の「案」をそれぞれの課に持ち帰ったものの、2回目の会議が開かれたのかどうか定かではありません。事故から2ヶ月余を経た今日(この日記を書いているのは6月21日です)に到っても、最終的な防止策は決定していない状況です。(なお当事故についての最終報告は、6月24日の本会議において町長の行政報告として予定されています)。
肝心の子どもたちに係る対策がこんなに遅れているというのは、どういうことでしょうか?これでは子どもも保護者も不安です(現に第四保育所保護者会からは、5月中旬に詳細な要望事項が出されています)。更には日々、一瞬一刻待ったなしの保育に当たっている現場の保育士たちは、何をよりどころに危機回避をしていけばいいのでしょうか。このような状況は保育行政の明らかな怠慢と捉えざるを得ません。
また「検討チーム」が開かれた同日に、関係職員4名に対し懲戒処分(保育所所長は減給10分の1を3ヶ月間、民生部子ども支援課課長・民生部理事・民生部長には各々戒告の処分)が行われています。今回の事故に係る職員の処分は当然ですが、何よりも優先すべきは子どもに係る不安要因を取り除く取り組みであったはずです。
 |
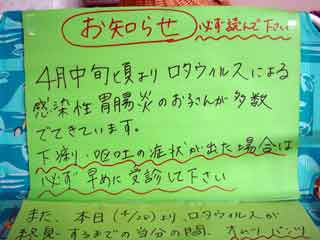 |
|
|