 |
 |
|
| キルン(乾燥塔)を模したウイスキー博物館 | 博物館内部(昔の蒸溜器具) |
今日は8月の15日(ちなみに私の63回目の誕生日でもあります)、毎日本当に暑い日が続いていますね。夏の疲れをお盆休みで回復した方も、休みが取れずに頑張って働いている方もおられることでしょう。私は8月11日から本日まで、次男が住む埼玉県所沢市を訪ねていました。日記をアクセスしてくださっていた皆様には空振りの数日でしたが、本当に申し訳ありませんでした(まあ、毎度のことなのですが)。
次男宅には三重県に住んでいる長男も合流して、久しぶりに一家が揃いました。我が家の息子たちはいずれも独身ですから、家族が増えるわけでもなく今まで通りの4人が顔を合わせたというに過ぎません。私は成人後の子どもたちには「親を当てにはしないこと。他人に迷惑をかけないなら、自分の好きなように生きよ」と言ってきました。2人とも私の叱咤激励には乗せられずに、平凡な勤め人となって10数年を経ました。二人とも島本町を離れ、それぞれの勤務地に居住しています。
次男が住む所沢市は人口33万人の中都市です。関東平野に広がる起伏のない町並みは、広々としてよく言えば開放的です。しかし山あり川ありの起伏に富んだ島本町の住人としては、いささか物足りなく「だだっ広い街やなあ〜」との印象が先に立ちました。自衛隊の施設やアメリカ軍の基地が存在するのも、広大な平地が活用できることに根拠があるのかもしれません。また航空公園や西武球場も広い土地があってこその施設なのでしょう。
今回所沢市を訪問した私の目的は、次男がどんな街で働き生活をしているのかを垣間見ることでした。勿論真っ先に大家さん宅にご挨拶に行きました。また同僚のご両親で「独身者は野菜が不足がちになるから」と、旬の野菜を下さる農家の方にもお礼に伺いました。よく行く餃子の店「満州」(ここの餃子は本当においしい!皮がモチモチしていて、水餃子にしてもグッドです)、スーパーマーケット、駅前のスターバックス等々、次男の日々の暮らしに溶け込んだ所こそ、私には興味がありました。そして全く縁がない土地に来ても、それなりに人との繋がりを築いている次男の様子が少し分かって安心しましたし、うれしくも思いました。
すみません。面白くもない次男宅訪問の話を長々としてしまいました。長らくの空白の言い訳にもなりませんが、私の夏休みのご報告です。次回は所沢を出発して随分な渋滞に巻き込まれながら、サントリーの白州蒸溜所(山梨県北杜市)を訪ねた話を少しさせてくださいね。白州蒸溜所はわが町の山崎蒸溜所から50年を経て開設されたそうです。標高700mに位置する白州蒸溜所は、世界でも珍しい高地に位置する“森の蒸溜所”としても有名です。平地の所沢から南アルプス甲斐駒ケ岳に囲まれた白州の森への訪問は、起伏に富んだ地形と共に興味深いものでした。
本日の本当の日付は8月18日です。お盆休みの間に出かけたミニレポートを日記の間に挟んでお届けしています。前回は所沢の次男宅訪問について触れました。今回は所沢を出発して、家族4人が大渋滞に巻き込まれながらサントリー白州蒸溜所を訪れた話です。
町内にあるサントリー山崎蒸溜所には、私も年に数回は行っています(たいていは息子たちのウイスキー購入に付き合う場合が多いですが、お土産用として求めに行くこともあります)。いつ行っても背景の天王山や館内の花々が美しく、働く人々も親切で気持ちがよいところです。サントリーには2ヶ所の蒸溜所がありますが、ひとつは身近な山崎蒸溜所,あとの一ヶ所が山梨県北杜市白州町にある白州蒸溜所です。
 |
 |
|
| キルン(乾燥塔)を模したウイスキー博物館 | 博物館内部(昔の蒸溜器具) |
私自身ウイスキーが好きというわけではありませんが、サントリーが打ち出す企業戦略の上手さには「ほ〜っ!」と感心することが多いです。折りしもJR新駅開業を来春に控えて、町ではタウンセールスプロジェクトチームが島本町の売り出しに知恵を絞っている最中です。プロジェクトの中には日本、いや世界的にも有名なサントリーの知名度を、島本町に結びつけたい意図の計画案も挙がっています(なかなか実現は難しいらしいですが)。
「何とか上手くいくといいのに」と私も応援していますが、片や白州蒸溜所における地元自治体との関係はどうなのだろうと思っていました。今回せっかく白州に来たのだから、白州町総合支所(7町村が合併して北杜市が誕生。白州町役場は支所になりました)に問い合わせてみました。支所長さんが丁寧に答えてくれました。行政主催のイベント等において飲料水の提供を受けることはあっても、特に行政とサントリーとの連携はないとのことでした。
むしろ広大な森林を有する白州蒸溜所と天然水白州工場への市民の訪問や、子どもたちに開放されている木工作業場、野鳥に親しむバードサンクチュアリ、森のレストラン「ホワイトテラス」の利用等によって住民とサントリーとの結びつきがダイレクトに深められているとのことです。支所長は最後に「サントリーさんは固いですから」と言いました。私は北杜市におけるサントリーのゆるぎない企業力を評しているのかと思いましたが、よく聞いてみると「サントリーさんは財布の紐が固い」と言っていることがわかりました。これはプロジェクトチームにとって、戦略建て直しの必要があるかもしれませんね!
 |
| 森の中に集う見学の人びと |
まあ、そんなこんなの情報もありましたが、私たちは山崎とは違った発酵槽(なんと4メートルを超える高さの木桶です)に驚きながら、蒸溜所の見学を楽しみました。また「バー白州」でインターナショナル�・スピリッツ�・チャレンジ2006の金賞を受賞した「白州18年」を頂き(有料です)、森のレストランで地場産野菜たっぷりの料理も堪能しました。蒸溜所内のウイスキー博物館は、山崎では見られないウイスキーの歴史と文化の変遷を知ることができました。
 |
| 1800年代のパブ |
山崎蒸溜所は市街地にも駅にも近い利便性の良さで人びとに親しまれ、一方白州蒸溜所は交通の便が良いとは言えませんが、広大な森に包まれた豊かな自然の恵みを実感させてくれます。私たちの町にある山崎蒸溜所の利点と島本町の良さをどのように重ね、いかに相乗効果を生み出すかは、さて誰の肩にかかっているのでしょうか?私はプロジェクトチームの発案を踏まえて、ここらでプロフェッショナルの手を借りるのも有効ではないかと思うのですがどうでしょうか?勿論予算は必要になってくるでしょうが、お金を掛けるところと掛けないところのメリハリを付けなければ、せっかくのアイデアも机上の空論で終わってしまう気がしてなりません。
本日の本当の日付は8月24日です。6・7月の日記の合間に、お盆休み(8月11日〜15日)のミニ旅行記を2回載せています。今日は川越市の散策です。
 |
| 「町並み通り」の蔵造り商家 |
川越市は次男が住む所沢の隣町です。“小江戸”と称される蔵造りの町並みは、重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。土蔵造りの江戸の商家は、火事の類焼を防ぐための巧みな耐火建築です。どっしりとした造りの町屋が軒を連ねているさまは、建屋の黒々とした外壁・瓦と相まって威圧感すら覚えるほどです。
 |
| 4百年まえから、今も時を知らせる「時の鐘」 |
現在の東京ではもう見られない江戸の面影をとどめている町筋は、結構広い地域に渡っています。しかも家屋は空きやでなく、今も商いをしながら住居としても使っています。昔の建物が単にポツポツ点在しているだけの、例えば当町の西国街道なんかと比べると、悔しいけれどケタが違います。
 |
| 懐かしい駄菓子屋が集まる「菓子屋横丁」 |
味噌屋・漬物屋・菓子屋・刃物屋等を冷やかしましたが、店舗の奥の座敷や中庭の設えも昔のままで風情がありました。川越名物サツマイモの老舗和菓子屋では2階を資料館として開放していました。また立派な店構えの建物ばかりでなく、ひとつ横道を入ると懐かしい駄菓子屋が軒を連ねる一角があったりして、散策には興味が尽きない“おもしろタウン”川越市を満喫しました。
お盆旅行の最終日は東京です。どこへ行こうかと迷いましたが、“花の東京”の今一番新しいスポット、東京ミッドタウンと国立新美術館に決定。ついでに近くの六本木ヒルズをおまけに組み込みました。あのヒルズがすでに“おまけ”になってしまうほど都心の開発スピードは速く、人びとの関心もまた超高速での変化を果てしなく繰り返しているようです。
 |
| 見上げてゴックン、つばをのむ六本木ヒルズ |
ミッドタウン内のブランド店では、ゼロの数が一目では読みきれない値札が付けられています。私は金額もさることながら、そこに人びとが群がっている現実に驚きました。高級食材を扱うスーパーマーケットの混雑、一切れ千円の小さな鰆の味噌漬けが当たり前の人びとが暮らしている東京ミッドタウンや六本木ヒルズ。私たち庶民にはやっぱり“夢まぼろし”の空間でしかありえないと改めて実感した次第です。
国立新美術館は大変な賑わいでした。1年前に開館したわが国で5番目の国立美術館ですが、コレクションを持たない始めての美術館として脚光を浴びているらしいです。私にはただのどでかい“貸しアトリエ”としか思えず、「税金の無駄遣いじゃないの?」との感も少々持ちました。今回は企画展(日展)と一般参加の住民に開かれた書展・絵画等の展示が行われていました。実はここを訪れる人びとの多くは作品の鑑賞だけでなく、建築技術の最先端を行く美術館と館内の有名レストランに興味を持って来ているようです。
 |
| キラキラ(ギラギラ?)輝く国立新美術館 |
確かに建物はユニークです。巨大な繭のような外観は総ガラス張りの壁面で覆われ、光の反射によって変わる表情は美しい(夜はもっときれいでしょうね)と思いました。ちなみに設計は、都知事選・参院選でお騒がせの黒川紀章氏です。昼食は私たちも長い順番を待って「ブラッスリー・ポール・ボキューズミュゼ」(どういう意味か分かりません。それにボキューズさんの3つ☆シェフの肩書きも、いまどきねぇ・・・とつぶやきながらも)で“おのぼりさんランチ”を楽しみました。料理はおいしかったでしたよ!
5日間の休日もあっという間に過ぎてしまいました。羽田から45分で大阪空港に到着。またいつもの日々が始まります。帰宅の翌日から、所沢近隣市で40度を越える超記録的な暑さが続きました。次男は私たちがまだ滞在中に短いお盆休みを終えましたが、猛暑の中仕事に励む姿を想像しテレビが伝える天気予報を恨めしく思ったことでした。
このホームページを開設してから今日(8月27日)で丁度1000日目です。もうすぐ9月というのに、日記は未だ遥か過去をさまよっています。申し訳ありません。トホホ状態も極まっておりますが、せめて9月の催しのご案内でお許し願いたいなぁ〜と。友人の澤島さんが呼びかけてくれた学習会のお知らせです。この頃は議会の委員会が迫っている日程ですが、私は勿論出席します。たくさんの方々のご参加を願っています。
 第2回学習会 第2回学習会
|
||||||||
| 『ここがちがう!フィンランドの教育・子育て』 | ||||||||
| 9月14日(金)午前10時〜12時 | ||||||||
|
||||||||
| 現地視察ビデオを見ながら学ぼう! | ||||||||
| 真の学力・教育改革とは? 子どもの視点に立つ子育て支援とは?
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
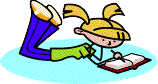 お問合せ 澤嶋真紀子 075(962)7307(FAXとも) お問合せ 澤嶋真紀子 075(962)7307(FAXとも) |