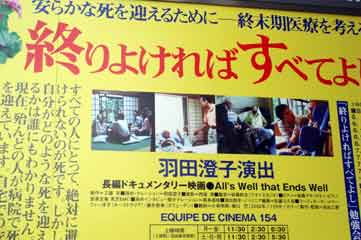辻元清美衆議院議員の国会報告会「永田町航海記」が、2時からふれあいセンターで開かれました。ゲストには小沢福子大阪府議会議員と、もう直ぐ選挙が始まる参議院大阪選挙区候補の服部良一候補が予定されていましたが、服部さんはどうしても抜けられない所用のため欠席でした。島本町の皆さんにとっては初めての服部候補ですから、参加者はちょっとがっかりの様子でした。
しかし服部さんの欠席を補っても余りある、小沢さんと辻元さんの迫力あるお話でした。今一番国民が怒っているのは、「年金問題」だと誰もが思っています。みんな我が身に係ることですから必死です。掛けていたはずの年金が抜け落ちているなんて、誰が想像したでしょうか。国が行っている事務は完璧だと思っていたからこそ、掛け落しから生じる支給減に対して自らを責めつつも、我慢と諦めを自身に言い聞かせてきたのです。
ところが社会保険庁の事務能力のなさと怠慢と隠蔽体質と無責任による“犯罪”行為が延々と続いていたが故の“事件”でありました。調査も修復も補償も当然行われるべきことです。これは選挙があろうがなかろうが、政府としてやらなければならない当り前の仕事です。ここで見逃してはならないのが「年金問題」に全てを置き換え、むしろ騒ぎをもっと大きくしておくように仕掛けられていないかということです。
憲法改悪から国民の目をそらせる企みに乗せられているのではないか?また憲法問題のみならず、人が生きていけないような社会の仕組を作り出す「格差問題」にも視点を据えて、参議院選挙の争点を見据えなくてはなりません。結局はいつの時代にも誰にも保障され変わらぬ平和、基本的人権をどのように守り育てていくのかが問われなければならないと、辻元さんも小沢さんも訴えていたと私は受取りました。私もまったく同感の想いでいます。


永田町航海記が終わり、大急ぎで家に帰ります。6時から私の議会活動報告「ボチボチサロン」を開くためです。6月に出した「なんぶニュース」の中で参加を呼びかけたのですが、実は事前の申し込みはたったのお二人でした。これではあまりにも寂しいので、今朝はお誘いの電話やファックスを送り続けていました。そのため掃除も食べ物も何にも用意できておらず、これから1時間半でお客さんを迎える準備を完了しなくてはなりません。
掃除機はまぁ〜るくかけて、ダスキンモップでシャッシャッと埃を払って、さすがにトイレはちょっと気を入れて・・・ヤレヤレお掃除終了。お次は軽食の準備です。はぁ〜っ、何とか間に合いました。完了です!後は参加者を待つのみ。果たしてお二人だけとの集会になるのか・・・まあエエかと腹をくくったところで、「こんばんわ」の声が続々と。結局全部で9人の集会となり、大成功!ほんまにうれしかったです。ワインや手づくりの梅酒、梅干・ラッキョウ、豚の角煮のお持たせもあって話も食欲も活況を呈しました。
足を痛めタクシーで来てくれた人には感謝感激。今回初めて参加の方は長く障がい児教育に携わっていた立場から、貴重な現場の声を聞かせてくれました。またPTAのOBとして、学校で地域文化の花を咲かせようと活動している人の話は、楽しくて元気が出る内容でした。精神に障がいをもつ人や引きこもりの若者たちをケアしている人、障がい者ガイドヘルパーの仕事からここへ直行してくれた人、障がい者のグループホームで食事作りをしている人、みんな(安い給料や報酬で)頑張って仕事に励んでいることが判りました。年長の男性からは戦争体験の話と医療費の疑問点が出ました。そして沢山の友人を持ちイキイキ活動している人は、様々な情報を提供してくれました。
私からは阪急水無瀬駅のエレベータ設置についての考えを訊いてみました。皆さん「必要」と答えました。しかし「町の負担額4億円は高すぎる」「もっと別の方法があるのでは」と疑問を示しました。みなさん今後の調査の必要性と阪急電鉄からの詳細な計画提示を求めていました。私も全く同感で、町や阪急電鉄に要求していくことを約束しました。2時間の予定が3時間近くまで盛り上がりました。日曜日の団欒を犠牲にして「ボチボチサロン」に集まってくださった皆さん、本当にありがとうございました。