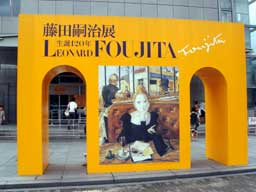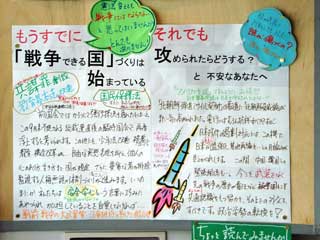とんでもない強引なやり方で進められた議員提案による「委員会条例の一部改正」案件(詳しくは後日の日記に書きます。改正の内容は5人会派の自由民主党クラブと山吹民主クラブから2名の議会運営委員を出させろというもの)提出によって、1日延長を余儀なくされた会期となりました。
私の一般質問は10人の質問者の内最後でしたが、午後2時過ぎに始まりました。今回は最後であることを幸いと思いました。それは前述した条例改正に対して意見を述べることが出来たからです。一般質問の前段として、世界情勢や社会的に影響のある事象・事件について思いを語ることは許されています。
私は登壇して先ずは傍聴者の方々に対し「ご多忙の中わざわざ議会傍聴にお越しくださいましてありがとうございます」とお礼を述べました。続いて以下のような発言をしました(即興で発言するわけですから、何を言い出すか議員も理事者もわかりません。通告がない分聞き取ってくれる効果は高いです)。
『2006年6月定例議会も、もうまもなく閉会いたします。私も通算14年の議員職を与えて頂いておりますが、今会議ほど議事の進めかたについて忘れることの出来ない印象を残す議会はありません。
異常ともいえる強引さで進められた議員提案による条例改正は、全く新しい体験でありました。断じて承服することが出来ません。もとより要件を満たし提出され可決した結果について、いまさら異議を唱えることはいたしませんし出来るものでもありません。
しかし議会運営委員会が機能しなかった、議長の強引過ぎる議事整理権が働いた、これらは傍聴者や理事者から見てもけっして望ましい議事進行ではなかったと思います。議会が醜い情けない姿をさらしたと私は残念でなりません。
今回の事態は今後の議会運営に多大の悪影響を与えていくのではないかと、危惧いたしているところです。』
続いて7月2日の日記に書いた通告書に沿って一般質問を行いました。ただし、それぞれの質問について削除すべき項目が生じたため、登壇しての実際の質問は通告書よりスリム化したものとなりました(内容についてはそう大して変化はありません)。私より前の質問者への答弁を聞いていると、肝心の答え以外で長々と発言される恐れが出てきたので、本会議2日目の終了後複数の理事者に削除の了解を取り付けました。質問は4点ありますが、今日は「行方不明の住民について町の係わりを問う」をお知らせします。質疑応答は3回往復しますが、私の質問の概要です。
Q 「山崎在住の年長者男性が行方不明になられてほぼ1ヶ月を経過しようとしています。島本町住民の中で、その所在が今もって全くわからない方がおられることに心が痛みます。行方不明後の経緯については、6月16日の議員全員協議会において町長の挨拶として述べられています。町として様々な制約があったにせよ、対策は万全であったか?悔いは残らないか?を問いたいと思います。
町長はご家族の初期の申し出により『緊急情報の共有等に関する要綱に沿っての対応は行わず、積極的に関係方面へ働きかけることを控えた』と述べています。しかし、事件発生2日後には家族は警察と協議のうえ役場にビラ(“この人を捜しています”と書かれたビラ)を持参されました。
この時点で町は緊急事態と捉え対応すべきではなかったでしょうか?緊急事態とは、重大な事件・事故の発生のみをさしているのではありません。これらの発生の恐れがあると危惧される、又は予測される場合をも緊急事態であると、町の要綱は位置付けています。
要綱第4条の緊急情報連絡会議は開催したのですか?関係部局間で対策等を協議したのですか?町長・助役は会議に参加したのですか?
今後町としてどのような対応が取れますか?今後このような事件が発生した折に、生かせる教訓はありますか?」
このような内容を3回に渡って質疑しました。それまでは「内々に」と進めてこられたご家族が、意を決して行方不明者を捜すビラを持参された、それを受けて町長は直ちに大々的な捜索体制を整えるべきであったと私は本当に残念でなりません。自治会経由でビラが回覧されたのはずい分後になってからでした。全町上げて、近隣市町にも出向いて駅頭でのビラ配布も可能であったはずです。警察や消防の専門性は無くても議会だって全議員で取り組めることはいくらでもあったはずです。ただ心配をするのみの毎日は私たちも本当に辛いのです。これでよいのかという私の思いが何処まで伝わったのか、答えはあえて書きません。しかし全くと言ってよいほど、事の本質を認識できていない答弁が返ってきたのには茫然としてしまいました。