 |
さて、細い方の栗、残った2本を挽きましたが、挽き方の順番を間違えてしまいました。下の図のとおり、両脇をへつって太鼓の半割にしようと思っていたのですが、それを忘れていきなり半割に。工房のバンドソーはリョービのBS−51。標準では挽き割り高さ、180mmですが、215mmまで挽けるよう改造してあります。この丸太の直径は27cmくらいで、板材をとるなら太鼓の半割にすれば、あとはバンドソーで加工ができます。 というわけで、半割にしてしまった丸太の耳をカット。 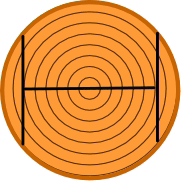 左の写真のように、半割にした切断面を垂直に固定してチェーンソーでへつります。挽く幅は狭いのでさくさくと、あっけなく切れます。挽くより、丸太を垂直に固定する方が手間です。 左の写真のように、半割にした切断面を垂直に固定してチェーンソーでへつります。挽く幅は狭いのでさくさくと、あっけなく切れます。挽くより、丸太を垂直に固定する方が手間です。 |
|
 |
 結構垂直には気を使います。今回挽くところはバンドソーに掛けたときに底面になるところ。チェーンソーのバーと直角になるように、切り始めと終わりの角度が同じになるよう慎重に材とスライドバーをセットします。 結構垂直には気を使います。今回挽くところはバンドソーに掛けたときに底面になるところ。チェーンソーのバーと直角になるように、切り始めと終わりの角度が同じになるよう慎重に材とスライドバーをセットします。 |
|
 |
両側を切り終え、太鼓の半割一丁上がり。この材にはちょっと節があるので、小物か旋盤のボールか。 この材を使うのは、、、老齢年金受給の頃になるのかなあ。 木の水分も抜けるけど、本人の水分も抜けそうだ。(@@) その頃に、今みたいに半割丸太を出し入れできる筋力が残っているかどうか、、。 まあ、還暦近くなっても、腕の筋肉の筋が割れるのは、こんな材木を扱っているおかげかな。 チェーンブロック用の三脚を扱うのも、結構大変です。3mの単管パイプを3本をまとめた上に、タコマンの吊り具が付いているから結構重い。持って運ぶだけなら簡単ですが、三脚に立てるのは、筋力に加えてコツが必要、慣れないと一人では危険です。 何本か挽いて、ようやく慣れてきました。三脚を運んで、立てたらチェ−ンブロックを吊って、材にスリングを掛けて、持ち上げて、一度移動させて降ろして、三脚の位置をずらして、また吊って単管の上に乗せて、挽く角度をチェーンブロックで材を回しながら見当をつけて、単管パイプの金具で材がずれないよう木ねじでピンを打って、芯からの板厚が同じになるようチェーンソーのスライダの高さを元口と末口で調整して、チェーンソーバーの角度が元口と末口で同じになるよう微調整して、スライダーにスタビライザーをかませて、三脚を外して、、チェーンソーのエンジンスタート。 |
|
 |
垂直のセットにずいぶん時間がかかってしまったので、残りの3本は、テーブルの方で丸鋸とセーバーソーで切ることに。 元口、末口同じ幅で罫書いて、丸鋸で深さを変えて2回に分けて切れ目を入れます。場所によって切れ残りがあるので、そこはセーバーソーで。のこ刃が狭い分だけチェーンソーよりロスは少ないようです。ただ、切り口は上でやったチェーンソーの方が綺麗かな。セーバーソーは刃幅も狭く、ガイドも無いので結構切断面は汚い。 セーバーソー、時々板の製材にも使いますが、結構切れます。もちろん使う前には研ぎは欠かせませんが、十分実用的です。 これで細い栗はおしまい。 このあと、30cmのケヤキを挽きましたが、ケヤキはやっぱり硬い。切削のスピードが遅いので、やたらガソリンとオイルを消費したような気がします。 残りは、最初に挽いた50cmの太い栗の末口側の2m材と30cmのケヤキが1本ずつ。暇を見つけてぼちぼち挽きます。ということで、とりあえず単管パイプの製材レポートはこのへんでおしまいということに。たまには木工もしないと。 |
|
| おまけのコンテンツ | ||
 |
あと2切りとなったところで、オレゴンの縦挽き用のソーチェーンが市販されているのを見つけ、試しに1本本発注してみました。 左の写真が刃の形状。,一瞬上側が刃のように見えますが、下の角度の鈍い方が刃です。研ぎの角度は10°/10° 横引きの刃が繊維を切りながら挽いていくのに対し、こちらは鍬で縦の繊維をこそぎ取るようなイメージです。 実際に切り始める。切れは良い。横引きの3,4割増しのスピードで切り進んで行きます。振動も少ない気がします。切り角度が浅く、左右の振動が少ないのだろうか。挽き幅30cm、長さ2mの栗の半割を一気に挽けました。1本目を挽き、一度チェーンソーを冷ましてから2本目のケヤキに。さすがにケヤキは硬いのか、研ぎが鈍ったのか、栗より切削スピードは落ちたようだ。それでも、横引きのソーチェーンよりは快適です。 やはり、リッピング用というだけあって、切削能力は高いようです。今回の製材はこれでおしまいなので、次からはこれ。 もっと早く見つければよかった〜。 (_ _) |