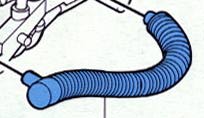
|
シールドライガーMk-1 |
極地戦用高機動型 |
ShieldLiger Mk-1 |
共和国 |
|
型式番号 |
RPZ-003(※1) |
シリーズ |
B/O |
|
タイプ |
<ライオン型> |
発売 |
- |
|
全長 |
21.6m |
定価 |
- |
|
全高 |
9m |
オペレーション |
バッテリー |
|
全幅 |
6m |
ライト点灯 |
無 |
|
重量 |
92t |
使用電池 |
単3×1 |
|
最大速度 |
250km/h |
部品点数 |
- |
|
乗員 |
1名 |
ゴムキャップ |
E(シルバー)23個 |
|
搭載ビークル |
無 |
主成形色 |
水色・グレー・ミッドナイトブルー・ネイビーブルー |
|
主要目的 |
格闘戦 |
キャッチフレーズ |
対サーベルタイガー用の決戦メカ |
|
ギミック |
口を開閉しながら4本足で前進。更に尻尾も上下に可動。まさに百獣の王の貫禄です。 |
||
|
その他 |
- |
※1:本来旧シリーズのシールドライガーのパッケージには「RPZ-002」となっていますが、旧グスタフとダブってしまうので、ここでは「RPZ-003」を用いました。
装備
|
装備名 |
搭載数 |
特徴 |
|
レーザーサーベル |
2 |
|
|
二連装加速ビーム砲 |
1 |
|
|
三連衝撃砲 |
1 |
|
|
ミサイルポッド |
2 |
特徴
|
帝国軍の最速メカ、サーベルタイガーに苦戦をしいられてきた共和国軍が対サーベルタイガー用として開発した決戦メカ。サーベルタイガーを上回る性能をとの要求に応えるべく最高速度はサーベルタイガーのそれを上回っており、時速250キロの高速を保持するために機体の各所にエンジン冷却用のラジエーターが装備されている。また背部の砲を胴体内部に収納して、空気抵抗を減らすシステムが採用されスピードアップに大きな効果をあげている。武装もレーザーサーベルをはじめ、体の各部に配備されておりコンパクトながら強力なものとなっている等、共和国軍が総力をあげて開発した対サーベルタイガー用の切札である。 今回ここで取り上げられる機体は、試験評価さえ受けていない、ロールアウト直後の機体である。 |
掲載バトルストーリー
|
- |
 見よこのメカメカしさ。
見よこのメカメカしさ。
これこそまさに、共和国ゾイド、と言わんばかり表面の複雑さ。最低限の装甲に、内部構造むきだしの側面。これを共和国ゾイドと言わずしてなんというのだろうか。構造フレーム、各種パイプ、サスペンション、油圧シリンダー、ラジエーター、本当に兵器としてこんなので役に立つのだろうか? しかし、視点を変えると、どんなに装甲が厚くても、兵器が進歩しすぎると防ぎ切れ無くなって、どうせ当たって機能不能になるので、最初から装甲分の重量を減らして他の部分に重量をさこう、なんて発想に基づくデザインなんでしょうか。そんな、共和国軍最速(当時)のゾイドを製作改造してみました。
もともと、シールドライガーは好きなゾイドなので、いつかは良い改造をしてみたいと思っていました。そこで今回の改造に際しては、他の改造同様、以前から思っていたいくつかの疑問点を削っていくというやり方をしました。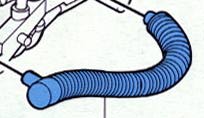
まずは、首の後ろのパイプ。どうもこれが固定されているのが納得いかなかったんです。もし、シールドライガーの口の開閉が下顎だけの開閉であれば、別になんとも思わなかったんでしょうが、これが上顎も動く、要は頭全体が動くようになっているから、よけいに首の後ろのパイプが動かないことに違和感を感じたわけです。
当初このパイプは、スプリングにブラスパイプを通すという、ガンダムのザク系の動力パイプのお約束の方法を採ろうと思っていました。しかし、市販のブラスパイプでは太さが思うように得られずあきらめました。次に、ビニール、ゴムを問わず、あらゆるパイプを探しましたが、色・形・柔らかさの面で思うようなモノが得られず、最終的にやってきた方法、スプリングにリード線を巻き付けて柔らかさと太さを確保するという方法に落ちつきました。でも、黄色に塗装するんであれば、最初から黄色のリード線を使えば良かったと、ちょっとこの辺は当初の計画の甘さが出てしまいました。
塗装方法ですが、今回は、将来の事を考えシールドライガーMk-1に準じた塗装にするということは大まかに決めていました。しかし、単純に旧Mk-1ではおもしろくないので、モールドのパイプを塗り分けようと考えました。
ご存じの通り、共和国ゾイドは、構造むき出しなわけです。そこで、このむき出しのままの構造とは、そのまま部隊カラーに塗られてしまって良いのであろうか? メンテナンスの時困るじゃないか? という疑問もあったのと、とにかく一度モールドされているパイプを全て塗り分けたい、というかねてからやりたかった塗装方針も含め、パイプと思える部分は、全てを塗り分けることにしました。 これで正しいかどうかというとまた問題もありますが、塗り分け方法は既に紹介してきたように、以下の通りです。
|
色 |
系統 |
設定 |
|
赤 |
燃料系 |
各所にエネルギーを送るためのパイプ |
|
青 |
循環系 |
各所で発生する熱を冷ますための循環液が流れているパイプ |
|
黄 |
動力系 |
内部にフレキシブル・ドライブシャフトが通っている動力パイプ |
 しかし、これが前足と後ろ足でモールド方法が逆になっているので、片方を黄色に塗るとモールドが異なりながらも黄色に塗らざるを得ない、と思わされたので、溝の入っているパイプは一括して黄色にしてしまいました。しかし、やってみた結果は、ちょっと黄色がうるさすぎるなというのが完成後の印象です。塗装中は気づかなかったのですが、かなり箇所に黄色を塗るはめになってしまったわけです。赤と
しかし、これが前足と後ろ足でモールド方法が逆になっているので、片方を黄色に塗るとモールドが異なりながらも黄色に塗らざるを得ない、と思わされたので、溝の入っているパイプは一括して黄色にしてしまいました。しかし、やってみた結果は、ちょっと黄色がうるさすぎるなというのが完成後の印象です。塗装中は気づかなかったのですが、かなり箇所に黄色を塗るはめになってしまったわけです。赤と 青は溝の無いパイプを選んで適当にやりました。比率的には、赤よりも青の数の方が気持ち多めにしてあります。この辺は、各人はどう解釈するかではないでしょうか? 特に前足の関節周辺はパイプが集中しているので、赤と青の塗り分けは効果的です。でも、これって組み立ててしまうとあまりよく見えないんですね。
青は溝の無いパイプを選んで適当にやりました。比率的には、赤よりも青の数の方が気持ち多めにしてあります。この辺は、各人はどう解釈するかではないでしょうか? 特に前足の関節周辺はパイプが集中しているので、赤と青の塗り分けは効果的です。でも、これって組み立ててしまうとあまりよく見えないんですね。
こんな風に塗り分けてみたことが、このシールドライガーが、ロールアウト直後の部隊塗装にされていないテスト前の機体、と設定した理由の一つです。(シールドライガーの牙がとがっているのに注目)
それから塗装するとなるとやはりコクピットの塗り分けも必要になります。
 こんなふうに塗り分けてみましたが、問題点があります。シールドライガーのコクピットには計器のモールドがないので、これを再現しなければならないのでしょうが、腕に自身がなかったのでやっていません。書き込みも行っていません。この辺どなたか良い方法なり、良いシールドライガーの定番コクピットを作ってもらいたいです。
こんなふうに塗り分けてみましたが、問題点があります。シールドライガーのコクピットには計器のモールドがないので、これを再現しなければならないのでしょうが、腕に自身がなかったのでやっていません。書き込みも行っていません。この辺どなたか良い方法なり、良いシールドライガーの定番コクピットを作ってもらいたいです。
 背中の装備には、砲口を作りました。こうしたミリタリー系のモノをする場合、砲口に穴を開けるというのはお約束の加工のようですが、今回初めて行いました。今まであんな細いところに穴を開けるなんて、と思い腕に自身が無くてやっていませんでした。今回の作業にあわせて、ピンバイスのバリエーションを増やしました。おかげで、背中のビーム砲には砲口が開けられました。
背中の装備には、砲口を作りました。こうしたミリタリー系のモノをする場合、砲口に穴を開けるというのはお約束の加工のようですが、今回初めて行いました。今まであんな細いところに穴を開けるなんて、と思い腕に自身が無くてやっていませんでした。今回の作業にあわせて、ピンバイスのバリエーションを増やしました。おかげで、背中のビーム砲には砲口が開けられました。
さて、最後まで引っ張ってきているのが、シールドライガー最大の疑問点である、尻尾のギミックです。少なくとも私にとっては、最大の疑問点でした。他の方からはどう見えていたのでしょうか? とにかくあれだけ手動で大きく上下に動くのに、連動しないんですよ。それに歩いていると重みで、カクンなんて落ちてしまう尻尾。悩みの種でした。そこで、私がシールドライガーを改造するからには、これを解決しないわけには行かないのです。
 今回とった方法は、口の開閉動力を尻尾まで伝えるという方法です。口の開閉の動きを後ろに伝えることは、既にグレートサーベルの改造で成功していたので、なんとかなるであろうと言う予想がありました。しかし、後ろまで導いた動力を実際に尻尾に伝える方法はかなり悩みました。結果的には尻尾の上側に軸を取り付けることで解決しましたが、引っ張るにしても針金で引っかけて引っ張ろうか、下側から押し出すようにした方がよいのか、色々悩みました。それ以上に、ビーム砲の下の空間を利用して、後ろまで動力を伝えるのに
今回とった方法は、口の開閉動力を尻尾まで伝えるという方法です。口の開閉の動きを後ろに伝えることは、既にグレートサーベルの改造で成功していたので、なんとかなるであろうと言う予想がありました。しかし、後ろまで導いた動力を実際に尻尾に伝える方法はかなり悩みました。結果的には尻尾の上側に軸を取り付けることで解決しましたが、引っ張るにしても針金で引っかけて引っ張ろうか、下側から押し出すようにした方がよいのか、色々悩みました。それ以上に、ビーム砲の下の空間を利用して、後ろまで動力を伝えるのに 、スイッチという大きな壁があり、ここをどう回避するかを考えた結果、上側に天板のようにするのが良いことがわかり、採用してきた方法
、スイッチという大きな壁があり、ここをどう回避するかを考えた結果、上側に天板のようにするのが良いことがわかり、採用してきた方法 に落ちついたわけです。ギミックの位置によっては、スイッチの動く範囲が異なりますが、幸いにもスイッチは、一番前側に押し込まないと電気が流れないようになっているので、中途半端な位置にあれば、結果的にスイッチは入らない状態になっています。
に落ちついたわけです。ギミックの位置によっては、スイッチの動く範囲が異なりますが、幸いにもスイッチは、一番前側に押し込まないと電気が流れないようになっているので、中途半端な位置にあれば、結果的にスイッチは入らない状態になっています。 そして、尻尾の上側には、ギミック部品の後端がちょっとだけ出入りするようになっています。
そして、尻尾の上側には、ギミック部品の後端がちょっとだけ出入りするようになっています。
では、実際にどのように動くかと言いますと。
|
|
口を閉じたときは、ギミック部品が最も後ろ側に下がることになるので、尻尾は一番下がった状態になります。ちなみに、製作の際は、この尻尾の一番下がった状態をどの位置にするかが一つのポイントとなります。 |
|
|
反対に、口を開いたときには、ギミック部品が最も前側に来ることになりますので、尻尾の上側が引っ張られ、尻尾は持ち上がります。 |
尻尾先端のビーム砲がありませんが、先端にあまりの重量物をつけてしまうと重すぎて尻尾が持ち上がらないので、装備をあきらめました。こうして、ビームを装備できなかったことも、この機体をロールアウト直後の部隊への配備前の機体と設定したもう一つの理由でもあります。なにか、もう一工夫すれば、なんとかなるんでしょうが、今回はあきらめたので、次回の課題といたします。
しかし、それ以上に尻尾と口の開閉の連動というのは、本来の動物の動きを考えると問題かも知れませんね。本当は足の動きに上手く連度させると良いと思うのですが実際の所はどうなんでしょうか?
この先、シールドライガーMk-2も同じようにやって行くつもりです。そして、最終目標はシールドライガーMk-1を成形色のままいろいろなギミック追加のみをやりたいので、それまでに訓練していくことが出来ればよいのですが・・・・・・
