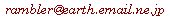人は文字を持ち、それを記録と記憶の手段としても用いてきた。残されたものには 時間が流れている。新しくても、古くても、そこには人の心の軌跡がある。川が死で満ちるとき (And the Waters Turned to Blood)verba volant, scripta manent. ことばはとびさり、かかれしものはのこる
前年 (2000年) から「魚の大量死」を目にすることがあって、その原因 を知りたいと考えてきた。福井県の環境科学センターや水産試験場や各種報道を注視 していたが、何も得られていない。河川水の採取や魚体の拾得はその地の者 (県など の職員も含む) によりされてセンターなどに送られている。採取方法に疑問はかなり あるが、一つの事実としてみることは可能だろう。それなのに、各当該市町に連絡が いったかどうかも含め分析・調査の結果は報告されていない。求めても出されるかど うか。公的試験研究機関なのに、この本でいう納税者に対し知らせるという義務を果 たさないのが問題なのである。ごく最近になってようやく情報公開のための法や条例 が整備され始めたとはいえ、まだまだこの国、というより社会での、特に意識の改革 は遅れている。積極的な報告とデータの開示提供はこれからどうするかを考えていく 上でも基礎となることで、早急な改善と公務員の姿勢の転換が必要である。研究社は 県内全域に出向いて調査を始終行えるはずもなく、そのときどきの住民の観察の報告 は重要な後の科学的調査の出発点となるはずだからである。公務員は上に立って見下 ろす態度は改めるべきである。住民と共に地域の環境監視と修復保全に取り組む必要 がある。
情報の公開も住民参加も進んだアメリカでもまだ問題は根深いことを教えてくれた。 公務員としての科学者が住民の側につくのではなく産業推進の立場を取って発言行動 している様は糾弾されるべきものであることは言うまでもない。環境破壊に立ち向か うべき公僕がその逆にある。事実を指摘し現状を摘示して目を覚まさせようとする、 バークホールダー博士らの奮闘ぶりは貴重な記録となって生き生きと描かれていた。 私も科学 (化学) を学びその本来の純粋な探求心と批判精神を信奉する人間の一人と して共感を強く抱いた。本来特定の利益集団などにかかわらず調査研究を推進できる はずの公務員としての科学者が利潤追求者の擁護にとられる態度をとり続けていると いう実態は驚きである。科学者と監督し政策を行う役人が結びついてしまっているの が問題の原因らしいことはわかるが、独立して活動できる科学者は率直に発言し良心 と責務に忠実に行動すべきと思う。他からの事実の指摘に素直に目を開き行うべき職 務を知らなければならない。それどころか、大量死の原因を単一の実証もされない説 明に帰して終わりとしているようでは科学者として失格である。
日本の社会の中での人々の権利と義務についての意識の低さや発言の場の少なさ (無 さ) を改められるような事件がないと直面している環境面での障害は乗り越えられな いような気がする。身近で現実に起こっている魚の大量死も充分なきっかけとはなり 得ていないのがやりきれないし、悲しい。
文化的遺産というものはどういった形態であれ、他の異なる文化的背景 をもった人々にとっての価値にはかかわることなく、それを生み出した人(々)を祖先 や現時点において持つ固有の精神的観念や心情で結ばれうる精神的集団においては (物理的隔たりが時間的・空間的に長くあろうとも)、それが持ち及ぼす意味は特有の 位置や地位を有形無形に占め得るものと言える。それが他の人々によって力ずくで 踏みにじられたときの心情には心有る人ならば誰しも同情しことばを失いかねない怒り とも悲しみともつかぬ思いが湧きあがってくるものだろう。とりわけその人々が歴史 上圧迫を受けることが多々有り、その返礼が為され得るにはあまりに力不足だとした らその人達や民族はどのような手段に訴えて自らの心情や主張を他へ伝えようとする だろうか。近代社会ならなおのこと、意識、知識、精神の高みにおいて本来なら極めて 適切に”処理”されるはずのことがらが、抵抗しようのない力により無理矢理抑え込 まれるとき、何が有効な解決手段になり得るのか。このような問いに対する一つの答え としての実例がこの書に”なぞ解き”の形で呈された。
彼らのドイツを中心とした強力な国々の人々への対峙姿勢は内的不服従であり、表面的 無関心無知であり、また、その対する国々への受けたことへの答礼は、おそらくは、 紙面上、必ずしも好ましいとはいえない方法ではあったが、偶然の好機に手に入れた これはこれで効果的な手法であったといえるし、他国の人々は強い非難を浴びせられ るほど自身は法的にはもちろん人として道義的にも立派であったわけではなかったわ けである。指導者達が共産党・労働者党でなkとも、彼らは似たことをその機会があ れば行っただろうと思われる。入手したものの取り扱い方についても著者がのべてい るとおり、被害者ならば誰しもそうするだろうと推察される。
登場する主要な追跡者たちもなかなかに興味深い。この背後の深層にあったはずのそ れぞれの”ペーパー”や”ポーランド”や”ポーランド人”や”文化”への思いを綴 らせて比較するとさらに多くの心象風景が描かれただろうに。