現在の副詞「全然」は否定・打消しの意味を持つ語に係るものとされ、 実際にもそう使われることが普通の言い回しとして認められ違和感もない。 ところが、おもに若い人達の間で目立ってきたのが、「全然...なのだ」 という肯定的な述語に結びつく全然の使い方である。この言い方を誤りだ、乱れだ、とする大人の声を”迷信”とするのが、小池 清治、『日本語はどんな言語か』(ちくま新書009)、1994、筑摩書房、のpp. 8-11 である。ここでは、志賀直哉、森鴎外、夏目漱石、芥川竜之介の作品中 の文例をあげ、「全然」の用法として、(イ)情態副詞(まったく/すべて...で ある)、(ロ)程度副詞(続く語を強める)、(ハ)呼応副詞・陳述副詞(打消し表現 と呼応する)の3つに分け、彼らが使っていたので”乱れ”とされる(イ)の使 い方は事実としてあったのだから嘆くことはない、としている。(ロ)について は、「...第一の意義は全然別個の観念なるが故に、また全然別個の訳語...」 吉野作造”憲政の本義を説いて其有終の美を済すの途を論ず”、中央公論、 大正5年7月号―有名な「民本主義」を提唱した論文―でも出ている。
確かに、歴史的に3種の用法が現れていたことは否定できないが、その頻度や 地域、階層、時間的な幅などは分からない。いずれも優れた小説家であること は誰しも知っていることゆえに、そのまま鵜呑みにしてそれでいいのだ、とバ カボンパパ的な納得と認容に走りがちだが、それは”誤り”である。彼らは多 数を代表していないし、すべてを知っていたから書いたのでもない。単に小説 の一部分に用いたにすぎない。明治以降の近代文学において(イ)が用いられて いるから多くの人々が全く違和感なく使っていたとするのは根拠として薄弱で あろう。文字に残された言い方を代表例とするのも拙速の感を否めない。
近年の辞書の多くは打消し表現と共に用いる(ハ)、(ロ)(否定の意を持つため) を通常の認容される使い方としていて、”非常に”の意で用いる(イ)は俗っぽ い、卑しい(語弊があるが)使い方として但し書きになっている。あることは否 定されていない。先の引用書の中で、(イ)−>(ロ)−>(ハ)と使用者の多数が 変遷してきた、と述べているが、その根拠は示されていないし、仮にそのよう な変遷変容があったとするならば、(ロ)や(ハ)はその当時違和感や嫌悪感を抱 かれたはずだが、そのような話しはきいたことはない。吉野作造をはじめとす る言論人は少数派であったろうか。また、多数派を形成すればそれでことばは なんでもかまわないのであろうか。おそらく現代の多くの人々は学校・社会教 育を通じて(ハ)または(ロ)でないと好ましくないと考えていると想像できる。 その根拠はそれを嘆き、そう話す人々が実際に多いことである。自然な変遷の 結果なら近年になってそれだけが”復活”してある意味で”正当化”される理 由はあるのだろうか。
なによりも、聞いていて嫌な感じ、変な感じ、奇妙な感じを受ける時、私たち はその言い方をおかしい、あるいは間違っている、と言うのだと思う。その時 その時代に生きていてそう思う・感じるとき、そうでない表現は違和感を感じ させないより自然な表現なのだ、と思うわけである。もう一つ理由とすべきは 論理的構成を要求されるような文章や口頭の議論において、曖昧さや文脈など で判断できない多義性のある表現は弱く受け容れられない、ということがある 。一貫性と明解さが論理には不可欠だからである。この意味でも、変な感じを 受ける言い方は避けられなければならない。
特に若い人達にみられることの多いこの種の現代の短絡的省略的言い方は自然 な変遷とは無関係と思われる。はっきりいって、「全然... でない」けれど「 (実は)... なのだ」というところを単に略して言っただけの手抜き表現でしか ないと思える。そこにはことばの意味を解し自らのことばとして発したところ はみられず、それとは”全然”違い、別なところからの甘えを含んだ言い方で しかないとさえ言える。最近の(イ)に似せた「全然」は”迷信”に対する反証 としての小説の中の情態副詞とは異なり、安易で安直で貧弱な言語環境に育っ てそれ以上研鑚を重ねていこうとしない者達の甘えと言い逃れの結果にすぎな いと言える。なによりもことばとしての滑らかさや豊かさを文脈(あるいは話し そのもの)から感じさせないからである。そういった表現は肯定的に受容できな いし、自然な変容による心理的な認容にはつながらないはずである。改める努力 をこそすべきである。
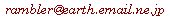 無断転載転用等固く禁じます
無断転載転用等固く禁じます