おすすめする本-コトバと教育を中心に
| № | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本コトバの会編 (責任編集・渡辺知明) |
コトバ学習事典 | 1988/8、2刷1990/9 | 一光社 |
| 2 | 渡辺 知明 | 放し飼いの子育て ―やる気と自立の教育論 |
1994/9 | 一光社 |
| 3 | 下川 浩 | 現代日本語構文法 ―大久保文法の継承と発展 |
1993/5 | 三省堂 |
| 4 | 渡辺 知明 | 表現よみとは何か ―朗読で味わう文学の世界 |
1995/12 | 明治図書 |
| 5 | エミール・ゾラ | 居酒屋 | 1970/12、26刷1987/6 | 新潮社 |
| 6 | フローベール | ボヴァリー夫人 | 1965/12、2刷1976/10 | 筑摩書房 |
| 7 | 松下 裕 | チェーホフの光と影 | 1997/4 | 筑摩書房 |
| 8 | O・ルブール | 人間的飛躍―アランの教育論 | 1996/7 | 勁草書房 |
| 日本コトバの会編/大久保忠利監修『コトバ学習事典』 (初版1988年/増補版1990年。一光社。2800円。図書館協議会選定図書)  日本コトバの会(創立昭和27年3月)創立35周年を記念して1988年8月に出版されました。コトバの理論と学習方法に関するこれまでの研究・学習活動の成果のエッセンスをまとめたものでした。一般社会人・学生・主婦から国語教師や専門の教育者まで、幅広い方々の要求に答える理論的実用書として多くのみなさまからご好評をいただきました。再販は1990年刊行『追補版』33項目を追加し138項目としました。(編集責任・渡辺知明) 本書の特徴(1)理論的知識・教養にとどまらずに、学習の具体的方法までを親切に示しているので、初心者の実用的利用からコトバ学習の指導書として最適。 第1部 理論編……やさしく・わかりやすく書かれた言語理論入門 |
|
渡辺知明著『放し飼いの子育て―やる気と自立の教育論』 (1994年。一光社1500円)(Amazonで注文する) まえがきより=「やる気」や「意欲」というものは、子ども自身が本来もっている自己運動のエネルギーです。アドラー心理学でいう「勇気づけ」とは、まさに自己運動の強化です。近ごろ注目されているホリスティック医学でいう自然治癒力も人間本来のエネルギーの力を生かそうという考えです。教育の原点は子どもたちの自己運動をよく見ること、そして、どのようなはたらきかけをすべきかを考えることです。
|
|
下川 浩著『現代日本語構文法―大久保文法の継承と発展』 (1993年。三省堂。3000円)
もくじ=第Ⅰ部 第1章 文と文章―文節と文素 必要成文と自由成分 文分析 日本語の主部 総主文 「主語」なし文 補文素と客文素 修用文素とは 文のシッポ/外助動辞 終助詞と文の論理的構造 命題と命題態度 日本語の文型 デス・マス体 テンの打ち方 第2章 複合文と文章―接続表現/接続文素(ツナギ) 修体文素と埋め込み文 文をマトめる吸着辞 重文とは? 文章の構成/テーマ展開 主題と省略 前提と省略 視点 主題と「主語」 コトバの意味と作用 文章のツナガリとマトマリ 文章の世界 脈絡と推論 第3章―品詞 品詞分類 形容詞・形容動詞 補足文素による動詞の分類 格助詞 ハとモ 副助詞 複合助詞 第4章 言語と文法―文法とは 言語とは コトバの習得と知能の発達 言語と意識 第5章 動詞の分類 第Ⅱ部 第1章 日本語の文の階層的構造―ドイツ人に対する日本語教授法の研究のために 第2章 日本語の文末の構造―大久保文法の継承と発展のために 第3章 日本語の複合文の構造―ドイツ語との対照から 第4章 談話における省略の構造―寄生構造について 第Ⅲ部第1章 内言の弁証法 第2章 チョムスキーの「合理主義」 あとがき |
|
渡辺知明著『表現よみとは何か―朗読で楽しむ文学の世界』 (1995年/明治図書/2301円+税/版元品切)
▼58ページ14行《誤》「散文は……なる。」→《正》「散文は……なるのは、このためである。」
|
|
(1970/26刷1987。新潮文庫。古賀照一訳) 自然主義の小説などというと、たいていの人が毛嫌いして読まないものです。しかし、この作品はとてもおもしろくて読みやすい小説なのでぜひ読んでほしいものです。全13章で構成されています。1章が1作品ともいえるさまざまな手法が工夫されています。
|
|
(1965/12。2刷1976/10。筑摩書房フローベール全集第1巻。伊吹武彦訳) 今回、読んだのが二度目でしたが、簡潔な表現のなかに人間の心理を見事に描き出しているのに感心しました。また、フローベールの持っているロマン精神が、伊吹武彦氏の名訳から感じられました。わたしの好きなチェーホフの作品にも通じる表現の象徴性もあるようです。現代の小説はやたらにべたべたと人間の心理を書きこもうとしますが、この作品は単純に見える人間の行動の奥の深さがあることを知らせてくれます。 |
|
(1997/4。筑摩書房) チェーホフ全集の個人訳(ちくま文庫版/全12巻)をした著者によるチェーホフ論集です。チェーホフの紀行「サハリン島」とドストエフスキー「死の家の記録」との関連を説きあかす「四 核としての現実」は新鮮な発見でした。この本の魅力は翻訳で磨きぬかれた著者の細かいこだわりが本の造りに生きていることです。チェーホフの作品を文章の細かい展開を基礎にして論じる点には感心させられます。
|
|
(1996.7。勁草書房) タイトルの「人間的飛躍」とは、子どもたち自身の秘めている人間的な能力のことです。ルブールはアランの教育論から、このことばをキーワードとして取りだしています。著者はフランスの教育哲学者です。だれよりも尊敬するアランの教育論から学ぶべき点を取りだしして紹介した本ですから、アランの教育論についての考えが分かるのは当然です。しかし、同時にルブール自身の教育論の解説にもなっています。
|
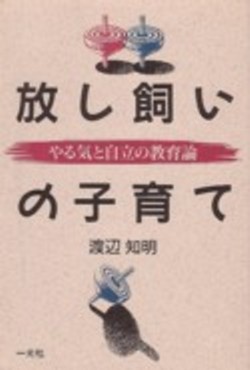 第一章 子どもの自立をはばむもの 動物の親子と人間の親子―母親はおこってはいけない/ガッツ石松の父―セコンドの役目/手塚治虫「どろろ」の世界―能力の獲得とは/子どもの自立をはばむもの―管理主義の教育/自由と自立の接近―人間に必要な土地/H君への手紙―ムリを楽しむのが勉強/美術教育のシステム―山梨県巨摩中学校ほか
第一章 子どもの自立をはばむもの 動物の親子と人間の親子―母親はおこってはいけない/ガッツ石松の父―セコンドの役目/手塚治虫「どろろ」の世界―能力の獲得とは/子どもの自立をはばむもの―管理主義の教育/自由と自立の接近―人間に必要な土地/H君への手紙―ムリを楽しむのが勉強/美術教育のシステム―山梨県巨摩中学校ほか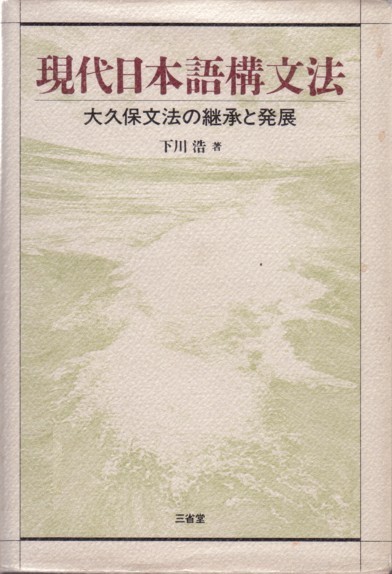
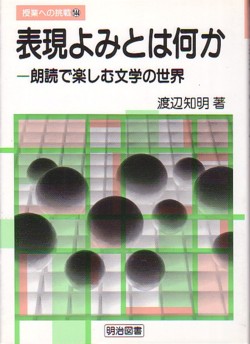 まえがきより=表現よみとは、声を出して文章をよむ音読の一種です。子どものころ、わたしたちは声を出して本をよみはじめますが、いろいろな理由でおとなになると音読することをやめてしまいます。しかし、音読は黙読にはないすぐれた点をそなえたよみ方なのです。この本は、音読・朗読の意義を見なおすとともに、より高度なよみに進むための理論と方法を示したものです。音読・朗読に興味をもつ方々ばかりでなく、コトバを声に表現することに関心をもつ方、音声化による文学作品のよみの問題を考える方々の要求にもこたえられるでしょう。
第一部 黙読・朗読・表現よみ
まえがきより=表現よみとは、声を出して文章をよむ音読の一種です。子どものころ、わたしたちは声を出して本をよみはじめますが、いろいろな理由でおとなになると音読することをやめてしまいます。しかし、音読は黙読にはないすぐれた点をそなえたよみ方なのです。この本は、音読・朗読の意義を見なおすとともに、より高度なよみに進むための理論と方法を示したものです。音読・朗読に興味をもつ方々ばかりでなく、コトバを声に表現することに関心をもつ方、音声化による文学作品のよみの問題を考える方々の要求にもこたえられるでしょう。
第一部 黙読・朗読・表現よみ